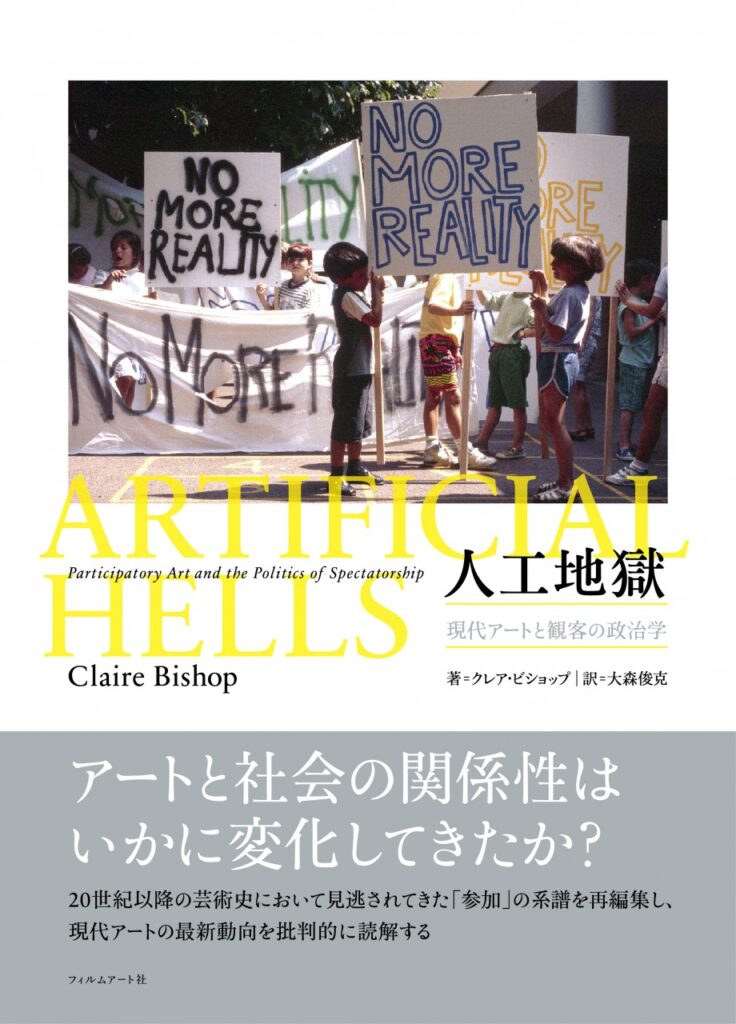序論
アーティストは、皆同じだ。彼らはより社会的で、より協働的で、そして芸術よりもリアルななにかを為そうと夢見る。
――ダン・グレアム
アルフレド・ヤーは、カラカスのカティア地区の住人に使い捨てカメラを配り、その写真を同地の美術館でのこけら落としの展覧会で展示する(《カメラ・ルシダ》、1996)。ルーシー・オルタはヨハネスブルクでのワークショップで、失業者たちにあらたなファッション・スキルを手ほどきし、集団的な連帯についてディスカッションするワークショップを開く(《ネクサス・アーキテクチャ》、1997~)。「スーパーフレックス」は、リバプールの公営住宅の高齢住人のためのインターネット放送局に着手する(《テナント・スピン》、1999)。ジャンヌ・ファン・ヘースウィクはロッテルダム近郊のフラールディングの住民のために、老朽化の激しいショッピングモールをカルチャー・センターに変貌させる(《繁華街》、2001~4)。「長征基金」は、中国の遠方の省で、切り絵の民間風習の調査を行なう(《切り絵プロジェクト》、2002~)。アンニカ・エーリクソンは「フリーズ・アートフェア」で、アイディアやスキルを交換または披露してもらおうと、グループや個人を募る(《オーディエンスはいかが?》、2004)。「テンポラリー・サービス」はロサンゼルスのエコパークの空き地で、即興的なスカルプチュアの環境と地域コミュニティをつくり出す(《コンストラクション・サイト》、2005)。ヴィック・ムニーズはリオデジャネイロの貧困地区の子供たちのために、アート・スクールを設立する(《ヴィック・ムニーズ・スペース・センター》、2006~)。
これらのプロジェクトは、1990年代初頭以降になされた参加(participation)と協働(collaboration)、およびグローバルな場のマルチチュードへの芸術的関心の高まり、そのほんの一部にすぎない。この「アトリエ制作以後ポスト・スタジオ」の実践の拡張された領域は、今日さまざまな名前で呼ばれる――ソーシャリー・エンゲージド・アート、コミュニティ型アート、実験的コミュニティ、対話型アート、浜辺のアート〔カナダのアーティスト、ブルース・バーバーが提起した概念。制度外部で社会的な交流を目指す芸術〕、介入主義的アート、参加型パーティシペトリーアート、協働型コラボレーティヴアート、コンテクスチュアル・アート、そして(直近では)ソーシャル・プラクティスといったふうに。私はこの動向を、「参加型アート」と呼ぶことにしたい。なぜならこれは、多数の(「双方向性」の、一対一による関係とは反対の)人々の関与を含意するからであり、そして「ソーシャル・エンゲージメント(社会的関与)」のあいまいさ――この語は、「関与絵画」〔アンドレ・フージュロンの炭鉱絵画などを指す〕からマスメディアにおける介入主義的な行為まで、幅広い行ないを指しうる――を回避するためだ。芸術が、たえずその環境(否定神学的なものですら)に対応するものである限り、いったい社会的関与ソーシャリー・エンゲージドではない・・・・芸術など、存在するのだろうか[1]。したがって本書では、演劇やパフォーマンスという手立てによって、人々の存在が芸術的な媒体メディウムと素材マテリアルの中心的要素となる、そうしたものとして参加を定義し、これを核に据える。
最初にことわっておかねばならないことがある。それは、本書で組上に載せられるプロジェクトは、ニコラ・ブリオーの『関係性の美学』(仏語版は1998年、英訳版は2002年に刊行)とほとんど無関係であるということだ――たとえ当該の表現をめぐる言辞に、少なくとも理論面で似通った点が看取されるとしても、である[2]。けれども実をいえば、本書の原動力となるプロジェクトの多くは、『関係性の美学』と、それが契機となった議論に続くかたちで現われたものだ。本書で論じるアーティストは、関係性の美学・・というよりも、むしろ政治化を遂げた活動プロセスとしての、参加の創造的な成果に関心を寄せる。ブリオーの著作の功績の一端は、議論的かつ対話的なプロジェクトを、美術館や画廊といっそう親和するものにしたことだった。とはいえ、彼の理論に対する批判的な応答が触媒作用となって、参加型アートをめぐるより批評的に洗練された議論が生まれることになった。1990年代の初頭まで、コミュニティ型のアートは美術界の周縁に追いやられていた。それは今日、それ自体の力に立脚したジャンルと化し、ソーシャル・プラクティスの芸術系修士コースもあれば、専門の賞も二つ存在する[3]。
この社会的コンテクストの指向性は、それ以降急速に発展し、そして最初に述べておいたように、いまや南米アメリカから東南アジア、ロシアに至るまで、ほぼ全世界規模の現象となった。ただし、もっとも顕著にその興隆がみられるのは、芸術への公的な財政支援の盤石の伝統を有する、ヨーロッパ諸国だ。商業的な美術界では、多くの場合、これらのプラクティスへの関心度は相対的に低い。集団的なプロジェクトは、個人で活動するアーティストの作品よりも市場に出すのが難しく、そして社会的なイベント、出版行為、ワークショップやパフォーマンスの断片的な羅列という以上には、さほど「作品」然とはしていないのである。にもかかわらず、それらは公的なコミッション・ワーク、ビエンナーレや政治的テーマの展覧会など、公共分野で無視しがたい立場を占めている。ここでは折に触れて非西欧圏のコンテクストから同時代の諸例に言及することになるが、しかし(以下に説明する理由から)この考察の核をなすのは、ヨーロッパにおける当該のプラクティスの台頭であり、そしてその地域で変遷する政治的な展望との関係性である。
しかし地理的な位置にかかわらず、1990年代における社会的なものへの芸術の指向性――その顕著な特徴は、芸術の物的対象、アーティスト、そして鑑賞者の間に横たわる旧来の関係を打開しようという、共有された一連の欲求である。つまるところ、アーティストは物的対象の創造主たる個人というより、むしろ状況・・の協働の試行者や実践主体とみなされるのだ。有限にして可動的な、商品形態をとりうる生産物は、起点と終点が定かではなく、持続し、そして長期におよぶ「プロジェクト」へとその認識を改められる。いっぽうで、かつて「観者」や「傍観者」とされていた鑑賞者は、今日では共同制作者や「参加者」へととらえ直される。後続の各章で明らかとされるように、こうした変節は、ときに実体化を果たした現実というよりも、理想論としてことのほか力強さを有している。とはいえそれらは例外なく、資本主義下の芸術生産や消費の旧弊の様式に対して圧力をかけようとする。まさにそれゆえにこの議論は、芸術――労働と専門的分業の区分への従属に逆らう、脱疎外の試みとしての芸術――に関する、マルクス主義とポストマルクス主義の著述の伝統を汲んでいる。
2006年のとある論考で、私はこの芸術を「社会的転回ソーシャル・ターン」を明示するものだとして、これに照準を定めた。しかし本書の中心的な議論の一つは、こうした発展が、より正確には社会的なものへの「回帰リターン」、芸術を集団性によってとらえ直す試みのなお続く歴史の一端として位置づけられるべきだという点にある[4]。このリサーチの基本的なモチベーションは、1990年代と2000年代の芸術に根ざしている。ただし、アーティストの参加とコラボレーションへの専心は、それ以前になかったわけではない。西ヨーロッパの見地からすれば、コンテンポラリー・アートの「社会的転回」は、過去の二つの歴史的契機によって文脈化されうる。これらは双方ともに、政治的な激動および社会変革の運動と重なっている。それは、1917年前後のヨーロッパにおける「歴史的前衛」〔ドイツの文学者、ペーター・ビュルガーの提起した概念。芸術と生の境界の無化を指向する前衛〕、ならびに1968年を終極とする「復活した前衛(ネオ・アヴァンギャルド)」〔ビュルガーによる概念。文化産業において形骸化した前衛〕である。そして私は、1990年代に目立ってみられる参加型アートの再興隆をもってして、1989年の共産主義体制の失墜を、変節の第三段階として措定するに至った。この三つの時勢は一体となり、社会の集団的なビジョンにおける、勝利の歓喜、英雄的な最後の抵抗、そして崩壊についての語りを紡ぎ出す[5]。それぞれの局面に伴うのは、芸術の社会的なものとの関係とその政治的な先行きについての、ユートピア的な再考の所作である。この点は、芸術が生産、消費、そして議論される際の手立ての再検証において明確なものとなる。
本書は、おおよそ三部構成をとっている。一つは、参加型アートの核となる鍵概念、およびヨーロッパの文脈で今日出版される意義を明らかとする、理論的な導入部である。二つめのセクションは、歴史的なケース・スタディだ。それは、芸術の社会的関与をめぐる今日の議論に深くかかわる問題が、ことのほか焦点として鮮明となる最初の橋頭堡である。三つめおよび最後のセクションでは、1989年以後の時代を歴史的に措定する試みがなされ、そして参加型アートの二つの同時代的な動向へと照準が定められる。
これらの章の全体にみられる鍵となるテーマ――そのいくつかを挙げれば、質と平等性の拮抗関係、単独の作者性と集団的な作者性、また芸術において政治と同等の位置を探し求めるという、なお続く取り組みである。演劇とパフォーマンスは、これらのケース・スタディの多くで重要となる。なぜなら、えてして参加の取り組みは、一定のコンテクストにあって組織化された演者たちの臨場的な出会いにおいて、もっとも力強く表出するものだからだ。願わくは、これらの草が、絵画(グリーンバーグの系譜の言説におけるように)、またはレディメイド(ロザリンド・クラウス、イヴ=アラン・ボワ、ベンジャミン・ブクロー、そしてハル・フォスターの2004年の著作『1900年以降の芸術』におけるように)ではなく、むしろ演劇という視座を通して20世紀の芸術史をあらたに組上に載せる、その気運を生じさせてくれればと思う。さらなる副次的テーマとして、教育と心理セラピーがある。双方は、間主観的な交流に依拠しつつ、プロセスに根ざした経験である。そしてこれらは続く章で、じつにその複数の局面から、演劇とパフォーマンスへと逢着する。
歴史に関する章のうち、最初の章の皮切りとなるのが、以下である。まず、イタリア未来派の夜会セラータ(1910年に端を発する)における、一般庶民の鑑賞者の創出。そしてボリシェヴィキ革命の後年に萌芽した、あらたな機軸となる演劇表現だ。そこで焦点とされるのは、理論、実践、文化政策、そして鑑賞者の受容の間に存在する、断絶だ。これらの闘争的な企ての営為に、1911年の「ダダの季節」が対置されることになる。この当時、アンドレ・ブルトンと彼の同志は、ダダのパフォーマンスの方向性を物議スキャンダルという趣向から引き離すべく、「街頭へと出た」のだった[6]。
これに続く四つの章では、戦後の四つのまったく異なるイデオロギーを背景とする、社会的参加のあり方をみていきたい。その際に目指されるのは、表向きには共通する芸術表現を附帯すると考えられる、異なる政治的取り組みの提示だ。
このうち最初となる第三章では、1960年代のパリに焦点を当てたい。そこでは、シチュアシオニスト・インターナショナルによって創案された、視覚芸術の代替が検証されることになる。このとき彼らの「構築された状況」は、いっぽうで「視覚芸術探求グループ(GRAV)」によって創案された参加型のアクションと、他方でジャン=ジャック・ルベルのアナーキーにして性愛指向のハプニングと対比される。シチュアシオニスト・インターナショナルについての浩瀚こうかんな文献は存在するものの、それらの視点は傾向として偏ってもいる。私の目標は――たとえそれが、このグループが公言する志向やその支持者たちの思惑に逆らうものであっても――シチュアシオニスト・インターナショナルの芸術への貢献を、批評的に読み解くことである。フランスのシーンで、ヨーロッパにおける消費資本主義への応答として解放運動的な領域が示されたいっぽう、南米での参加のアクションは、1960年代半ばに始まった、一連の非情な軍事独裁政権との係累において形成された。アルゼンチンを揺籃の地とする、攻撃的にして断片的な、そして芸術的にして演劇的な表明の手立てが、第四章のテーマとなる。
第五章では、東欧とソビエト連邦をあつかう。そこでとくにみていくのは、1960年代後半と70年代初期における、旧チェコスロバキアの参加形式のハプニングの普及、そして「集団行為」という、1976年に活動を始めたモスクワのグループの表現だ。社会主義を背景とするこの諸例は、「参加が集産主義と同様のものであり、ゆえにそれは資本主義に対立する」といった今日みられる主張の問題点を顕在化させる。これらのケース・スタディは、支配的なイデオロギーにおける集産主義的な教条をいっそう強めるのではなく、以下の点を指摘するものだ。つまり、社会主義国家の参加型アートは、ときに個人の表現のための、プライベート化された領域を切り拓く手段として展開したのである。
計四章の「イデオロギー」に関するもののうち、最後の章では、福祉国家的な社会民主主義における参加に光を当てて、1970年代のイギリスで興隆した二つの画期的な芸術の試みに目を向ける。それは、「コミュニティ・アート運動」と「芸術家斡旋グループ」〔略称、APG〕である。このいずれの動向に関しても、美術史における研究はほとんど進んでいない。ここにおける刺激的な共振作用が引き金となって、引き続く議論が生じてくれればと思う。
本書の第三のセクション、第七章から第九章は、共産主義社会の崩壊後――その時代のヨーロッパでのコンテンポラリー・アートにみられる、ソーシャル・エンゲージメントの興隆を語る切り口を示すところから始めたい。そこで焦点となるのは、左派の構想プロジェクトが政治的な夢想として潰えたと考えられる時代における、ユートピア的であり、内々になされた独創的な試みとしての「プロジェクト」である。そして第八章と第九章の焦点となるのは、コンテンポラリー・アートにおいて広まった二つの参加様式――「委任された」パフォーマンスと教育的なプロジェクトだ。前者では、アーティストの代理としてパフォーマンスを行なうべく一般人が雇われる。後者では、芸術は教育の活動と目標に向けて収斂する。この双方の章の狙いは、プロセス型の参加型アートに含まれる方法論的な意味を理解することと、こうした表現を考察する上でのオルタナティブな基準を打ち立てることだ。本書を締めくくるのは、20世紀を通じての鑑賞者のアイデンティティの変動についての考察である。そしてそこでは、民主主義の芸術におけるモデルが、民主制の実体とあくまで希薄な関係を有することが示唆される。
本書がカバーする範囲は、言うまでもなく網羅的であるとはおよそ言いがたい。多くの重要なプロジェクトや昨今の動向には、触れずじまいである。例えば、学際的な、リサーチ型の、活動家的、ないしは介入主義的な芸術が論及対象とはされていない。その理由の一つには、こうしたプロジェクトでは基本的に、人々の存在が作品の媒体や素材として関与しないということがある。ほかの理由としては、これらはそれ自体で議論すべき一連の問題をはらんでいるが、私は将来的にそれを分けて論じたいということもある。同様に、本書の地理的な範囲についてもはっきりとした線引きがある。それは、歴史的前衛の伝統を中心としている。そしてそれが意味するのは、東欧と南米を含むが、アジアは入らないという判断である[7]。
読者はまた、北米のケース・スタディがやや少ないという印象を持つかもしれない。このリサーチを始めた当初、私は対抗的な歴史の系図を引くことに関心を持っていた。なぜなら、ソーシャル・エンゲージメントについての議論はあまりにも長い間、北米の批評家による北米の芸術についての著述に統べられていたためだ。その著述の基底をなすのは、「ニュー・ジャンル・パブリック・アート」〔アーティストのスザンヌ・レイシーによる概念。アメリカの公共彫刻に対抗する社会的な芸術活動〕、サイト・スペシフィシティ(場の特定性)、対話的なプラクティスだ。私はこれらの議論を保留する。しかしそれは、間接的にその重要性を損ねたいということではない。それどころか、これらについての批評家や歴史家たちの仕事は、本書の領分の素地や、その分析の道具立てとなる諸概念にとって重要である[8]。しかしリサーチが進むにつれ、私は北米の美術史の再論を避けるというナイーブで反主権的な意志の代わりに、より政治的関心に焦点を合わせることにした。ただし最終的には、いくつかの鍵となるアメリカの事例を含めるかたちをとった。本書の背景にあるモチベーションの一つ――それは、ヨーロッパの文化政策で社会福祉制度の解体と相関しながら発展したような参加型アート、その手段化をめぐる徹底した両義性をもととする。新労働党ニューレイバー(1997~2020)のもとでのイギリスの状況にあって、抑制をきかせたソーシャル・エンジニアリング〔政府による大衆の行動規範への操作〕の一形式として、このタイプの芸術がとりわけ活用されたのだ。アメリカの状況は、公的な財政支援がほぼまったく存在しないこともあり、芸術の手段化という問題とのかかわりは本質的に異なっている。
私はこの序論を、人々と社会的プロセスに関与する芸術をリサーチするにあたっての、いくつかの方法論的な特徴によって結ぶことにしたい。一点、明らかなことがある。これらのプラクティスの多くを理解する手がかりとなる記録資料に接するとき、視覚的な分析が充分ではないということだ。参加型アートをイメージのみで理解することは、不可能といってよい。話したり、食べたり、ワークショップに出たり、上映会やセミナーを行なう人々のラフな写真群――それらは私たちに、所与のプロジェクトのコンセプトや状況的背景について、わずかというより、ほぼなにも語らない。それらが提供するのは、せいぜい断片的な証拠だ。アーティストをそれらのプロジェクトの実践へと至らせ、人々をそれらの参加へと向かわせる情動面での動因については、なにも伝えないのだ。これは、どれくらい目新しい問題なのだろうか。1960年代と70年代のコンセプチュアル・アートとパフォーマンス・アートの一部の代表例でも、やはり一過性の経験が称揚されつつ、商品としての物的対象への抵抗が試みられた。ただしこの使命にあっては、視覚性はつねに重要な位置を保っていた。いかに「脱技術化」ないしは「脱主体化」されていようと、コンセプチュアル・アートとパフォーマンス・アートは情動的な反応を幅広く引き出しうる。その記録写真は、抑制された悦び、気まずい当惑、イコン的存在への敬意、または胸が悪くなるような不快さをかき立てる能力を持つ。
いっぽう今日の参加型アートでは――決定的なイメージ、コンセプトや物的対象を超えた――プロセスを前面化させるにあたり、ときに困難が生じる。それは往々にして、不可視のものに価値を置く。例としては、集団の活力、社会的状況、エネルギーの交感、意識の昂揚といったことだ。かくしてその芸術は、直接的な経験によって方向づけられ、長期に(数日、数ヶ月、ときに数年にも)わたることを望ましいあり方とする。長期の参加型プロジェクトの全体を目にする立場にある観察者は、ほんとうにわずかだ。学生や研究者はふつう、アーティストやキュレーター、数える程度のアシスタント、そして運がよければ、一部の参加者が提供する説明を頼みの綱とする。本書の同時代に関するケース・スタディの多くは、試行錯誤となる実地調査の旅行をもとに築かれた。結果として私は、インスタレーション・アートやパフォーマンス、展覧会の批評の書き手としてつねづね慣れていたよりも、このすべての表現がその場でそのときにかかわることを要求するものだとわかった。理想的には、複数回の訪問が必須であり、機会を長期に拡散させるべきものだった。そしてそれは、収入の足りない批評家や忙殺された大学の研究者には手が届きにくい贅沢である。こうした個々のコンテクストや特徴の複雑さは、以下のような結果を招く原因の一つである。つまり、各プロジェクトに責任を持ち、ときに――しばしばアーティスト以上に――一部始終に立ち会う唯一の存在となるキュレーターの手に、参加型アートのおもな語り手としての権利が委ねられるということだ[9]。
この研究の重要なモチベーションとなったのは、こうしたキュレーターたちの語りにおいて、批評的な客観性が排されていることへの私の失望であった。ただし、特定のプロジェクトを何度か旅程の合間に訪れた私は、この末路が批評家にもおよびつつあると気づいた。かかわりが深まるほど、客観的で居づらくなるのだ。とくに、プロジェクトの中心要素に人間関係の形成があり、それが特定の主体によるリサーチに否応なく影響を与えてくるような場合に、である。したがって、懐疑的に距離を置くことから多畳たじょう的関係(imbrication)へと向かう変遷が、本書に底流する視座となる。創り手との関係が強まるにつれて、居心地のよい私のアウトサイダーとしての(非力だが、自身の批評的特権が約束されている)スタンスは、より建設的な流れに沿って再検証される必要があった。
この道のりは、本書に反映されている。あるいは読者は、第一章(その短いバージョンは、2006年が初出となる)の議論と2011年の結論との間にある変化に気づくだろう。本書のタイトルとなる「人工地獄アーティフィシャル・ヘルズ」は、参加型アートの肯定と否定、両方の記述素として作用するよう意図されている。この名前は、公共圏における社会的な乖乱の突出した可能性を訴えた、アンドレ・ブルトンによる1921年春の「大いなるダダの季節」についての事後分析から取られている。このタイトルは、より果敢にして情動的で、そして紛争を辞さない、そうした参加型アートと批評の形式を主張する。ブルトンの分析はまた、次のことを示唆する。すなわち、それがなされた当時に(1921年の「ダダの季節」のように)実験として失敗だと創造主体によって烙印を押された作品が、しかし未来のあらたな状況へと共鳴しうるということだ。この遅発的な触媒のモデルは、私が事例を選ぶにあたっての基礎となっている。それらの事例を含めた根拠は、それらが表現された当時における重要性というより、その今日との関連性である。
学術的な見地からすれば、社会とそこにいる人々に関与するあらゆる芸術は、たとえ全面的にではなくとも、方法論として社会学的な視座を要する。言うなれば当該の芸術の分析は、従来的には人文科学よりも社会科学において普及している概念――コミュニティ、社会、権利の委任、行為主体性など――と交わることが必須となる。参加に対するアーティストの関心の拡大に従って、社会機構と民主主義の範例に関する固有のボキャブラリーが、コンテンポラリー・アートの分析とのあらたな関係性を帯びるようになった。とはいえ、参加型アートは社会的活動というだけではなく、象徴的な営為でもある。そしてこの双方とも、世界に内包されるとともに・・・・そこから一定の距離を置くものだ。したがって実証主義的な社会科学は結局のところ、政治哲学の深遠な考察に比して有用性は低い。この「社会的転回」の方法論的な特性は、コンテンポラリー・アートの展開された場をあつかうにあたり、美術史家や批評家にとって課題の一つとなる。参加型アートは私たちに、もはやたんに視覚性のもとに留められてはいない、芸術のあたらしい分析手段を見出すように求める。ただし伝達手段の重要な基体として、形式・・は存続するのだ。理論と概念は、本書で論じられる表現の分析を目的として、政治哲学からだけではなく、演劇史、行動学、文化政策、建築からも援用される[10]。この融合は、美術史における別の学術横断的な局面(例えば、1970年代のマルクス主義や精神分析学、言語学の援用)とは一線を画している。今日問われるのは、所与の政治的な立場から美術史を書き換える方法論をあつかうということでは、もはやない(ただしそれは、むろん機能はしている)。むしろ問題となるのは以下の点の了解である。つまり、これらの規範を考慮することなく社会を指向する芸術を適切にあつかうことは、不可能なのだ。そしてこの学術横断性は、芸術そのものの目論みや内容と連動(そして、それに由来)しているのだ[11]。
同時に踏まえておくべきなのが、以下の点だ。本書では目標の一つとして、参加型アートへの実証主義的で社会学的な(例えば、実証可能な成果が関心の的となる、文化政策のシンクタンク機関の調査によって提起されるような)アプローチの不十分さが示される。そしてまた、人文科学の特徴となる「質」についての建設的にして開かれた考察の継続、その必要性を強めることも目標の一つとなる。参加型アートの領域では、「質」という語はときに反発にあう。それは、多くの政治寄りのアーティストやキュレーターによって、市場および権力を有するエリートの興味に資するものとして拒絶され、さらに慧眼としての美術史〔の機能〕を想起させるために、損ねられている。さらに進むと、高尚と低級の間の境界を乱すことが声高に言われたり、あるいは別の語が好まれたりする(トーマス・ヒルシュホーンの言葉では、「活力は要るが、質は要らない!」である)。
本書は、価値判断が不可欠であるという前提を基礎とするが、それはエリート文化の外堀を埋めるための、また芸術と非芸術の境域を統制するための手段としてではない。そうではなく、所与の歴史的契機において、私たちが共有している価値を理解して明らかにする方途としてである。一部のプロジェクトは、交錯した表現とその一定の時間や場所、状況内の位相を構想するためのアーティストの能力によって、ほかのプロジェクトよりも明らかに豊かで密度が高く、そして深度をそなえている。喫緊の課題であるのは、社会指向のアート・プロジェクトから生じる概念的にして情動的な複雑さの形式への関心を取り戻すこと、そしてとくに、美学的な質を拒むことを求めるような形式への関心を〔多層的な観点から〕取り戻すことである。その目的は、それらにいっそうの力を与えて、そしてそれらを歴史へと布置することだ。とはいえ、美学の拒絶は過去にいくつもの前例がある。ダダのキャバレーやシチュアシオニストの「転用」、あるいは脱物質化されたコンセプチュアル・アートやパフォーマンス・アートは、独自の制作や拡散の美学を持つものと認識されるようになった。まさにそれと同じように、ときに形式がないかに見える参加型プロジェクトの記録写真は、独自の経験的な体制を有している。重要なのは、これらの反美学的な視覚的事象(読書エリア、自費出版の新聞、パレード、デモ、場所を選ばない合板製のプラットフォーム、人々が写った際限のない写真群)を、あたらしいフォーマリズムの対象とみなすことではない。そうではなく、これらがいかに社会や芸術の生成されていく経験に寄与し、そしてそれを強化するかを分析することが不可欠となる。
第二の方法論的なポイントは、私のリサーチの実践面にかかわっている。私は地理的な範囲について、先に述べておいた。それは国際的だが、グローバルであろうとはしない。ローカルに留まることは、地方主義というリスクを負うことだ。そしてグローバルになることは、希薄化のリスクを負うことだ。言葉の問題は解消されていない。私はケース・スタディを行なう際、かくも多様なコンテクストの一次資料にあたるための言語的な要件を満たしていないという、厳然たる事実にぶつかった。よいか悪いかは別として、英語は美術界の共通言語であり、そして私がこのリサーチの大部分を行なうために依拠した言語である。なおかつ、参加型アートは特性として経験に基づくものであり、正典との関係も希薄であるため、このリサーチの大部分は議論を指向することになる。それは、私のレクチャーを聴講した人々や辛抱強く対話をしてくれた同僚たち、複数の学校の学生たちは言うまでもなく、アーティストやキュレーターとの7年にわたる会話やインタビュー、議論だ。
本書の目的の一つは、協働的な作者性やスペクタクル性の興亡を論じるにあたっての、より細やかな差異をはらんだ(そして率直な)批評の語り口を生み出すことだ。目下のところ、この議論はあまりにも頻繁に、「能動」と「受動」の観客性という無用の二項関係を核に据えてしまっている。より最近では、「悪しき」単独の作者性と「善き」集団的な作者性という、誤った双極性が中心となっている。この二項関係は糾弾されねばならない。そしてまた――私がこれまで参加した、この表現についてのあらゆる公共の議論で開かれたような――「単独の作者性は、おもにアーティストのキャリアや名声を美化するのに役立つ」といった浅薄な意見についても同様だ。こうした批判でなお槍玉に挙げられるのが、参加型アートである。しかし事実はといえば、1960年代後半以降、あらゆる表現分野のアーティストが、異なる人々との対話的で創造的なネゴシエーションにかかわり続けているのだ。そうした人々とは、技術者、職工、キュレーター、公共団体、ほかのアーティストたち、知識人、参加者などだ。音楽や映画、文学、ファッションや演劇といった分野には、共存的な作者性のスタンスを言い表すためのボキャブラリーがふんだんにある(監督、作家、パフォーマー、エディター、プロデューサー、キャスティング代行機関、音響技師、スタイリスト、そして写真家)。そのすべては、所与のプロジェクトの創造性の発揮のために不可欠とみなされる。同時代の視覚芸術には、これらに相当する用語が不在である。そしてその不在は、倫理的な義憤に支えられた卑小な批評の枠組みへと逢着してしまう。
学術的なリサーチも同様に、単独の作者性と集団的な作者性の価値づけのパラドックスにさらされている。単一のテーマについての単著には、論叢よりも高い地位が与えられる。いっぽうきわめて評価の高い研究者が、「相互査読」なる集団の検閲行為に服している。私はこのリサーチが従来どおりの形式であり、そして展覧会やDVD、ウェブサイトやアーカイブ、あるいはより協働的なかたちでの成果ではなく、単一のテーマについての研究書となることを、強く意識している[12]。他方で、このテーマをめぐるアンソロジー的な論叢や展覧会カタログはすでに多く存在するものの、そのうち継続的な議論を打ち出すものはわずかだ[13]。私たちは、すぐれた芸術や作者性のための不変の秘訣といったものはないということを心に留めておくべきだろう。ロラン・バルトが1968年に私たちに教示したように、あらゆる種類の作者性は多重的であり、そして継続的に他者の存在に依拠している。
重要なのは、これらの相互作用からもたらされる、発想、経験、可能性である。本書の中心課題は、参加型アートを語るための――そしてたんにプロセスに目を向けるのではなく、むしろ参加型アートが創出するものの意味に重点的に取り組む――方法を見出すことだ。この結果となる媒介的な対象、コンセプト、イメージやストーリーは、アーティストと二次的な鑑賞者の間にある、必要不可欠な紐帯だ。そしてこの二次的な鑑賞者とは、あなたや私、そして参加しなかったほかのすべての人々である。私たちが紛れもなく存在しているということは、歴史的事実だ。そしてこの歴史的事実は、たとえ、そしてとりわけ、参加型アートがこれを否定しようとするときにさえ、観客性の政治学を分析することを必要とするのだ。
[註]
1:「フランシス・ベーコンはソーシャリー・エンゲージド〔のアーティスト〕で、ウォーホルもそうです。画家であれ彫刻家であれ、良いアーティストというのは社会に関与しています」(若者による2005年4月12日のジェレミー・デラーへのインタビュー)。
2:例えばブリオーは、リレーショナル・アートが「自主的かつ私的な・・・象徴空間の主張ではなく、 むしろ人間の相互交流とその社会的コンテクストの領域」をその理論的地平とすると言う (Bourriaud, Relational Aesthetics, Dijon:Presses du Réel,2002,p.14.)。しかし、彼がその言説から離れたところで支持するアーティストをみると、そうしたアーティストはさほど間主観的な関係性や社会的コンテクストに関心を抱いていないことがわかる。彼らが関心を向けるのはむしろ、視覚提示法や一過性の状況、フィクション、デザイン、あるいは「シナリオ」の体系的に遍在するような観客性である。本書の端緒となるのは、『関係性の美学』に対する私の以下の批判である。’Antagonism and Relational Aeschetics’,October,110, Fall 2004,pp.51-79.〔クレア・ビショップ「敵対と関係性の美学」星野太訳、『表象 05』、表象文化論学会、月曜社、2011年、75-113 頁〕
3:例えば、ポートランド州立大学とカリフォルニア美術大学の「アート・アンド・ソーシャル・プラクティス」の美術学修士コース。また、カーネギーメロン大学(ピッツバーグ)の「コンテクスチュアル・プラクティス」の同コースなどがある。また、ニューヨークの「芸術と社会変革のためのレオノーレ・アネンバーグ賞」が2009年に、そしてイタリアのエミリア=ロマーニャ州の振興による「参加型アート国際賞」が2011年に発足された。
4:Claire Bishop, ‘The Social Turn: Collaboration and Its Discontents’,Artforum, February 2006,pp.178-83.
5:この3つの要素からなるイデオロギー構造は、本書であつかう〔以下の〕2つの地域にはさほど該当しない点に触れておかねばならない。アルゼンチンにおける1968年という年は(アーティストはフランスでの謀反を知っていたし、彼らの作品内で言及もしたのだが)左派改革で はなく、むしろ軍事的圧制(オンガニーア独裁政権)への抵抗に関与している。ニコラス・グァニーニはこう述べる。「どちらかというと、南米の年代記述はブラジルの1964年の軍政令第5条と1990年のアウグスト・ピノチェトの退陣の間を範囲として変動しています。68年に至る まで南米社会が経験したのは、圧制です。この亜大陸でのそれ以降のすべての表現(「芸術集団活動グループ」、「ヴィーナス・プロジェクト」、「エロイーサ・カルトネーラ」、シシド・メイ レイレスの介入行為)は、独裁政権、ヘンリー・キッシンジャーの政策、コンドル作戦などが破壊した社会的連携の再構築を目指しています」(グァニーニから著者へのメール、2010年 10月8日)。旧チェコスロバキアにおける1968年は、ソビエト侵攻といわゆる「正常化」の始まりを意味する。対照的に旧ユーゴスラビアにおける1968年とは、信頼に足る共産主義の政体への学生の要求の年であった。このように、この地域におけるより重要な時局は、1968年ではなくむしろ1947年のソビエト圏の形成であるだろう。
6:André Breton, ‘Artificial Hells, Inauguration of the “1921 Dada Season”‘,October,105,Summer 2003,p.139.
7:行なった調査旅行には、リクリット・ティーラワニットとカミン・ラーチャイプラサートの《ランド》(チェンマイ)と、ルー・ジェの「長征基金」(北京)がある。しかし、双方のプロジェクトの主導者は西欧圏で教育を受けてはいるが、これらは私の言説上の視点に適合することはなかった。
8:主要文献として以下が挙げられる。1990年代初期の「ニュー・ジャンル・パブリック・アート」に関する議論(メアリー・ジェーン・ジェイコブ、スザンス・レイシー、マイケル・ブレンソン)。芸 術とアクティヴィズムについてのテクスト(ニナ・フェルシン、グラント・ケスター、グレゴリー・ショレッテ)、そしてパブリック・アートとサイト・スペシフィティへの理論的アプローチ(ロザリン・ドイチェ、ミウォン・クォン)。これらの著者のうち、私がもっとも〔その言説に〕負っているのはロザリン・ドイチェである。
9:ウォーカー・アート・センター(ミネアポリス)でのキュレーターと教育部門のスタッフとの組織内の対話から、多くの事例が浮かび上がった。アーティストは別の展覧会の作業を理由に離れるとき、自身の共同プロジェクトの継続を教育部門に任せていたのだ(ウォーカー・アート・セン ターでのディスカッション、2008年10月31日)。
10:例として次を参照。Jeremy Till, Peter Blundell Jones and Doina Petrescueds,Architecture and Participation, London: Spon, 2005.
11:芸術の社会科学への言説上の転回は、1990年代後半以降の多くの展覧会の「読本」に反映されている。そこでは、従来のカタログの形式(美術史の論考、質のよい図版写真、そして展示作品についての記述)が排されている。これに関して決定打となったものに、グループ・ マテリアルの『デモクラシー』(Group Material, Democray [Seattle:Bay Press,1990])、 そしてマーサ・ロスラーの『ここに住むとして』(Marcha Rosler,If You Lired Here [Seattle:Bay Press,1991])がある。またペーター・ヴァイベルによる、1993年のヴェネチア・ビエンナー レのオーストリア館のカタログもこれに該当する。
12:実際にこのリサーチにとっての理想の形式は、授業(seminar)である。教室での討論と分析の持続的な動因によって、テーマは活力を保ち、書籍におけるよりはるかに対抗の場面に遭遇し続けることになる。
13:次を参照。WHW(eds.), Collective Creativity, Kassel: Fridericianum,2005; Blake Scimson and Gregory Sholetce(eds.),Collectivism After Modernism:The drt of Social Imagination After 1945,Minneapolis: University of Minnesota Press,2007; Johanna Billing,Maria Lind and Lars Nilsson(eds.),Taking the Matier into Common Hands: On Contemporary Art and Collaborative Practices, London:Black Dog Publishing,2007;Charles Esche and Will Bradley(eds.),Art and Social Change:A Critical Reader, London:Afterall and MIT Press,2007.
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。