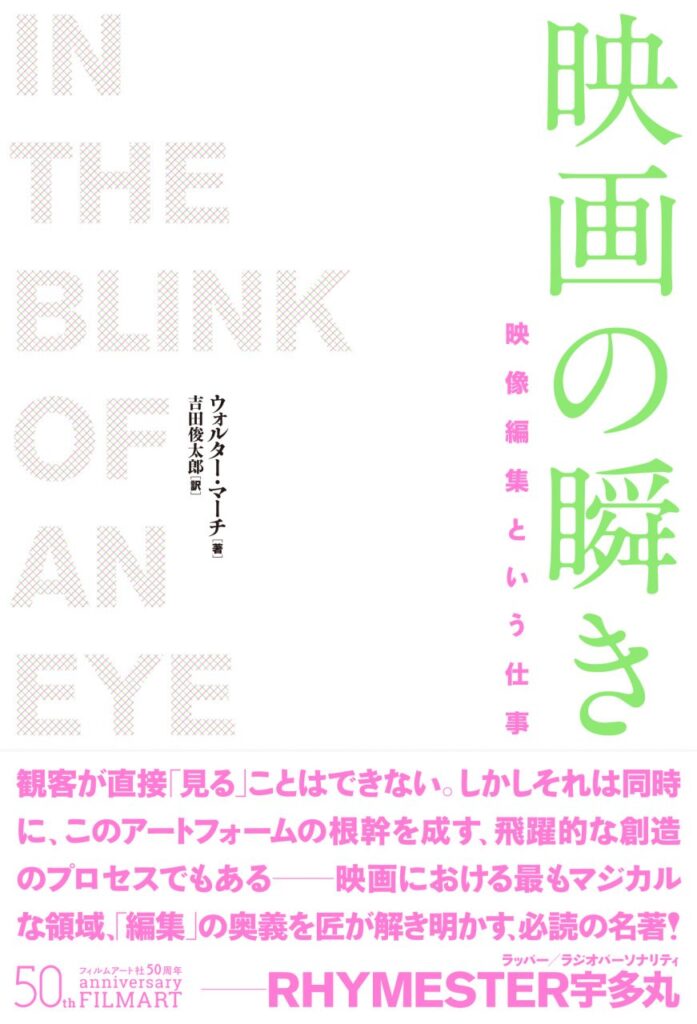Cuts and Shadow Cuts
作品の影にあるもの
極端な例を観察した方が、その事物の本質をよりよく理解できるということが多々ある。たとえば水について知ろうとするなら、水そのものよりも、氷や水蒸気からの方が、より水の本質を見極めることができたりするだろう。映画作品について、それが作られる価値あるものであれば、どれもこれも独創的に違いないし、世の中には実にさまざまなタイプの映画があるのだから、そもそも「標準的」な映画などという表現はおかしいのかもしれない。それでも、たとえば『地獄の黙示録』(79)などは、あらゆる映画製作の側面(スケジュール、予算、芸術性、技術)において極端な作品、つまり映画における氷や水蒸気に相当する作品のひとつとしてあげることができると思う。完成までに費やされた期間だけをとっても、私がこれまで関わってきた数ある作品の中で群を抜いて長いポスト・プロダクション(以下、ポスプロ)を経ている(映像編集に1年、サウンドの下準備とミキシングにさらにもう1年を費やした)。それだけ極端だからこそ、この作品を振り返ることで、かえって「標準的」な映画作品とはどんなものなのかが見えてくるのではないだろうか。(注1)
編集作業がここまで長期になった理由のひとつは、撮影された素材の量が膨大だったことだ。プリントされたフィルム125万フィートは時間にして230時間あまりに相当する。完成品の長さが2時間25分弱なので、完成作品の1分間につき95分間ぶんの「日の目を見ない」映像が存在する計算になる。ちなみに通常の長編映画における比率は1分につき20分(1:20)が平均とされている。
比率1:95の世界の旅は、奥深い森を進んでいたら唐突に視界の開けた草原に出くわし、しばらくしてまたふたたび森の中に突入して行くような感じだ。たとえば例のヘリコプター部隊の爆撃シーンのように、撮影された素材の量が異常なほど多かった部分もあれば、逆に撮影量がずっと少ないシーンもあったわけだ。あのキルゴア大佐[ロバート・デュバル]のシーンは確かフィルムにして22万フィートも撮られていたと思う。でも完成作品では、わずか25分程度使用されただけであり、その比率はおよそ1:100にのぼる。一方で、小さなシーンの多くはマスター・ショットのみでしか撮られていない。つまりコッポラ監督は、大きな核となるシーンに大量のフィルムと時間を注ぎ込み、その代償として繋ぎのシーンなどは必要最小限の映像を撮影するにとどめていたのである。具体的なシーンを挙げて説明してみよう。ワーグナーの「ワルキューレの騎行」が流れる中「チャーリーズ・ポイント」をヘリコプター部隊が襲うシーンは、ひとつひとつの動きが綿密に演出された数々のショットから成っているのではなく、どちらかと言えばドキュメンタリー的な手法で、実際に目の前で展開されていることを随時撮り進める形で振影されたものだ。それは多くの人員と機材とキャメラが広大な空間で展開する舞踏であり、一度ネジを巻いて手を離したら勝手に動き出して制御することのできない、あのいまいましいオモチャのようなものだ。コッポラ監督が「アクション」と叫んだ瞬間から、本物の戦闘さながらの光景が展開され、その模様をひたすらキャメラに撮り収めていく。地上とヘリコプターに配された8台のキャメラが一斉に回され、それぞれが1,000フィート(11分間)のフィルムを積んで撮影される。
それが1回終わるたびに、特に問題がなければ、今度はキャメラ・ポジションだけを変えて、同じことが最初から繰り返される。さらにキャメラ・ポジションを変えてもう一度、そしてもう一度、またもう一度。素材として必要なだけ撮れたと監督が納得できるまで作業は繰り返され、結果的には一度の撮影で1テイクにつき約8,000フィート(1時間半)費やされた。しかもひとつとして同じテイクはない。これはドキュメンタリーとまったく同じ状況である。
作品が完成して無事に劇場公開までこぎつけた段階で、私はやっと一息つき、私たち(編集者)の作業比率を計算してみた。全部で何日間働いたかを数え、それを完成品のカット数で割り、編集者1人が1日に編集するカット数の割合を計算すると、なんとたったの1・47カットという答えが出た!
それはつまり、もしも完成品がどのように編集されるのかを最初から「完璧に」知りつくした上で編集室に同じ日数だけ通っていたとしたら、1日わずか1回半フィルムを繋いだだけということを意味する。言い換えるなら、朝から自分の席でフィルムを一箇所だけ繋ぎ、次のカットについて考えたら帰宅し、翌日またやって来て前日考えた部分を一つ繋いだらまた帰宅するということを繰り返せば、同じだけの日数で映画が完成するという計算だ。
フィルムを1回半繋ぐという物理的な作業が10秒たらずで出来てしまうことを考えれば、編集者たちは、映像を「切って繋ぎあわせる」という具体的な作業よりも、そのための「道筋を見いだす」ために多くの時間を割いているという事実が、この『地獄の黙示録』の極端な例で鮮明に浮彫りになったと思う。もちろんこの事実は「標準的」な映画でも同じように当てはまる。(注2)撮影された素材が多ければ多いほど、当然ながら、熟考すべき道筋や相互的な可能性がいくつも増え、結果として、答えを導きだすためにより多くの時間が必要になる。これは撮影した素材の多いあらゆる作品に言えることだけれど、こと『地獄の黙示録』に関しては、そのデリケートなテーマ性や大胆かつ独創的な構成や革新的な技術など、あらゆる要素が相まって、ベストをつくさなければならないという重圧を他の作品以上に感じさせられていたことも確かだ。そこにはまた、これが巨額な予算で巨大なキャンバスに描かれた映画であるにもかかわらず、フランシス・コッポラのきわめて私的な作品だったという事実も大きく作用している。あれほどのクオリティと野心が同時に存在する映画には、残念ながら、そう滅多にお目にかかれるものではない。
完成作品におけるフィルムのカット(繋ぎ)1つにつき、「陰の」カット(一度は繋いで検討した結果、繋ぎ直しや削除となったもの)がおそらく15はある。それを計算に入れたとしても、1日のうち11時間58分は、フィルムを切って繋ぐという物理的な作業ではないものに費やされている。明確な道筋を探り出し、試写をし、話し合い、巻き戻し、再び試写をし、会議を開き、スケジュールをたて、フィルムのトリミングをし、ノートをとり、記録をつけ、それ以外にも数々の熟考を要する問題に頭を悩ませる。フィルムのカット(繋ぎ目)、それは、あるショットから次のショットへと転換する瞬間であり、見た目にはシンプルで無頓着、願わくは誰にも気づかれないくらいでなければならないものだけれど、フィルムを切り繋ぐというこの地味ながらも重大な作業にたどり着くまでには、これほど周到な下準備が必要なのである。
(注1)しかも私がこの作品に参加したのはかなり後になってからだ。撮影終了の数カ月後にあたる1977年8月に私が加わる以前、リッチー・マークスとジェリー・グリーンバーグ9ヵ月間の編集作業をすでに行なっていた。私が入ってからジェリーが抜ける1978年の春まではこの3人で、またジェリーが抜けてからはリサ・フラックマンが加入して3人体制で続けられた後、私がサウンドトラックの作業に入るため途中で抜けている。
(注2)ちなみに通常の劇場用長編映画における1日の平均編集カット数は8程度。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。