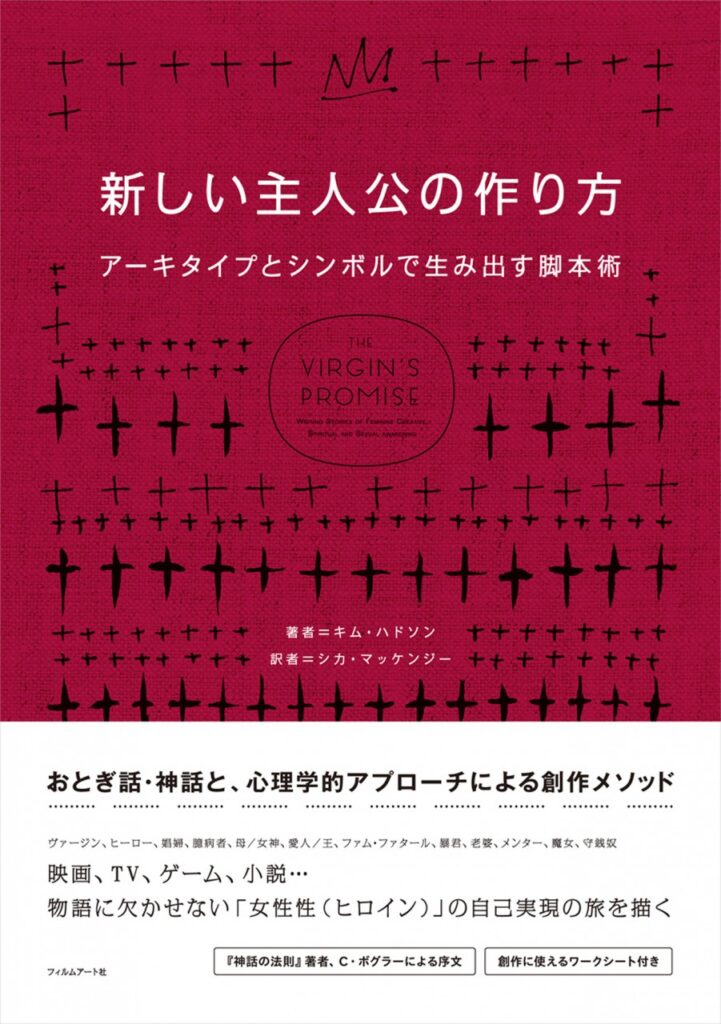序文 クリストファー・ボグラー
ジョーゼフ・キャンベルは著書『千の顔をもつ英雄』で、物語には英雄の旅というパターンがあると指摘した。英雄の旅は私たちの人生にも当てはまり、読者や観客の感情や願望にはたらきかける。そのため、ストーリーテラーやアーティストのロードマップとして重宝されてきた。普遍的で万能であるため、移動や転居や起業など、人生の転機を乗り切るためのガイドブックとされてきた。
しかし、このアプローチには何かが不足している感が拭えない。ほんの少しだけだが、観点が男性寄りなのである。私は性別にとらわれず、できるだけ中立的な解釈を心がけているけれど、やはり「偏っていませんか」とのご指摘を頂く。そしてある時、私は気づいた。英雄という言葉からして男性寄りなのである。私の講義を聞く人も、英雄という言葉からアクション映画や戦隊もののヒーロー、軍人を想像しがちであるようだ。女性の方々は「男が何かを勝ち取りにいく話はわかったわ。じゃあ、女はどうなの?」とお思いになっているだろう。
私には、よい答えが浮かばない。私は男だし、男の視点でものを見る。もしも私が女性だったら、などと想像しても正確なところはわからない。そこで私は、マリー=ルイズ・フォン・フランツやマリヤ・ギンブタス、モーリーン・マードック、キャロル・ピアソンといった女性研究者に目を向けた。女性の神話的アーキタイプや成長過程について、彼女たちは独自の見方をしていることがわかった。本書の著者キム・ハドソンは、女性の旅は言葉どおりの「旅」である必要はないと述べ、むしろ内面的な成長プロセスに注目している。またモーリーン・マードックは女性の体験の節目をアウトラインにし、パターンを独自に定義した。だから私は「女性の旅は?」と尋ねる人に、マードック氏の著書をお勧めしている。
だが、もっともっと女性のアーキタイプの研究が広がればよいのに、という思いが残った。社会学者やセラピストの見解をストーリーテリングや映画脚本術に応用できれば特にありがたい。私は機会あるごとに、ドラマや人生のパターンに女性版があるとしたらどんなものか、理論にまとめてほしいと呼びかけた。
私の声に応えてくれた人々の中に、ロマンス小説作家たちがいた。みな英雄の旅を学び、テンプレートとして生かしているという。自分の人生に重ね合わせながら、女性を描く時には独自に手を加えたり言い回しを変えたりするそうだ。英雄の旅の要素のある部分は強調し、他は控えめに。あるいは業界や観客、読者にふさわしい用語に言い換えたり、自分の好みの表現に言い換えたりしているらしい。そうした自己流アレンジもまた、ジョーゼフ・キャンベルの考えにふさわしい。英雄は千の顔を持ち、幾多の解釈を生むはずだから。そして「ストーリーは変幻自在でありながら驚くほど不変であり、これから新しく語られることよりもまだ多くが残っていると常に思わせられる」(ジョーゼフ・キャンベル「千の顔をもつ英雄」)。変幻自在の形の中には、女性ならではの表現がたくさんあるに違いない。
映画脚本へのアプローチに男女の違いがあるとしたら、その一つは構成ではないかと私は睨んでいた。ドラマを展開するには、どのような構成が効果的なのか? たとえばシド・フィールドは図を使って説明している。線路のように直線を描いて説明してもよいし、ピラミッド型か放物線のようなカーブで表してもよい。私はジョーゼフ・キャンベルにならい、円を描いて説明している。だが女性のドラマを説明するとしたら、いくつもの円の連続か、らせん形が適しているのではないだろうか。外の世界へ飛び出していく男性キャラクターと違い、女性キャラクターは段階的に、内的な世界で成長するようだ。女性ヒーローはいろいろな円を持っており、それぞれの円の中心へ向かっていくように思える。円が表すのは父母、他の女性、男性、子供、神や女神などとの関係だ。そして最後に自己の本質へと向かっていく。それぞれの円で学んだことを生かしながら、らせんを解きほぐして戻ってくる。そうして女性キャラクターが体験することは、英雄の旅と似たようなことなのだろう。だが、男性キャラクターが冒険や身体的な危機に直面する一方、女性キャラクターは人間関係への関与が大きいようである。
そんな考察をしながら、どなたか女性の視点からドラマのしくみを解明してくれないかと願っていた。あなたのお手元にあるこの本が、その取り組みをしてくれている。
本書を読んで、男性の視点と異なる語り口と思考に驚いた。著者ハドソン氏はヒーローに対するヒロインといった呼び名をあっさりと捨て、「ヴァージン」というアーキタイプを提案している。大胆でユニークな試みだ。本書に出てくる用語の多くは英雄の旅に置き換え可能で、中には女性的な側面を強調しただけのものもある。一方、英雄の旅にない独自の見解もある。女性ならではの、ドラマや人生に対する内的で感情的なアプローチがなされている。男性キャラクターにヴァージンの旅を当てはめて論じている部分もあり、ヴァージンの男性版は「プリンス」と呼んでもいいそうだ。
プリンスと言えば、私が仕事でよく出会うハリウッドの御曹子たちが思い浮かぶ。プリンスの物語と言えば、道楽息子のハル王子が屈強なヘンリー五世に成長するさまを描いたシェイクスピアがさきがけか。王国を受け継ぐ者たちのアーキタイプを探ることは、非常におもしろいことだと心から思う。
本書の著者は、正反対の特徴を持つアーキタイプを比較し、図式化して洞察を導き出している。たとえば、ヴァージンの反対は娼婦。二つのアーキタイプがどう関係し、互いの映し鏡になっているかを見せてくれる。また、ヒーローの反対は臆病者。私はこれを悪者とかシャドウと呼んでいるが、臆病者と呼べばヒーローの勇敢さがよりよく伝わり、悪者やシャドウの本質をも言い当てる。彼らは正義のための自己犠牲などしない。身勝手で利己的な行動に走るのだから「臆病者」がぴったりだ。
本書を読み、何度私は自分の無知に打ちひしがれたかしれない。著者のリサーチは非常に丹念だ。難しくなりがちなアーキタイプや心理学の理論について、これほどすっきり明確に書かれたガイドブックは他に例をみない。前にも述べたとおり、男女のアーキタイプのバリエーションがうまく図式化されており、人生の各ステージにおけるプラスとマイナスの可能性も示されている。これだけでも価値がある上、さらに多くの宝が詰まっている。たとえば、おとぎ話と神話の違いについての画期的な発見。おとぎ話は女性的で家庭的、身近な世界で展開されるものが多い。それに対し、神話には男性的なエネルギーが強く見られる、というのが著者の見解だが、独断的にならず、例外も多数紹介してくれている。ヴァージンのコンセプトを理解する鍵をここに見出しながら、女性の物語を紡ぐのに必要なニュアンスを引き出していく。
本書はジョーゼフ・キャンベルや私の著作と並行して読めるように書かれている。英雄の旅を否定せず、むしろ大きなシステムの一部として眺めることが可能になっている。ぶつかりあうのではなく、互いに補完するものとなっている。ヴァージンとヒーローとを比較すれば、創作のためのツールが完璧に揃うだろう。 私は常に、脚本家や小説家は多くのツールを持つようにと勧めてきた。可能性を広げるための言語も豊かに持つべきだ。人間のあり方を一つの考え方で語り尽くせるわけがない。多くのテンプレートやモデル、用語や表現方法が創作には必要だし、他のアーティストに伝える時にも必要だ。この本には用語やツールについての記述も多く、考えを深めるきっかけを与えてくれるだろう。たとえば、私は英雄の旅は男女の区別なく中立的なものだと考えてきた。キム・ハドソンが女性に特化した考察をしたのだから、今度は誰かが男性に特化したセオリーを見出すべきかもしれない。
新たな理論の出現を待つ間、この本で現状にある隙間を埋めるとしよう。最後に一点、特筆しておきたいことがある。本書では「光」が一貫して使われている。著者が提案する十三のステージのうち、「輝くチャンス」「輝きの発覚」「光の選択」の三つは光そのものを示す表現だ。そしてセオリー全体にも光のコンセプトが散りばめられている。「ギリシャの女神アフロディーテが輝く美しさで知られているように、内面からにじみ出る美は『輝く』『光る』『つややかな』『まばゆい』『きらめく』といった言葉で表現されます……つまり、ヴァージンの美は魂の輝きを表します」。この本も女性の人生体験の神秘に光を当て、脚本家やストーリーテラーに恵みを与えてくれるに違いない。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。