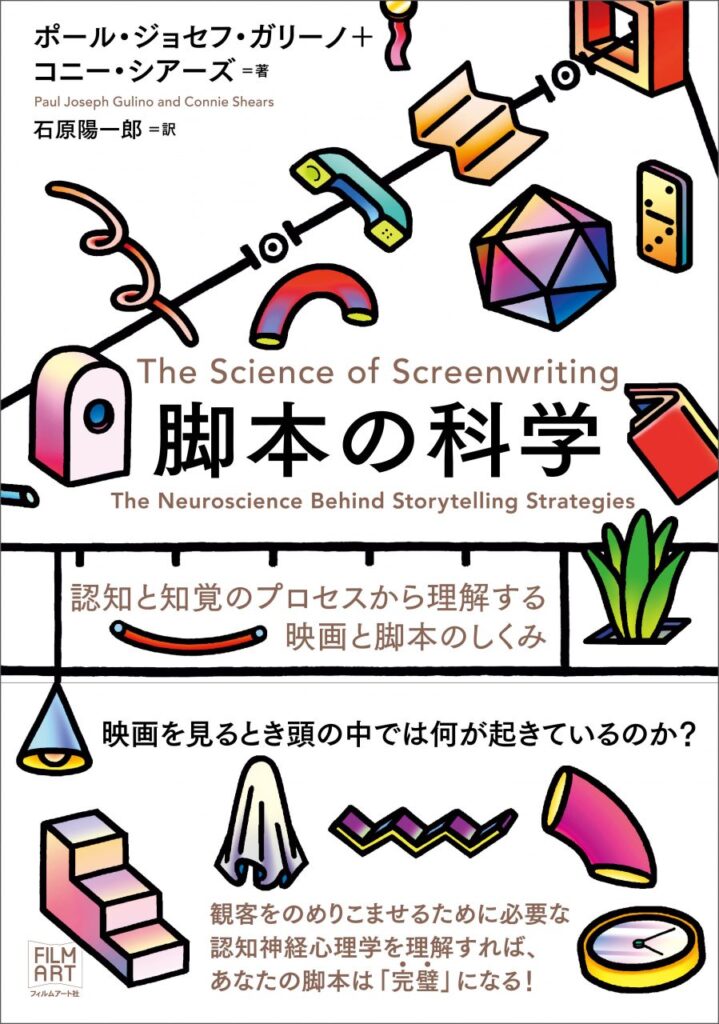イントロダクション
あるいは、私は猫を救ってヒーローを旅立たせるべきであろうか?
創造的な芸術は、豊かで、一見したところ無限の広がりをもつように思えるが、ひとつひとつは狭い生体のチャンネルを通して人間の認知のフィルターにかけられる(1)
――エドワード・O・ウィルソン
多くの脚本の入門書や講座、セミナー、講演、ブログ、動画、フェイスブックのページは、宇宙の膨張よりも急速なスピードで拡大しているようにみえる。アドバイスはいたるところに転がっており、そのそれぞれは互いに矛盾していることが多い。単一神話(モノミス)があったかと思えば英雄の旅(ヒーローズ・ジャーニー)があり、プロットポイントがあるかと思えば十七のステップ(さらには二十二のステップ)があったり、三幕だったり、四幕だったり、七幕だったり、ゼロ幕だったり、という具合だ。
本書は、この情報の洪水を泳ぎ渡るための、より深いレベルでの理解に関わる問題を探る試みだ――すなわち人間の生理学および心理学のレベルのことだ。脚本を読んだり映画を見たりしているとき、読者や観客の脳内で進行している認知や知覚のプロセスはどのようなものなのか? 脚本家/映画監督はどのようにこうした脳のプロセスの知識を活用して、より効果的で感情的にインパクトのある題材を生み出すことができるのだろうか? 脚本家や映画監督はいつ「ルール」に従い、いつルールを破ればいいかをどのようにして知るのだろうか? そしてこうしたルールはまずどこから出てくるのだろうか?
本書は、どのようにして人間の脳のプロセスが視聴覚的情報を処理するのかということについての役に立つ知識を読者に紹介する。そしてどのようにして映画が観客に影響を及ぼし、なぜ成功した映画はいくつかのパターンに従う傾向をもつのか、そして、観客が脚本あるいは映画をどのように知覚するかについてどんな科学が教えをもたらしてくれるかについてのユニークな理解の方法を伝授する。私たちはまず、観客がメインキャラクターや、状況説明や、原因と目的や、場面の構成と緊張や葛藤とどのように関係しているかについて一般的に通用している原則を調べ、その後で、こうした原則の科学的根拠を掘り下げて考えることにするつもりだ。これは脚本家や映画監督が使うことのできる効果のある戦略と、またそれをどのようにして効果的に実現するかについての科学の教えに基づいた1クラス上の脚本入門書である。人間の知覚の限界と観客の脳の無限の認知的プロセスを理解することは、いろいろな伝統的なツールを完全に混ぜ合わせクリエイティブに活用する助けとなるだろう。
本書は医学部進学課程の学生向けではない。脳外科は敷居の高い職業だが、本書を読了すればのスペシャリストになることを恐れる必要はなくなる。脳はあらゆる生体器官のうちでもっとも複雑かつ神秘的なものだが、すべてが一つの目的のためにできている――生命を維持することだ。脳機能イメージング(*)全盛の現在、誰もが脳に対する意識の高い消費者になっている。誰もが脳科学者になっているとはいわないまでも。脳回と脳溝――大脳皮質の奇妙な隆起と襞のこと――の絡み合いは、テクノロジーのおかげで鮮やかなカラーで見ることができるようになっている。このテクノロジーのおかげで今では脳の持ち主がまだ存命で元気なうちに、フルに機能している脳を研究できる。(画像に面食らってはいけない――生きている脳はくすんだ淡いグレーであり、素敵なイエローでもブルーでもない。けれども、ちょうど脚本が白いページにくっきりとした黒い文字で書き出されるように、脳機能イメージングの画像は構造上の違いがわかるようにさまざまな色を使って細部が巧妙に描きこまれているのだ)。本書は脳の機能にフォーカスを当てているが、脳の構造にはそれほど当てていない。結局、あなたが理解したいのは、観客がどのようにあなたの作品を評価するかであって、どのように電子が脳のシナプスの中のカルシウムチャネル〔細胞の生体膜にあり、細胞内の電位を調整するためにイオンを流出入させる経路となるタンパク質の層〕を刺激するかではないからだ。
第1章では、脳が世界についての知識からではなく、世界についての手がかりから現実をどのように構築しているかを示す。その手がかりを、脚本家と映画監督は強力な効果を出すために操作することができる。第2章では、生き残ることを何よりも優先して考えるという脳の性質を探る。脳のこの性質ゆえに、観客はキャラクターと感情的な絆を結ぶのだ。さらにこの章では、「キャラクターアーク」〔ストーリーが進むにつれて登場人物に起きる内面的変化〕という概念の進化論的な根拠を探り、ヒーロー(英雄=主人公)が果たしてストーリーの中の一員になっているかどうかを理解する。第3章は観客の感覚器官をざっとひとめぐりしてみるが、さまざまなかたちをとったコントラストの使用が、どのようにして映画監督と脚本家が直面する最大の危険を避けるために役立つかということに注意を向ける。その危険とは、観客を眠らせてしまうことだ。第4章は「インフォダンプ」の使用と乱用について、および、どのように作り手自身が状況説明に楽しみを味わうことができるのかについて論じる。第5章では、人間の認知能力の根本的な不思議が紹介される。この章では因果関係に沿って世界を理解したいという人類のやみがたい衝動と、観客に筋をたどらせるにはどうすればよいかが考察される。第6章では注意力が入念な取り扱いを要する貴重で便利なものとして論じられ、第7章は葛藤をテーマにする――一体なぜ私たちは実生活では葛藤を避けるのに映画ではその誘惑に逆らえないのだろうか? 第8章では、注意を観客の脳から脚本家と映画監督の脳へとシフトさせる。クリエイティブな能力は生活のスキルとして役に立つのだ。第9章では、脚本を科学的に解明するいくつかのアプローチを試みる。最後に第10章で、それまでのバラエティに富むレッスンを総ざらいして、どのようにジョージ・ルーカスが『スター・ウォーズ』であれだけの儲けを叩き出したかを理解する。願わくばあなたも儲けにありつけますように。
本書は主として映画にフォーカスを当てるが、ときにはストリーミング配信もしくはテレビの連続ドラマから事例をとっている。連続ドラマを視聴するときの知覚および認知のプロセスは、映画を鑑賞するときに用いるものと基本的に同じである。
ボーナスとして、そして科学の精神に則って、各章の末尾に知覚と認知のDIY用の実験を載せてある。
コミュニケーションとパフォーミングアーツの哲学者イネス・アドルネッティ(2)は、ホモ・サピエンスにおける言語の発達そのものがストーリーを物語る必要性から生まれたと指摘している。私たちの前頭葉が(地球上のその他の生物に比べて)桁外れに大きなプロポーションに進化したのは、人間の言語能力に密接に関係している。アドルネッティによると、道具の使用や出来事の前後関係を説明する必要が、ことばで説明する必要、物語る必要を生み出した。なんらかの変化や目標への到達という結果を説明するには、ものごとを順序立てなければならない。そんなわけで、ストーリーというものは説明の必要から、人間ならではのコミュニケーションの方法として生まれたのだ。本書そのものが言語というツールと同じように、あなたにとって強力なツールとなればうれしいと思う。
(*)脳機能イメージング
生きている人間の脳内の各部位の生理学的な活性を測定して画像化すること。脳の各部位がさまざまな精神活動においてどのような機能を担っているかの研究資料になる。
原注
(1)Edward O. Wilson, The Social Conquest of Earth (New York: W. W. Norton, 2012), p. 268.〔エドワード・O・ウィルソン『人類はどこから来て、どこへ行くのか』(斉藤隆央訳、化学同人、2013年)、321頁〕
(2)I. Adornetti, “On the Phylogenesis of Executive Functions and Their Connection with Language Evolution,” Frontiers in Psychology (2016), doi:10.3389/fpsyg.2016.01426.