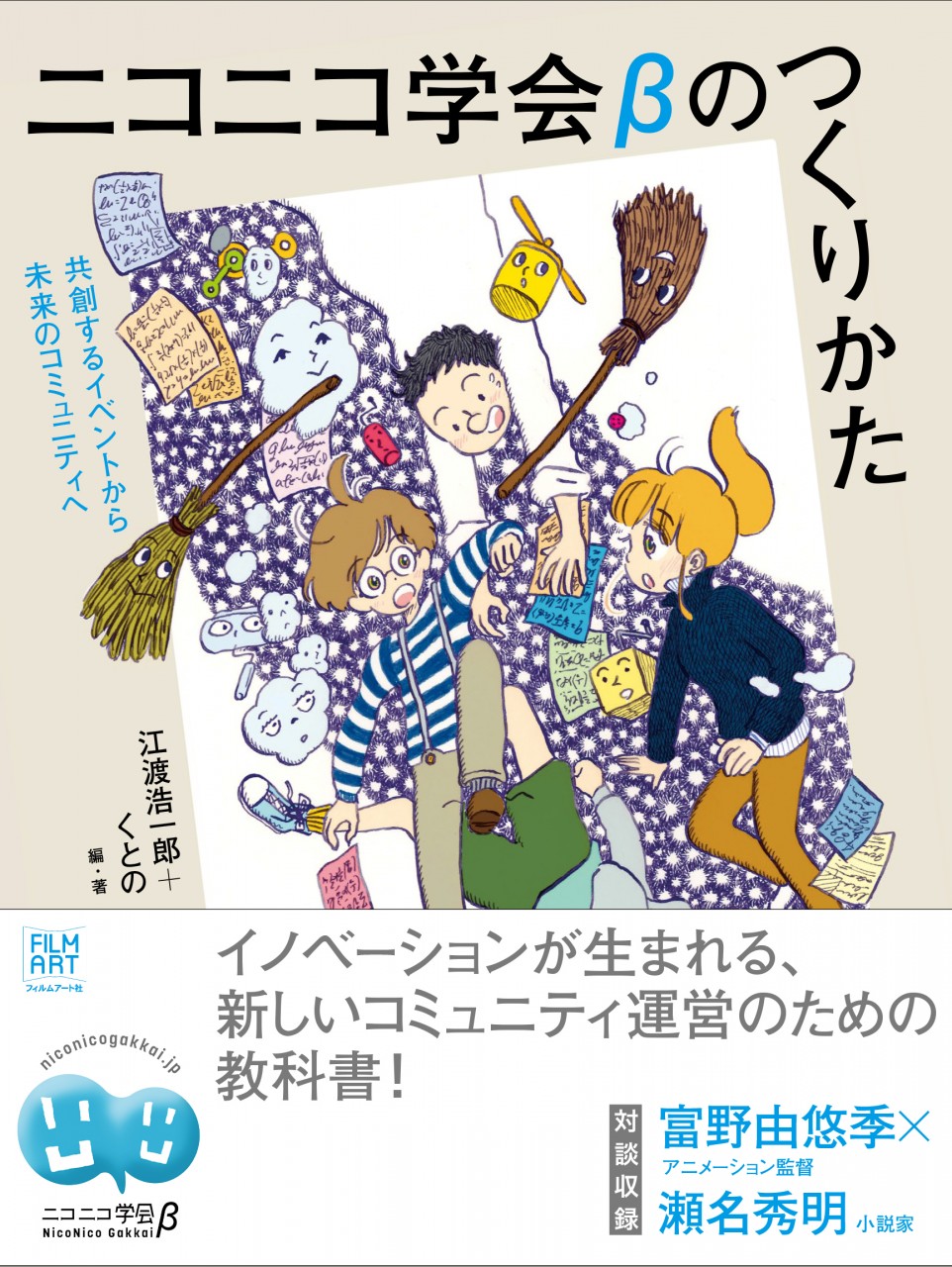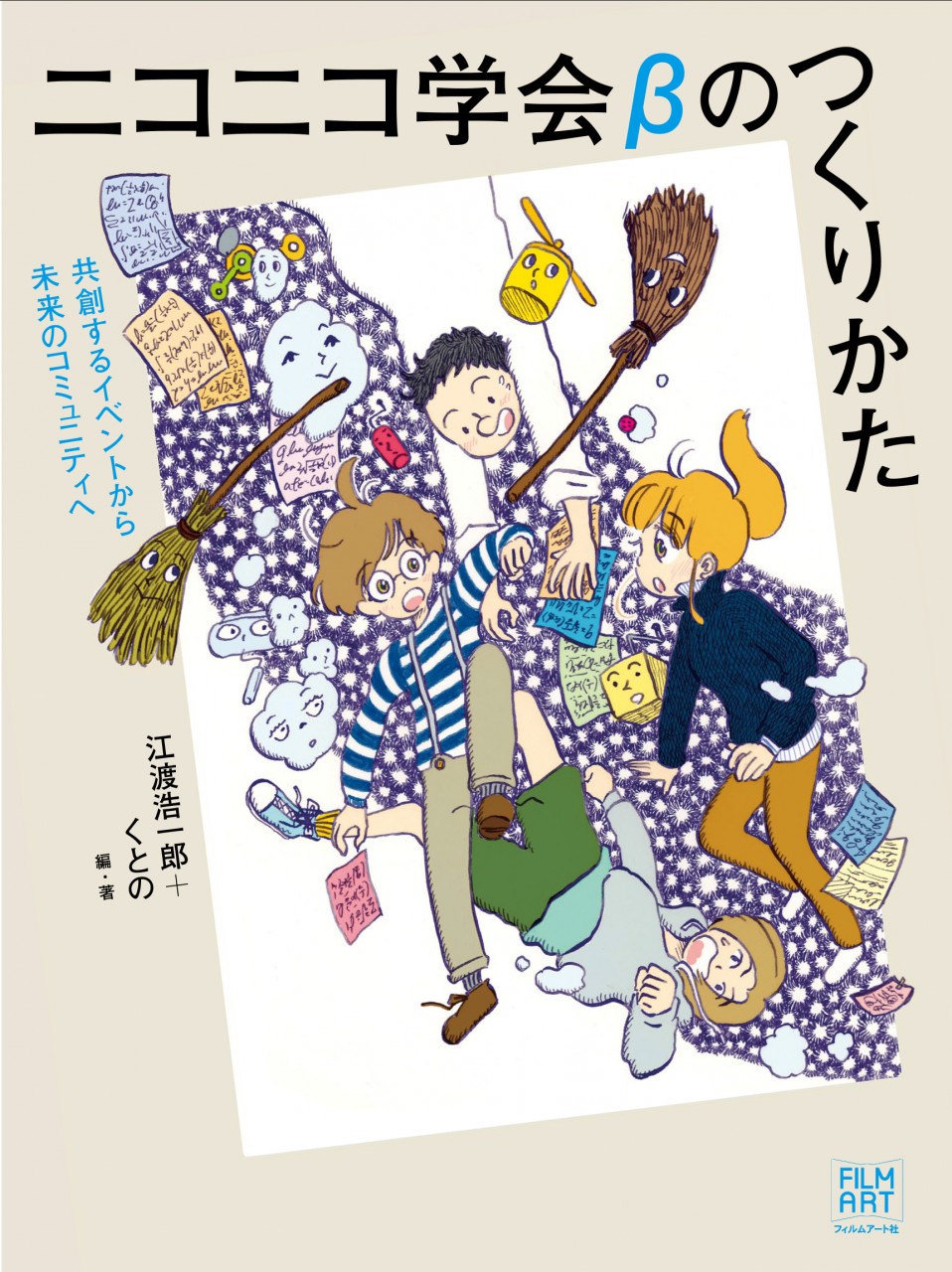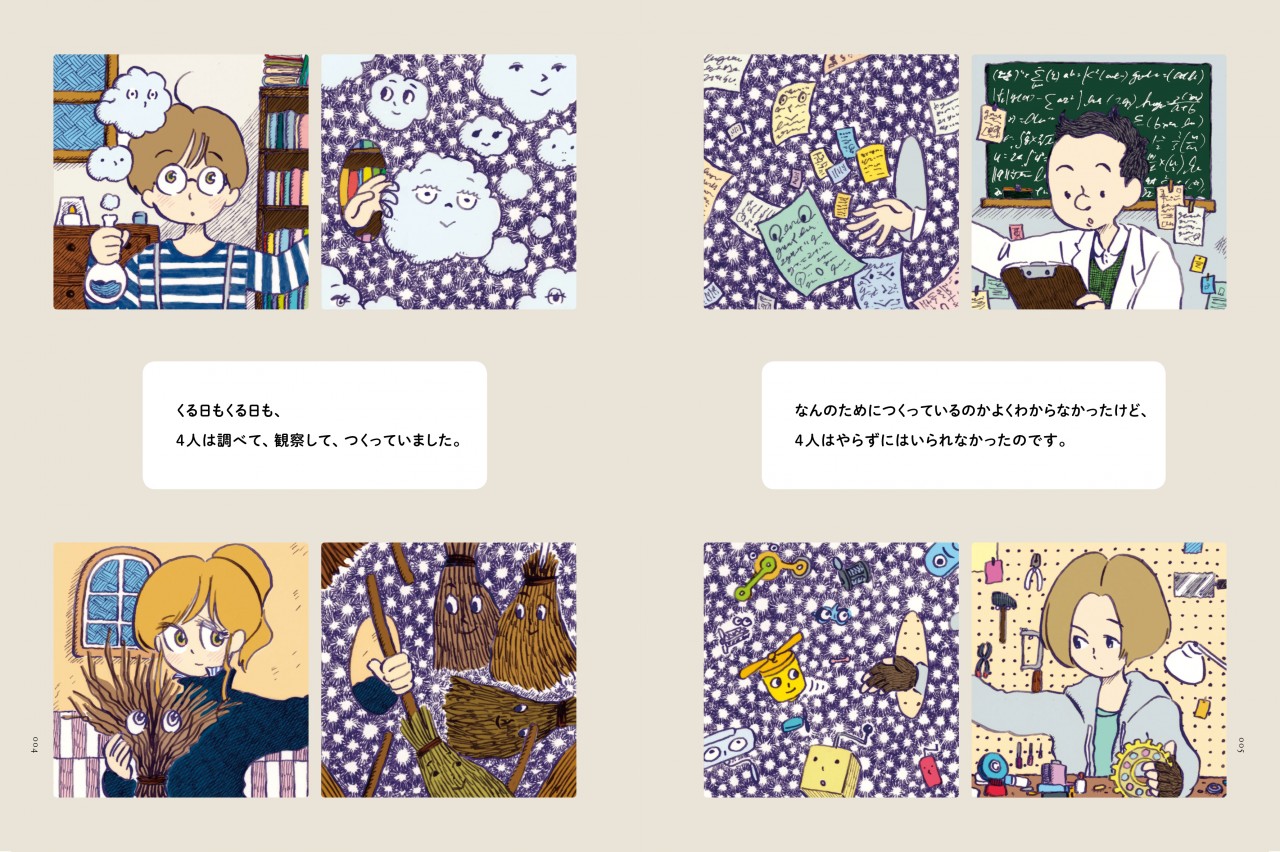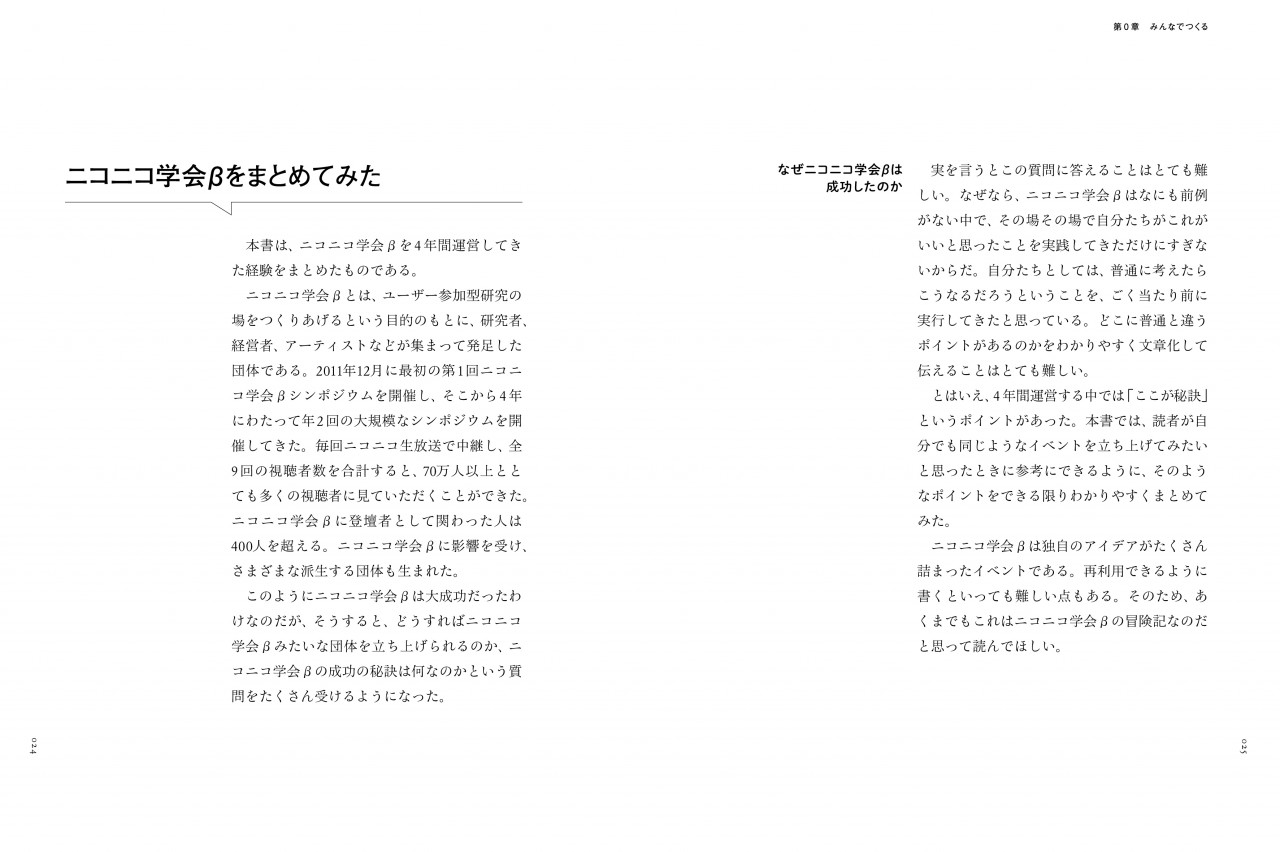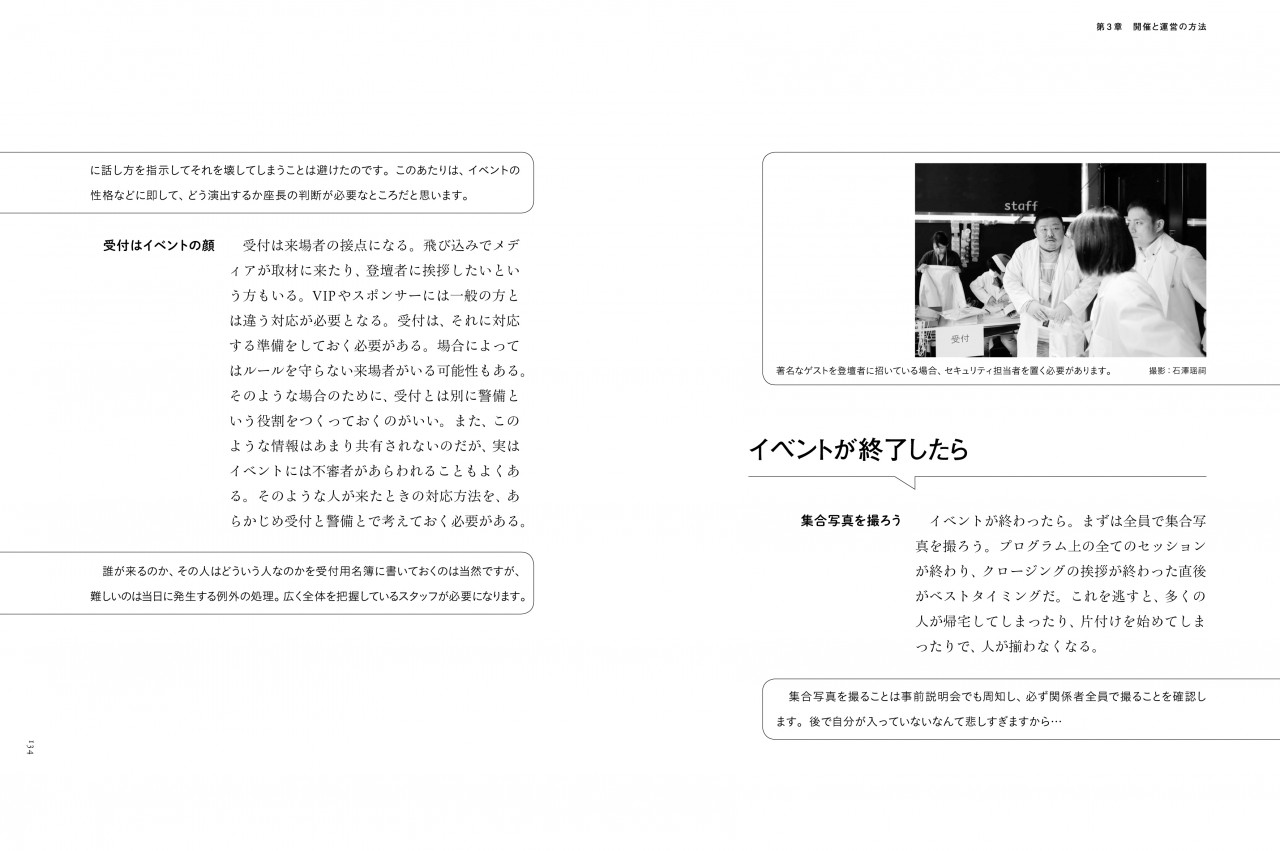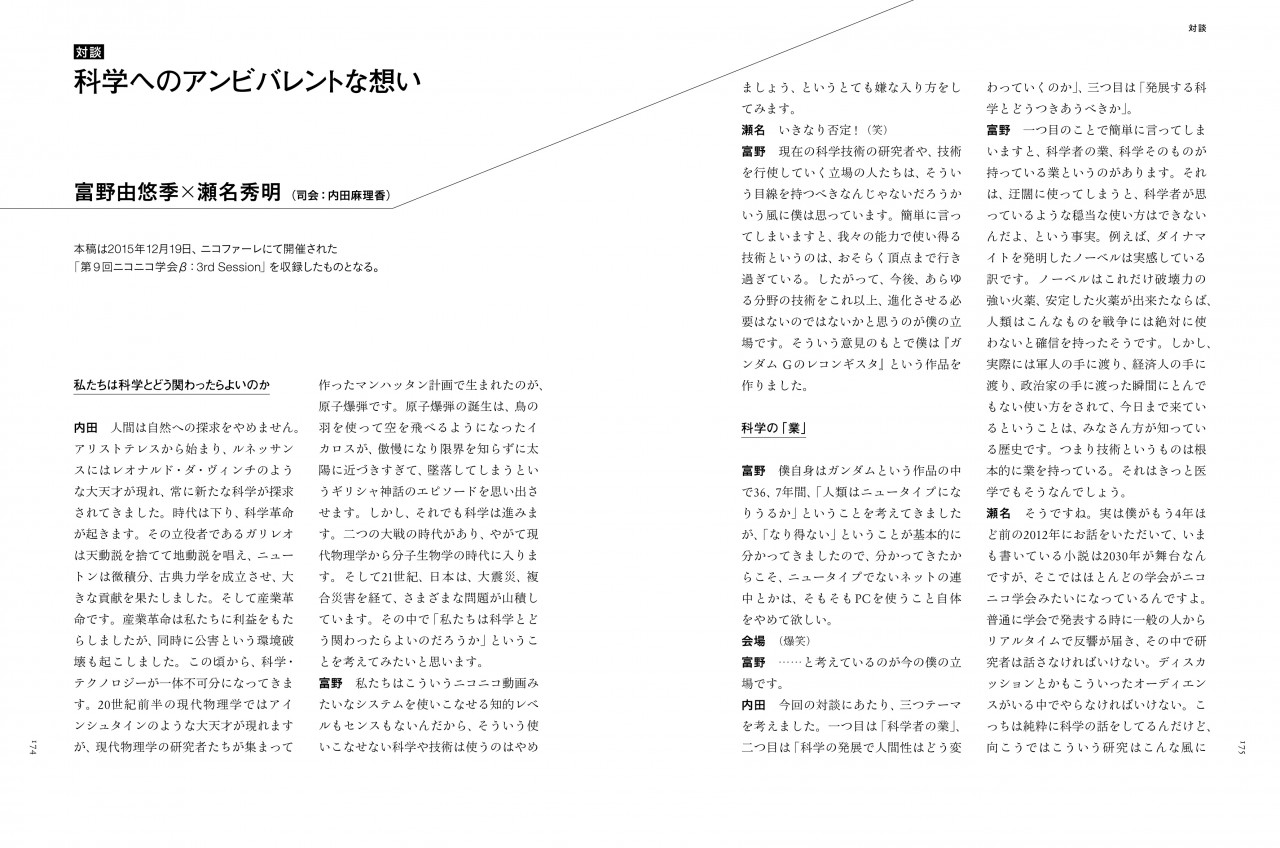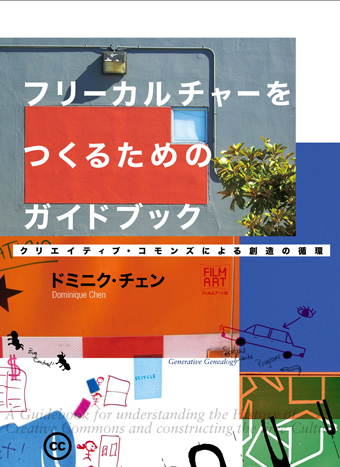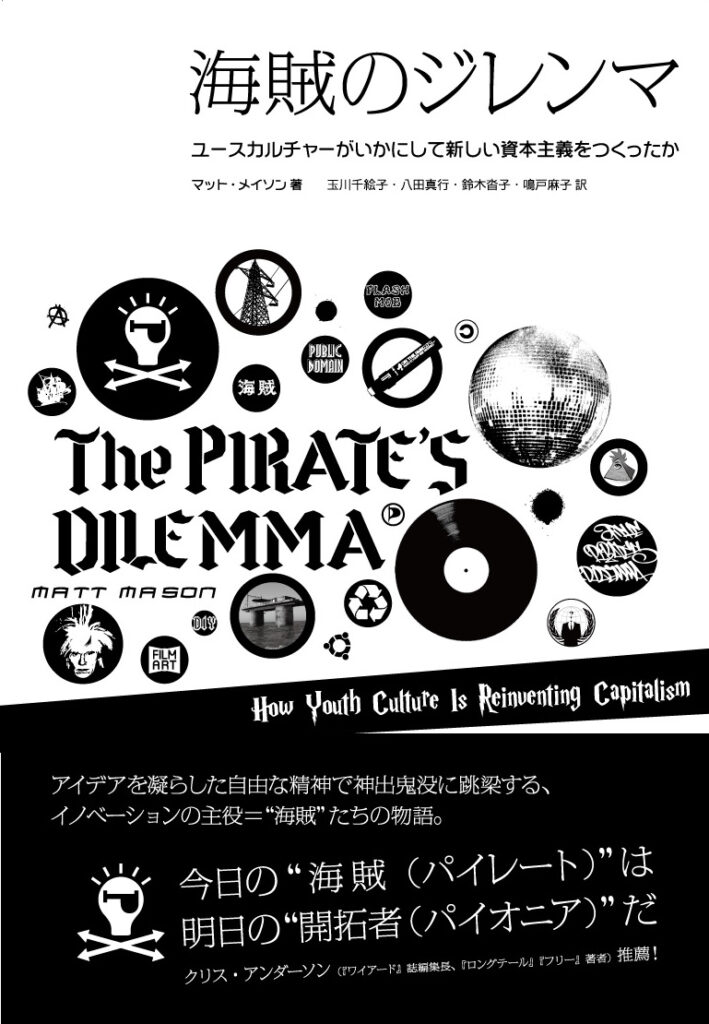富野由悠季(アニメーション監督)×瀬名秀明(小説家)対談収録!
イノベーションが生まれる、新しいコミュニティ運営のための教科書!
なんだかちょっとわくわくする、科学と技術とコミュニケーションが融合する「共創」のかたち。
「ユーザー参加型研究」を謳い、「研究100連発! 」「研究してみたマッドネス」などの名企画を生んだイベント「ニコニコ学会β」。大学や専門機関に属さなくても研究者として自分の興味のあることを追求する「野生の研究者」を応援することをモットーに、さまざまな広がりを生み出した「ニコニコ学会β」の、「作るをつくる」イベントのアーキテクチャと実践をまとめた1冊。
「やりたいことは明確にあるけれどどう始めていいかわからない」「仲間がいない」「ひとりではなく誰かと一緒にやってみたい」という人必読の書!
共創するイベントが、コミュニティの未来のかたちを切り拓く。
学術や研究における共創型イノベーションは、いつか起こる未来の話ではなく、もう現実になってきている今日の話なのです。
(中略)
もう来ている未来をさらに面白くしていくのは、そう、あなたです。あなたが実現したいことは手の届くところまできっと来ています。
(中略)
ニコニコ学会βがつくろうとしたコミュニティは、未来に向けて誰もに開かれたものです。いまあなたに何か特別な才能やアイデアがなくてもいいのです。ニコニコ学会βを見て、触れて何か心揺さぶられるものがあったら、あなたも共創の未来を担う1人なのです。面白いと思えるコミュニティは他にもあるはずです。まずはそれに参加することで全ては始まります。そこから次のステップでこの本を読み返してみると、あなたの前にはきっと新たな世界が広がっているはずです。
(本書・エピローグより)
イベント
「学問とニコニコの交差点——『ニコニコ学会βのつくりかた』刊行記念イベント」
江渡浩一郎×くとの×東浩紀
日時:7/16 (土) 19:00 – 21:00
場所:ゲンロンカフェ
(西五反田1-11-9 司ビル6F)
・当日券は3100円 (1ドリンク付き)です。ゲンロン友の会会員証または学生証のご提示で2600円(1ドリンク付き)になります。
・友の会会員限定席を複数予約される場合は、お連れの方が会員でなくても結構です。
・お席はチケットの申し込み順ではなく、当日会場にご来場頂いた順にご案内致します。
・開場は開演1時間前の18時00分となります。
メディア掲載
-
「学問とニコニコの交差点」(7/16、ゲンロンカフェ)を振り返った記事が掲載されています!
-
琉球新報〈集合知によるイノベーション〉にて、片岡義博さまにご紹介頂きました!
目次
■プロローグ 「星が降る日」 絵・佐々木充彦
■第1部 コミュニティのつくりかた
第0章 みんなでつくる
ニコニコ学会βをまとめてみた ──なぜニコニコ学会βは成功したのか
共創とは ──集合知から共創へ/群衆の知恵/共通善と共創
共創プラットフォーム ──共創コミュニティ
ニコニコ学会βというコミュニティ ──ニコニコ学会βの共通善
第1章 最初のイベント
まずは1人のパートナーを探そう ──目的を考えよう
ニコニコ学会βの出発点 ──企画案をつくろう/仲間を増やしてキックオフ
第1回の外枠を決めよう ──場所の特別さ
体を表す名前にしよう
イベントの3本柱 ──よいプログラムの秘訣/運営委員会による実務/後のために大切なこと/最後のことも考えよう
●解説: 最初の2人から始まるストーリー
第2章 プログラムをつくろう
他のイベントを参考にする ──ニコニコ学会βの元になったイベント/まずはよいイベントに参加してみよう
テレビ番組を参考にしてみる
中身優先で講演者を選ぶ ──登壇者のモチベーションを理解する/観客の質と量がポイント/有名でない人でも積極的に依頼してみよう
プレスリリースからイベントを組み立てる ──ニコニコ学会βのプレスリリースドリブン
全力を出し切る
アンカンファレンスによる共創 ──アイデアを出し合う/セッションを決める/役割を決める/セッションの長さと数/アンカンファレンスのメリット/アンカンファレンスの歴史
●解説: ニコニコ学会βのアンカンファレンス
第3章 開催と運営の方法
イベント全体の段取りを把握する ──イベントの1日の流れ/スタンバイリストの役割/申し込みと受付
一番重要な指標はなにか ──KPIの意味/KPIは設定の仕方が大事
役割分担
スタッフの集め方 ──スタッフのモチベーション/事前説明会をする/ゴールをビジュアルで共有する/スタッフの中での調整
スムーズな会議のひけつ ──議事録は必ず共有する
情報ツールの長所と短所 ──新しいツールも積極的に
仕事を任せる
香盤表をつくる ──セッション香盤表と全体香盤表
運営マニュアルをつくる
安全はすべてに優先する
イベント当日の役割分担 ──リハーサルは超重要/受付はイベントの顔
イベントが終了したら ──集合写真を撮ろう/撤収は迅速に
イベントの独自性を出す
第4章 記録しよう
ニコニコ生放送という体験 ──アーカイブとしての動画記録/ニコニコ生放送の公式生放送
記録で気をつけること ──映像で記録する意味
ニコニコ学会βと科学コミュニケーション
運営記録の保存 ──KPTによるふりかえり/感想を集める
書籍や雑誌にする
第5章 これからのコミュニティ
コミュニティから生まれるイノベーション ──イノベーションのゆりかご
共創型イノベーション ──共創的科学技術イノベーション
●エピローグ: ニコニコ学会βが創発した共創型イノベーション
■第2部 ニコニコ学会βはどこから来てどこに向かうのか
[対談] 富野由悠季×瀬名秀明(司会・内田麻理香)
科学へのアンビバレントな想い
[インタビュー1] メレ山メレ子
ニコニコ学会βは
全力の大人も、初心者の参加者も、優劣なく活躍できる場所
[インタビュー2] 辻 順平 tsujimotter
ニコニコ学会βは
「野生の研究者」を育てる可能性を秘めた場所
[インタビュー3] ガレージ 高井浩司
ニコニコ学会βは
研究文化のチェルシーホテル
プロフィール
[著]
江渡浩一郎(えと・こういちろう)
(ニコニコ学会β実行委員長・プログラム委員長)
1997年、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了。2010年、東京大学大学院情報理工学系研究科博士課程修了。博士(情報理工学)。メディアアーティストとして、「sensorium」でアルス・エレクトロニカ賞グランプリを1997年に受賞。国立研究開発法人産業技術総合研究所主任研究員として「利用者参画によるサービスの構築・運用」をテーマに研究を続ける傍ら、2011年11月に「ニコニコ学会β」を立ち上げた。おもな著書に『進化するアカデミア』(イーストプレス)、『ニコニコ学会βを研究してみた』(河出書房新社)、『パターン、Wiki、XP』(技術評論社)。
くとの
(ニコニコ学会β運営委員長)
電子工作や自作真空管アンプにいそしんだ小学生の頃、将来の夢はリニアモーターカーの研究開発。人間が生きる根源を問いたくて哲学・宗教学の道に進路変更するも、大学生時代は文系学部からロボットコンテストに参戦。その後は宗教思想の文献研究を続けたが、ひょんなことでLED5000個使用の初音ミク電飾ウェディングドレスをチームで制作してからニコニコ学会βに関わり、研究者人生に大きな転機が訪れる。文系学部の危機が叫ばれるなか、実装のない思想・思想のない実装を打破すべく「作る人文学」をかかげ、人文系と理工系の境界領域で活動。抽象的で難解な宗教思想の概念を視覚化・可触化し、誰にも理解しやすい感覚対象として表現するなど、先鋭的な研究を進めている。