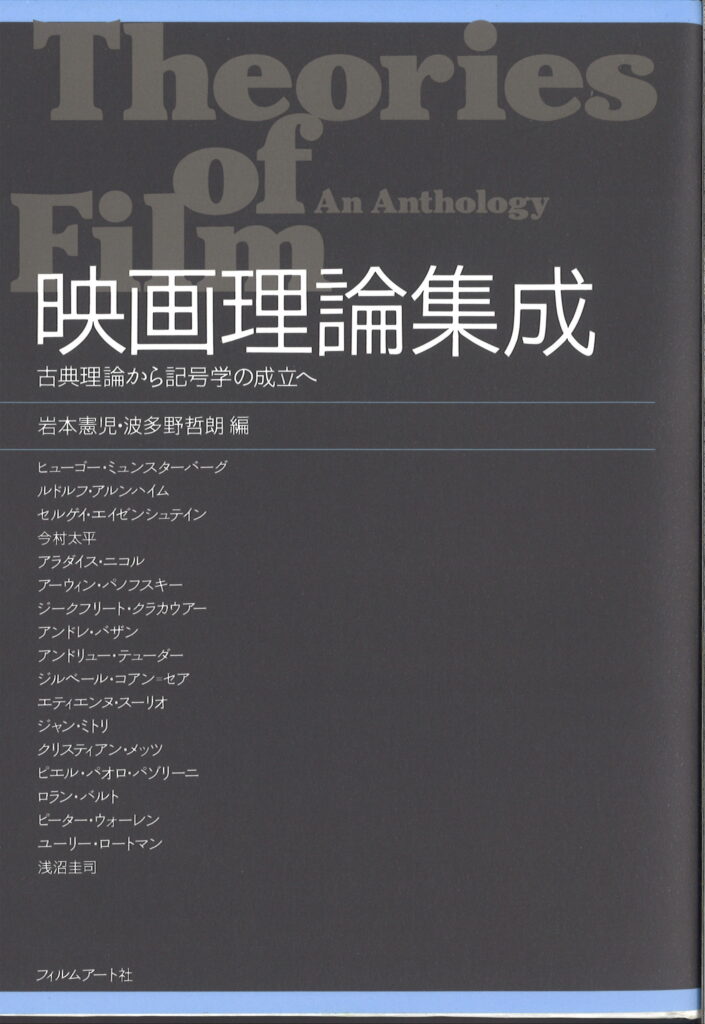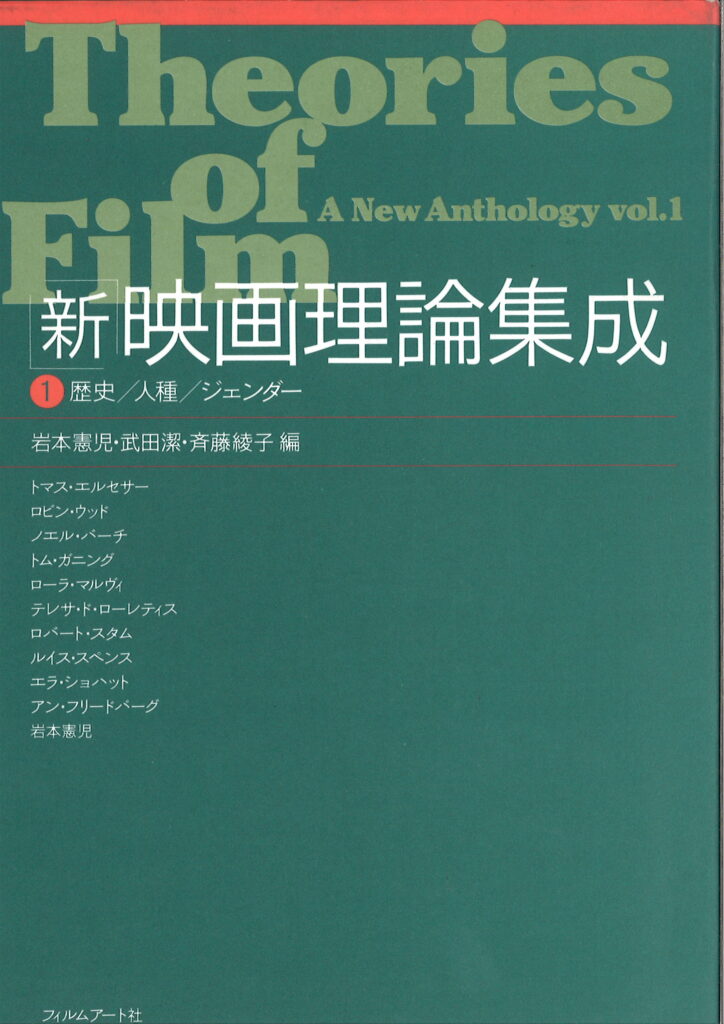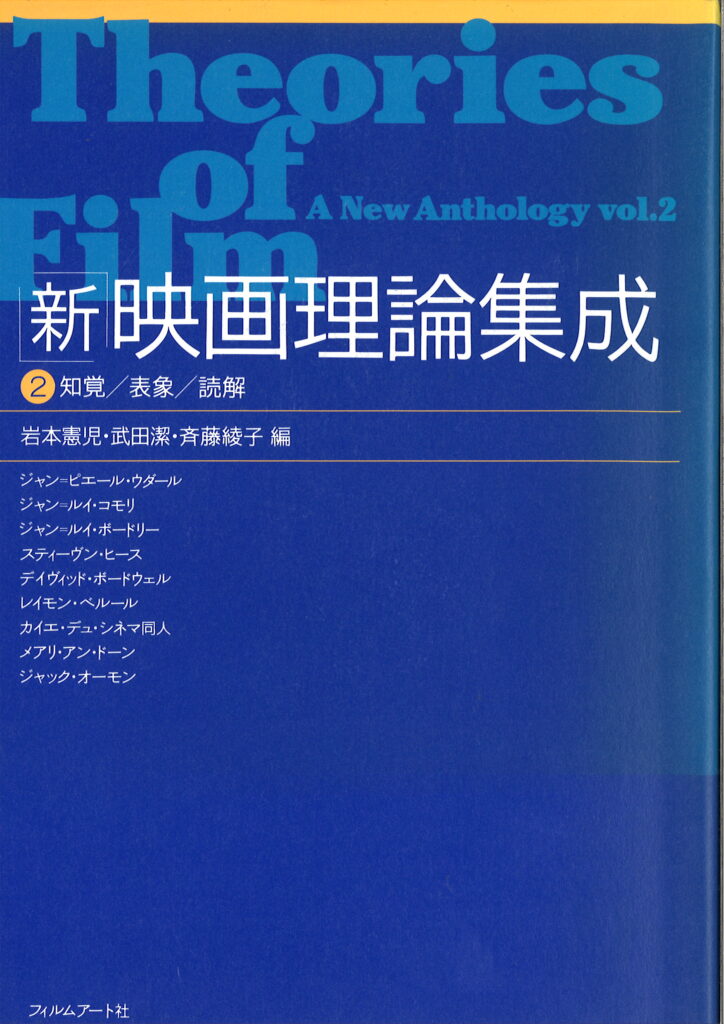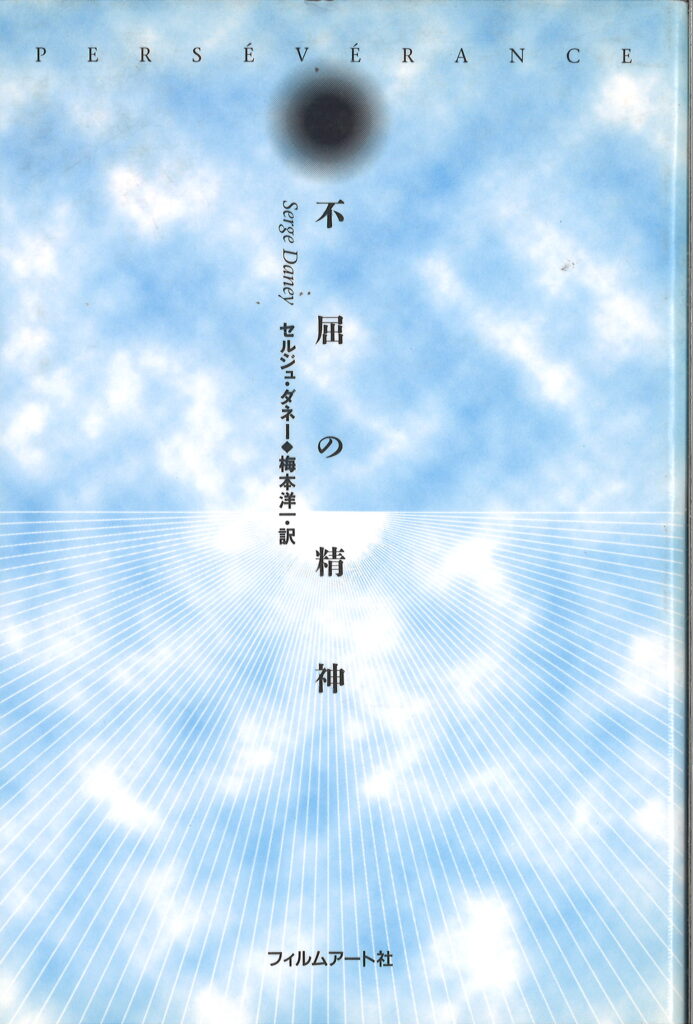「シネマの大義の下で撮られたフィルムだけが、全人類に関わる」
蓮實重彦以来の「シネマ」概念をめぐり、その「大義」とは何かを問うべくして書かれた、2006~2017年までの廣瀬純による主要映画批評・論考を一挙収録。
「映画批評とは何をなすべきか」をめぐっての現代日本の最も果敢な実践がここにある
☆黒沢清(映画監督)推薦
「ただちょっと面白いだけで、あとはさっぱり役立たずだった映画というものが、廣瀬純の言葉によって今ようやく何かの役に立とうとしている!」
現代日本において最も先鋭的かつ実践的な映画批評を手がける廣瀬純による、現時点までのキャリアを総括した初の映画論集が完成。
単行本未収録論考はもちろん、国内未発表テクストほか、講演、討議、座談会まで、廣瀬純による「言葉」をめぐるパフォーマンスをこの一冊に凝縮した。
映画を見ること、映画をつくること、そして映画を思考することとは、いったいどのようにこの世界と関わるのか? 映画に携わるあらゆる人々のために、そして映画それ自体のために紡がれた、映画批評の真の現在形がここにある。
個人的な思いつき、突飛なアイディア、逞しい想像力といったものが原因(cause)となって創造されたフィルム〔……〕個人の大義(cause)の下で撮られたフィルムはその個人にしか関わりがない。「シネマの魂」が原因となって創造されたフィルムだけがすべての者に関わるのだ。シネマの大義の下で撮られたフィルムだけが、全人類に関わるのである
──本文より
メディア掲載
-
「週刊読書人」 評者:堀潤之
「21世紀初頭の映画批評の金字塔として屹立しつづける」 -
「東京新聞」(10月4日付)
-
「キネマ旬報」(10月下旬号) 評者:荻野洋一
-
「boidマガジン」評者:結城秀勇
-
「CINRA.NET」
-
「ウラゲツ☆ブログ」
目次
●プラトン/レヴィナス/ゴダール/小津 切り返しショットの系譜学
●エリック・ロメール クレールの膝、緑の光線、青の時間
●クロード・シャブロル 『悪の華』と再生産
●ポー、エプシュタイン、青山 ユリイカ対ユリイカ
●カトリーヌ・ドゥヌーヴ 脱性化されたモンロー
●エイゼンシュテイン/グレミヨン/ローシャ/ストローブ=ユイレ 地理映画(ジオ=シネマ)の地下水脈
●『ダゲレオタイプの女』問題、あるいは、黒沢映画の唯物論的転回
●ストローブ=ユイレ/フォード そよ風の吹き抜けるサイエンス・フィクション
●若松孝二『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』 道程に終わりはない
●フーコー/イーストウッド 無理な芝居の一撃
●クエンティン・タランティーノ Shoot This Piece of Shit
●空族『サウダーヂ』 Outra vez…, mas!
●レオス・カラックス『ホーリー・モーターズ』 疲労、ルックス映画の極北
●マルコ・べロッキオ『ポケットの中の握り拳』 暴力階級と垂直落下
●高倉健 客分として生きる
●ロべール・ブレッソン 不確かさと二階層構造
●鈴木清順 運命、恥辱、人民
and more……
プロフィール
[著]
廣瀬純 (ひろせ・じゅん)
1971年東京生まれ。1999年、パリ第三大学映画視聴覚研究科DEA課程修了(フランス政府給費留学生)。2004年4月、龍谷大学経営学部講師に就任、現在は同大学同学部教授。映画批評誌「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」(勁草書房)及び仏・映画批評誌「VERTIGO」元編集委員。著書に『資本の専制、奴隷の叛逆 「南欧」先鋭思想家8人に訊く ヨーロッパ情勢徹底分析』(2016、航思社)『暴力階級とは何か 情勢下の政治哲学2011-2015』(2015、航思社)『アントニオ・ネグリ 革命の哲学』(2013、青土社)『絶望論 革命的になることについて』(2013、月曜社)『蜂起とともに愛がはじまる 思想/政治のための32章』(2012、河出書房新社)『シネキャピタル』(2009、洛北出版)『闘争の最小回路 南米の政治空間に学ぶ変革のレッスン』(2006、人文書院)『美味しい料理の哲学』(2005、河出書房新社)。
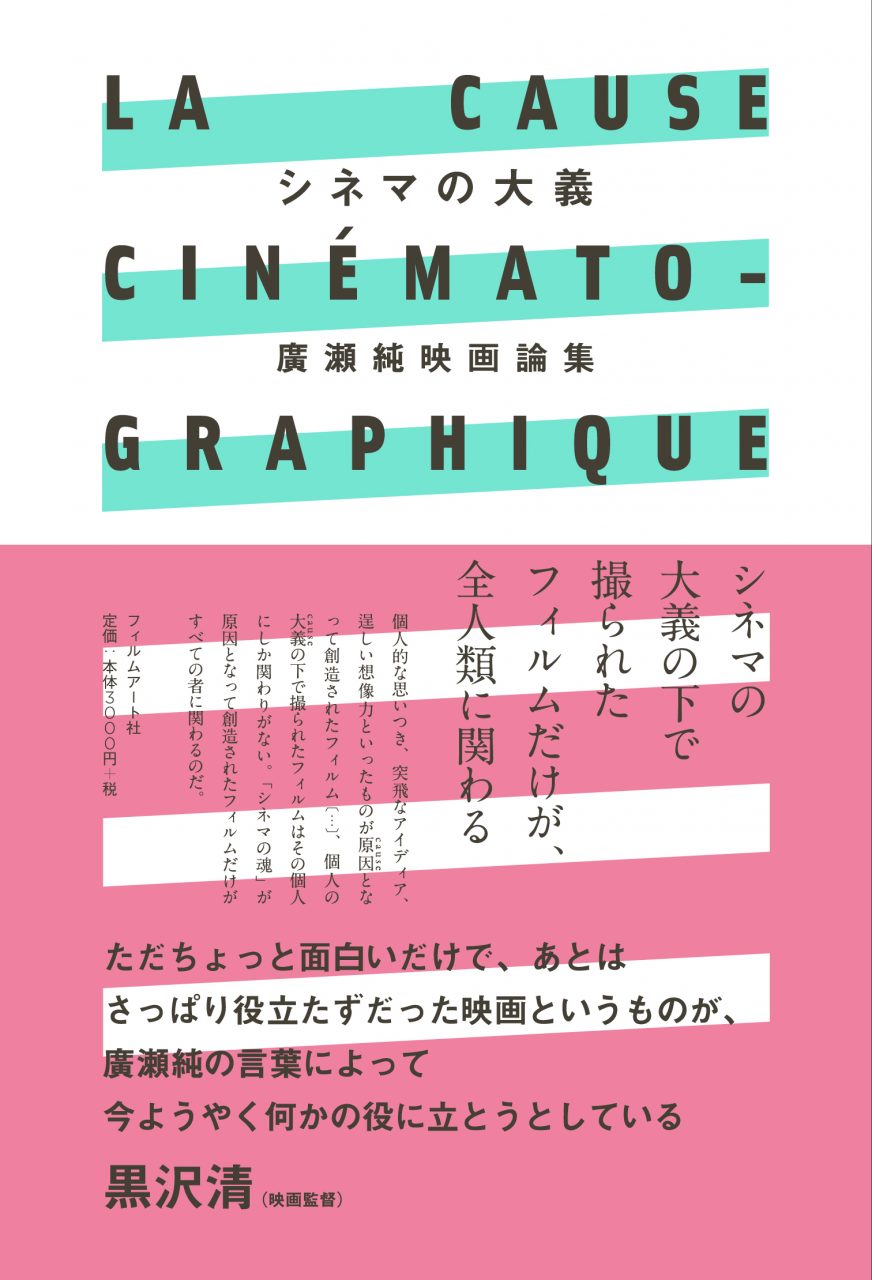
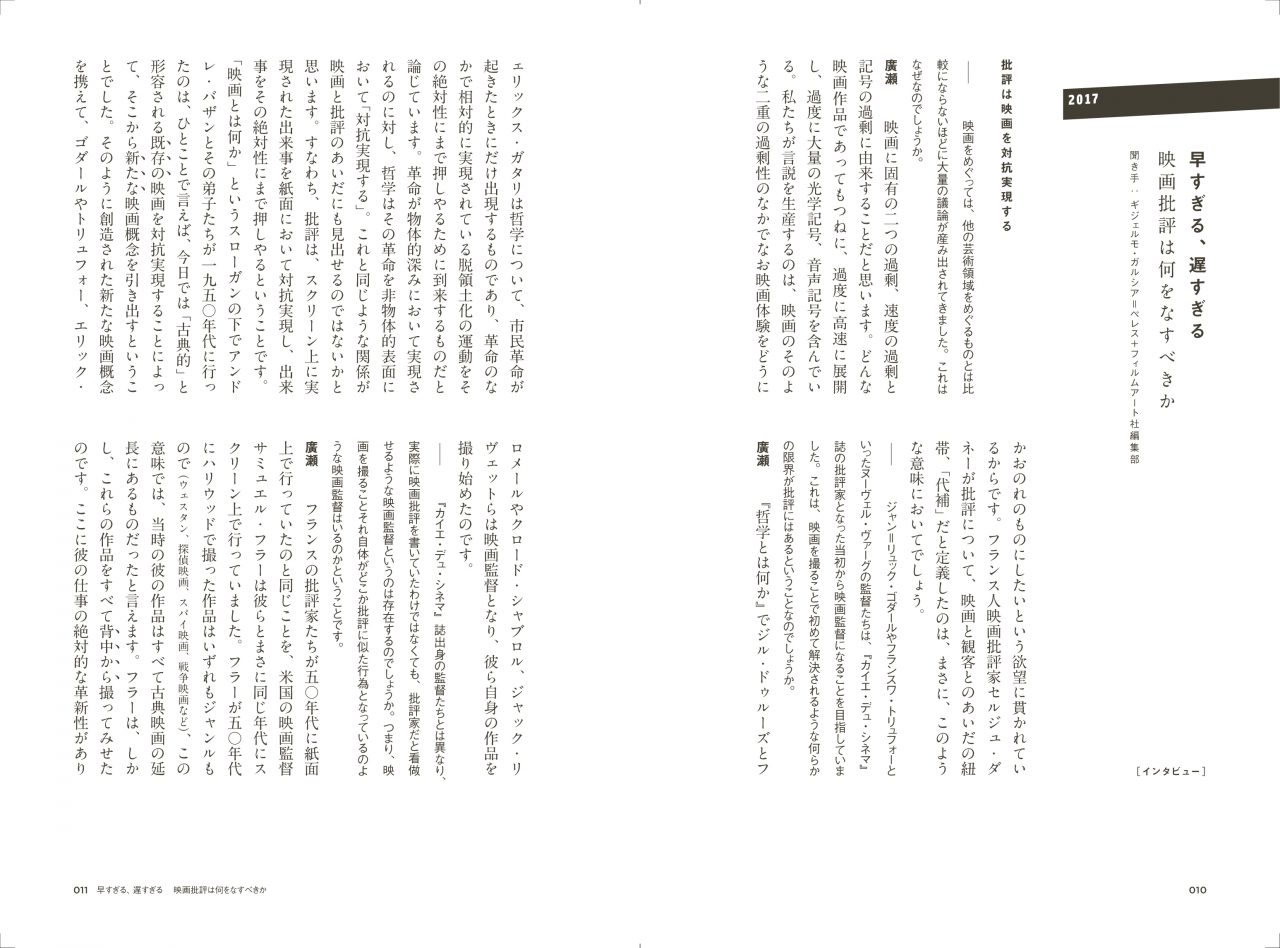
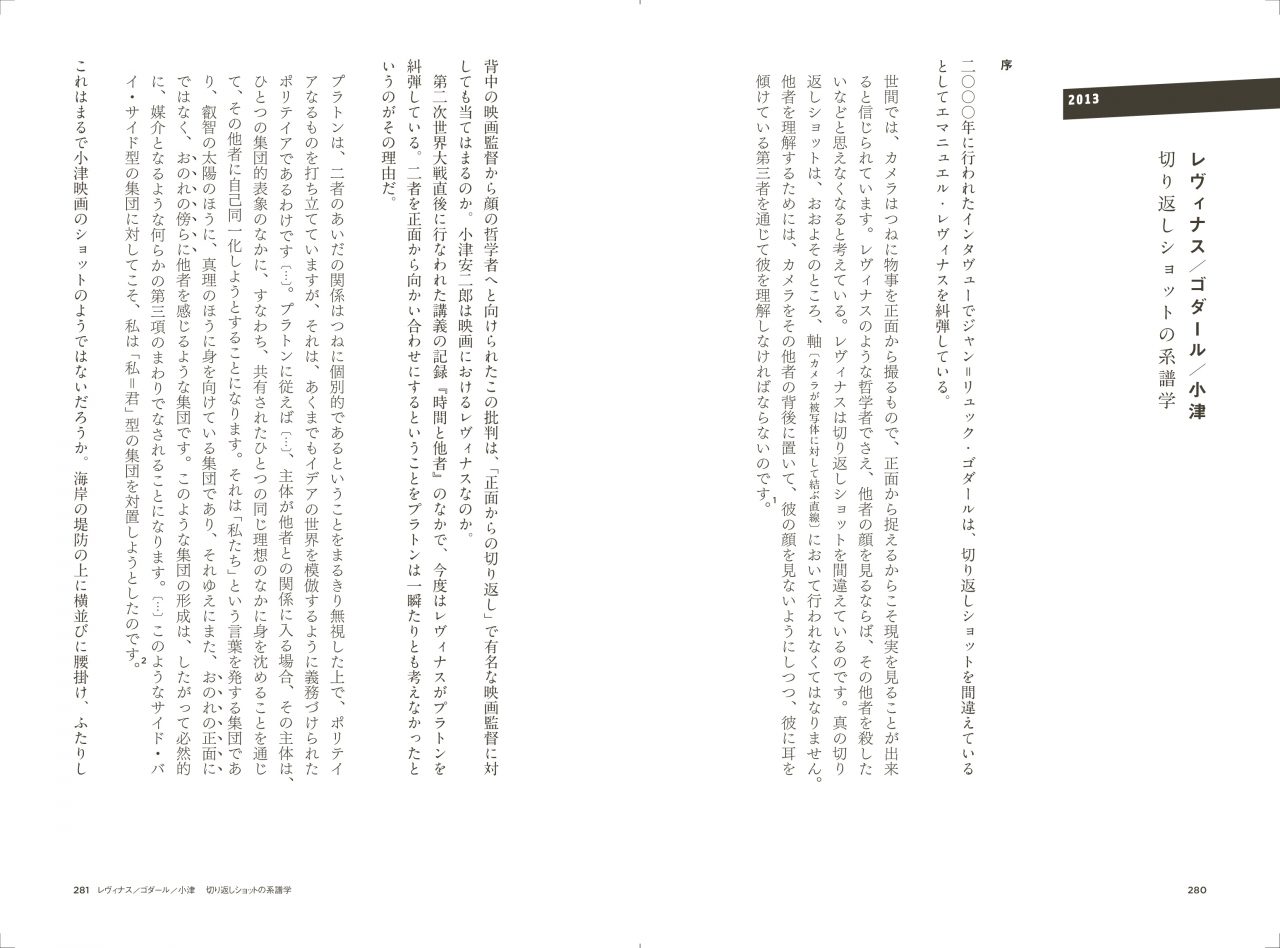
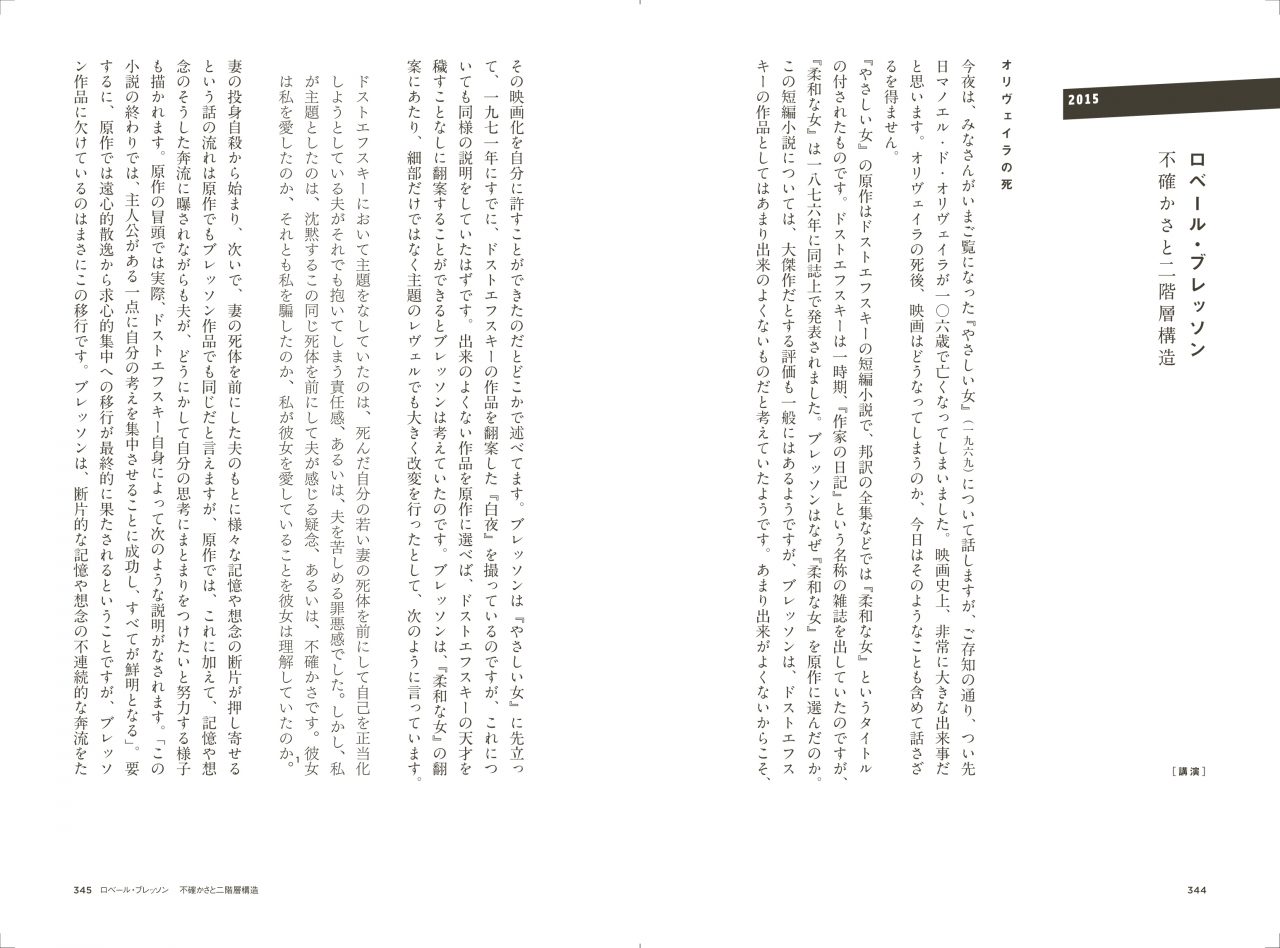
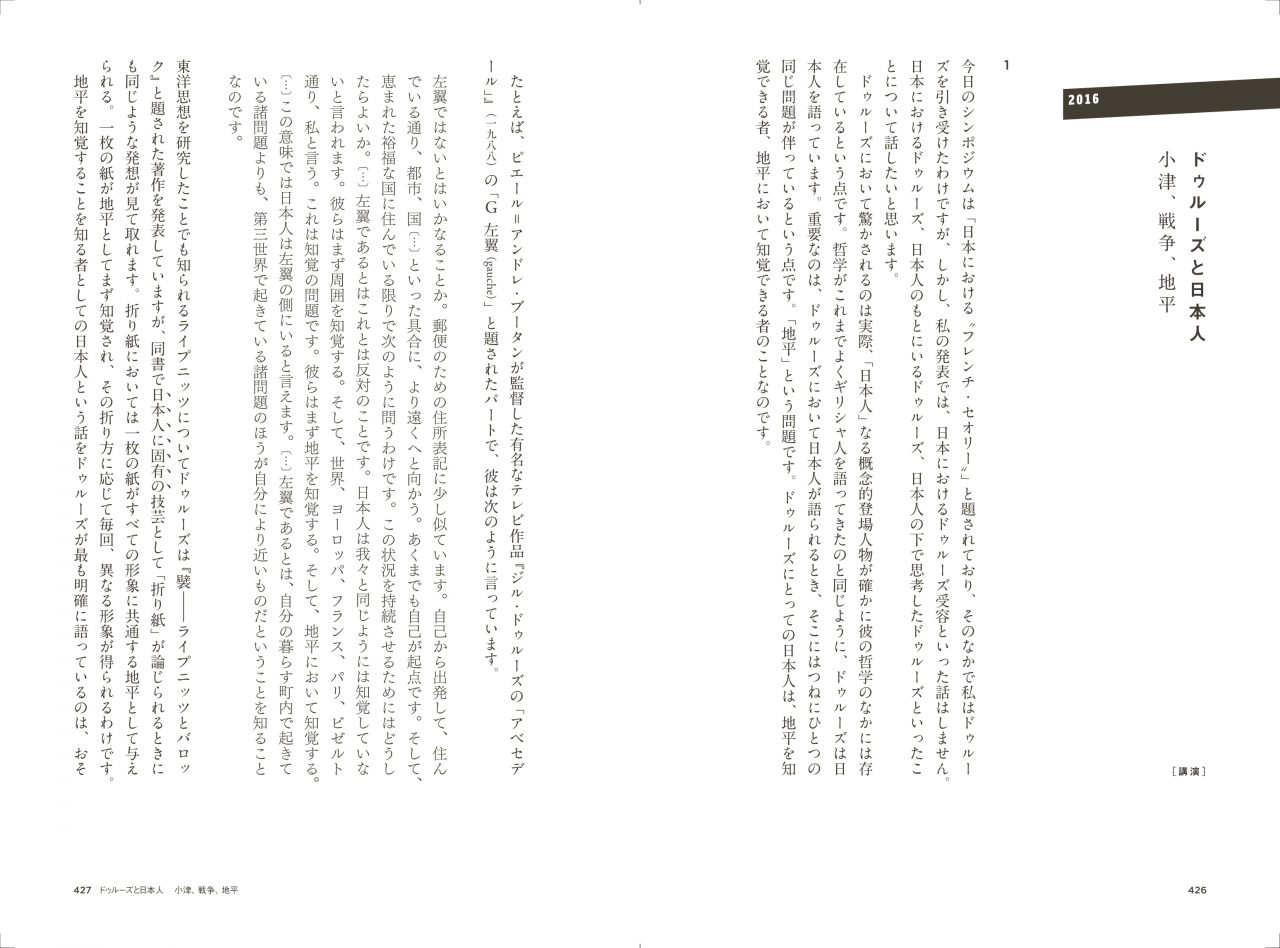
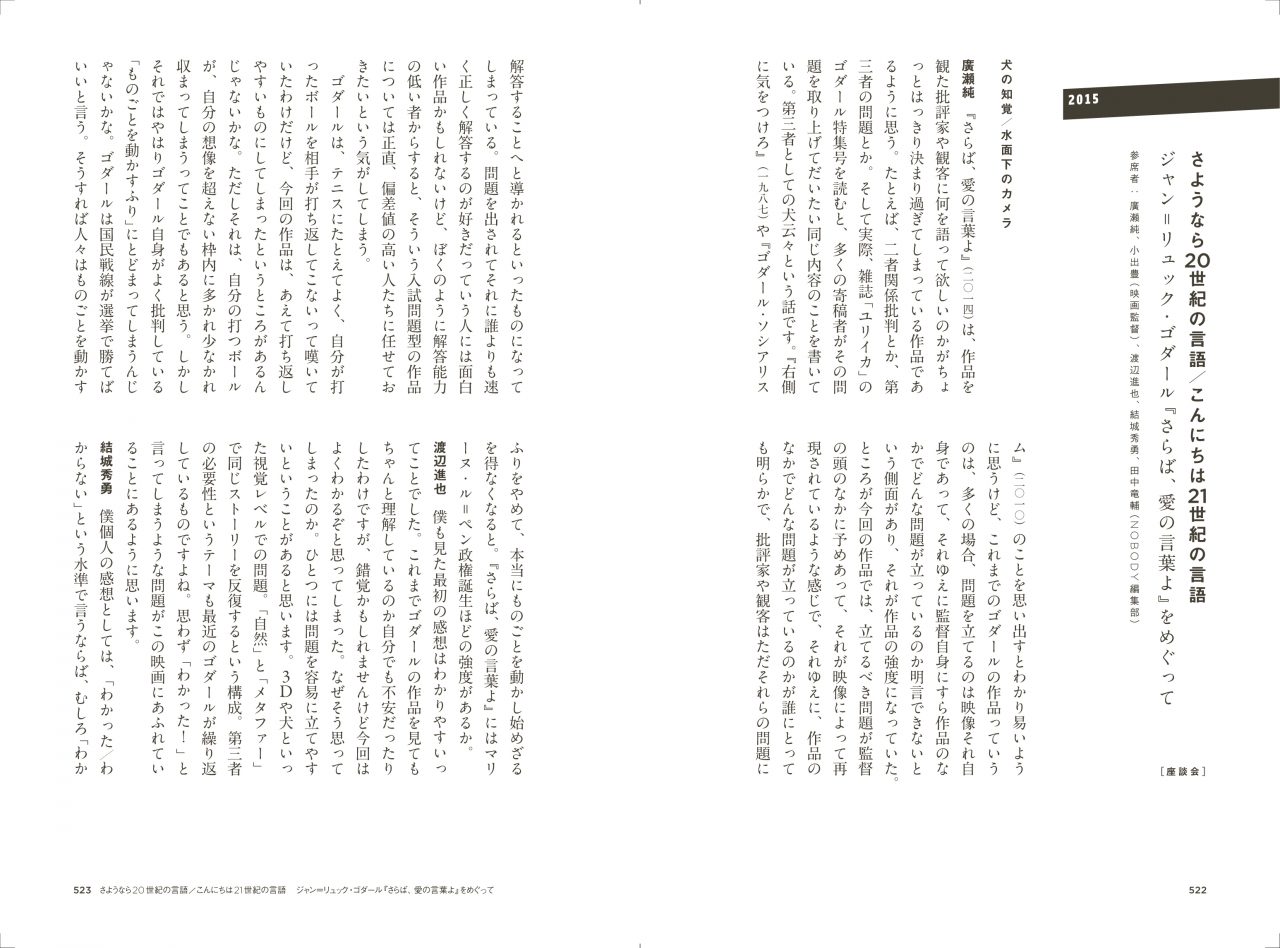
![シネマの記憶装置[新装版]](https://www.filmart.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/9784845918119.MAIN_-877x1280-1-702x1024.jpg)
![映画はいかにして死ぬか[新装版]](https://www.filmart.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/9784845918102.MAIN_-874x1280-1-699x1024.jpg)