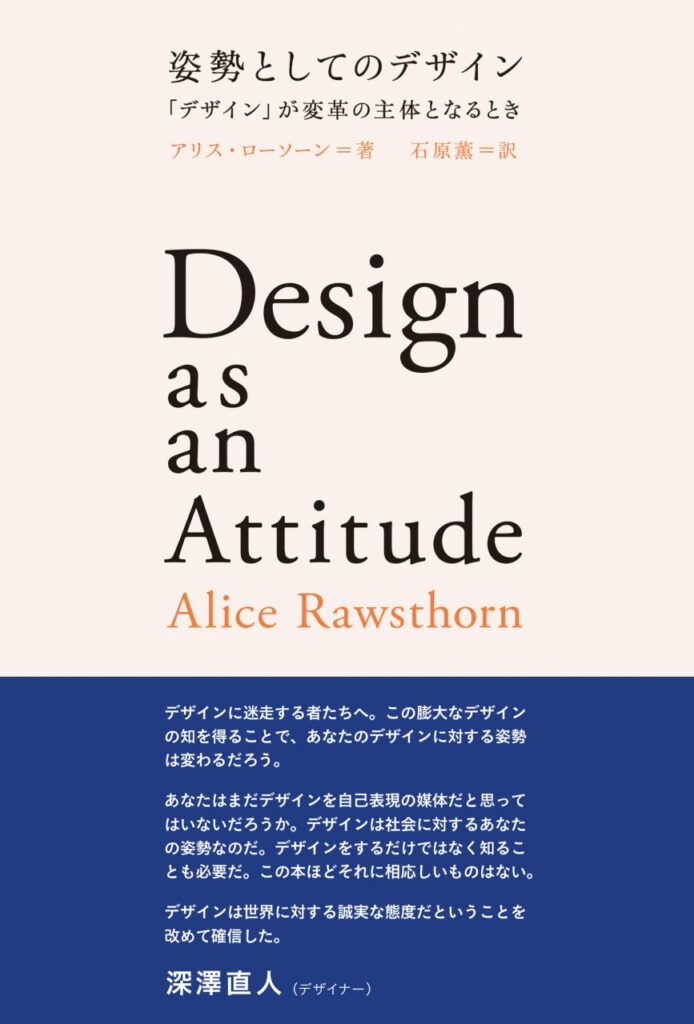PROLOGUE
Design as an Attitude 姿勢としてのデザイン
「デザインをすることは職業ではなく姿勢である」
――ラスロ・モホリ=ナジ
幸先の悪い年初めだった。シカゴにデザイン学校を新設しようと、この6年間、財政難や政治的ないざこざと闘ってきたラスロ・モホリ=ナジ[ラズロ/モホイ/ナギとも表記される]だったが、1945年初め、再び理事会とぶつかった。今度は学生の定員割れをめぐってだった。さらには、建物の賃貸契約が春に切れるため、新しい校舎を見つけなければならなかった。モホリ=ナジがシカゴに最初に設立した学校は1年余りで閉鎖され、今、2校目も同じ運命を辿ろうとしている。結局、理事会が折れ、学校の存続が決まったが、学校を守るためのすさまじい闘いは、モホリ=ナジ自身に大きな代償を払わせることになった。
1945年、モホリ=ナジは50歳を迎えた。2年前から書き始めた視覚理論の本にもっと時間をかけられると思っていた。ところが厄介な学校問題のせいで、日中は授業と事務処理、夜は家族を養うために引き受けていた商業デザインの仕事で手一杯になり、本に取り組めたのはなんとかやり繰りして作った週末の数時間だけだった。さらに悪いことに、1945年秋に重い病に冒され、白血病と診断された。入院中も妻シビルに自分の写真作品や絵画作品やメモを持って来させ、輸血や注射、レントゲンの合間に本のレイアウトを考えた。
モホリ=ナジは、クリスマス直前に退院し、翌月学校の職から退いた。春も夏も、使える時間のすべてを本の完成に注いだが、病状が悪化し、1946年11月24日に亡くなった。その本Vision in Motion[以下『ヴィジョン・イン・モーション』]は翌年出版された。当時の、または現代の読者には、著者がどれほどの辛苦と闘いながらそれを書いたのか、きっと想像もつかないだろう。その本は、デザイン、アート、テクノロジー、創造的教育とそれらが社会で果たす役割について、モホリ=ナジのビジョンをまとめた宣言書であり、類まれな才能と活力に満ちた個人の思想と洞察の粋が詰まっている。第一次世界大戦後、母国ハンガリーでロシア構成主義の誕生を、1920年代のドイツでバウハウスの絶頂期を、1930年代にまずイギリスで、次にアメリカで、モダニズムの台頭を経験した。執筆中の苦しい病状にもかかわらず、『ヴィジョン・イン・モーション』からはエネルギーと希望、とくに「デザインにはよりよい世界をつくる力がある」という彼の信念がはっきりと伝わってくる。
デザインに携わる人々を力づけるようなこの広範なデザインビジョン、そして「デザインに対してよりオープンで進歩的なアプローチを取ることは社会の利益になる」という確たる思いは、『ヴィジョン・イン・モーション』第2章の次の言葉に集約されている。「デザインすることは職業ではなく姿アティテュード勢である」。「デザインする(designing)」という表現が少し古風ではあるけれども、私の大好きなフレーズだ。「デザインという概念、デザイナーという職業は、1つの専門職から、《個人や社会のニーズから離れることなくその関係においてプロジェクトを捉え、目の前の問題を解決し、無から有を生みだすという広く意味のある姿勢》へと認識を改める必要がある」とモホリ=ナジは書いている。「デザインの問題はすべて究極的には1つの大きな問題に還元される。つまり、《design for life(生きるためのデザイン、生活のためのデザイン)》である。健全な社会では、すべての職業がそこに向かってそれぞれの役目を果たそうとする。なぜなら、それぞれの仕事がどれだけ関与するかによって、文明の質が決まるからだ」。
産業革命以降続いていた専門職という縛りからデザインを解放し、あらゆる人々に開かれた、直観と創意と問題解決能力に根ざした柔軟なメディアとして定義し直したのは、モホリ=ナジらしかった。勇敢かつ寛大、反体制的で好奇心旺盛な、私の大好きなデザイン史上の人物の1人だ。バウハウスでは技術への情熱を示すためにつなぎ姿で教壇に立ち、かつては男性しか学べなかった学科も女性の希望どおりに学ばせた。そんな知性派の亡命芸術家に惹かれない人がいるだろうか。そして、アメリカへ渡ったあとのモホリ=ナジの勇気ある行動に、尊敬の念を抱かずにいられるだろうか。制服をビジネススーツに着替えたが、政治思想においてはそれまで以上にラディカルであり続け、シカゴで隔離教育がなされていた時代に、自分のデザイン学校にアフリカ系アメリカ人学生を受け入れた。どこにいても、どんな状況に置かれても、実験への情熱を失わなかった。当時新しいメディアだった映画や写真で先駆け、それらが視覚文化や日常のあらゆる側面にどのような影響を与えるかを調査した。
「姿勢としてのデザイン」という考え方は、駆け出しの芸術家だったモホリ=ナジが第一次世界大戦直後のブダペストで出会い、青年期に傾倒したロシア構成主義運動に根ざしていた。当初の構成主義者の活動において、デザインは重要な役割を果たしていた。ロシアの前衛芸術家、作家、知識人たちは、大戦が終わるまでの数年間、集まって意見を交わし、社会改革を計画した。メンバーには、アレクサンドル・ロトチェンコ、妻のワルワーラ・ステパーノワ、その友人のアレクセイ・ガン、エル・リシツキー、リュボーフ・ポポーヴァなどがいた。1920年代前半にモホリ=ナジがウィーンやベルリン滞在中に出会ったロシア構成主義の支持者たちにも彼らの考えが共有されていた。つまり芸術家やデザイナー、科学者は産業界と協力して、ポポーヴァの言う《新しい生活のための新しいもの》を生みだし、よりよい平等な社会づくりに貢献すべきだという考えだ。
これが、1923年3月にバウハウスの教員になったモホリ=ナジが持ち込んだデザインビジョンだった。それからの5年間、学校随一の影響力を持つ教師になり、バウハウスが進歩的でインクルーシブな、実験に熱心な学校として位置づけられる基礎を作った。1928年にバウハウスを去ったあとも、『ヴィジョン・イン・モーション』で見事なまでに鮮明に提示した《姿勢としてのデザイン》の概念と同じ精神のもとに、シカゴの学校を含むすべての新しい事業に取り組んだ。
この本を「Design as an Attitude(姿勢としてのデザイン)」と名づけたのは、モホリ=ナジへのトリビュートの意味もあるが、この言葉が本書で紹介する作品のほとんどを端的に言い表しているからでもある。本書は、アートマガジン「フリーズ」に2014年から2017年まで連載した「By Design」というコラムに基づいている。このコラムでは、私が今のデザインにおいて最も重要だと思う問題や課題を掘り下げた。今はデザインにとって非常にチャレンジングではあるが心踊るほど刺激的な時代だと思っている。私が目指すのは、そんな今の時代を描きだすことだ。今、デザインという分野そのものと、それが人々の生活に与える影響は、劇的に変化している。
デザインは、時代や文脈によってさまざまな意味を持たれてきた。誤解や飽き飽きするよう
な説明もたくさんされてきた。そこで、まずは私が考えるデザインを定義することから始めようと思う。いくつもの顔を持つデザインだが、それは一貫して「世の中に起こるあらゆる変化――社会、政治、経済、科学、技術、文化、環境、その他—―が人々にとってマイナスではなくプラスに働くように翻訳する《変革の主体》としての役割」を担ってきた。かつてないほどのスピードと規模の変化がさまざまな局面で起こり、リスクも多いこの激動の時代に、デザイナーたち(本職かどうかにかかわらず)は、その役割をどのように果たしているのか。それを本書で取り上げる。
そうした変化の中には、深刻化する環境問題や難民危機、貧困や偏見、不寛容、過激思想の高まり、生活のために存在していた前世紀のシステムや制度の多くがもはや機能しないという認識、確実に社会を変革させるが必ずしも良い方向に進むとは限らないさらに複雑で強力なテクノロジーの奔流といったグローバルな問題がある。本書は、たとえば気候変動対策の計画と実践、医療・公共サービス制度の機能不全領域の改革、人工・自然災害の被災者への緊急支援、地域社会による難民支援、社会的正義の擁護などに取り組み、問題の対処に乗り出している「デザイナー」たちを紹介する。また、アートやクラフトなど他の分野とデザインとの関係の進化や、「メイキング(作る過程)」(手でも機械でもデジタルでも)への興味回復にデザインが果たしている役割についても取り上げる。また、性別、地理、人種という意味においてだけでなく、デザインを勉強した経験はないがデザインに関与したい異分野の人々を受け入れるなど、デザイン界のダイバーシティとインクルージョンの向上によって、デザイン文化が変化していることについても触れる。
技術革新は、繰り返し取り上げられるテーマだ。本書では、かつて困惑するほど未来的だったのに今ではユビキタスとなった技術とその応用、たとえばスマートフォン、ソーシャルメディア、ブロックチェーン、生体認証ソフトといったデザイン開発の成功と失敗を振り返るのと同時に、近い将来確実に私たちに影響を及ぼすAI、量子計算、無人自動運転車、デジタルファブリケーションといった技術革新のインパクトを予測する。そうしたイノベーションを受けて、私たちはデザインに何を求めるようになるだろうか。生活のさまざまな場面で私たちはどこまで自分で選択し、コントロールできる余地を残しておきたいと思うだろうか。また人々のアイデンティティがますます個別に、不安定になりつつある今、自己表現のあり方はどのように変わっていくのだろうか。
この本で紹介するプロジェクトすべてがモホリ=ナジの言う(職業デザイナーではない)「姿勢」としてのデザインの実践者によるものではないが、多くを占めている。デザインを「姿勢」と定義したモホリ=ナジは、デザインが社会でより影響力を持つようになること、つまり商業的な制約に囚われない《変革の主体》としてのポテンシャルを認識していた。どの時代にもそれを実践してきたデザイナーがいる。ロトチェンコ、ステパーノワ、エル・リシツキー、ポポーヴァ、ガン、モホリ=ナジ自身だ。アメリカの型破りなデザイナーで、エンジニア、建築家、アクティビストのR・バックミンスター・フラーもその1人だ。1920年代にすでに工業化による環境破壊を激しく批判し、その緩和に人生を捧げた。また、第二次世界大戦中から戦後の住宅不足を具体的に解決するデザインに身を投じ、素早く安全に建てられるプレハブ構造を開発した。1960年代から70年代にかけては、「包括的・総合的デザイナー」運動を世界で展開するキャンペーンを仕掛け、デザイナーがコマーシャリズムを捨てて、総合的な視点から考え、それぞれのスキルをよりよい未来の構築に注ぐことを期待した。モホリ=ナジの言う姿勢としてのデザインの概念と驚くほど似ている。
デザインは、政治抗議の雄弁な手法としても展開されてきた。1968年5月の学生蜂起では、フランスの若い芸術家やデザイナーがパリの美術学校エコール・ド・ボザールを占拠してアトリエ・ポピュレール(民衆工房)を設立し、「抗争のための武器」だというポスターを何百枚と制作した。1980年代後半から90年代前半にかけては、「グランフューリー」の無名のメンバーたちが世界でエイズの認知を高め、誤ったイメージを正そうと、バナーや掲示板、Tシャツ、ステッカーなどをデザインした。グランフューリーといえば、一連のポスターに掲げた言い得て妙なスローガンが記憶に残る。「人を殺すのはキスではなく欲と無関心」。
こうしたプロジェクトは大きな励みだが、姿勢としてのデザインは、20世紀のデザイン界ではほとんど注目されなかった。ところがここ10年の間に、デザインは『ヴィジョン・イン・モーション』に書かれているような、制約のない柔軟なメディアへとラディカルに変貌した。
一番のきっかけは――当事者個人の決意や頑張りは別として――デザインのあり方や可能性を変えるデジタルツールの大量出現だ。その技術のほとんどはベーシックで安価だが、想像的に活用すれば、デザイナーが自発的に大きな仕事をすることも夢ではなくなる。たとえばクラウドファンディングを使えば資金集めができる(また、アキュメン、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ基金、ケンデダ基金など、ソーシャルデザイン、人道的なデザイン事業を支援するチャリティ財団の助成金もある)。デザイナーは、ふつうのパソコンで膨大な量の複雑なデータを管理し、ソーシャルメディアを使って自分の仕事を知ってもらい、協力者やサプライヤー、ファブリケーターなどを集め、資金援助を受け、メディアに取り上げてもらうことができる。これらの変化は、個別にはデザイン文化にプラスの影響を与えただろうけれども、全体としてはプラスにもマイナスにもなっている。また、「きわめて重要な領域で確立されている手法がもはやその目的にそぐわなくなっている」という認識の高まりも、今日の志あるデザイナーにとって好都合だ。社会サービス、医療、経済開発、災害対策といった領域の専門家はますます柔軟に新しいアプローチやその試みを受け入れつつある。
すべてのデザイナーが姿勢としてのデザインを実践するというわけではないし、そうするべきでもない。今後も多くはこれまでどおり専門分野——カー、ファッション、グラフィック、インテリア、プロダクト、ソフトウェア、ユーザーエクスペリエンスのデザイン——を従来の方法で学び、商業デザイナーになるだろう。それに喜びややりがいを感じ、価値のある生産的な仕事だと考える幸運な人もいるだろうし、中には社会や環境の改善につながるような商業的なデザインプログラムに貢献する人もいるだろう。たとえばクリーンな再生可能エネルギーをより効率的に生成するシステムの開発などのように。政治、文化、環境など、関心のある問題を追求するこのチャンスに飛びつく個人デザイナーは、今後もっと増えるだろう。独自のやり方を見出し、アーティストやプログラマーのほか、経済学、政治学、考古学、社会学、心理学、統計学などのスペシャリストと連携する人も増えるだろう。またそうした分野にもデザインやデザイナーを受け入れる素地ができるだろう。まさにモホリ=ナジがビジョンとして描いたように。
姿勢としてのデザインを実践するとはどういうことかは次の章で説明するが、その前に2つの例を紹介したい。1つは、今のところ最も大それた、最もメディアに注目されているプロジェクトの1つ、「オーシャンクリーンアップ」だ。オランダの非営利組織が世界最大の汚染問題の1つに対処するため、海を汚している大量のプラスチックごみを取り除こうとしている。2013年、工学部在学中の19歳の学生ボイヤン・スラットが、休暇でギリシャへダイビングに行き、魚よりビニール袋が多いことに気づいて、設立した。オーシャンクリーンアップは、まずクラウドファンディングで220万ドルの資金を集め、巨大な浮体構造を考案した。スラットは、これを使って太平洋に形成された巨大なごみベルトのプラスチックごみを回収しようとしている。その計画は、科学者や環境専門家の批判を受けながら、3000万ドルの資金集めに成功し、プロトタイプを完成させ、初期テストをクリアして、2018年には太平洋でのトライアルを開始する。
露出は少ないが、同じくらい野心的なのが、「セへト・カハーニ」だ。すでにパキスタン女性への医療の質に大きな影響を与えている。2人の医師、サラ・クーラムとイファ・ザファルの本能的ともいえるデザインの才能のおかげだ。パキスタンでは、国内の医大卒業生の4分の3が女性であるにもかかわらず、深刻な女医不足に悩まされている。卒業してもすぐに結婚する女性が多く、家族や周囲から仕事を辞めるよう大きなプレッシャーをかけられる。クーラムも妊娠後、仕事を辞めざるを得なくなった。パキスタン女性の多くが男性の医師にかかりたがらないため、結果として女性を診る女医が不足している。クーラムとザファルは、パキスタンの社会起業家アシェル・ハサンとテレクリニック(遠隔医療)のネットワークを作り、女医が自宅にいながらにして、女性患者をライブ動画で診察できるようにした。治療は、連携するクリニックの女性看護師や地域の保健活動員が手配する。もともと「Doct HERS」と名づけられたこの構想は、2014年にカラチのスルタナバードで試験運用されたあと、他の都市や医療資源がさらに希少な農村部に展開された。クーラムとザファル、他のスタッフたちも、数多くの問題にぶつかった――地方のクリニックでは電力供給が不十分だったり、技術に疎い患者に画面の医師が本物だとなかなか信じてもらえなかったりした—が、解決してきた。現在はセへト・カハーニのネットワークを全国に広げようとしている。
パキスタン、カラチにある「セへト・カハーニ」の「E-Hub Model Colony」で医師の遠隔診療を受ける患者。セへト・カハーニはパキスタン全土に女性や女児がオンラインで女医の診断を受けられる遠隔医療ネットワークを構築している。
従来、医師の不足やプラスチック汚染を、デザインで解決できると考える人はいなかった。個人のデザイナーがオーシャンクリーンアップほどの壮大な環境事業の立ち上げに3000万ドルもの資金を集められたことや、クーラムとザファルのような医師が自分の仕事にデザインが役立つと気づくことなど想像できなかった。今もって「デザイン=スタイリング」「海のプラスチックごみを回収するどころか、生みだしている張本人だろう」と多くの人が思いがちだ。モホリ=ナジの《design for life》というビジョンを実現するには、そのような既成概念を払拭しなければならない。それには、自発的なプロジェクトかどうかにかかわらず、デザインがデザイン以外の場面で有益であることを証明していくしかない。そうでなければ、デザインが戦争犯罪被害者の正義を実現し、効率的なグローバル電子ごみ処理システムを開発できると政治家や官僚やNGOは認めてくれないし、医師は今後も実験を続けようと思わない。デザインが生活においてもっと影響力のある大きな役割を演じる権利を得るには、そうする価値があることを実証していくしかない。『ヴィジョン・イン・モーション』に書かれているように、《目の前の問題を解決し、無から有を生みだすという広く意味のある姿勢》で、賢くセンシティブに活かされることによって。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。