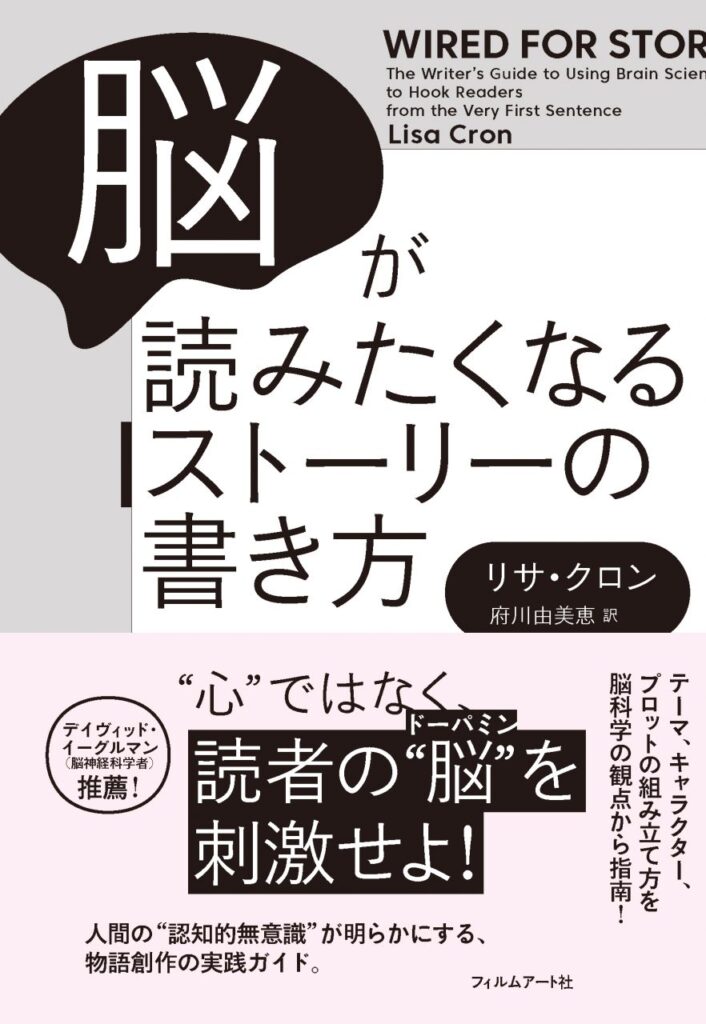Introduction はじめに
むかしむかし、賢い人々は、世界は平らだと信じきっていた。しかしその後、世界は平らではないことがわかった。それでも彼らは、太陽は地球のまわりを回っているのだと信じていた……その理論も間違いだとわかるまでは。さらにそれよりもずっと長いあいだ、賢い人々は、物語がただの娯楽の一形式だと信じていた。物語が与えてくれる限りない楽しみ、面白い物語が私たちに残してくれる一時の喜びと深い満足感のほかに、物語そのものには欠かせない目的などないのだと思っていた。もちろん物語がなければ、人の生活ははるか昔からもっと彩りの欠けたものになっていただろうが、それでも人間は生き延びてこられたはずだ、と。
これも間違いだ。
物語は人間の進化にとって重要なものだ――ほかの指と向きあっている親指(オポーザブル・サム)よりもずっと。親指があるおかげで、人間は物をしっかりつかむことができるが、物語は何をつかむべきかを教えてくれる。物語とは、未来に起きうることを想像し、それに備える能力を与えるものだ。親指があろうとなかろうと、ほかの生物にはない妙技だ[1]。物語は、隠喩としてのみならず、文字どおり私たちを人間たらしめてくれる。脳科学の近年の飛躍的な進歩により、人間の脳には物語に反応する神経系統が組み込まれていることがわかっている。よくできた物語がもたらす喜びとは、人間が物語に注意を向けるよう誘い込むための、自然の手だてなのだ[2]。
つまり人間は、世界の動きを教えてくれる物語に反応するようにできているというわけだ。誰にだって、高校時代の歴史の先生がドイツの君主の名を懸命に暗唱するのを聞きながら、つい眠気を誘われた経験はあるだろう。それは名誉にも、あなたが人間である証だ。
人がノンフィクションよりフィクションを好みがちなことも、そう考えれば驚きではない。歴史書よりも歴史小説を、無味乾燥なドキュメンタリーよりも映画を好む人間は多い[3]。それは人間が怠け者だからではなく、人間の神経回路が物語を求めるようにできているからだ。優れた物語が誘発する陶酔感は、人間を隠れ快楽主義者にするためのものではない。この陶酔感のおかげで、人間は個々の物語が伝える大量の教訓を吸収し、熱心に学ぶ生徒としてしつけられていく[4]。
これは作家にとっては、事態を一変させる情報ではないだろうか。調査研究の助けを借り、読者の脳に組み込まれた物語の真実の青写真を解明できれば、脳が物語に何を求めるのかも明らかにできる。さらに興味深いことに、力強い物語は、読者の脳を書き換えることもできるという―たとえば感情移入を使うなどの方法で[5]。だからこそ作家は、つねに世界に大きな影響力を持つ人間と見なされてきたわけだ。
作家は自分のキャラクターの目を通じ、ただ人生というものを垣間見せるだけで、人々の考えを変えてしまうこともできる。読者を、行ったこともない場所へ連れだしたり、夢見ていただけの状況へ投げ込んだり、読者の現実認識を完全に変えてしまうような世の中の複雑な真実を明かして見せたりすることもできる。苦境を乗り越えるために必要な、大なり小なりの助けを与えることもできる。こうしたことは、決してささいなことではない。
ただし難しい点もある。読者の心をとらえる物語を書くには、たえず読者の神経系統が期待するものに応えなければならない。アルゼンチンの作家、ホルヘ・ルイス・ボルヘスが「芸術とは炎に代数を加えたもの」と言ったのも、このことだろう[6]。これについて少々説明しておきたい。
〝炎〞は、書き手には確かに重要なものだ。どんな物語でも、これが第一の構成要素となる。情熱は執筆を駆り立て、自分の言いたい何か、人と違う何かがあるという刺激的な感覚を与えてくれる。
だが、瞬時に読者を魅了できる物語を書くためには、情熱だけでは足りない。優れた物語を創るには、炎――燃えるような野心、創造の火花、真夜中にはっと目が覚めてしまうような鮮烈なアイデア――があればいい、と勘違いしている作家は多い。喜び勇んで物語に飛び込んでも、物語の方程式に必要なもうひとつの因数、つまり〝代数〞を忘れてしまえば、書いたすべての文章が失敗に行きついてしまう。
この点でボルヘスは、のちに認知心理学と脳科学が解明したことに、直観的に気づいていた。つまり、こうした情熱、こうした炎で読者の脳を焚きつけるには、まず物語の基盤となる潜在的な枠組みがなければならないことを知っていた。この枠組みがない物語は読まれない。そしてこの枠組みを持つ物語なら、どんなに頑なな読者の度肝も抜くことができる。
物語創作にはアイデアや言葉の選択以外にも大事なものがあるということを、受け入れたがらない作家が多いのはなぜだろう? 人間は読む物語には夢中になりやすいが、そのぶん書く物語への理解を曖昧にしがちだ。誰もが本能的に、どんなものが面白い物語かはわかると信じている――逆に、面白くない物語もすぐにわかる。面白くないと思ったら、せせら笑って本棚に戻せばいい。あきれて目をぐるっと回し、それから映画館へ出かけてもいい。親戚のおじさんがぶつぶつと南北戦争を語り始めたら、そのときは深呼吸をして、早く話が終わることを祈るしかないが。人間は、出来の悪い物語には3秒と耐えられない。
出来の良い物語もすぐにわかる。人は3歳ぐらいからその識別ができ、以来さまざまな形式の物語に耽溺する。人間の神経系統が、物語の最初の一文からこれは面白いとわかるようにできているのなら、面白い物語を書くのだって簡単なはずではないか?
これについても、進化の歴史が答えを提供してくれている。そもそも物語は、人間の生命を維持する特定の情報を共有するため、仲間をまとめる方法として生まれた。「ほら、そこの若いの、そのつやつやした赤い実を食べちゃいかん、でないと隣のネアンデルタール人みたいなしわがれ声になるぞ、実は前にこんなことがあったんだ……」。そんなふうに、かつての物語は単純で実用的なものであり、現在ではゴシップと呼ばれるものとも大した差はなかった。長い年月を経て書き言葉が進化すると、物語は近隣のニュースや共同体の心配事にとどまることなく、自由に広がり始めた。その結果、読み手――神経系統にあらかじめ物語への期待が組み込まれた読み手――は、物語そのものの魅力に惹きつけられるようになった。どんな時代にも熟練の語り手は存在していただろうが、頭がいかれたいとこのちょっとした噂話を共有するのと、〝偉大なるアメリカ小説〞を生みだすのでは、話はまったく違ってくる。
もちろん、野心ある作家も物語を読むのは好きに違いない。が、読者を惹きつけるものは何かという問いに最高の答えを与えてくれるのは、彼らがむさぼり読んだお気に入りの本たちだろうか?
違う。
これも進化によって生じた効果だが、人間が面白い物語に接すると、「どうやってこんな魅力的な現実の幻影を創ったのだろう」という脳の問いかけは、完全に麻痺させられてしまうものらしい。つまり、面白い物語は、幻影とは感じられないものなのだ。まさに人生そのもののように感じられる――文字どおりに。最近『サイコロジカル・サイエンス』誌に報告されたブレインイメージング研究によれば、視覚、聴覚、味覚、そして現実生活の動きといった感覚を処理する脳の部分は、人が魅惑的な語りに夢中になったときに活性化されるという[7]。真夜中を過ぎても読書をやめられずに徹夜してしまうとき、人があざやかな心的イメージ〔現実に物理対象が存在しないにもかかわらず生じる類知覚体験〕や本能的な反応を感じるのもそのせいだ。物語が人の心を奪うとき、読者は物語の渦中にいて、主人公が感じることを感じ、わが身に起きたことのように体験している。物語の仕組みに注目する余裕などない。
要するに、どんな魅惑的な物語の根底にも、相互に組み合わされてひとつにまとまり、一見そうは見えなくても精密に構築された網の目のような要素があるのだが、それに読者がまったく気づかないとしても驚くことではない。このため読者は、自分が引き込まれたものがなんなのか、正確に理解しているような気分になりがちだ。しかし、美しいメタファー、本物らしく響く会話、興味深い登場人物、そうしたものがいかに魅力的であっても、実際には二次的な要素でしかない。読者を引き込むのはもっと全然別の、奥底からひそかにこうした要素に生気を与えているものなのだ――私たちの脳はそれを〝物語〞として理解している。
人が物語を読むときに無意識に反応しているものは何か。何が実際に人の脳の注意を惹いているのか。少し立ち止まってそれを分析しないことには、読者の脳をとらえるような物語を書くことはできない。書きたい作品が文学的な小説だろうと、ハードボイルドなミステリーだろうと、ティーン向けの超自然的なロマンスだろうと同じことだ。ジャンルということでは読者に個々の趣味はあるにしても、物語が読者の脳に組み込まれた期待に見合ったものでなければ、その本は本棚に置き去りになるだけだ。
あなたの書く物語がそんな目に遭わないようにするため、本書では、全12章の各章において脳機能のさまざまな側面に焦点を当て、物語に関連した思いがけない真実や、物語作品において実現すべき要点を明らかにしていこうと思う。各章の終わりには、チェックポイントのリストがある。あなたの作品が今どの段階にあっても使えるリストだ。執筆に取りかかろうとしているときでも、毎日の執筆作業が終わったあとでも、ひとつの場面や章を書き終えたときでも、あるいは夜中の2時に冷たい汗をかいて目を覚まし、自分の書いている物語は史上最悪の作品だと思い込んでしまった場合でもいい(きっとそんなことはない、大丈夫)。このリストを使えば、あなたの作品は軌道をはずれることなく進み、あなたの知り合いでなくとも読みたいと思ってもらえる作品に仕上がるチャンスが膨むはずだ。
警告をひとつ。自分の物語のことは、あなたが書店で手に取る小説や、リモコンに指を載せたまま観始めた映画と同じくらい、正直な目で見るようにしてほしい。本書の目的は、作品のどこに問題点がひそんでいるかをつきとめ、問題が雑草のごとく広がって全体をだいなしにする前に修正することだ。この作業は、やってみると想像以上に楽しい。自分の作品を磨き、物語であることさえ読者が忘れてしまうような魅惑的な作品に仕上げるのは、これ以上なく爽快な体験だからだ。
1. M. Gazzaniga, Human: The Science Behind What Makes Your Brain Unique (New York: Harper Perennial, 2008), 220.[マイケル・S・ガザニガ『人間らしさとはなにか?―人間のユニークさを明かす科学の最前線』柴田裕之訳、インターシフト]
2. J. Tooby and L. Cosmides, 2001. “Does Beauty Build Adapted Minds? Toward an Evolutionary Theory of Aesthetics, Fiction and the Arts,” SubStance 30, no. 1 (2001): 6-27.
3. 同上.
4. S. Pinker, How the Mind Works (New York: W. W. Norton, 1997/2009), 539. [スティーブン・ピンカー『心の仕組み―人間関係にどう関わるか〈上中下〉』椋田直子訳、NHK出版]
5. M. Djikic, K. Oatley, S. Zoeterman, and J. B. Peterson, “On Being Moved by Art: How Reading Fiction Transforms the Self,” Creativity Research Journal 21, no. 1 (2009): 24-29.
6. J. L. Borges, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius,” in Ficciones, trans. Emecé Editores (New York: Grove Press, 1962), 22.[J・L・ボルヘス「トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス」『伝奇集』鼓直訳、岩波書店]
7. PhysOrg.com, “Readers Build Vivid Mental Simulations of Narrative Situations, Brain Scans Suggest,” January 6, 2009, http://www.physorg.com/print152210728.html.
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。