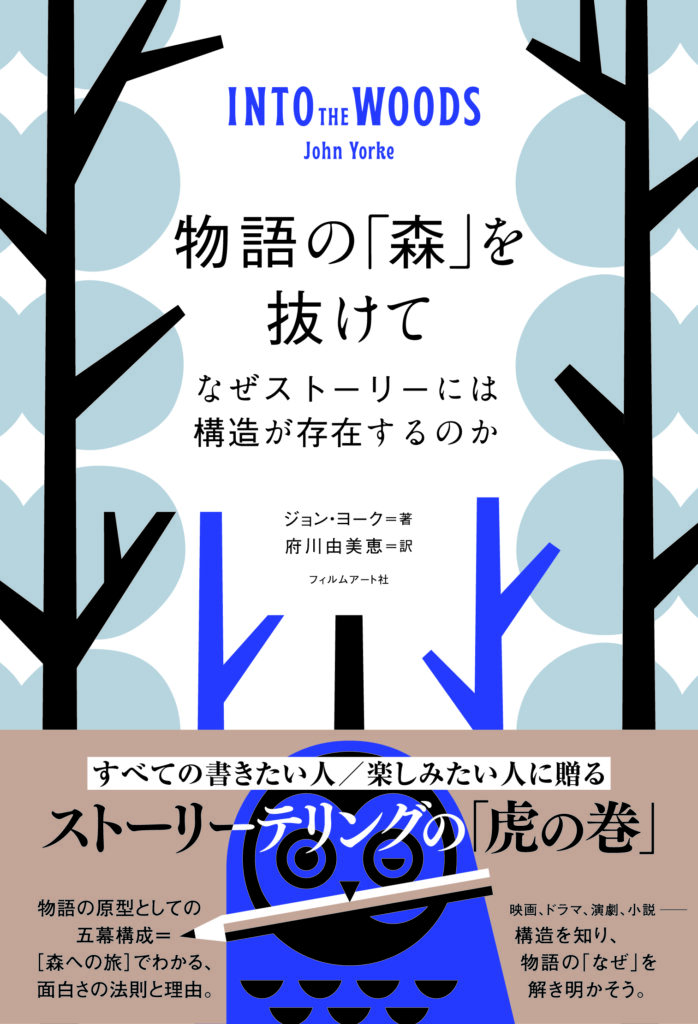1 物語とは何か?
「むかしむかし、あるところに……」
出だしのこのフレーズを読めば、これから自分が物語の舞台と出会い、そこでさまざまな出来事が起きるのだということがたちどころにわかる。だいたいの人間がそう思うはずだ。物語についての基本的な言葉、物語の定義そのものだ。「むかしむかし、これこれこういう場所に、こういうことが起きました」。もちろん、これから触れるとおり、もっと複雑な説明も出てくるが、ここまですべてを包括している単純な言葉はないだろう。
原型的な物語は、まず中心的な登場人物、いわゆる主人公を紹介し、読者が主人公と一体化するように誘いかける。主人公は、物語における読者の実質的な化身となる。読者は主人公を自分に重ね合わせ、それを通じて物語を体験する。主人公が危機に陥れば、読者も危機に陥る。主人公が熱狂すれば読者もそうなる。『トランスフォーマー』シリーズや、テレビドラマ『シークレット・アイドルハンナ・モンタナ』を観ている子どもを観察してみるといい。子どもたちの感情が視聴の過程で変化し、自分を重ねている架空の人物の運不運と切り離せなくなっていくさまには、目をみはるものがある。
そんなふうにして、読者は中心的な登場人物を得て、彼らに感情移入する。その彼らに何かが起き、それが物語の始まりとなる。ジャックは豆の木と出会う。ジェームズ・ボンドはブロフェルドが世界征服を企んでいることを知る。この「何か」は、ほとんどの場合厄介事だが、厄介事を装ったチャンスの場合もある。たいていその何かが、主人公の住む世界をおかしくしてしまう。彼らの正常で着実な生活ペースに、なんらかの爆発が起きる。アリスはウサギの穴に落ちる。『MI-5英国機密諜報部』のエージェントたちは過激派テロリストの陰謀に気づく。ゴドーは現れない。
主人公は解決しなければならない問題を抱える。アリスは現実世界に戻らなければならない。エージェントたちは午後二時にロンドンのどまん中で爆弾が爆発するのを阻止しなければならない。ウラジーミルとエストラゴンはゴドーを待たなければならない。物語とは、彼らが与えられた問題を解決するために続ける旅だ。その途上で彼らは、自分についての新しい何かを知る。克服しなければならない一連の障壁にも直面する。物語の終わり間近では、すべての望みが潰えたように見えるが、ほぼまちがいなく望みは土壇場で復活し、最後の闘いがあり、敗色濃厚から一転して勝利をつかむ。
どんな物語においても、この形(もしくはその悲劇バージョン)がある程度機能しているのは見てとれるだろう。『エイリアン』や『ジョーズ』のように、大きく明確な形を示していることもあれば、『普通の人々』のようにそれとない形のこともあり、その形に対する反発的表現として出てくる場合もある(ジャン゠リュック・ゴダールの『ウイークエンド』のように)。それでも、必ずそこにあり、デル・トロ、カウフマン、ヘアーの作品にもあるものだ。特に古典的な犯罪ものや、病院ドラマの枠組内でははっきりとわかる。人が殺される、あるいは誰かが病気になる。刑事は殺人犯を見つけなければならず、医者は患者を治療しなければならない。こうした物語は文学における麻薬のようなものだ――あらゆる不純物が排除されたストーリーテリングであり、喜びの注射であり、最低限の努力で最大限の見返りが得られる。刑事もののフィクションが人気なのはそのせいだ。どんな物語においても大なり小なり現れる統一的なファクターは、特にこうしたジャンルではいちばん活用しやすい。
だが、問題とその答えの探索が物語の枠組を作るとすれば、物語は実際にどんな要素から構築されているのだろう?
必要不可欠な構築ブロック
主人公
主人公は物語の中心にいる人物である。通常は誰がそうか明白にわかる。バットマン、ジェームズ・ボンド、インディアナ・ジョーンズ。複数の主人公がいる物語であればわかりにくいこともあるが(テレビドラマ『イーストエンダーズ(EastEnders)』やロバート・アルトマンの『ショート・カッツ』のように)、つねに観客がいちばん気にかける人物が主人公だ(少なくとも主人公が正しく機能しているうちは)。
とはいえ、ここですでに難しい問題がある。「気にかける」とはしばしば「好き」と同義に解釈されがちで、そのためたくさんの脚本家のもとに「主人公を善人にしてほしい」というメモが(執筆活動をしないお偉方から)回ってきたりする。テレビドラマ『ブルックサイド(Brookside)』の脚本にも参加し、イギリスでも最も成功した映画脚本家のひとりであるフランク・コットレル゠ボイスは、かなり強くこう主張する。「共感は、業界幹部にとってはクラック・コカインのようなものだ。私も、よく書けた自分の脚本を、共感マニアの幹部に一度ならずだいなしにされたことがある。もちろん、観客には登場人物と心理的つながりを持たせる必要があるが、その人物を是認する必要はない。登場人物が何かひどいことをすると、ハリウッドはすぐ弁明できる形にするよう要求してくる」◆01
人は『失楽園』に登場する悪魔のことが嫌いではない――むしろ大好きだ。完璧な邪悪の権化として面白いからこそ愛されるのだ。親切な登場人物はつまらなくなりがちで、短所や不愉快な部分が何もなければ、人を惹きつけることもない。荒削りな部分や暗い部分があるほうがずっと興味をそそるし、人はそういうのが大好きだ。自分では認めていないとしても、そうしたものは人の心の奥深くに触れてくる。『グランド・セフト・オート』や『コールオブデューティモダン・ウォーフェア』などのゲームをやったことがある人間(何百万人といるはずだ)なら誰でも、文字どおりのアバターに入り込んで、邪魔な誰かを殺したり、ひどい傷を負わせたり、破壊したり、眠らせたりしている。人は誰の頭の中にも入っていける。劇作家のデイビッド・エドガーは、ナチス・ドイツの建築家アルベルト・シュペーアを題材とした自分の戯曲の正当性を、次のように説明している。「恐ろしい真実――良くも悪くも恐ろしい真実なのだが、偉大な演劇作品の多くが観客に求める反応は、『はい、それで結構です』でもなければ『いいえ、私はちょっと』でもなく、『私と同じですね?』なのだ。さもなければもっと現実的な言葉、『神のおかげだ、私は運が良かった』だ」◆02
だとすれば、感情移入の鍵は、礼儀正しさでも品行方正さでもない。よく言われるように、動機を理解できればいいというものでもない。確かに、登場人物の行動の理由がわかれば、観客はよりその人物を好ましく思うというのはある。だが、それは感情移入の兆候ではあるが、根本的な理由ではない。観客が共感できるかどうかは、その人物が観客の無意識に近づき、結びつきを生みだすことができるかどうかにかかっている。
フィクションの警官、それに医者もそうだが、なぜ彼らは一匹狼が多いのだろう? 脚本家が怠惰なだけかもしれないが、特定の登場人物の特徴が広く行きわたったせいなのだろうか? 『THE KILLING/キリング』の視聴者の多くが、サラ・ルンドにどうしようもなく惹かれるのはなぜなのだろう? 三文小説の似たタイプの登場人物と同様、サラもルールを破り、上司の言うことを無視し、その意向に背いて動く。上司からは「二十四時間以内に手を引かないと、君をこの事件からはずす」と言われる。なぜサラのような一匹狼は、人気が出るのだろう?おそらく、誰もがときおり同じ気持ちを感じるからだ。自分のまわりには、愚か者や、頭が硬くて官僚主義的な上司や、上役の顔色ばかり見て目の前の真実が目に入らない、創造性のない同僚しかいないと考えたことは、誰にでもあるのではないか?
架空の登場人物の頭の中に入ることが感情移入だとすれば、当然、自分と似た感覚を持っている頭のほうが入っていきやすい。サラ・ルンドが上司の言い分を拒否するのを見た視聴者は、「自分もそうできたらいいのに」と考える。『コール・ザ・ミッドワイフロンドン助産婦物語』でミランダ・ハート演じるチャミーを観ていると、つい彼女の不器用さに同情し、その無力さを自分に重ねてしまう。復讐を遂げる、自分の価値を証明する、あるいは(サラ・ルンド刑事のように)最終的に自分の正しさを証明する登場人物の生きざまを追体験するのは、非常に魅惑的だ。願望成就、慈善行為、自己破壊欲求の楽しみも侮れない。『シンデレラ』の普遍性や、マーベルのフランチャイズ作品の世界的支配力はその典型だ。スパイダーマンになることにあこがれる人々の中には、必ずピーター・パーカーがいる。人々のお気に入りのキャラクターとは、暗黙のレベルにおいて、良くも悪くも、醜い部分までも含めて、自分がなりたい人物の具現化なのだ。人はアドルフ・ヒトラーにも感情移入できると言われればたじろがれるかもしれないが、『ヒトラー最期の日間』を観れば可能なことなのがわかる。優れた脚本家は、観客を誰とでも結びつけてしまえる。◆03
観客が物語のたくらみにとらえられる瞬間は、演劇全般における最大の魔法のような瞬間だ。いちばんよくわかるのは、劇場で芝居を観ているときだ。主人公が観客の内に入り込み、支配権を握った瞬間、劇場が静まり返る。感情移入についてはまた後述するが、『モダン・ウォーフェア』のゲーム内で虐殺が認められるのは、世界を救うミッションをおびているキャラクターがプレイヤー自身だからだということは指摘しておこうと思う。
ミッションは重要なパートだ。登場人物の目標や欲求から、彼らに関するたくさんのことがわかる。登場人物が、失われた聖櫃をナチスから救いだしたがっている、あるいは、警察に追われてメキシコに逃亡したいのに、自分が性的暴行を受けたテキサス州を通る楽なルートは避けようとするといったことから、彼らの人となりがだいぶわかる。
原型的な物語は、例外なくひとつの必須の教義に定義される。中心となる登場人物には、能動的な目標があるということだ。彼らは何かを求めている。でなければ、登場人物に関心を持つのはほぼ不可能だし、関心を持つ理由もない。彼らは観客の化身であり、入口でもある。観客がいちばん勝利してほしい、報われてほしいと望む人物だ。また、観客は潜在意識の中で、自分の欲求に対する深い自虐性を持つことがあるため、登場人物が罪を犯せば罰を受けるべきだと感じがちだ。登場人物は実質的に観客自身なのだ。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。
注
◆01 Frank Cottrell Boyce, ʻHow to Write a Movieʼ, Guardian,30 June 2008
◆02 David Edgar, ʻIn Defence of Evilʼ, Observer, 30 April 2000. 記事はこう続く。「メアリー・ベル〔1968年に11歳で連続殺人を犯したイギリスの少女〕事件の被害者の両親が、サン紙に『メアリー・ベルは感情のある人間として考慮される価値などない』と書いたのは、理解はできるが悲しいことだし、ほかの人間たちに責任逃れをさせているだけだ。悪と呼ばれるものが存在し、それが悪人とそれ以外の人間を分けているという考えは、なぐさめにしかならない幻想だ。不快な真実を理解するには、認識と共感が必要なのだ。邪悪な人間の目を通して世界を見て、自分自身の内にもある衝動や怒りや恐れを見いだし、痛みのなかで認めなければならない――別の状況下なら、自分もそうしたものによって、恐ろしい行動に駆り立てられる可能性があることを。
ピーター・ブルックが『なにもない空間』で書いているように、『劇場では、過去の過失はつねに清算されている』のである。演劇は、人々の最も暗い衝動を、実験室的な状況のもとで試し、直面することのできる試験用飛行機だ。そこでは観客は、結果を気にすることなく、欲望を体験できる。演劇は、父王を荒野に追いやった人間の魂ではなく、追いやりたいと思っている人間の魂を、観客にのぞき見させてくれる。
だが、衝撃は最初だけにすぎない。次の瞬間には、観客はそのながめを楽しんでいる。その楽しみこそが、われわれに、自分の我慢ならない面と向き合わせてくれるのだ」。
◆03 ポール・シュレイダーは『タクシードライバー』についてこう言っている。「観客が共感の価値がないと感じる人物に、(観客を)共感させることができる。そうなれれば、かなり面白い立ち位置にいるということだ」(The Story of Film, More 4, 2011)。