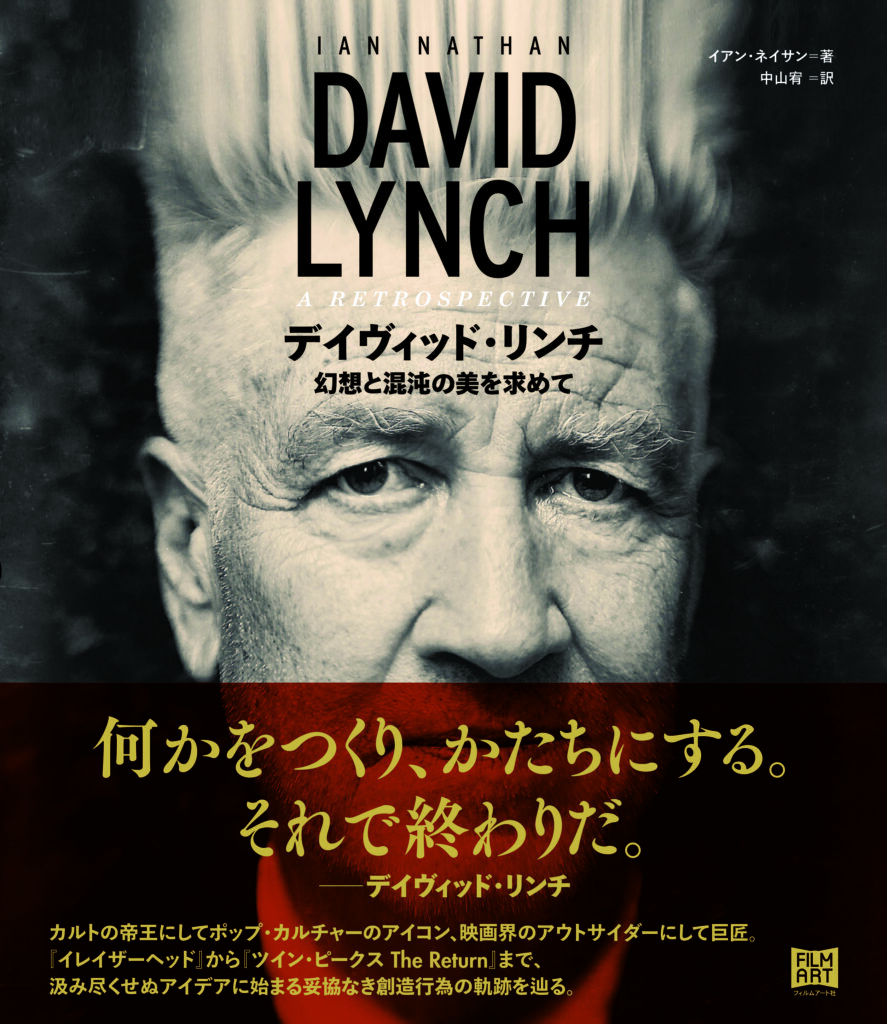イントロダクション
答えは単純明快だ。彼がインタビューに応じるようすを聞けばわかる。懐かしのテレビホームコメディ『ビーバーちゃん』から抜け出てきたかのような、古風で純真無垢な声調。模範的なボーイスカウトのリーダーを彷彿とさせる。テレビアニメ『ザ・シンプソンズ』に出てくるいつも陽気な隣人、ネッド・フランダースは、彼の冷静で礼儀正しい話しかたをもとにつくられたキャラクターだとの噂もある。それは真偽が定かでないにしろ、D・B・クーパー特別捜査官の魅力は、間違いなく、そのような落ち着いた話しぶりにある。ともあれ、先に結論を言っておこう。デイヴィッド・リンチが映画監督になったのは、自分の絵画に動きを与えたかったからだ。
時は1966年。私たちは今、「リンチアン」という芸術上の旋風の発生地であるフィラデルフィアの街にいる。言い換えれば「リンチアン」の源泉だ。リンチはペンシルヴェニア芸術アカデミーに通っている。とはいえ、講義室へ足を踏み入れることは滅多にない。日々を絵画に捧げている。それは使命感というより、原始的な衝動だ。人生をダークに描写し、みずからの扉の外の世界を独特なスタイルで精製していく。少年のような端正な顔立ちの奥に、独自の思考を秘めている。
彼は大きなアトリエの中に小さなブースを持っており、そこで夜の庭の絵を描いている。「ほとんどが黒で、ところどころに葉の緑が混じっていた」と彼は回想する。彼がその絵を見つめて立っているうち、そよ風のさざめきが聞こえ、葉が動き始める。風はどこから来たのだろう――疲労から、カフェインから、アイデアが湧き出す内なる領域から――彼には分からない。しかし、ある確信が生まれた。自分は“動く絵画”をつくりたいのだ、と。
「あの人は、自分の絵画にもっと多くのことをさせたいと思ったんです」リンチの4人の妻のうち最初の妻、ペギー・リーヴィーは、そう語る。「音を出させたかった。さらにいろんなことをさせたかった」
こうして、アメリカ映画史上、最も過激で、強烈で、奇妙で、滑稽で、恐ろしく、深遠で、忘れがたい作品の創造が始まった。テレビへの貢献も忘れてはならない。リンチほど熱く論じられ、深く分析され、愛され、拒絶された監督はほかにいない。にもかかわらず、彼はつねに、制作過程を非常にシンプルなものとして捉え、いつも同じやりかたでインスピレーションを待つ。すなわち、数々のアイデアが自分のほうへ吹き寄せられてくるのを待ち続けるのだ。それがゆっくりと蓄積され、やがて『ブルーベルベット』や『ツイン・ピークス』や『マルホランド・ドライブ』のような作品になる。
長年にわたって、リンチを形容するフレーズが数多く生まれた。「奇想の皇帝」「アメリカ屈指の前衛芸術家」……。優れた批評家ポーリン・ケイルは、リンチを「夢の論理のフランク・キャプラ」と定義した。メル・ブルックスは「火星から来たジェームズ・ステュワート」と評した。元テレビ司会者のジェイ・レノは「サイコパス版のノーマン・ロックウェルのよう」と紹介した。映画と夢のあいだに横たわる境界の国に、私たち観客をこれほど近づけた映画作家はいない。善と悪が同じ町、同じ人々のなかに棲みついているという、人生の二面性をこれほど露わにした映画作家はごくわずかしかいない。
「人間は探偵に似ていて、何が起こっているのか、真実は何なのかを知りたがる」とかつてリンチは言った。彼の映画には、さまざまなサイズやかたちの探偵が登場し、不可解なものと遭遇して戸惑う。と同時に、リンチは、私たちのなかにある覗き見趣味と探偵心をざわつかせる。かといって、やがて明確な答えを提示してくれるわけではない。映像の背後に何があるのか、あらゆる問いかけを拒む。理屈で説明を付けてしまったら、謎を終わらせることになるからだ。「エンディングは偉大な美しさを持つことができる」とリンチは言う。「ただし、夢見る余地を残していれば、だが」
リンチについて書こうとすると、いつも、彼の映画に含まれる無数の謎と、解決の欠如が、複雑に絡み合い、踊り始める。その不確実さこそが、リンチの作品に欠かせないパワーなのだ。私たちは、彼が創造した暗い世界のなかで、みずからの力によって道を見いだすほかない。
本書は、そうした映画やテレビドラマの謎を解き明かそうとする本ではない(その種の試みにも多少は手を出さずにいられないが)。あなたの前にあるのは、よく使われる「リンチアン」という言葉を理解するための探究書だ。「リンチアン」とは、リンチの映画ならではのスタイル、感覚、雰囲気、物語の語り口、登場人物のタイプ、ジャンルのアレンジ、話しかた、風景、街、ユーモアとホラーの融合、現実というヴェールの向こう側への旅、心の奥底にある欲望の考察、リンチが故郷と呼ぶ国の奥深くへの探検をさす。リンチの友人であり、俳優、詩人でもあるハリー・ディーン・スタントンは言う。「デイヴィッドはアメリカ人の精神へ深く分け入っている」
じつのところ、「リンチアン」はある種の共感覚にたとえられる。観客は『イレイザーヘッド』を嗅ぎ、『ブルーベルベット』を味わうことができると言っても過言ではない。かねてから知られているとおり、リンチは、自分が求めている音を視覚的に描いたり、音楽がどのように見えるべきかを言葉で説明したりする。この先くわしく論じるが、要するに、感触や雰囲気、つまりテクスチャーこそがすべてなのだ。
本書は、監督としてのリンチについての本であると同時に、芸術家としてのリンチについての本でもある。「美しいのは行為そのものだ」と彼は言った。それぞれの映画や番組で、アイデアを探し、人生や芸術から得たインスピレーションを注ぎ込み、ストーリーを見いだし、そのあと撮影現場で俳優やスタッフをまとめ、自分のきわめて個人的なイメージをスクリーンに投影し、多くの場合、すさまじい反応を引き起こす。
リンチは、自分のやりかたはシンプルであると語る。すなわち、ふさわしいと感じられるまで作業を続けるのだ。彼の創作物は、流行や商業主義の卑俗な要求に屈していないぶん、監督と芸術がごく緊密に結びついている。共同作業を経て完成したとはいえ、どれもが紛れもなく彼の作品だ。妥協まみれの超大作『デューン/砂の惑星』さえ、「リンチアン」らしい欠点と非凡さをたたえている。『ブルーベルベット』について熱を込めて書いた映画評論家ポーリン・ケイルは、リンチは天才的な異端者であり、彼の映画は特異であると評した。「この映画作家の精神と、観客である自分とのあいだに、装飾や技巧によって生じる隔たりがほとんどないと感じるとしたら、通常ありがちな抑制が少ないせいかもしれない」とケイルは述べている。リンチは、深層心理や直観からの反応に調整や修正を加えず、自然の流れに任せている。
フェリーニやベルイマン以来、みずからの無意識をこれほどまでに掘り下げてインスピレーションを得た映画作家は例がない。しかし、リンチといえども、他との関連性がないわけではない。精力的な批評家であり映画監督でもあるウォルター・チャウは、映画評論サイト「フィルム・フリーク・セントラル」に載せた記事のなかで、リンチ作品にみられる文化的な手がかりを指摘している。「『ブルーベルベット』ではロックウェリアンな(画家ノーマン・ロックウェルふうの)アメリカーナ(アメリカの伝統文化)、『デューン/砂の惑星』ではアントニ・ガウディを介したバウハウス、『ロスト・ハイウェイ』や『マルホランド・ドライブ』ではヒッチコック後期作品に特徴的なアイデンティティの謎が扱われている」
リンチに会うのは鮮烈な体験だ。インタビュー中、彼はどこまでも礼儀正しく、謙虚で、魅力的で、淡々としており、摩訶不思議な信号のように指をくるくると回す。しかし、質問に対するこたえはひどく限定的だ。本書でこれから先、キャリアの浮き沈みをたどりつつ旅していくなかで、彼が謎めいたフレーズを繰り返し発したり、熱のこもった質問をあまりにも難解な返答でかわしたりする場面に出会うだろう。数年後のインタビューでも、一言一句同じ返答をすることが少なくない。服装がつねに一貫している――首までボタンを留めた白いシャツ、黒のジャケット、カーキ色のスラックス――のと似ている。
あらかじめ断わっておくと、本書は、映像作家としてのリンチに焦点を当てており、おびただしい数の絵画、彫刻、写真集、コマーシャル、舞台作品、アルバムには、簡単に触れるだけにとどめている。多様で豊富な芸術や表現が、10本の映画と2本のテレビシリーズを取り囲み、支えており、それらの映像作品を展望することが本書の主眼である。
監督とアーティストという二つの役割を切り離すのは不可能だ。リンチは生来、独創性と個性的演出を明確に打ち出す映像作家、すなわち「オトゥール」といえる。彼の作品は―いや、似たような作品すら―ほかの誰にもつくれない。彼が描き出す風景は、彼自身の心のなかにある。俳優、スタッフ、プロデューサー、スタジオ、さらには熱狂的なファンたちを自分の頭のなかに取り込み、世界で最も有名なシュールレアリストになったというところに、彼の大きな魅力がある。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。