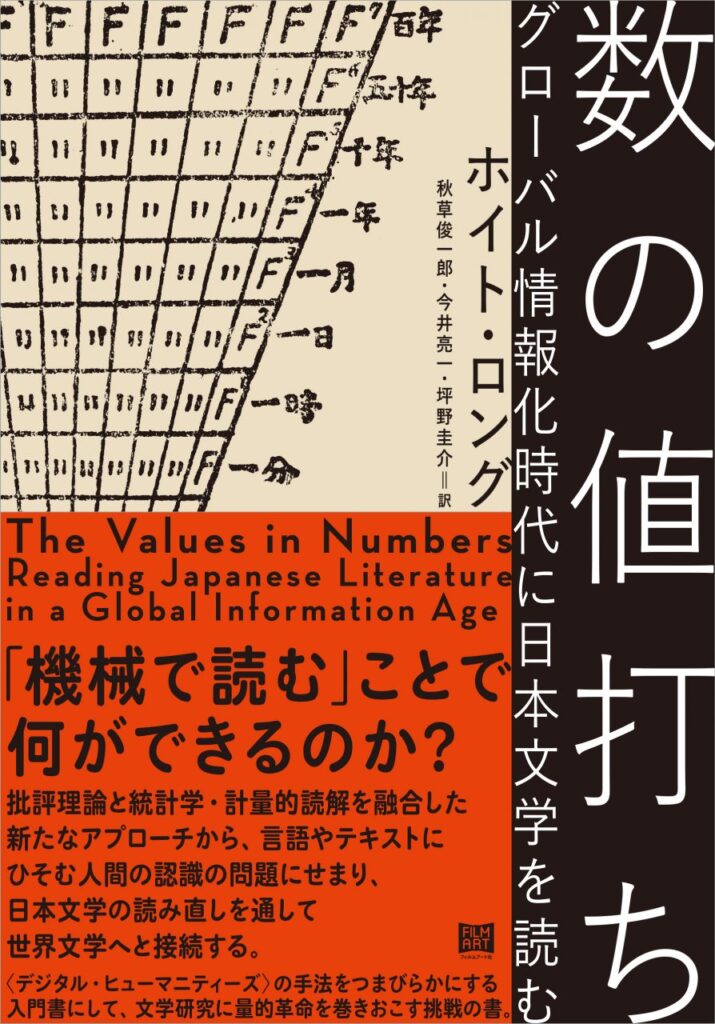序章 数の不確かさ【後編】
【前編】はこちら
本書ではまず、日本文学を読むうえで数の値打ちが認知され、これまでにない理論化の圧力にさらされた瞬間瞬間の系譜を追うことからはじまる。第一章「事実と差異」ではこうした瞬間を、量的手法に訴えかけることが切に求められた制度的、技術的、認識論的コンテキストがいかなものだったのかを読み解くうえでのポイントと見なしている。それぞれの瞬間で、なにが批評家や学者を駆り立てたのか──量的手法を用いて新たな比較と等価の空間にテキストを位置づけたその理由と動機を検証した。夏目漱石が数学的な形式主義をなぜ採りいれたかといえば、国外からはいってきた文学評価のヒエラルキー(欧米の価値観から日本文学は外れていた)から距離をとるためだった。『文学論』(1907)において、漱石はヴィクトリア朝末期の読書の生理学理論にもとづいて、テキストの形式や認識は感情的反応と相関することをしめそうとした。1930年代に波多野完治は、漱石が読者に合わせていた焦点を作者にむけた。学術的には波多野の関心は心理学・言語学・社会学にあり、そうしたものを組み合わせて文体論を展開したのだ。その方法論は、語彙や文法の特徴を分類して集計し、作家特有の文体を標準的な大グループからより分けるというものだった。1950年代には集計作業は、推計統計学者や、冷戦期の情報理論や心理言語学の最先端で活躍していた研究者の一団にとってかわられた。こうした方法は何十というテキストに適用できるため、テキストの形式上の比較がゆるされるようになり、作家や作品と言った使い古されたカテゴリーでの分析を解体していった。1980年代には批評家の小森陽一によって解体は新たな頂点に達した。この時期の小森の仕事は、同時期のモレッティが取りくんだ形式の社会学をどこか思わせる。小森は社会的・文化的ヒエラルキーによって言説が歴史上いかに進化してきたのかという関心をいだき、それを文体論に吹きこんだのだ。いずれの場合も、数字はテキスト上の差異を事実として把握し、提示するための手段だった。そしてそれは、既存の事実と解釈実践の方法に逆行するものでもあった。
この系譜からわかるのは、ある領域の事実(たとえば、平均とはばらばらな測定値を束ねて、意味あるものとして提示する)が引き継がれて、別の領域に適用されるプロセスである。その領域はその領域で、かけ離れた対象同士の関係について、別の事実の束と古くから伝わる知恵をもっているのだ。それぞれの瞬間においてプロセスは、どの事実が文学研究の手法として認められ、どの事実がディシプリン内で幅を利かせる規範によって弾かれるのか、テストをおこなう。これは、文学テキストの意味と価値と同じくらい、数字の意味するところを決定するものでもあった。日本におけるこの系譜をたどることで、このプロセスが共通の技術的インフラと情報のエコノミーをつうじていかにグローバルな知の潮流と合流したのかがわかるだけでなく、さらにはそうしたインフラとエコノミーにはつきものの不均衡とローカルな文脈によっていかにプロセス自体が変容したのかもわかるようになる。このプロセスの結果、かたちになった成果は、多くの場合、短命で儚いものではあったが、今日のスローガン(遠読やカルチュラル・アナリティクス)をも超えたところで、文学を数字で議論するための入口になりそうな地点を押しひろげもしたのだ。同時に、成果のなかには現在のコンピュータによるアプローチを下支えする道具だて(表、語数計算、特徴選択、サンプリング、記述統計)もある。第一章の最終的な目標は、テキストおよびテキスト同士の関係をめぐる認識論的仮説のうちのいくつかに説明をあたえることだ。後者は上述のような道具だてにときに組みこまれ、ときに支えられている。
第二章「アーカイヴとサンプル」では、現在の量的転回を有望かつ論争的なものにしている統計上のアイデアのひとつをあつかっている──サンプリングだ。なぜ数字への転回が質的なちがいを生みだすのかといえば、以下のような理由があげられる。自然言語を処理するための人工知能・統計手法の進歩。デジタルリテラシーの向上が求められるメディア環境。新自由主義による大学教育の変容。なかでも(以前はありえない規模の)巨大なデジタル・コーパスの利用・アクセスの増加が、数の議論を著しく活性化させた[23]。議論を呼ぶのは、ひとつにはこの見かけ上の利用可能性が、なにが・どうデジタル化されたのかという点において極めてばらつきがあるせいであり、もうひとつにはこうしたコーパスが、部分と全体、個別の観察事例と全般的なパターンの関係を考えるうえで悩みの種となるせいだ。フランスの医師が平均や大数の法則の確実性の見込みに翻弄されたのとまったく同じだ。ある法則や原理を一般化するにはどれだけの事例がいるのだろう? 個々の健康状態はてんでばらばらなのに、集計すれば、本当に平均とかいう背景となる健康状態になるのだろうか? [24]新たな規模のエヴィデンスは、部分と全体についての新しい認識のかたちをもたらしたが、医師の暗黙の了解を白日のもとにさらすよう迫るものでもあった。本章では、大規模なテキストコレクションで必要となる統計的サンプリングの実践と、文学研究におけるケーススタディの概念のあいだで繰り広げられる、この共通のダイナミクスに焦点を合わせる。キャサリン・ボーデ、アラン・リウ、ジョン・ギロリー、ローレン・バーラントといった研究者、コンテンツ・アナリシスの分野からさらに幅広く、書誌学、クリティカル・データ・スタディーズといった研究に依拠しつつ、部分と全体をいかに組みあげ、考えるかについての理論的・方法論的提案をいくつかおこなった。
この提案をする上で決定的だったのは、研究者に開かれたものとしては最大の日本近代文学のデジタルコレクションである青空文庫の発掘調査だった。プロジェクト・グーテンベルクにも似て、青空文庫は数百人のボランティアの手であらゆるジャンルの著作権切れの作品をデジタル化し、1997年の開始以来、16,000以上のタイトルを収録するにまで成長した(うち約40パーセントがフィクションに分類される)。青空文庫はすばらしいアーカイヴだが、「日本近代文学」の全体像をつかめるどころか、その代表作を十分に収録しているとすら言いがたい。これはアーカイヴであると同時にサンプルでもあり、現代の嗜好、かつての正典化の過程の残滓、著作権法の現実といった選択の論理の組み合わせからなっている。しかし、青空文庫をやみくもに「不完全」なものとして切り捨ててしまうのではなく──それでは、ほぼデジタル化され尽くした文学以外はコンピュータで読まないということになる──私はその「不完全さ」を意味づけようとした。その手段として書誌データを用いたが、それこそ常にして観念的なものならざるをえない全体についての不完全な視点を同じように与えてくれるものなのだ。こうしたデータには、戦前の日本の文芸翻訳(3万タイトル)、20世紀の文学全集(4万タイトル)、高校の教科書に掲載された文芸作品(13,000タイトル)が含まれる。それぞれが、時代・ジャンル・ジェンダーなどといった観点から青空文庫のまとまりやばらつきを把握するための、代替サンプルになっている。方法論的には、複数の種類のサンプルを分析することで、サンプルを実際に処理するうえで有用なコンセプトをいくつも紹介できるだけでなく、書誌データセットを調べるためのさまざまな尺度や、データのヴィジュアル化のテクニックも示すことができる。
第三章「ジャンルと反復」は、コンピュータを用いたテキスト分析の先鋭的な手法を適用した3つのケーススタディの最初のものになる。あつかう作品の数は次第に増えていく。第三章では数十だが、最後の章では数千になる。分析の単位という観点では反対に章が進むにつれて小さくなり、最初は文書全体だったのが、最後には文や語になる。ジャンル研究は今日の量的転回では頻出のトピックで、マーク・アルジー・ヒューイット、アンドルー・パイパー、テッド・アンダーウッドといった研究者が、文学言語の規則性(テキスト上の証拠)とさまざまな制度的メカニズムによってテキストに適用されるカテゴライゼーション(社会的証拠)にどれぐらい整合性があるのかを判定する手法を開発してきた。この2種類の証拠の関係を習得する機械学習メソッドは、特定の読者コミュニティによって育てられるジャンルというモデルを、言語や構文上の規則性の識別に長けたコンピュータによるテキストモデルと照らしてテストするうえでとりわけ有用なことが明らかになっている。本章でとりあげるジャンルは私小説だ。研究者や批評家が近代日本文学を語るうえで欠かせないと見なしながらも、いまだにプロット、キャラクター、ナラティブのようなフィクションのごく基本的な要素で定義しかねているジャンルである。これは偽のジャンルではなかろうか? この有益な曖昧さ(この自己言及的な執筆モードを読むうえで不可欠だ)を解決してしまうのではなく、私はコンピュータによるモデルを、過去の読者が私小説をジャンルであるともそうでないとも判断するうえで用いてきた概念上の枠組をときに裏づけ、ときに反駁するものとして提示した。
そのために私は、テキスト同士の関係をしめすコンピュータによる枠組を作成した──語彙の反復を尺度とする枠組だ。私小説をめぐるより複雑な特徴を把握しようとして、研究者はこうした尺度を選んできた(日常語の使用、西洋語の文法パターンの使用、狂気を表現するための心理描写の焦点化など)。もっとも、心理言語学の分野や、精神異常の量的な指標の模索において、それぞれに複雑な歴史があるのだが。こうした歴史や二次文献を念頭に置きつつも、私は尺度同士を結びつけ、反復というシンプルな文体のモデルを考案したうえで、名だたる私小説と大衆小説をサンプルにどれほどこの反復という文体があらわれるのかを調査した。大衆小説は、作家や批評家が芸術としての私小説を述べるうえで、しばしばその反対のものとしてきたジャンルである。このモデルで、文体のおおまかな傾向をとらえることができただけでなく、私小説が過去の読者にいかな差異を提示したのかを把握するうえで、反復が有用だとしめすことができた。同時にこのモデルを使えば、反復をより打ち出している私小説がどれなのかや、ジャンルの慣例に背いて反復を採用している大衆小説がどれなのかもわかるようになる。既存の研究からジャンル全体におよぶスケールアップした読解へと歩を進め、はたまた今度は詳細なテキスト分析へと戻ってくることで、量的分析が駆動しやすい解釈サイクルのためのロードマップを提示した。つまりはこうだ──文体的特徴をつかむための尺度を作成する。尺度の識別機能をテストするためのコーパスをつくる。こうした特徴をしめす度合いに応じてテキストを関連づける。そして個々のテキストを精読して、モデルの評価がほかの研究とどこで合致し、どこで逸脱するのかを調べる。このモデルのおかげで、反復への衝動を通じて、私小説の歴史を語りなおすことができる。それは芸術的価値を担保してきた、これ以上なにかに還元できない主体の歴史を語りなおすことでもある。
よく知られているように、この歴史は、国という枠組に厳密に縛られてきたわけではない。私小説は、言語、美意識、文化のようなたがいに連動する差異のシステムの集合から立ちあらわれたものだ──。この、特有の構成は日本に限られているわけではなく、日本での流行のわずか10年後に中国でもくりかえされることになる。第三章は文体としての反復モデルを用いて、この軌跡をたどれないか考察する。他方で第四章「影響と判断」は、そのようなコンピュータ化されたモデルが文学的形式の国境を越えた流通の理解に資するものはなにかという疑問をとりあげる。また、文化の境界をこえた影響関係の(不)可能性についてなにかを語れるのかについてもあつかう。この問いが投げかけられるのは1920年代後半という時代であって、まさにグローバルな規模で興隆したモダニズムが、またしても日本で、書かれた自己を再構成し、社会とフィクションの関係を再定義する試みを誘発した時期だった。断絶の決定的動因のひとつこそ、「意識の流れ」であり、この語りの手法は、新たな世代の作家たちが注目を集めるためにしのぎを削り、文学マーケットが見たこともない経済規模に変容していくなか届けられたのだ。当事者たる作家や批評家が語る意識の流れの伝播についての物語はみな、2つの評価のあいだを揺れ動いている。一方では日本文学はうまくこれを取りいれたとか、主体を描くうえで凝り固まったモデル(すなわち私小説)を見事に覆したとかいった声がある。他方ではもっぱら誤解されていた技法だったとか、日本文学そのものにあたえた影響という観点からは拙速で、表層的かつ短命なものに終わったと断じる声もある。このような評価の揺れは、世界史的な形式としての意識の流れという物語とパラレルだ。それだけではない。このような形式一般がいかに移動するのかを説明する理論にも、一方では世界を股にかけて広まるという話があれば、他方では広まりなんてしないという話があるのだ。こうしたさまざまな物語や説明は、文学の影響をめぐって判断が競合する事例にあたるが、本章ではここに、私が「アルゴリズム能力」と呼ぶものによる別種の説明をくわえてみたい。
第四章の狙いもまた、言語や文学の技能をアルゴリズムですげかえることではない。むしろアルゴリズムは、言語や文字の技能に暗にふくまれている思考モデルや思考の型を再考するとっかかりを提供するのだ。それが、意識の流れが成功したか失敗したかというローカルな物語であろうと、構造主義者(モレッティ、パスカル・カザノヴァ)やポスト構造主義者(エミリー・アプター)のような競合する理論家が異文化間・異言語間の影響関係を説明するうえでよりどころにする世界文学のグローバル理論であろうと、そうするのだ。それぞれの物語や理論を下支えするのは、あるテキストがほかと等価であったり、あるいは異なるという概念であり、それは社会や歴史、文化によって決定される。この点ではコンピュータ化されたモデルも同じくバイアスを受けるが、そのテキストを比較する方法は独特のもので、ほかの判断をかたちづくっている時間や地理、文化的嗜好といった輪郭線に圧力を加えることができる。この別の視角を構築するうえで私がとった方法は、個々の特徴の分析からはじめて複数の特徴の分析へと移行するというものだ。その過程で、語りの形式を分類し、各国文学の枠内/枠外でそれがどう広まっていくのかを調べうる、より複雑なモデルを実際に組みあげてみせている。意識の流れのような、曖昧でぼんやりした形式のモデルを、ある言語の中でいかにつくることができるのか、そしてほかの言語にいかに翻訳しうるのかをこの章では見せていく。そして結果、モデルがどこまでうまくいき、どこで破綻するのかを見てみよう。これは二重の翻訳である。散漫な語りの技法が抽象モデルに翻訳され、それがまたある言語のコンテキストから別のコンテキストに翻訳される。ゆえに、技法そのものについて考えようとしても、どうしても制約をうけてしまう。だが私が言いたいのは、こうした制約は世界文学をめぐるほかの物語とアプリオリに一致するようなものではないが、むしろ制約のおかげで、世界文学という物語をめぐる過去の判断や、判断を生んだ尺度や証拠という制約に新たな解釈の光をあてることができるということだ。これはとりわけ、日本におけるモダニズム小説の受容や、作家による心理描写の探求を、ありふれた形式をさまざまに組み合わせて選択的にとりこむプロセスとして再考する道を開くものである。
最終章「言説とキャラクター」は、個々の心理と語りの形式の相互作用から一転、社会心理──とりわけ人種・民族的他者表象──と切り結ぶ言説に焦点をあわせる。私小説や純文学のモダニズムにおける自己投影のモデルから、1890年から1960年という大日本帝国の興隆と凋落のあいだに刊行されたありとあらゆるタイプの散文から抽出された差異のモデルへと舞台は移る。人種は日本文学研究、日本史研究における一大関心事であって、ここ20年にわたって研究者たちは、帝国植民地という関係が、帝国たる自己と植民地たる他者のそれぞれの文化イメージにいかなインパクトを与えたのかを理解しようと努めてきた。豊富な先行研究をもとにして、この永遠の謎に私はコンピュータを用いてあたった。いかにして個々の作家は人種や民族的他者性についての支配的な言説(おそらくは執筆環境をかたちづくった社会制度やメディアに普及していたもの)を知り、流用し、転覆したのだろうか? この疑問の背後には、めったに直接問われることのない別の疑問が隠されている。人種差別的言説のおおまかな輪郭を──「おおまかな」という規模に十分に応えるかたちで──いかにして描けるのか? 根底にあるのは、エドワード・サイードが『オリエンタリズム』でとりあげた、個々の発言とより広い言説システムのあいだのダイナミクスをめぐる疑問である。アン・ストーラーとメアリー・ルイーズ・プラットのようなポストコロニアリズムの理論家の一団が、帝国の支配下における人種差別の論理の「語彙」と「文法」を可視化するためにサイードにつづいた。こうした言語的な枠組のモデルと、より広範なテキスト群における意味関係をモデル化するための最新の方法を結びつけることで、私は複数の尺度にまたがる人種差別的言説を考察する新たな道を案出した。
本章のサブテーマである「キャラクター」は、これらの尺度のあいだを行き来するための概念的・文学的ブリッジの役割を果たしている。最大の尺度では、「キャラクター」の人種差別的・本質主義的概念──つまり個々の身体は、それぞれ固有の文化的・生物学的特性の総計としてカテゴリー化しうるという考え方──をもちいて、同時期の約2,000の小説作品と9,000以上の雑誌記事のなかからステレオタイプの言語パターンをつきとめる。小説、雑誌のいずれのコーパスでも、私は(たとえば「朝鮮」と「日本」のような対比される)人種・民族の識別子と共起する傾向にある、関連する意味をもつ術語のクラスターをつきとめた。たとえば、声に関連する語(叫ぶ、喚く、悲鳴、大声を出すなど)が、「日本」よりも「地元の」とか「土地の」といった語のまわりにあらわれやすいといったことをつきとめた。この調査の最終的な結果は、コーパスにおける人種差別的言説のおおまかな輪郭をつかまえうる意味論上のグリッドであって、このおかげで人種的・民族的他者のキャラクターが、アイデンティティ・カテゴリーや文章のジャンルによってどう変わるのかがわかるようになる。結果、こうしたグリッドは個別のテキストにズーム・インしなおして、おおまかな言説の傾向が維持されているのか、破棄されているのかを事例ごとに──より重要なのは、小説上のキャラづけのレベルで──見せてくれるようになる。日本の作家の作品だけでなく、デイドラ・リンチ、アレックス・ウォーロック、フィリップ・ブライアン・ハーパーらのキャラクターの理論をも引用して、私は植民地小説のサブセットにおけるメジャー、マイナーなキャラクターを特定することで、グローバルな意味論上のクラスターが、ある作品のキャラクター空間というローカルなレベルにどこまで密着しているのかをしめした。私の発見は、「ネイティヴ」のキャラクターがどこまで日本人の民族的アイデンティティに同化しているのかを指標化するために、声に関連する語彙を用いる作品があるということだ。こうした作品を精読すれば、個々の作品の美的ストラテジー(つまり、人種的性格づけに付随するもの)をより大きな言説のパターンに位置づけるうえで、量的手法がいかに新しい道筋をつけるのかをしめすことができる。大きな尺度で読むための制限は(テキストの意味の抽象化、観察可能であるものへの過度の依拠、アルゴリズムのバイアス)、カルチュラル・ヒストリー研究に欠かせない差異の理論に光をあてる(掘り崩すのではなく)のに有用である。
コンピュータが差異の理論化を助けるという主張は、この序論の冒頭で見たものと同種の反統計的バックラッシュを招いてしまうかもしれない。しかしこうした意見は、数字を用いた議論が政治性を帯びるという事実から目を背けないという、私の試みの核心にせまるものでもある。それは、批判者が言うほどわかりやすいものではないのだ。平均の話に戻ると、この議論は計算だけでなく道徳も、数学の公式だけでなくこの複雑な世界の理論と解釈も巻きこんでしまうのだ。数字、そしてその延長である統計的思考も、物事のあいだの差異を測定して、均してしまいもすれば、増幅してしまいもする。また規範となるカテゴリーを解体し、破壊してしまいもすれば、逆に構築して実体化することもある。こうした計算がなにを意味するのかは、理論や社会の中での用いられ方によるし、どれだけ資本が投下されるかにもよる。それでもフランス医学界での議論にも似て、文学研究における数の批判は主に、数字が特殊性や多様性を洗い流し、人間の読者たる専門家の判断にとってかわるのではないかというものだ。もちろん、潜在的な還元主義によって、権力と抑圧の構造に連なってしまわないように目を光らせなくてはならない。19世紀統計学による優生学への後押し。数字の根拠となるデータを生みだす労働者の肉体の抹消。今日の機械学習アルゴリズムによって、人種・階級・ジェンダーの不平等が増大していること[25]。しかし数字のポリティクスに着目することは、それが支える「事実」について議論を開くことでもある──そのためにはディシプリンやほかのコミュニティが「事実」に同意するに至った歴史的プロセスを認識しなくてはならない。完全に拒絶してしまうのではなく、さまざまな理論の噓が事実をつくりだす交渉に我が身を開き、事実が支えているかもしれない他の噓に想像をめぐらせるような立ち位置をとらねばならない。
約200年が経過し、平均はいまや医療における事実になっただけなく、日常生活の事実にすらなった。当時の批判者たちにはまったく想像できなかったことだ。現在の文学にこめられた統計的抽象化や量的思考モデルに、200年後には同じように交渉の余地なき事実と思えるようになるものがあるのだろうか? 文学研究がディシプリンの共同体にそのような抽象化を迎えいれるのを長らく拒んできたことを思えば、懐疑的になってもしかたない。事実や意味を生みだす道具として弾みがつけば、ほかのディシプリンの所有物としてあつかわれるか(言語学、社会学、心理学)、切り離されて、サブ的な分野にそっと押しこまれるか(文体論、ブック・ヒストリー、ヒューマニティーズ・コンピューティング、カルチュラル・アナリティクス)のいずれかの処遇を受けがちだ。この意味で、数を文学史と批評に持ちこもうとする試みはどこまでいっても「SF」チックなものである──柄谷の『日本近代文学の起源』がジェイムソンの目にはSFチックに映ったのと同じように。これらの新たな抽象化は、「まだ存在してはいないが経験すると面白いだろう」批評における現実のかたちをモデル化する[26]。『数の値打ち』も、そんな抽象化は結構おもしろいんだよと、文学研究者を説得する長い道のりの一歩である。おかげで批評における現実をモデル化でき、そこで既存の学術的事実を支えている質的抽象化を補ったり、あるいはそれと組み合わせたりもできるのだ。量的抽象化がおもしろいのは、ほかの思考モデルの代替品だからでも確実性を担保してくれるからでもなく、過去の文学について私たちがなにを/いかに知っているかについての生産的な疑念を生みだすからだ。今日の数的抽象化がほかのディシプリンでも市民権をえるようになり、人工知能についてのSFが科学的事実となって私たちの情報化社会の屋台骨に組みこまれるとき、言語・文化・芸術について数的抽象化が生みだす新たな事実と現実をめぐる交渉に、文学研究者は発言権をもつべきである。つまり、数的抽象化をささえる思考モデルをきちんと向きあい、そのモデルと自分たちのものだと思えるモデルをつなぐ概念上の動線を追うこと。そうなれば、質的推論の確実性を固められるようになるだけでなく、私たちの読書する心に、天賦の才と計算機のあいだの広大な解釈空間を彷徨う自由を与えてやることもできるのだ。
[23]文学研究における現行の量的転換を指摘する議論は枚挙にいとまがない。以下にあげる文献はごく一部である。Ted Underwood, “A Genealogy of Distant Reading,” Digital Humanities Quarterly 11, no. 2 (2017), http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/11/2/000317/000317.html; Matthew Jockers, Macroanalysis: Digital Methods and Literary History (Urbana: University of Illinois Press, 2013); Alan Liu, “The Meaning of the Digital Humanities,” PMLA 128, no. 2 (March 2013): 409–23; Daniel Allington, Sarah Brouillette, and David Golumbia, “Neoliberal Tools (and Archives): A Political History of Digital Humanities,” Los Angeles Review of Books, May 1, 2016, https://lareviewofbooks.org/article/neoliberal-tools-archives-political-history-digital-humanities/.[24]Cryle and Stephens, Normality, 90, 86–87.
[25]優性思想と推計統計学との関わりについては、以下の文献の第四章と第八章を参照のこと。Desrosieres, The Politics of Large Numbers. あるいは以下の文献を参照のこと。Tukufu Zuberi, Thicker Than Blood: How Racial Statistics Lie (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001). 労働者と肉体の抹消については以下の文献を参照のこと。Lauren F. Klein, “Dimensions of Scale: Invisible Labor, Editorial Work, and the Future of Quantitative Literary Studies,” PMLA 135, no. 1 (January 2020): 23–39. アルゴリズムがいかに人種・階級・その他社会的不平等を助長するかについて、最近の研究にはたとえば以下のようなものがある。Safiya Noble, Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism (New York: New York University Press, 2018); Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy (New York: Crown, 2016); Virginia Eubanks, Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor (New York: St.Martin’s, 2018).
[26]Fredric Jameson, “Foreword: The Mirror of Alternate Modernities,” in Karatani, Origins of Modern Japanese Literature, x. 〔フレドリック・ジェイムソン「異なる近代を鏡として」田尻芳樹訳『批評空間』第2期1号、1994年、79頁を一部改変を施して引用。〕
(前編へ戻る)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。