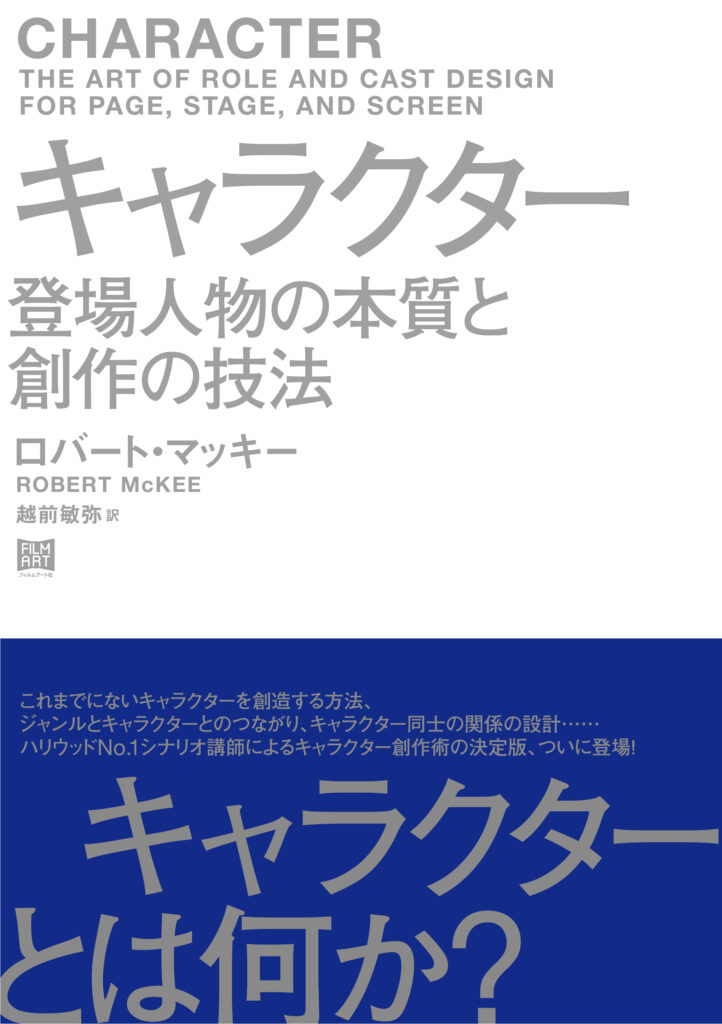6 役柄とキャラクター
役柄はキャラクターではない。役柄はストーリーの社会秩序における一般的な立場(母親、上司、芸術家、一匹狼)を担い、それに応じた役目(子供に食べさせる、従業員を管理する、キャンバスに絵を描く、他人を避ける)を果たすにすぎない。まっさらなキャンバスを囲む額縁のように、役柄はキャラクターを描きこむための空白のスペースを作家に差し出す。
完成されたキャラクターは、ストーリーに登場すると、まず基本的な立場を担って、ただひとつの個性をそこへ詰めこみ、その役目を比類のない形で果たすことで、ほかの登場人物と唯一無二の関係を築きあげる。登場人物を設計するときは、同じ立場を担ったり、同じ役目を同じようにおこなう者がいないように、役柄とそれぞれの関係を戦略的に配置する。
登場人物の構成
ストーリーにおけるそれぞれのキャラクターには、複雑な人間関係のネットワークが張りめぐらされている。この相互関係を整理するために、登場人物を太陽系になぞらえて、太陽を取り巻く惑星、衛星、彗星、小惑星として見てみよう。脇役は三つの同心円で、さまざまな距離を置いて太陽のまわりを移動し、太陽や脇役同士に大なり小なり影響を与える。影響力の強いキャラクターは主人公の近くを、あまり影響力がない脇役はその外側をまわり、一シーンしか登場しない端役、台詞のない通行人、その他おおぜいは外べりをまわる。こうして宇宙が完成する。三人称の語り手は、目に見えない神のようにこの宇宙を遠くからながめている。
登場人物を設計するには、まず主人公からはじめて、外側へ大きくひろげていく。
主人公
あるキャラクターを読者や観客の前に立たせて、それがいかにおもしろく、魅力豊かで、貴重な時間を費やすに値する人物かを示すには、勇気が必要だ。そこで、まずは主人公に不可欠な資質について考えよう。
(1)意志の力
人間の心は、死に絶えることを何よりも恐れ、安全を求めるため、ストーリーの契機事件によって人生の歯車が乱れると、主人公の本能は生命が危機に瀕しているかのように反応する。そして、欲求の対象を思い描く。それは、人生の均衡を取りもどすことができると感じる物理的、個人的、社会的な目標だ。この目標を追求していくと、敵対する力が行く手を阻む。最後の危機で直面するのは、ストーリーのなかで最も強力で困難な敵だ。真の主人公は、自分の目的を達成して人生の均衡を取りもどすための最後の試みとして、この究極の難題に挑み、究極の決断をくだし、究極の行動をとる意志の強さを持っている。最後の行動は失敗に終わるかもしれないが、意志の力を使い果たすまでは失敗とは言えない。
(2)複数の資質
主人公は、精神的、感情的、肉体的な資質を一体にして、自分の限界まで、あるいは限界を超えて人生の目標を追い求めていく。こうした資質はストーリーによって異なる。若いのか、ある程度の年齢に達しているのか、裕福なのか、貧しいのか、教養があるのか、無教養なのか、といったさまざまな資質のなかから選び出し、主人公の選択や行動が本人にしかできないもので、その本質に忠実であり、信頼できるものだと読者や観客が感じるものにすべきだ。
主人公の行動は、ストーリーを読者や観客の想像も及ばぬ結末へ導くような、じゅうぶんに広い、そしてじゅうぶんに深い影響をもたらすものでなくてはならない。主人公が望むものを得られない場合でも、その行動によって最後は人間性がすべて明らかになる。
ストーリーの社会的、物理的な設定へ出来事を広く拡大するために、作家はしばしば主人公をエリート層に属させる。医師、弁護士、戦士、政治家、科学者、探偵、企業の幹部、犯罪王、著名人などだ。高い地位にあるエリートの行動は、社会的階層のなかで広範な結果をもたらし、多くの人々がかかわる話が生まれる。
ストーリーの出来事が混乱に陥って、内に隠れた領域に踏みこんだときに、深みを探求できる複雑さと、変化に対応できる柔軟性を持っているのであれば、主人公はどんな階層の住人でもいい。
そしてもちろん、ストーリーは主人公の世界をひろげると同時に、深く掘りさげることもできる。『ブレイキング・バッド』とその前日譚『ベター・コール・ソウル』のジミー・マッギルの例を考えてみよう。物語の序盤では、ジミーは詐欺まがいのことで稼ぎながら弁護士をめざす、社交的でチャーミングな人物だった。しかし、ソウル・グッドマンという別人格をまとうことで、ほんとうの自分を奥深くに隠す。その一方で、彼の小さな法律事務所の仕事はどんどんひろがり、十億ドル規模の麻薬ビジネスに巻きこまれていく。
(3)劣勢の立場
主人公を片方の手のひらに載せて、精神的、感情的、肉体的な資質を量ってみよう。つづいて、反対の手に、ストーリーの流れのなかで主人公が直面するすべての敵対する力を載せてみる。これに含まれるのは、主人公の内面にある消極的な思考や感情、友人や家族や恋人との個人的な対立、立ちはだかるすべての組織とそこに所属する人々、そして、悪天候や致命的な病気や時間的制約などの物理的な問題などだ。
主人公の力を、敵対するすべての力を合計したものと比較すると、敵対する力が大きく上まわり、明らかに劣勢だとわかるはずだ。主人公には欲求の対象を手にする可能性もあるが、あくまで可能性にすぎない。
(4)感情移入できる
読者や観客は、架空の世界に足を踏み入れた瞬間に、そのストーリーの価値要素をすばやく吟味して、プラスとマイナス、公正と不正、善と悪、興味があるものとないものを選び分け、感情移入できる安全な場所である「善の中心」を探す。
「善の中心」とは、ストーリーの奥深くで光を発するプラスの価値要素(正義、善、愛など)であり、それを取り巻く暗いマイナスの価値要素(専制、悪、憎しみなど)と対極をなすものだ。このプラスの光が共感を呼ぶのは、人間は心の奥底で自分はおおむね善良で正しいと思っていて、プラスと認識したものに自然と共感するからだ。例外もあるが、ほとんどのストーリーは善の中心を主人公に置いている。
例をふたつあげよう。
マリオ・プーゾ原作の『ゴッドファーザー』三部作(72、74、90)は、腐敗した警察官や買収された裁判官に囲まれたマフィア・ファミリーの世界を描き出す。だが、主役となるコルレオーネ一家には忠誠心というプラスの資質がある。ほかのファミリーは互いを欺き、裏切り合う。そのため、悪のなかでもさらに悪の存在となる。コルレオーネ一家は団結してお互いを守るので、悪のなかでは善の存在になる。この一家に善の中心を見いだしたとき、観客は直感的にマフィアに共感を覚える。
トマス・ハリスの小説『羊たちの沈黙』では、読者の関心をふたつの善の中心へ向ける。FBI訓練生クラリス・スターリングの勇敢さはたちまち共感を呼ぶが、物語が進むにつれて、ハンニバル・レクター博士もまた共感を呼ぶようになる。
作者はまず、暗く卑劣な世界にレクターを置く。FBIは、海の見える独房へ移すという偽りの申し出で協力させようとする。病院長はサディストで功名心が高く、レクターに殺される警察官たちは無能だ。
一方、レクターのなかには明るい光が満ちている。知性にあふれ、ユーモアのセンスがあり、囚人でありながら驚くほど冷静で礼儀正しい。マイナスの社会のなかでレクターが持つプラスの資質にふれた読者は「だから人間を食べるんだな。世の中には、それよりひどいことがたくさんあるからな。とっさには思いつかないが、ぜったいにある」と肩をすくめる。共感を覚えた読者はこう考える。「もしも自分がサイコパスで人肉を食べる連続殺人犯だったら、レクターのようになりたい。やつはクールだ」
(5)好奇心を掻き立てる
主人公は、そのストーリーのなかで最も複雑で、それゆえ最も魅力的なキャラクターだ。ひとりのキャラクターのなかにふたつの相反する性質があると、読者や観客は当然「いったいどんな人間なんだろう?」という疑問を持つ。その答えを追求することで、物語に引きこまれていく。
(6)登場時間の長さと内面の深み
主人公は物語の前面に立ち、大部分の時間で読者や観客の心を支配する。その主人公がきびしい選択を重ねたすえ、潜在的な動機や隠された欲求が最終的に明らかになる。クライマックスで、主人公は最も内面の深いところまで知られるキャラクターとなる。
(7)変化への対応力
人間は時が経つにつれて、知識を身につけ、新しい信念を見いだし、新しい環境に順応し、衰えゆく肉体を受け入れる。その一方で、内なる本質は不変であることが多く、一部の例外を除いて中核の自己は変化しない。よい方向への変化を思い描くことはあっても、それは可能性というより願望に近い。ほとんどの人間は生涯にわたって本質的な自己を保ちつづけるので、変化しないキャラクターこそ真実味があり、現実的に感じられる。
変化するキャラクターは、変われば変わるほど現実から遠ざかり、象徴的な存在へと向かう。前向きな態度で進むキャラクターは理想に向かって進化し、悲観的な方向へ沈むキャラクターは暗黒の元型に向かって進化する。そして、すべての登場人物のなかで、最も変化する可能性が高いのが主人公だ。
変化する主人公の例として、スクルージ(『クリスマス・キャロル』)やジェシー・ピンクマン(『エルカミーノ:ブレイキング・バッド THE MOVIE』)は心を入れ替え、テオ・デッカー(『ザ・ゴールドフィンチ』[19])やフリーバッグ(『Fleabagフリーバッグ』)は教訓を学び、ジャッキー・ペイトン(『ナース・ジャッキー』)やトルーマン・カポーティ(『カポーティ』[05])は堕落する。トニー・ウェブスター(『終わりの感覚』)やデヴィッド・ルーリー(『恥辱』)は幻滅し、デイヴィッド・コパフィールド(『デイヴィッド・コパフィールド』)やスティーヴン・ディーダラス(『若き芸術家の肖像』)は作家となる。
(8)真実を見通す力
葛藤によって人生のバランスが崩れると、キャラクターの心は、物事がいかにして、なぜ起こるのか、そして、人はいかにして、なぜそのような行動をとるのかといったことを考える。最も強い葛藤に苛まれるのは主人公なので、決定的啓示エピファニーを受ける可能性が最も高くなる。
決定的啓示とは、古くは、神が崇拝者の前に突然姿を現すことを意味した。現代では、現実を見抜く突然のひらめき――物事の表面下に隠された本質的な原因や力を直感的に認識すること――を意味する。決定的啓示を得た主人公は、何も知らず、意識すらしていなかった状態から、心を掻き乱すような真実へと導かれる。これによって人生は大きく変わり、その結果、成長する場合もあれば破滅する場合もある。
悲劇では、アイデンティティを悟ることによってクライマックスを迎えることが多い。主人公が自分のほんとうの姿に突如として気づく、衝撃的な自己認識の瞬間だ。ソポクレス『オイディプス王』のオイディプスは、妻が自分の母であったうえに、自分が父を殺していたことを知り、おのれの両目をえぐり出す。シェイクスピア『オセロ』のオセロは、だまされて無実の妻を殺してしまったことを知り、自分の胸にナイフを突き立てる。アントン・チェーホフ『かもめ』では、ニーナの愛を得られないと悟ったコンスタンチンが命を絶つ。『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』(80)では、ダース・ベイダーが自分の父親であることを知ったルーク・スカイウォーカーが自殺を企てる。
古代ローマのある喜劇〔プラウツス『メナエクムス兄弟』〕では、つつましい召使いが、自分にはほくろが目印の双子の兄弟がいることを知る。母親が嵐の洋上で出産したため、生き別れになっていたのだ。しかも、母親は遠い国の女王で、ふたりは莫大な富の相続人である。それから二千四百年後、シットコム『ラリーのミッドライフ★クライシス』のラリー・デイヴィッドは、自分がユダヤ人ではなく、ミネソタ州に住む敬虔なキリスト教徒で典型的なスカンジナビア系の家族から養子に出されたことを知る。実の家族を訪ねたラリーは、ユダヤ人のほうがいいと考える。
自分のアイデンティティの発見にとどまらず、決定的啓示はときに不安を掻き立てるような心境へ導く。シェイクスピア『マクベス』のマクベスは最後の独白で、人生には「愚か者が語る物語」ほどの意味しかないと嘆く。
その三百五十年後、サミュエル・ベケットの戯曲『ゴドーを待ちながら』で、ポッツォは人生のはかなさを嘆く。女性は墓穴にまたがって出産し、その赤ん坊の人生は子宮から出て墓に落ちるまでのあいだに終わるとして、こう語る。「女たちは墓石にまたがってお産をする、ちょっとばかり日が輝く、そしてまた夜」(『ベスト・オブ・ベケット1』所収、安堂信也・高橋康也訳、白水社、1990年、163頁)。
ドラマシリーズ『ナース・ジャッキー』のジャッキー・ペイトンは決定的啓示によって、薬物に手を出したのは、はじめて産んだ子供が泣きやまないのに耐えられなかったからだと認めることになる。つまり、薬物依存は自分自身のせいだ。しかしこの事実は、ジャッキーが薬物をやめる自制心を持っていないので、彼女を救うことはできなかった。
決定的啓示は絶対的な出来事であり、だからこそ危険だ。ストーリーのなかで最も壮大で心に残る瞬間を生むことができるかもしれないが、大げさで気恥ずかしくなる瞬間になる可能性もある。
演劇でも映画でも、決定的啓示を表現するには、その前後を描くすぐれた脚本と、それを演じるすぐれた俳優が必要だ。たとえば、『カサブランカ』(42)第三幕のクライマックスで、リック・ブレインが自分の未来を見つめて「これも運命のようだな」と言うとき、観客はそのことばの裏にある広大なサブテクストを堪能する。
一方、小説で決定的啓示を表現するには、より大きなリスクをともなう。登場人物を突き動かすような事実の解明には、作者の表現の才能のみならず、読者の想像力やキャラクターの信憑性も重要となる。そのため、多くの意味を詰めこんだ、人生を変えるような啓示についての記述は、飾り立てた文章になりがちだ。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。