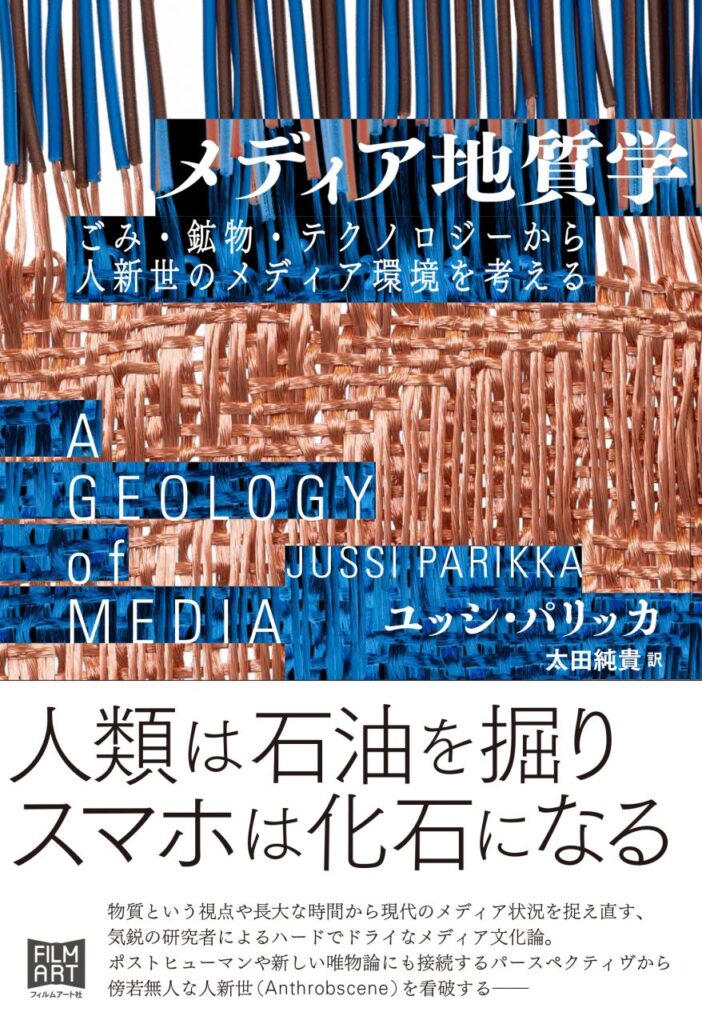日本語版への序文
Netflixのヒット映画『Don’t Look Up』(2021)で、視聴者と文化批評家はハイテク複合企業の描写を楽しんだ。この映画では、地球へと突進する小惑星が、金銭的価値の高い金属を含む巨大な岩塊であったため、まさかの一儲けの機会になる。だが無理に宇宙に行かなくても、地球という惑星のあちらこちらでも採掘作業はある。地球での採掘作業には、根本的な地政学の争点(金銭的価値の高い鉱物を押さえる者、手を伸ばす企業、結ばれる協力関係)と、父祖伝来の土地を焦点とする作業にみられるような物質をめぐる倫理的関係、この両方が反映される。地球自体が巨大な岩塊で宇宙空間を横断して突進しているということは、化石燃料に依存する宇宙船地球号としてバックミンスター・フラーが描き出した内容とぴったり合うだろう。
もし私たちが、「宇宙船地球号」の上に数十億年にわたって保存された、この秩序化された貯金を、天文学の時間でいえばほんの一瞬にすぎない時間に使い果たし続けるほど愚かでないとすれば、科学による世界を巻き込んだ工業的進化を通して、人類すべてが成功することもできるだろう。これらのエネルギー貯金は「宇宙船地球号」の生命再生保証銀行口座に預けられ、自動発進機能が作動するときにのみ使われる。「宇宙船地球号」に積み立てられた化石燃料は、自動車でいえばバッテリーに当たるもので、メイン・エンジンのセルフ・スターターを始動させるためにエネルギーを貯えておかなければならないものだ。だから私たちの「メイン・エンジン」、つまり生命の再生プロセスは、風や潮汐や水の力、さらには直接太陽からやってくる放射エネルギーを通して、日々膨大に得られるエネルギー収入でのみ動かねばならない。[1]
この引用が与える印象は、原著が出版された1968年と2022年の今とでは、少し異なっている。メディアテクノロジーによって地図化される有限の資源で進む同じ宇宙船に私たちは依然として乗船しているとしても、だ──メディアテクノロジーには、この世界[2]とこの惑星と同様に、限りがある。
『メディア地質学』が意図するところは、2015年の初版でも、この日本語版でも変わらない。この本は、気候変動の時代におけるメディアと文化の理論のあるべき姿の一つを示唆している。すなわち、物質という観点を大いに取り入れること、それゆえにメディアと文化の理論の語彙をアップデートすること、Netflixその他の消費メディアのプラットフォームにとどまらない、広きにわたるメディアテクノロジーの争点を理解することである。『Don’t Look Up』の場合、そこでは気候変動に対する鷹揚な態度が示す自己安定化のアイロニーについては多くのことが語られているが、この映画を流すNetflixというプラットフォームがどのような物質に依拠しているのかについてはあまり語られてはいなそうだ。
本書のタイトルが示すところにアプローチするときに、助けになりそうな二つの入口がある。一つはメディア学者のパースペクティヴ、もう一つは地質学者のパースペクティヴである。私自身がこのカテゴリの一方と大きく共鳴するのは間違いない。そして、もう一方のカテゴリ〔=地質学者のパースペクティヴ〕は、近代世界の専門的知識にかかわり、特定の科学的時代を示す歴史的参照点として付いて回る。どちらのカテゴリも、メディアを支える物質、デジタル文化まで支える物質にかんする本書の主題を検討する際には重要である。地質学的パースペクティヴをとれば、鉱山からデスクトップコンピュータまでの現代文化を構成する物質について理解できる。AIから電気自動車のバッテリーまでのテクノロジー装置やインフラストラクチャーの背景となる物質リストは、リチウムやコルタンといったレアアースが発見・採掘される領土の文脈と関連する。一連の理論的・実践的な学説としての地質学は、数百万年におよぶ非宗教的な地球史への時間的パースペクティヴを備え、原材料および採取主義[3]産業と操作的な関係にある近代世界を築くのに中核的な役割を果たす。こうして、地質学は魅力的な分類と層序学(依然として完新世なのか、それとも人新世に移行したのかという論議)にかかわるだけではなくなるのだ。地質学は、資源を地図化して調査し、道具化して最大限に利用しようとする機関によるさまざまな規模の探査にもかかわるのである。地質学には、この惑星の表層について行われる、そして表層にとどまらないリモートセンシングが付き物だ。それは、マルチスペクトルでハイパースペクトルなイメージングの技法として拡張されたメディア地質学であり、ギョクチェ・エナル*1が呼ぶところの「採取の視界が生むメディアエコロジー」の一部である。
メディア理論の言説とデジタル文化の学者は、両方ともテクノロジーにかかわる化学と地質学にさほど精通してはいないかもしれない。だが、上述の深い時間がもたらした非宗教的な時間性が意味するところや、依然としてメディア文化の一部であるような広範囲におよぶコロニアリズム的関係と採掘をめぐる採取主義的文脈が接続することを、メディア理論の言説とデジタル文化の学者は詳述できるだろう。批判的なメディア理論研究者にとって、コルタンという希土類鉱物はその採掘の文脈(コンゴ民主共和国)と使用(電子メディアのタンタルコンデンサー)ゆえに、数年にわたり繰り返し登場するトピックであった。今では同じことがリチウムにも言えるだろう。リチウムはテスラの電気自動車用バッテリーなどに欠かせない。それはこの序文の最初のほうで引用したバックミンスター・フラーが語る車のバッテリーのメタファに対する一種の捻りを加える。この種の鉱物は両方とも人間の媒介行為を可能にする媒介物質として語ることができるだけでなく、それらは風景の改変において重要な役割を演じもするのだ。この点については、多くのアーティストと学者とアクティヴィストとともに、サミール・ボウミックが論証している通りである。リチウムがもたらす風景とは、メディアテクノロジー的に重大な移行が生じていることをこの惑星の表面で示す記号なのである。*2
媒介行為をめぐるすべてのスケールを検討できるようにせよというのは、メディア理論に難題を押し付けることになるだろう。だが、複雑で困難なタスクはとても刺激的で重要な探求にもつながる。具体的には、化学的で地質学的であるけれども、政治美学的でもあるデジタル文化へのパースペクティヴを検討する手法を発展させること、手の中のデバイスと生産のために変形した風景とを往き来できるようにすること、データにかかわる抽象=抽出と具体的な採取の場について語れるようにすることにつながるのだ。本書の場合、「メディア自然」という術語で指し示そうとしたのは、こうした複数のパースペクティヴとスケールの連続体である。
以上の意味で、『メディア地質学』は人新世時代のメディア理論についての本である。とはいえ、人新世という──〔その指し示すところについて〕異論が出ては何度も修正されて、この惑星の変形をめぐる植民地時代の歴史と資本主義の文脈を考慮するようになっている──術語が本書で目玉となることはそう多くはない。だが、争点に似通ったところがあるのは明らかである。両者は、エコロジーとテクノロジーだけでなく主観性の生産も文脈化する環境の変動に対して人文科学が主導する探究に目を向けて、そうした探究同士を横断しながらつなげる要素を理解しようとする点で通じている。*3ここで問題となる主観とは、物質の変形にかかわる持続の多様な水準で分節化される。もしくは、それは、断固として非人間中心的で、インターセクショナル[4]なポストヒューマン的フェミニズムのさまざまなパースペクティヴを真剣に受け止めることに全面的にかかわり*4、生きられる経験とエピステーメーにかかわる抽象概念(還元主義が生み出す敵ではあるけれども、惑星スケールのメディア理論のための変化する参照スケールを理解する助けとなるツールでもある)とを粘り強く調停する。
『メディア地質学』はこのような理論的パースペクティヴの文脈だけでなく、アート(および設計)をめぐる実践との対話でも陶冶される。ベルリンで開催されるアートとデジタル文化のフェスティバルであるトランスメディアーレのような制度的な文脈のおかげで、ソフトウェアとハードウェアの開発の背後にある地質学的で化学的な力のスケールに、アートの言説が取り組むための窓口ができた。本書もこうした文脈のいくつかを組み込みはしたが、この種の開発〔を扱うアート〕についての美術史としては十分ではない。だが、私の興味は、取り上げたアートプロジェクトが方法論上の秘訣を用いて提供してくれる内容にある。例えば、本書の第3章で「心理地球物理学」という術語について特筆しているが、その要点は、心理地理学は間違っているのでドゥボールらを読むのをやめるべきということではなく、心理地理学という成果を参照するためのスケールは複数あり、この点を踏まえれば心理地理学はロバート・スミッソンの「抽象的地質学」とも共鳴するということなのだ。私たちの精神、私たちのコレクティヴ、私たちの政治の内側にも、抽象的地質学はある。
最後に、『メディア地質学』は私の他の著作たちのように、それ自身のストーリーで充足することを目指してはいないという自省的な註釈を添えておきたい。『メディア地質学』はプラットフォームになることを目指している。後方支援とさらなる展開を目論んでいるのだ。一冊の本が手助けとなって思考や訂正、変異や見解が現れ出て、特異なパースペクティヴや方向性が生まれる。私見ではそれが最良の結果である。すでにいくつかのアート作品や展覧会が、この本を参照点にしてくれた。願わくば、この新たに翻訳された日本語版によっても、理論的著作ならびに創造的実践が誘発されんことを。
2022年3月、デンマークのオーフスにて
原註
*1 Gökçe Önal, “Media Ecologies of the ‘Extractive View’: Image Operations of Material Exchange, ”Footprint: Delft Architecture Theory Journal Vol.14 No.2(2020): Issue #27(2021). Online at https://journals.open.tudelft.nl/footprint/article/view/4694.
*2 Kate Crawford, Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence(New Haven: Yale University Press, 2021).
*3 Fèlix Guattari, Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm, trans. Paul Bains and Julian Pefanis(Bloomington: Indiana University Press, 1995). 〔フェリックス・ガタリ『カオスモーズ』宮林寛・小沢秋広訳、河出書房新社、2004年〕
*4 Rosi Braidotti, Posthuman Feminism(Cambridge: Polity, 2022).
訳註
[1] バックミンスター・フラー『宇宙船地球号マニュアル』芹沢高志訳、ちくま学芸文庫、2000年、127頁。
[2] 原文ではCubit 2016の表記のみ。おそらく以下の文献と思われる。
Sean Cubitt, Finite Media: Environmental Implications of Digital Technologies (Duke University Press, 2016).
[3] 採掘主義とも。本書ではminingを採掘と訳しているため、区別するため採取の訳語を当てている。採取=採掘される対象(資本主義の「外部」)が論者によって異なることから、一律の訳語を当てることの困難さを北川眞也と箱田徹は指摘している(北川眞也+箱田徹「採掘‐採取、ロジスティクス──現代資本主義批判のために」、『思想』2021年2月号、11頁)。サンドラ・メッザードラとブレッド・ニールソンは「概念としての採取主義は、採取活動の拡大と激化に支えられた経済・政治・社会構造の大まかな特徴を捉える一つの方法」と述べている(サンドラ・メッザードラ+ブレッド・ニールソン「多数多様な採取フロンティア―現代資本主義を掘り起こす」、『思想』2021年2月号、14頁)。
箱田も述べるように、採取主義はそれを可能にするロジスティクスや金融と結びついているため、必ずしも狭義の資源採掘にはとどまらない概念である(箱田徹「多数多様な採取フロンティア──現代資本主義を掘り起こす」訳者解題」、『思想』2021年2月号、13頁)。
[4] 下地ローレンス吉孝によれば「インターセクショナリティとは、人種、階級、ジェンダー、セクシュアリティ、ネイション、アビリティ/ディサビリティ、エスニシティ、年齢などさまざまな要素の交差する権力関係と社会的立場の複雑性を捉える概念である」(下地ローレンス吉孝「日本の社会とインターセクショナリティ」、パトリシア・ヒル・コリンズ+スルマ・ビルゲ『インターセクショナリティ』小原理乃訳、下地ローレンス吉孝監訳、人文書院、2021年、343-344頁)。
参考文献
Samir Bhowmik, “Lithium Landscapes: From Abstract Imaginaries to Deep Time and Multi-Scalar Topologies, ”Media Fields journal, May 21(2021).
Online at http://mediafieldsjournal.org/lithium-landscapes/.
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。