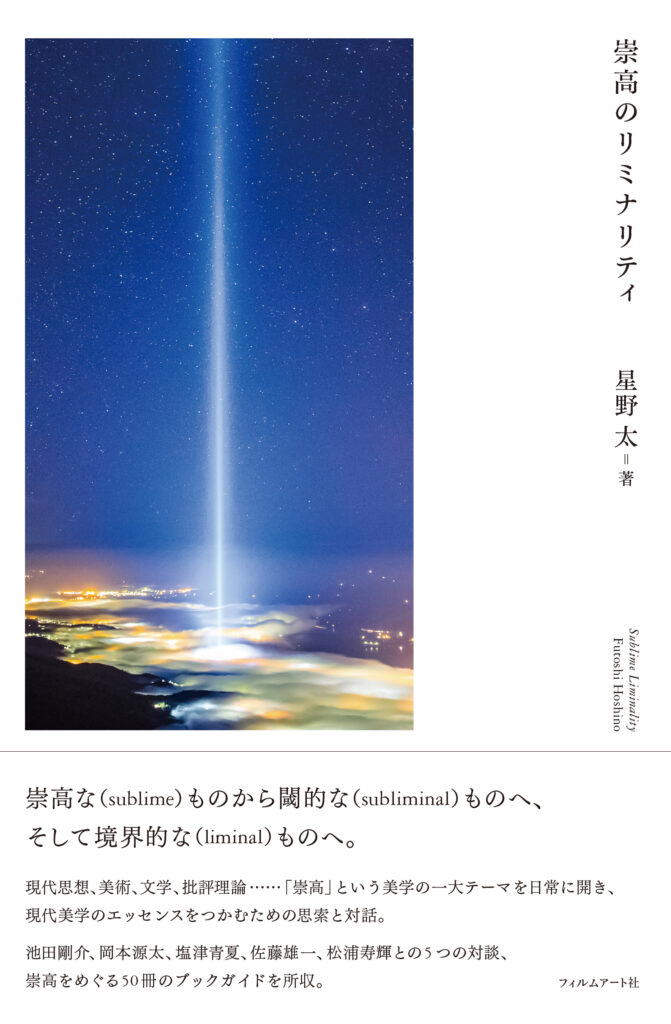はじめに
本書は「崇高」という美学の一大テーマをめぐる対談集である。
崇高[英:sublime|独:erhaben|仏:sublime]――おそらく、ほとんどの読者にとっては耳馴染みがないと思われるこの言葉は、とりわけ「美」や「芸術」をめぐる西洋の思想において、長らく重要な地位におかれてきた。そうした美や芸術をめぐる思想は、18世紀後半から今日にいたるまで、伝統的に「美学(aesthetics)」という名称で呼ばれてきたものである。本書の目的は、そうした美学の問題圏において、なおかつ言語、倫理、政治の諸問題にも目をむけながら、この「崇高」という概念が今日においていかなる意義を担いうるのかを示すことにある。
本書の意図は、「崇高とは何か」という問いへの答えを、いわゆる通史的なかたちで示すことにはない。本書はこの概念の使用法に徹する。つまり、およそ2000年あまりにおよぶ概念の歴史を詳細にたどるのではなく、その主要な論点を洗い出し、それを学ぶことが今日においていかなる意味をもちうるのかを、なるべく幅広い視野のもとで示すことに専念する。「崇高」の一般的定義や歴史的変遷、さらにより細かなトピックについて知るための文献は、本書を読んでいけばおのずと明らかになるだろう。
本書は序論、5つの対談、50冊のブックガイドからなる。
序論では、のちの対談への導きとして、あらかじめ「崇高」概念の主要なマトリックスを提示する。そのために前半ではまず、そもそもこの概念が西洋の思想史においていかなる意義を担ってきたのかを、カントをはじめとする過去の議論を参照しながら概説的に論じる。そのうえで後半では、20世紀末から今日までの「崇高」論の変貌をめぐって、いくつかの見通しを示すことになるだろう。ここでは本書の前提をなす美学・批評理論にも適宜ふれることになるため、諸々の基本から押さえたいという読者には、まずこの序論に目を通すことを勧めたい。
それに続く5つの対談は、いずれも拙著『崇高の修辞学』(月曜社、2017年)をめぐって、2017年から18年のあいだに行なわれたものである。むろん各対談の内容は、同書の議論をただ敷衍するのではなく、むしろそれを異なる立場から拡張するものとなっている。あえてジャンルで分けるなら、それぞれの対談は①現代美術(池田剛介)、②美学(岡本源太)、③美術史(塩津青夏)、④現代詩(佐藤雄一)、⑤人文学(松浦寿輝)の諸問題をめぐってなされている。なおかつ、各対談の内容はかならずしも「崇高」という概念のみに収斂するものではなく、その外部へと開かれた発展的な議論を含んでいる。すでに「崇高」をめぐる思想についてひとかどの知識をもっている読者は、序論を経由せずにこの対談パートに進んでもらってもかまわない。
最後のブックガイドは、日本語以外のものも含め、今後このテーマについてさらなる探求を試みる読者への誘いとして執筆した。ドイツ語やフランス語をはじめとする異言語の文献については、タイトルから少しでも内容が想像できるように、日本語による仮題も添えてある。選書は「崇高」についての理論書や研究書が中心だが、そこにアンソロジーや展覧会カタログなどを加えることで、なるべく現代の「崇高」論の広がりを伝えられるような50冊にした。
さきほど、本書は「崇高」という概念の「使用法」に徹する、と言った。それが意味するところは、ひとえに、本書がひとつの道具箱として構想されているということにほかならない。ここからの序論や対談、さらにはそれらに添えられた註や書誌が、読者にさまざまな思索のきっかけをもたらすことになれば幸いである。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。