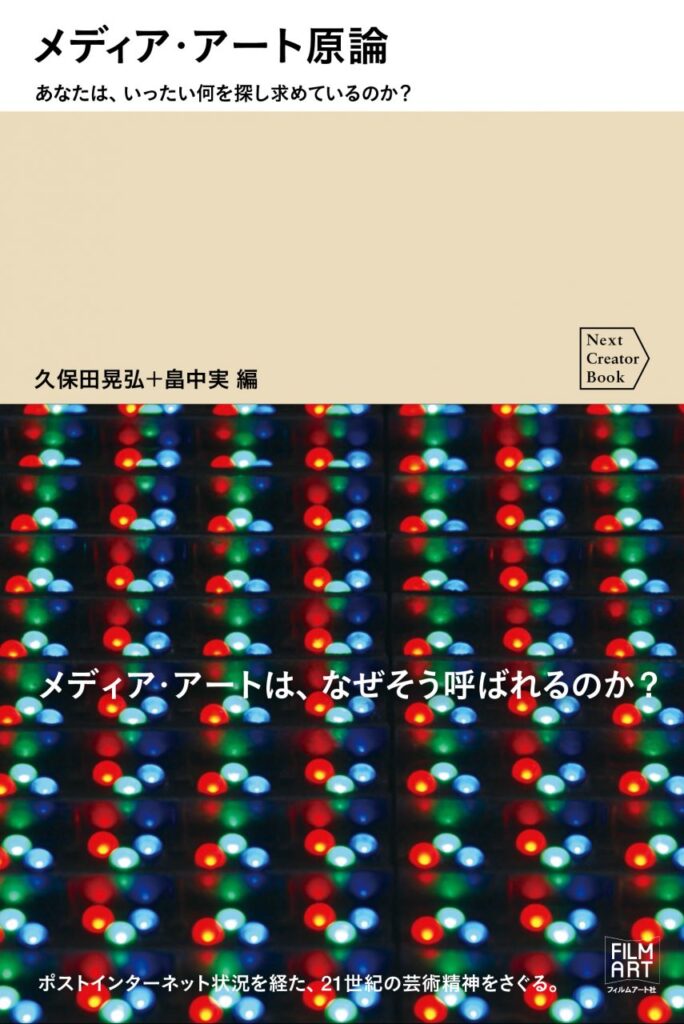メディア・テクノロジーを使用した美術作品の総称というだけにとどまらず、技術を応用したデモンストレーションやエンターテイメントも含めて幅広く使用されている「メディア・アート」という名称。定義が難しいうえに、メディア・アートに関する言説も複数が錯綜しているため、入門者にとってはややとっつきにくいイメージがあるかと思います。『メディア・アート原論 あなたは、いったい何を探し求めているのか?』は、最先端の工学に明るく、創作者としても活躍中の久保田晃弘さんと日本のメディア・アートのメッカ、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC]で20年間メディア・アートの現場に携わってきた畠中実さんという第一人者の二人が、メディア・アートに関する論点をわかりやすく整理・解説した入門書です。
今回の「ためし読み」では、「Introduction メディア・アートとはどのような芸術か ――アート、テクノロジー、サイエンスの諸相」の全文を公開いたします。
Introduction
メディア・アートとはどのような芸術か
――アート、テクノロジー、サイエンスの諸相
畠中実
現在、メディア・アートという名称は、一般的にはコンピュータをはじめとする同時代のメディア・テクノロジーを使用した美術作品を総称するものとして使用されている。しかし実際には、技術を応用したデモンストレーションなども含めて幅広く使用されており、明確な定義があるわけではない。現在進行形の芸術動向において名称および定義とは、あくまでも便宜的なものにならざるをえないが、メディア・アートをめぐっては、複数の言説が錯綜しているのが現状と言っていいだろう。
また、メディア・アートには、それを成立させるための特定のメディウムというものが存在しない。そこで使用されるテクノロジー、およびその使用法、さらにはテクノロジーとの関わり方や、その手法は多岐にわたり、アーティストそれぞれが異なるメディウムとの接点をもっている。それゆえ、メディア・アートに明確な定義を与えることは、より困難になっており、いまなお議論され続けている問題でもある。
一例として、映像装置や音響装置、コンピュータやインターフェイス、インターネットやスマートフォンなど、さまざまなメディア・テクノロジーが使用されているのが特徴である。しかし、メディア・アートで扱われる領域には、現在普及しているテクノロジーだけではなく、現在研究中、開発中のテクノロジー、さらには現在から照射され、再発見された過去のテクノロジーなど、多様なコンテクストからのテクノロジーとの関わりが含まれている。
メディア・アートは、1950年代、60年代より続く、テクノロジー・アート、エレクトロニック・アート、インターメディア、環境芸術などと呼ばれてきた動向を継承するものである。当時は世界的にテクノロジー・アートの台頭が起きているが、たとえば、50年代に音楽、美術、文学、演劇などを出自とするメンバーによって結成され、同時代の新しいテクノロジーを表現に取り入れ、諸芸術ジャンルを横断するような活動を行った実験工房がその嚆矢として挙げられる。また、とくに日本では、高度経済成長後期にあたる60年代半ば以降、1970年に大阪で開催された日本万国博覧会をひとつのピークとして台頭したテクノロジー・アートの動向も、メディア・アートの起源のひとつである。これらの動向は、日本におけるメディア・アート前史と言えるものであり、日本においては、経済成長期における企業による支援によって実現されたという側面を少なからずもっている。
こうした大阪万博へと向けた助走としてのテクノロジー・アートの隆盛から一転して、70年代は、万博が掲げた未来礼賛に対する疑念が表れ、テクノロジー・アートが凋落した時代ともなった。そのため、美術ジャーナリズム、美術研究からは一過性の流行現象として、日本の戦後美術史においても見過ごされてきた。たとえば、万博以後にはテクノロジー・アートと入れ替わるように、70年代日本の現代美術における主要な動向となる「もの派」のような、非テクノロジーの傾向をもつ一群のアーティストが台頭する。「もの派」は自然の、あるいはつくられたままの素材を使用し、その理論的な主導者である李禹煥による「つくることの否定」を標榜した。しかし、70年代に「もの派」以降に台頭した動向には、つくらないことから脱却し、制作することを問い直す動きが見出せる。そこでは、ヴィデオやテープレコーダー、あるいは機械的な反復などを用いた、手仕事に寄らない手法によってつくることの再検証が行われている。
ヴィデオ・アートもまた、万博という国家主導によるイヴェントを経た状況を背景にして登場したものでもある。それは、社会に対するメディアのオルタナティヴなあり方や創造的文化を模索する表現である。また、市民運動とも連動するなど、ヴィデオというメディアによってアーティストたちはもうひとつの表現語彙を探求した。ヴィデオ技術のポータブル化と普及に伴って登場し、ヴィデオというメディアの特性を生かしたインディペンデント・メディアとしての性質によって台頭したヴィデオ・アートは、メディア・アートの前史として位置づけられるものでもある。
メディア・アートというジャンルが、現在その名称によって指示されるような作品とともに顕在化するのは、80年代末ころからである。70年代のヴィデオ・アートが、80年代以降、ヴィデオやコンピュータ・グラフィックスの隆盛、パーソナル・コンピュータの普及などを背景に、メディア・アートへと移行していくことになる。
芸術表現と技術的な進歩は、20世紀以降の美術のなかでも、未来派やポップ・アートといった、テクノロジー化する現代社会に反応して現れた表現を生み出した。テクノロジーを直接表現手段として使用することにとどまらず、テクノロジーやそれによってつくられる社会や環境に触発されて生まれた表現、さらには、工業技術から生まれた新しい素材や新しい制作手段を取り入れるなど、社会との関わりにおいて展開され、その影響関係は広範囲におよぶ。
イギリスのアーティスト、リチャード・ハミルトンのコラージュ作品や、アメリカのアーティスト、アンディ・ウォーホルのシルクスクリーンの技法による作品なども、当時の現代社会を反映した作品である。ハミルトンの代表作であり、ポップ・アートの嚆矢となった作品《今日の家庭をこれほどに変え、魅力あるものにしているのは、一体何か?》は、当時の生活がどのようにそれ以前と変わりつつあったか、あるいは変わっていくのかという、変化の認識がつくらせた作品である。また、ウォーホルは、広告やマスメディアにおける表現をモチーフにし、まるで商品カタログのような写真をシルクスクリーンで大量に刷り、「機械になりたい」と語り、自分のアトリエを「ファクトリー」と呼んだ。
テレビなどの電子メディアがもたらす社会、文化の変容という問題は、テクノロジー・アートのみならず同時代の芸術にも 大きな影響を与えている。カナダの英文学者、マーシャル・マクルーハン(1911-1980)は、60年代に『メディア論――人間の拡張の諸相』(1964)などを著し、電子メディアの革命的な性質にいち早く着目した。それは、新しいメディアは古いメディアをその内容として現れるという性質であり、写真というメディアが絵画を、映画というメディアが文学や演劇を、テレビというメディアが映画をその内容とする、というように、新しいメディア環境を可視化することが芸術家の役割だと考え、そうした電子テクノロジーの時代に、あらためて芸術家の役割を指摘した。
また、60年代の中ごろ、AT&Tのベル電話研究所のエンジニア、ビリー・クルーヴァー(1927‐2004)を中心として、ロバート・ラウシェンバーグ(1925-2008)などのアーティストによって結成されたE.A.T.(Experiments in Art and Technology)は、軍事技術を頂点とする、実用的に機能するために開発されるテクノロジーを芸術表現に用いることで、テクノロジーを精神や創造性のために奉仕しようと考えた。そこには、新しいテクノロジーのよりよい利用法、使用法を芸術家との恊働によって生み出し、芸術表現のために開発されるテクノロジーを示唆する考えがあった。
こうした、メディア・アートにおける、与えられた技術のなかから異なる目的や意味を見出すという性質は、1968年にロンドンのICAで開催された、コンピュータ・アートによる展覧会の嚆矢となった「サイバネティック・セレンディピティ(Cybernetic Serendipity)」にすでに表れている。それは、本来の目的とは異なる価値や意味を見つける能力(セレンディピティ)というものが、メディア・アートがアートたる所以であるということをよく表している。
ヴィデオ・アートのパイオニアとして知られ、電子メディアを駆使した作品を制作し続けた、ナムジュン・パイク(1932-2006)は、一貫して通信メディアの可能性を探求し続け、芸アー術トと通コミユニケーシヨン信が融合する新しい芸術形式を構想した。パイクは、テレビ局とともに実験的なヴィデオ・アートを制作し、また技術者とヴィデオ・シンセサイザーなどの映像変調装置を共同制作した。さらには、大規模な同時多元中継プロジェクトや情報スーパーハイウェイ構想にもとづく作品の制作も構想するなど、電子メディア以降の芸術家像と言うべきものを体現していたのがパイクだった。それによって、現在では、パイクはヴィデオ・アートのみならず、メディア・アートの祖と見なされている。
80年代以降のメディア・アートにおけるパイオニアのひとりであるジェフリー・ショーは、60年代に、オランダで「イヴェントストラクチャー・リサーチ・グループ」を結成。一種の環境芸術とも言える、空気で膨らませたバルーン状の彫刻のようなものを遊び場として公共空間に提供した。また、コンサートのステージにそうした彫刻作品を応用し、レーザーを使った演出を行った。
90年代後半以降、パーソナル・コンピュータの処理速度の向上とインターネットの通信環境の高速化などのマルチメディア時代の到来を大きな要因として、海外での動向も含め、メディア・アートが新たな芸術潮流として注目されるようになる。とくに、作品を鑑賞者が、たんに鑑賞するだけではなく、作品が観客の介入によって、観客との関係性のなかで変化していくことを特徴としたインタラクティヴ・アートは、鑑賞者のアクションや環境の変化をパラメーター(変数)として作品に反映させる新しい表現形式として多くの作家や作品を生み出した。その隆盛は、とくに当時のコンピュータ技術の発達に負うところが大きく、現在にいたるまでメディア・アートを特徴づける要素のひとつとなっている。
90年代より、日本でもインタラクティヴな作品の制作を行うアーティストが多く登場している。とくに、技術の本質をとらえていく視点を明確にもつ藤幡正樹の作品は、コンピュータが現れたことによって、見る、聴く、読む、書く、作る、などの体験が対象化されることで、新しいテクノロジーをより根源的なところで考えるきっかけを与えるものとなっている。
また、2010年以降には、メディア・アートをはじめとして、ゲームなどのエンターテインメントや、マンガ、アニメーションなどが含まれたジャンルとして規定された「メディア芸術」という言葉が衆目を集めた。しかし、そのジャンルの規定は、メディア・アート周辺の関係者に一種の混乱をもたらし、「メディア・アートとは何か」という議論をうながし、メディア・アート再考の契機ともなった。
メディア・アートにおける、ハッキングやベンディングといった手法は、テクノロジーがどのようにして芸術に転用可能かという問題意識をもっていたE.A.T.の時代から変わらぬ、テクノロジーに対するアーティストのスタンスであるとも言える。
現在、インターネットの全世界的な普及と一般化などのメディア技術の浸透度の高まりを背景にした、「ポスト・インターネット・アート」や、3Dプリンターやレーザーカッターなどの普及に伴うデジタル・ファブリケーションの動向などは、メディア・アートにとどまらず、デザインや広く現代美術の領域へ、さらにはゲームや舞台演出などのエンターテインメント分野へも展開されるものとなっている。また、メディア・アートの先駆者たちの試みは、現在の、ライゾマティクスをはじめとした、テクノロジーを駆使したエンターテインメントの演出などにも接続される。さらに現在では、バイオ・テクノロジー、宇宙開発技術、人工知能、アンドロイド技術など、これまで芸術の範疇になかったさまざまなテクノロジーが例外的な芸術表現として試行され、より広範囲な表現へと広がり、芸術表現の可能性を切り開こうとしている。
(このつづきは、本編でお楽しみ下さい)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。