『闇の左手』『ゲド戦記』などの作品で知られる小説家、アーシュラ・K・ル=グウィンの創作指南書『文体の舵をとれ』は2021年の邦訳刊行直後から「文舵」という愛称で呼ばれ、創作者の間で大きな話題となりました。本書収録の練習問題に対する解答(作品)を「#文舵練習問題」というハッシュタグでSNS上に投稿するというムーブメントが発生し、創作者がオンライン上で集い合評会を行うという動きもありました。
今回は文芸サークル「サ!脳連接派」を主宰し、二度にわたり「文舵合評会」を運営した経験をもつ大戸又さんと、その合評会に参加し「竜と沈黙する銀河」で第14回創元SF短編賞を受賞しデビューした阿部登龍さんのお二人に、創作者目線で『文体の舵をとれ』について語っていただきます。
また、本書の翻訳を担当した大久保ゆうさんには、作家アーシュラ・K・ル゠グウィンについて、そしてアメリカにおける創作教育の歴史についてお話しいただきます。
プロフィール
阿部登龍(あべ・とりゅう)
作家、獣医師。百合とドラゴンとSF、ファンタジーが好き。2023年、「竜と沈黙する銀河」で第14回創元SF短編賞を受賞(同作は『紙魚の手帖vol.12』に掲載)、他に「父のある静物」(Kaguya Planet)。同人では『竜の骸布』、「熊神たちの沃野」(『Neverland, Neighborhood』)など。今年8月には『紙魚の手帖vol.18』にて、受賞後第一作「狼を装う」を発表予定。大戸又(おおと・また)
会社員、アンソロジスト(野生)。SF/ファンタジーを主軸に、テーマアンソロジーを定期刊行するサークル「サ!脳連接派」主宰。既刊で取り上げたテーマは「ドラゴンカーセックス」「都市」「サイバーパンク」「アーバンファンタジー」など。今年の冬コミでは全作オリジナルのハイファンタジー中編を集めたアンソロジーを刊行予定。
大久保ゆう(おおくぼ・ゆう)
翻訳家。幻想・怪奇・探偵ジャンルのオーディオブックや書籍のほか、絵画技法書や映画・アートなど文化史関連書の翻訳も手がけ、芸術総合誌『ユリイカ』(青土社)にも幻想文芸関連の寄稿がある。代表的な訳業として、アーシュラ・K・ル゠グウィン『文体の舵をとれ──ル゠グウィンの小説教室』(フィルムアート社)、『現想と幻実──ル゠グウィン短篇選集』(共訳・青土社)がある。

――『文体の舵をとれ』を未読の方のために、翻訳者の大久保さんから簡単に本書についてご紹介いただいてもよいでしょうか。まず著者のアーシュラ・K・ル゠グウィンについておうかがいできればと思います。
大久保ゆう(以下、大久保):アーシュラ・K・ル゠グウィンはアメリカの作家で、代表作に『闇の左手』(ハヤカワ文庫)を含む宇宙もの、日本では『ゲド戦記』(岩波少年文庫)として知られる連作などがあり、日本ではいわゆるSFやファンタジーの作家として知られている方です。残念ながら2018年にお亡くなりになったんですが、非常に大きな影響力を持っている作家でした。
西海岸の北部にあるオレゴン州ポートランドという、とてもリベラルな雰囲気の場所で主に活動し、優れた想像力と文体を駆使して、数多くの作品を送り出してきました。なかなか翻訳では伝わりづらいところではありますが、作品ごとにさまざまな文体を用い、内容と文体を一致させるというような技巧的な試みをする作家でもあり、また実に読みやすい・わかりやすい文章を書くということでも知られています。
そういう作家なので、文体について人に教えられることもたくさんあるはずだと、当然思えるわけで、ル゠グウィンの文体論、創作指南書というだけでものすごく惹かれるものがあるのは確かです。
ル゠グウィンは、同時代小説、Sci-Fi&F、詩、歴史小説、絵本、翻訳などさまざまなジャンルの作品を書いていますが、本人はそのようなジャンル分けをあまり好まなかったようです。例えば『現想と幻実 ル=グウィン短篇選集』(青土社)という短編集では、既存のジャンル分けを採用せず、作品を「地上のどこか(現実世界)」と「外宇宙・内なる地(想像力の範囲の世界)」のふたつに分類しています。
書籍のタイトルは『現想と幻実』で、「幻想」と「現実」の「げん」の字をひっくり返しているんですが、作風としても同じようなところがあります。ル゠グウィンは、現代小説でものすごく幻想的なものを書く一方で、SFやファンタジーになるとかなりリアルな設定を詰めてくるんです。そういうところも含め、現実と幻想的なものを混ぜていくタイプの作家であるといえます。ル゠グウィンは単なるリアリティから少し逸れたファンタジーを書くことを非常に大事にする人で、もちろんそれは彼女にとっての幻実でもあるし、そこから広がる作品それぞれの独特の世界というものを「見たい」あるいは「見せたい」という部分があるのだと思います。
――そのル゠グウィンの作品観や創作観が反映されているのが、この『文体の舵をとれ』になると思うのですが、どういった内容の創作指南書になるのでしょうか。
大久保:『文体の舵をとれ』の「はじめに」に「本書は初心者向けの書籍ではない。本来の対象は、もう自作の執筆に励んでいる人たちである。」と書いてあるように、本書はすでにある程度執筆経験のある方を対象にしている指南書です。
自分の文章(最近の文学用語では「声」といいますが)あるいは作品の声をいかに制御していくのか、その方法論が全10章にわたって解説されており、各章には演習問題が用意されています。そしてみんなで作品世界に響く声について考えて意見交換していく「合評会」とその運営方法についても書かれています。
ル゠グウィン自身いろいろな場所で創作ワークショップを行っていましたが、その中で得た知見やワークショップで実際に使っていた演習問題を整理し直して作ったのが、この『文体の舵をとれ』ということになります。複数の人が同じ練習問題に取り組んで、それを見せ合う「合評会」はものすごく刺激的です。その中でル゠グウィンが特に大事にしていたのが「敬意」という部分です。敬意を忘れずに、お互いの作品について有益なコメントを付け合い参考にする、そういうやり取りをとても大事にしていたことが分かります。それは、他の創作指南書にはなかなかない、よい部分だと思っています。
他の人と同じ課題について話し合うことで、自分の作家としての特徴や相手の特徴などがはっきりと分かるようになるんですね。これは文体や声を見つけるうえでものすごく大事なことだと思います。そこがやはりワークショップという形式のいいところでもあるし、ル゠グウィンがいうように、創作の「海」に立ち向かう仲間がいることの効果はすごく大きいんじゃないかと思っています。
――次に書き手である阿部登龍さんと大戸又さんにお聞きします。そもそもお二人は『文体の舵をとれ』に限らず、この手の「創作指南書」を読む機会は多かったのでしょうか。
大戸又(以下、大戸):自分は読む方です。10年ほど前に小説を書こうと思い立ったときは、図書館で小説の書き方の本を手に取りました。書名は覚えていないのですが、「アウトラインを重視する」内容の本でした。ただその時は書籍の内容はあまり身にならなかったと記憶してます。
コンスタントに小説を書くようになってからは参考になりそうな指南書がないか常に探しています。内容すべてが執筆の役に立ったという本は多くないのですが、1ページでも実作に活かせるところがあれば買った甲斐はあったと思います。最近は手に取った創作指南本がかなりの高確率でフィルムアート社さんの出版で、「またか」みたいな(笑)。
阿部登龍(以下、阿部):僕は読み物としてこの手の本が好きなんですよね。映画が好きなので、ブレイク・スナイダーの『SAVE THE CATの法則』(フィルムアート社)のような映画脚本術の本は、執筆に役に立つだけでなく、映画を観る楽しさも増してくれて、アウトプットとインプットの両輪で役に立つと思っています。
その他に良かった本を挙げますと、大戸さんと共通の友人のお勧めをきっかけに手にとった、平田オリザさんの『演劇入門』(講談社現代新書)ですね。また、非常に影響を受けたのは、脚本家・映画監督・スクリプトドクターの三宅隆太さんが書かれた『スクリプトドクターの脚本教室・初級篇』『スクリプトドクターの脚本教室・中級編』(ともに新書館)です。三宅さんは「マンガ家のためのプロット講座」を開かれているのですが、その第1回目を受講して学んだことが僕の中で軸になっています。実は『文体の舵をとれ』の合評会と時期が被っていたので、合評会が隔週で、講座が毎週あって、かなり大変でした。ただ、お陰ですごく力がついたと思っています。
いわゆる「三幕構成」の原点であるシド・フィールドの『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと』(フィルムアート社)も折に触れて読み返しています。直近では『読者を没入させる世界観の作り方』(フィルムアート社)を読みましたが、こちらも良かったです。特に、良いプロローグと不要なプロローグ、ファンタジーにおける魔法の設定、マジックシステムについての項目がお気に入りです。
文章自体の書き方の本でいうと、本多勝一『日本語の作文技術』(朝日文庫)が役に立ちました。新聞記者であった本多さんによる、「わかりやすい文章」「伝わる文章」のルールは明快で、小説の文章においても学ぶところがありました。特にSF小説では、何かをわかりやすく説明しなければならない場面、というのが思いのほか多いんですよね。
【阿部登龍さんおすすめの指南書】
平田オリザ『演劇入門』(講談社現代新書)
シド・フィールド『映画を書くためにあなたがしなくてはならないこと』(フィルムアート社)
三宅隆太『スクリプトドクターの脚本教室・初級篇』(新書館)
三宅隆太『スクリプトドクターの脚本教室・中級編』(新書館)
本多勝一『日本語の作文技術』(朝日文庫)
大戸:先日(2024年5月21日)文学フリマがあり、そこで阿部登龍さんにもご参加いただいてアーバンファンタジーアンソロジー『Neverland, Neighborhood』(サ!脳連接派)という同人誌を刊行したのですが、そこに収録されている新作を書いたときにめちゃくちゃ役に立ったのが、リストに「☆」をつけている本でした(下リスト参照)。
【大戸又さんおすすめの指南書】
☆K.M.ワイランド『キャラクターからつくる物語創作再入門』(フィルムアート社)
☆ジェシカ・ブロディ『SAVE THE CATの法則で売れる小説を書く』(フィルムアート社)
☆平田オリザ『演劇入門』(講談社現代新書)
ブレイク・スナイダー『10のストーリー・タイプから学ぶ脚本術』(フィルムアート社)
カール・イグレシアス『「感情」から書く脚本術』(フィルムアート社)
ロバート・マッキー『ダイアローグ』(フィルムアート社)
アリストテレス『詩学』(光文社古典新訳文庫)
佐藤亜紀『小説のストラテジー』 (ちくま文庫)
筒井康隆『文学部唯野教授』(岩波現代文庫)
――お二人が挙げている平田オリザさんの『演劇入門』が小説を書く方にとっても役立つというのは意外でした。
大戸:平田オリザさんは演劇の方ですが、『演劇入門』は演劇以外にも応用が効く書籍だと思います。エンタメを作るうえで重要な、どんな台詞が良い台詞なのか、どんなシチュエーションを舞台にするべきなのか、どんな人物を登場させるべきなのか、について理解が深まります。特に参考になったのは、「情報量の差」という概念です。詳しくは購入して読んでみてほしいです(笑)。
アリストテレスの『詩学』は創作論の古典です。悲劇と喜劇におけるカタルシス(浄化)の機能についての説明は小説執筆の参考になると思います。
佐藤亜紀著『小説のストラテジー』からは小説に登場するモチーフの読み方について学びましたし、筒井康隆著『文学部唯野教授』はパロディ小説でありながら、文学の潮流や理論を大まかに知ることができて面白いです。まず、こういう書き方をする一派があり、それのアンチがいて、更にそのアンチでまた戻って、みたいな揺り戻しみたいなのがあるんだということが書かれていて、こういう文学史的な知識が小説を読んでいくうえでのベースになるんじゃないかなと思っています。
――普段から多くの創作指南書に目を通されているお二人は、この『文体の舵をとれ』をどのように評価されているのでしょうか。ほかの指南書と違う点や特に役に立ったと思えるポイントがあれば教えていただければと思います。
阿部:そもそも「文体」にフォーカスした指南書っていうのが、あまり類例がないんじゃないでしょうか。
大戸:そう思います。
阿部:脚本術の本にも『文体の舵をとれ』のように練習問題が収録されていることがありますが、さすがに脚本向けの練習問題となると、小説には直接役立ちづらいかなと思っていて。ですが『文体の舵をとれ』には、具体的で、小説の文章に特化した練習問題が揃っています。なおかつ合評会という形で実践しようと勧めている。そこがこの本の大きな特徴だと思います。文学論のような抽象度の高い話題だけでなく、非常に実践的でもある。本文でル゠グウィン先生も書いていますが、「芸術」と「技術」の両輪があるのがいいところです。
そして大久保さんもおっしゃっていたように、この本は中級者向けの本なんですよね。まったく書いたことのない初心者が隣に置いて使う本というより、一定程度の経験があり、熱意を持って執筆に取り組んでいる人に向けて書かれている本だと思います。そういう意味でも類書がないのではないでしょうか。知らないことを知れたり、復習になったり、足りない部分が見つかったり、頭打ちの状態からさらに一歩先に進むために必要な本だと思います。
自分の話をすると、僕は中学生の頃から小説を書き始めて、細々とですが15年以上書いています。それで、自分で言うのもおこがましいのですが、大学に入った頃くらいから徐々に、「もうこれ以上文章は上手くならないな」「成長できないな」と、自分の限界を感じはじめていたんです。残るは人物の魅力やストーリーの面白さを伸ばすしかないのかなと。でも、『文体の舵をとれ』と出会い、合評会をやってみて、「いやまだまだ全然伸びしろがあるし、もっと書けるんだ!」と気づけました。それはものすごく嬉しかったですし、すごい本だなと感じましたね。
大戸:やはり魔力があるんですよね、ル゠グウィン先生が書いているから。あと基本「スパルタ」っていうのもいいですよね(笑)。小説ってやろうと思えばどこまでも自分に対してルーズに書けるわけじゃないですか。そういうものに対して、「いや、何かやるからにはもっとうまく書こうよ。やり方は私が教えるから」と言っているような、背中を押してくれる魔力が宿っている感じがします。あとは登龍さんのおっしゃるとおり、「芸術」と「技術」の両方の視点があることでしょうか。
先にいくつか挙げた「おすすめの指南書」は基本的に「プロットや構成」に関する指南書です。これらの本を読めば「ストーリーをどういう順番で物語ればよいか」という問いに対して明確な回答が返ってきます。もちろんその意味では便利な本なのですが、小説の場合は当然文章が連なることで小説になっているわけで、じゃあどういう文章を書くかという、よりミクロな問いが生まれます。そこに明確な回答を提示してくれたのが、『文体の舵をとれ』のいちばんすごいところかなと思います。
どういう文章を書くか、つまりそこには人称、視点、声の選択があり、その選択は必然的に構成にも影響してきます。なぜその人称、視点、声を選択しなければならないのか、選択することによってどういうことが語れるのか、を教えてくれる本です。
この本を読む前は「語り」とか「文体」という言葉を知ってはいても、それが一体何を指している言葉なのか自分のなかで明確になっていませんでした。『文体の舵をとれ』を読んで、「文体」とはなにか、どういったものによって構成されているのかを知ることが出来ました。
小説の中でもっともミクロな要素である「文章の書き方」の指針を与えてくれるというのは、唯一無二なのではないかと思います。
――本書の「はじめに」には次のように書かれています。
この本はそもそも自習帳である。練習問題は意識を高めるためのもの。文体作りの基礎要素のほか、物語るコツと様式について、自らの認識を鮮明かつ強固にするのが、そのねらいだ。こうした文体技巧の要素について自覚がはっきり深まったあとでなら、その訓練と活用も可能になるし、続けていけば―それこそがあらゆる訓練の勘所なのだが―そのことをあえて意識しなくてもよくなる。技術として身につくからだ。
「小説に書き方などない」という考え方も根強くあると思います。小説や文章の書き方、あるいは文体というものは学んで身につけることができるものなのでしょうか。
大戸:できると思います。原書で「craft」という単語を使っているように、「小説の書き方」は「技術(クラフト)」であって、体系化し得るものだと思っています。指導する人間がいて、適切な指導を受ければ、誰でも向上することができるのが「技術」というものだと思います。ル゠グウィンはそこを意識して「craft」という言葉を使ったのではないでしょうか。反復練習することによって、小説を書く技術も向上していくはずです。
野球でもサッカーでも基本的なフォームがあり、そのフォームを基礎として試合で活躍するための技能を習得しようとするはずです。「小説を書く技術」もまったくこれと同じだと思います。「文体」は小説の基本フォームと言い切ってよいと思います。
阿部:僕もまったく同じ意見です。ここでスポーツの例が出てくるのもよくわかります。僕は以前から不満に思っていることがありまして、たとえばスポーツのトレーニング方法、あるいは同じ芸術でも絵なんかの場合は、デッサンの方法や色相環についての知識など、必要なメソッドや知識が体系化されて広く共有されていますよね。ただ、小説に関してはそれがない。そして、ないことで小説や小説家が神秘化・神格化されている雰囲気があると思うんですよ。
僕が最終的にル゠グウィン先生と肩を並べられるかはまた別の話ですが、小説の執筆に関しては、世間で言われているよりもはるかに技術の部分が大きいはずなんですよね。そこを力のある小説家であるル゠グウィンが丁寧に、惜しみなく説明してくれている。しかもそのエッセンスを練習問題という形に凝縮して、われわれに扉を開いてくれている。そこがやはり、『文体の舵をとれ』が他の指南書と違うところなのではないかと。
――『文体の舵をとれ』の大きな特徴として、みなさんが「練習問題」や「合評会」の存在に触れてくださいました。ただ日本ではまだまだ合評会というのはあまりメジャーな方法ではないような気がします。大久保さんにお聞きしたいのですが、ル゠グウィンの生まれたアメリカの創作環境や執筆技術の習得環境はどのようなものなのでしょうか。
大久保:この本に書かれていることは、ル゠グウィンの完全なオリジナルということではなく、彼女が受けてきた教育にルーツがあると思っています。先ほどもお話にでてきたアリストテレスの『詩学』は物語の構成や構想(アイデア)の部分ですごく大きなヒントを与えてくれるものですし、『詩学』とセットでよく語られているホラティウスの『詩論』という作品があるのですが、こちらはどちらかというと二次創作のススメみたいな本です。ただ、やはり詩に関する本なので、われわれが書こうとしている散文や小説にとってはなかなか役に立ちづらいところもあります。
では、何が参考になるのか、ル゠グウィンが教える際に何を参考にしてきたのかということを考えたとき、「古典修辞学」にそのルーツを求めることができると思っています。修辞学というのは、いわゆる弁論の演説の技術、つまり喋る技術です。古代の演説というものは、一方で最終的に文章として残されるものなので、やはり散文の技術でもあったんですね。
修辞学は、例えば古代ローマの円状になった議場に立って人々を説得するときに聴衆に語りかける、あるいは裁判で誰かを弁護するときに人前で語る、そういうときに必要な「説得の技術」なんですね。古くだとキケロという名演説家がいますが、こういう人たちが古代ギリシャから学び、古代ローマで確立した技術でもあるんです。
その人たちの技術論を見ていくと、説得するための喋りをする中で、どういう風に演出をして相手を納得させるか、人の心を動かすのかっていうことを考えるんですね。物語も結局、お話を語って人の心を動かす技術なので、これはものすごく散文・小説の創作に近いところがあるんです。
この技術は西洋ではたいへん大事なものとして高等教育の中で教えられてきたことでもありまして、いわゆる物語技術として普及する前は、法学を勉強する学生たちが学ぶ基礎教養としての弁護術、あるいは神学の場合は僧侶が教会でお説教する際にそれを聞いている信者をいかに感動させるのか、みたいな時にも重要視される技術だったんですね。
そして実際に彼らがそれらの技術をどういうふうに学んでいたのかというと、文書として残っている演説家や作家の文章、そういうものを真似していたんですね。その文書に出てくる技術や様式あるいは表現を真似ましょう、ということや、古代ローマや古代ギリシャで書かれた文書であれば、自分達の言語に翻訳をして真似していきましょう、そういう課題がものすごくスパルタ的に出るんですね。ある種の筋トレのように。
実際のお手本を見て真似をして、そして実際に自分で実践して、ということを繰り返しながら自分達の文章技術、あるいは語る為の技術を磨いてきたという歴史があるんですね。これは実は今でも西洋圏の一定レベルの学校、特にアメリカとイギリスで顕著なんですけども、言語表現を学ぶ上でベースとなる部分ということで、大学・高校あたりででもみっちりと教え込まれるところがあります。おそらくル゠グウィンも実際にこのような道を通ってきているはずです。ル゠グウィンはもともとラドクリフ・カレッジという、ハーバード大学がまだ男子校だった時代に女子教育の場所として存在していた付属の女子大学の出身で、しかもまさに古典を専攻していました。
したがってル゠グウィン自身がおそらく文章の基礎的な修業の部分で、古典や修辞学から大きな影響を受けてきたのはまず間違いありません。この『文体の舵をとれ』にもたくさんの例文が出てきて、ちょっと真似してみましょう、ということが書かれています。これはル゠グウィンが受けてきた教育を考えるととてもよく理解できます。こういう高等教育を受けてきた人であれば、当然こういうやり方をするだろう、と。そして練習問題もセットにしてスパルタ的にやるっていうのは、やっぱりル゠グウィンが受けてきた表現教育を考えると、当たり前だろうと思うんです。
こうした修辞学の伝統みたいなものは、日本に入ってこなかったわけではなく、明治期に海外に留学していたような人たちは向こうでこのような教育を受けているはずなんです。たとえば、夏目漱石の『文学論』(岩波文庫)という本があります。これも『文体の舵をとれ』に近いところがたくさんあります。西洋の文学に例を見ながら、文体や技術をいろいろと解説していて、本人もこれは一種の修辞学である、といっています。ただ残念なことに、同じ明治期には『作文講話および文範』(講談社学術文庫)という名著もありますが、特に戦後は軽めの『文章読本』を経て本格的に続くものが目立たず、日本における修辞学の勢いは途絶えてしまった感があります。そういう日本の状況において、古典修辞学の流れを汲む『文体の舵をとれ』がひとつ穴を埋めてくれる役割を担ってくれているんじゃないかと思います。
大戸:めちゃくちゃ面白いですね、なるほど。
阿部:勉強させてもらってます(笑)。
大久保:1950年代、特にSF界隈で創作ワークショップが盛り上がりを見せます。SFはもともとアマチュア的な要素が強いジャンルだと思うのですが、そういう中で「もっとみんなプロ意識を持とうよ」「自分たちの技術を高めていこうよ」ということを、著名なアンソロジー編集者でありSFのフィクサーだったジュディス・メリルという人が言い始めます。このジュディス・メリルとデーモン・ナイトという人が始めた「ミルフォード・ライターズ・ワークショップ」に、やはりル゠グウィンも講師として何度も参加しています。
この「ミルフォード・ライターズ・ワークショップ」でも合評会的なものがものすごく大事にされたそうです。大会(カンファレンス)というくらいですから、集まった参加者がお互いの作品についていろいろと指摘し合うことになります。そういうことがプロ意識につながっていくんだというんですね。
そしてこの「ミルフォード・ライターズ・ワークショップ」からいろいろと派生的にワークショップが誕生します。そのうちのひとつで今でも存在するのが「クラリオン・ワークショップ」です。そして70年代に、このワークショップが大学へと舞台を移すんですね。つまり大学で創作を学ぶ時代が来たということです。そもそもアメリカの大学では40年代くらいから、創作科の本家本元といわれるアイオワ大学というところで、ワークショップで文章や作品を書き、それがいわゆる学位論文になる、というカリキュラムがはじまります。それがすごくうまくいって60年代以降、アイオワ大学からピュリッツァー賞を受賞するような作家がどんどん誕生するということもあり、すごく注目されるようになりました。
アイオワ大学に影響を受けて、他の大学にもいろんな創作教室というものができてきます。そしてさきほど挙げた「クラリオン・ワークショップ」も大学の中に組み込まれていきました。しかもアイオワ大学にも「合評会形式」がやはり存在します。本当にスパルタ的なものらしく、『文体の舵をとれ』よりもかなりハードな合評会だったようです。例えば誰かが何かを書いてきて、その作品を半時間~小一時間くらいみんなで囲んで合評するというような。
阿部:やるほうもやられるほうもきつそうですね(笑)。
大久保:村上春樹が翻訳していることでも有名なレイモンド・カーヴァーという短編小説家がいます。カーヴァーもそのようにして各地にできた大学の創作教室のひとつに通っていました。カーヴァーが小説のすべてを学んだと語っているのが、クリエイティブ・ライティングの世界で伝説となっているジョン・ガードナーという教師でした。
ジョン・ガードナーはもともと中世英文学(つまり古典)の教師で、大学で学生たちに創作技術を教えていく中で自分自身も学び直し、自分もその後本当に小説家になったという人です。教師も学生も一緒に学んでいくようなワークショップがどんどん広まりを見せ、カーヴァーをはじめとした大学で創作を学んだ作家が、アメリカで活躍していくようになるんですね。
京都大学の吉田恭子先生や翻訳者の小磯洋光さんなど、英米の大学で創作を体系的に学んできたという日本の方もいらっしゃいますが、日本では大きなムーブメントという感じにはなっていないというのが現状のようです。そこが日本とアメリカの大きな違いだろうと思います。
――日本の創作の状況については、阿部さんや大戸さんはどのように認識されていますか。
阿部:創作教室としては、カルチャースクールの小説講座みたいなものは見かけます。ただ、何を指針として選べばよいのか分からないですし、本当にプロを目指すのか、あくまで趣味の延長なのか、というあたりで自分が欲しているものとは少し違う気がしています。ジャンル小説であるSFを書いているので、純文学系の多い印象のあるそうしたカルチャースクールは、なおさら違うかなとも。SFだと今は、「ゲンロン大森望SF創作講座」くらいしか学べる場がないのではないかと思います。ただ、僕は北海道生まれなので、ゲンロンのSF講座などはどうしても東京の文化、自分からは遠いものという気がしてしまいます。東京近郊に住んでいなければそうした場に参加さえできない状況がある。そう考えると、やはり創作について何か学ぼうとすると、はじめはインターネットになるのかなと思います。
中学2年生で小説を書き始めたときは、まずYahoo!検索で「小説 書き方」と調べるところからはじめました。文章作法に関して扱う個人サイトなどが出てきて、そこで表記の基本、たとえば「行頭一字下げ」なんかを学んでいきました。今だとフィルムアート社さんがカクヨムで連載している「本当に学びたい人の小説の書き方講座」は、めちゃくちゃいいなと思って見ています。
僕が書き始めた時代は、今のような形のSNSもなくて、インターネットを通じたコミュニケーションも密ではなかったです。それがだんだん、作品を通じて人とコミュニケーションを取るとか、仲良くなるという場面が増えてきて、よいところも多い反面、初心者の段階から作品外でのコミュニケーションや作品に付随した数字まで考えざるを得ないといった、ある種の難しさはあると思いますね。
あとは、小説投稿サイトの盛り上がりによって「小説投稿サイト用の小説」というのが明らかに登場してきたと思います。行頭で一字下げしないとか、空行を多めにとるとか、セリフやイベント中心で描写は控えめとか、文章表現の流行も変わってきたのではないかと。なので、いわゆる書籍ベースの小説とは異なるウェブ小説向けの「文体」も生まれてきていると感じます。
大戸:アメリカ的な創作コミュニティみたいなものは無いかもしれません。さきほど大久保さんがおっしゃっていたように、そもそも日本国内で創作を体系的に学ぶ場が存在していない、あるいは本当に少ないという状況だと思います。自分も『文体の舵をとれ』の合評会をリアルの場でやってみるということも考えたのですが、ちょうどコロナのタイミングだったということもあり、リモートを選びました。東京の一極集中を避けられるという意味でも、今だったらインターネットを活用して、そういう場を作っていくのがいいんじゃないかと思います。
阿部:大学生なんかは、毎週部活としてガンガンハードワークをやったらいいと思うんですけど、社会人だとリアルで集まって、というのはなかなか難しいですよね。
大戸:SF界隈だと人間六度さんが日本大学芸術学部の文芸学科出身で、そこは創作系のワークショップをカリキュラムに取り込んでいると聞いたことがありますが、そのような場が用意されている大学は多くない印象です。そもそも大学に入るという時点で、親の収入や年齢などがハードルになってきます。とするとやはりインターネットの世界で、ということになるのでしょう。
――誰もが簡単にいろんな情報に触れることができるという意味で、SNSを含めたインターネットの世界は便利ですが、情報を発信している人も実にさまざまで、いったいどの情報を信じればよいのか分からない状況も発生しているのではないでしょうか。
大戸:発信した方のプロフィールを確認するのを心がけています。自分は権威主義的な部分もあるので、『文体の舵をとれ』はル゠グウィンが書いてるのだから絶対面白い本なのだろうと思って手に取りました。あとは発信している人のSNSのプロフィール欄に作品へのリンクがあったら、とりあえずその作品を読むということはします。そして書き出しを読んで判断する、ということをしています。
阿部:僕もほぼ同じ動きをします(笑)。ネットの情報も当然利用しますが、やはり本という形になっている情報を信頼しています。そういう意味で僕も権威主義的ですね。僕の場合は、ある程度リテラシーがついた状態で今のネットやSNSに触れることができたので良かったと思いますが、いま書き始めの若い方とかが、まっさらな状態で玉石混淆の膨大な情報に触れたときにどうなってしまうのか、というのは心配になりますね。
――ありがとうございます。さきほどご紹介いただいたフィルムアート社の「本当に学びたい人の小説の書き方講座」は完全無料コンテンツとなっていますので、何を勉強すればよいのか分からないという方はまずは一度ご覧いただくとよいかもしれませんね。ではいよいよ『文体の舵をとれ』の合評会の運営についてお聞きすることにします(後編:「文体の舵」のとり方:どのように合評会を運営するのか?につづく)。
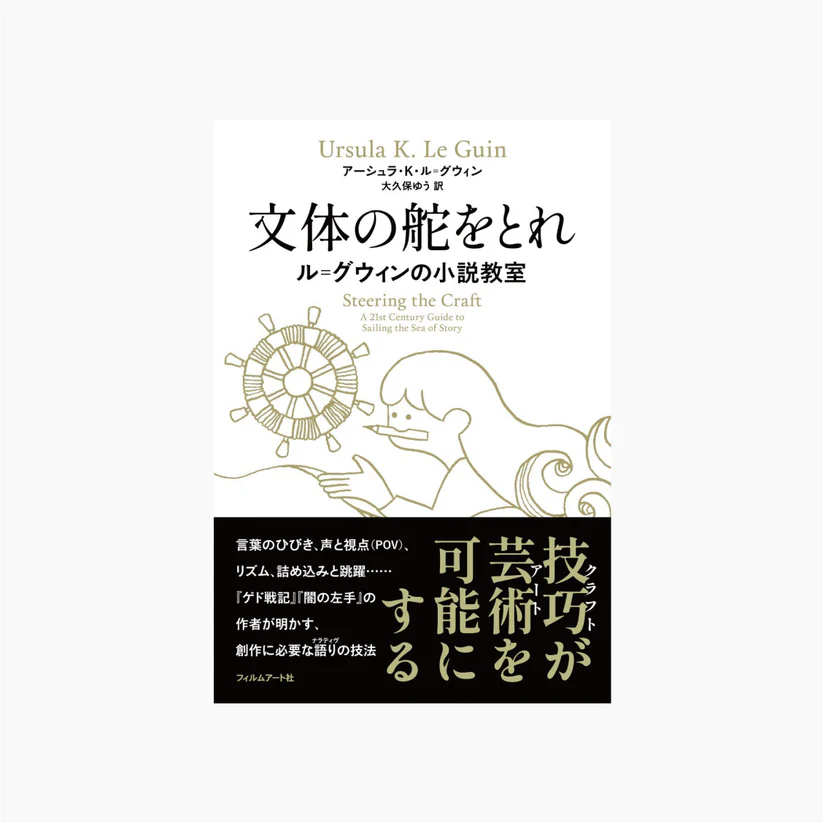
購入する
文体の舵をとれ
ル=グウィンの小説教室
アーシュラ・K・ル=グウィン=著
技巧(クラフト)が芸術(アート)を可能にする
『ゲド戦記』『闇の左手』のアーシュラ・K・ル=グウィンによる小説家のための手引き書
ハイファンタジーの傑作『ゲド戦記』や両性具有の世界を描いたフェミニズムSF『闇の左手』などの名作を生み出し、文学史にその名を刻んだアーシュラ・K・ル=グウィン。本書は、ル=グウィンが「自作の執筆に励んでいる人たち」に向けて、小説執筆の技巧(クラフト)を簡潔にまとめた手引書です。
音、リズム、文法、構文、品詞(特に動詞、副詞、形容詞)、視点など、ライティングの基本的なトピックを全10 章で分かりやすく解説。各章には、ジェイン・オースティンやヴァージニア・ウルフ、マーク・トウェイン、チャールズ・ディケンズなど偉大な作家が生み出した名文が〈実例〉として収録され、ル=グウィン自身がウィットに富んだ〈解説〉を加えています。また章末に収録されている〈練習問題〉を活用することで、物語のコツと様式について、自らの認識をはっきりと強固にすることが可能になります。
ためし読み
第5章 形容詞と副詞
訳者解説