1991年に原書が刊行された『絵には何が描かれているのか 絵本から学ぶイメージとデザインの基本原則』。絵の作用とその原則を知ることで、作ること/見ることについての新しい視点が得られ、理解を深めることができます。
本書の日本語版刊行を記念して、第一線で活躍するデザイナーや研究者の皆様による選書ブックフェア〈心を動かす絵のひみつ〉を開催しました。選者は、本書に特別解説を寄稿いただいた山本貴光さんをはじめ、松田行正さん、名久井直子さん、大原大次郎さん、細馬宏通さん、平倉圭さん、菅俊一さんの豪華7名です。
本記事では、皆様がその際にセレクトした選書リストを、各選書へのコメントとともに公開いたします。
選者:山本貴光
~はじめに~
モリー・バング『絵には何が描かれているのか』の横に置いて読みたい本を27 冊ほど選んでみました。全体を大きく三つのパートに分けてご紹介します。「イメージと人間のあいだ」「イメージ」「人間」の三つです。「イメージ」⇒「人間」⇒「イメージと人間のあいだ」と並べたほうが、単純な要素からその組み合わせへという流れになってよさそうだとも考えたのですが、ここでは逆に「イメージと人間のあいだ」で生じていることから出発して、「イメージ」と「人間」というそれぞれの要素に注目した本を並べてみることにしました。モリー・バングの本に近いものから先にお目にかけようという趣向です。もちろんそんな意図とは関係なく、どこからなりともご覧あれ。
1:イメージと人間のあいだ
イメージと人間のあいだでは何が起きているのか。これは分かったようでいて、存外よく分からないことの一つです。このたび翻訳されたモリー・バングの『絵には何が描かれているのか』は、まさにこのよく分からない出来事に迫る道筋を示してくれる本でした。このパートでは、同じようにして人がイメージを目にしたり、触れたりするとき、そこでは何が起きているのかを考察させてくれる本を選んでみます。
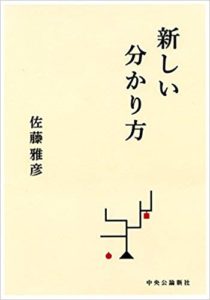
2枚の写真がある。一方は板の上に釘が立っている。まだ深く打ち込まれていない。他方は釘が打ち込まれている。その隣には、トンカチの写真。「ああ、これで釘を打ったんだな」と分かる。ページをめくると同じ2枚の釘写真の横に、今度は石の写真。「ああ、これでもなんとかなりそうだ」。さらにページを繰ると、石の代わりにバナナの写真。「これは無理……いや、バナナがかちかちに凍っていればいけるかも」などと考える。日頃、私たちはいろいろなことが「分かる」瞬間を味わう。でも、「分かる」ということがどういうことなのかは必ずしも分かっていない。この、いろいろな分かり方の図鑑とでも言うべきこの本を眺め終わると、たぶんあなたの分かり方もかわるはず。分からせ方もまた。

2. 岡崎乾二郎『抽象の力──近代芸術の解析』亜紀書房、2018年
抽象芸術と言われてどんなものが思い浮かぶだろう。幾何学図形のような絵画のようなもの、あるいは一見してなにか具体的なものが描かれているようには見えない筆の跡。ひょっとしたらそういうものを連想するかもしれない。しかし、抽象とはそういうものではない。私たちは各種の感覚を通じて、時々刻々と刺激を受けている。人は脳裏で、そうしたバラバラの感覚刺激を、そのいずれとも違う形でまとめて把握する。例えば私たちは目にした映画を丸ごとそのまま覚えているのではなく、「こういうものだった」と自分なりに圧縮し、象り、まとめて捉えている。モダニズムの前衛芸術がさまざまに試していたのは、こうした意味での抽象の力だったと岡崎さんは言う。これは具体的な作品や試みの検討を通じて、こうした抽象の力を再発見するための本である。必読。
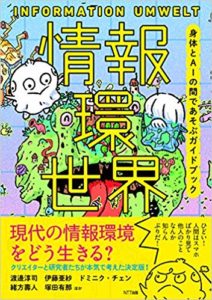
3. 伊藤亜紗, ドミニク・チェン他『情報環世界──身体とAI の間であそぶガイドブック』NTT 出版、2019年
私たちが生きている世界は、自然環境と人工環境からできている。とりわけこの数十年でインターネットとそれを利用する装置という情報技術が爆発的に普及している。それはすでに、人が意識的にコントロールできるものではなく、むしろ私たちがその中で暮らす環境の一種といってよい。しかもそこは、それぞれの人のネット上での行動履歴や使うツールによって、同じサイトでさえも人によって見え方が違っていたりする。こうした状況を、生物学者のヤーコプ・フォン・ユクスキュルが提唱した「環世界」という見方で考えてみようという賑やかで楽しいガイドブック。
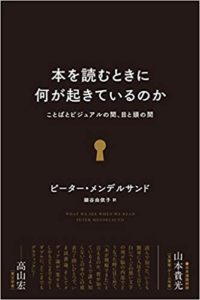
4. ピーター・メンデルサンド『本を読むときに何が起きているのか──ことばとビジュアルの間、目と頭の間』細谷由依子訳、フィルムアート社、2015年
人が本を読むとき、頭や心のなかでは何が起きているのか。ごく普通にやっていることなのに、言われてみたら何が起きているのかよく分からない。ブックデザイナーの著者は、この難問に言葉とグラフィックで挑んでいる。例えば、小説を読むとき、私たちは登場人物の顔や姿をどこまでヴィジュアルで想像しているのか、いないのか。文章を目で追いながら、そのつどヴィジュアルを思い浮かべているのか、いないのか。言われてみると、自分のことながらよく分からなくなってくる。読めば読むほど不思議なこの本で確かめてみよう。

5. 鈴木一誌『ページと力――手わざ、そしてデジタル・デザイン 増補新版』青土社、2018年
書物とは、長い時間をかけて私たちの身体にとって使いやすい形に仕立てられた道具である。では、その書物、そのページ、その組版、その書体は、どのように企まれているのだろうか。物質としての書物は、読み手になにをもたらしているのか。練達のブックデザイナー、鈴木一誌さんによる本書は、書物のデザインを通じて、読者の経験を設計する手わざを惜しみなく教えてくれる。
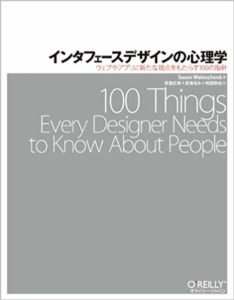
6. Susan Weinschenk『インタフェースデザインの心理学──ウェブやアプリに新たな視点をもたらす100 の指針』武舎広幸+武舎るみ+阿部和也訳、オライリージャパン、2012年
スマートフォンでアプリを使っているとき、なんだか使いづらいと感じたことはないだろうか。ボタンが現れる位置が画面ごとにあちこち変わったり、どこを押したらいいのか分からなかったり、そもそも情報がごちゃごちゃしていて見づらかったり。設計者が、アプリを使う人の目や手の動きをどう考えているかによって、使いやすさにも天と地の差が出るもの。これは、ユーザーの心理を踏まえた操作の設計で押さえるべきポイントを整理している得がたい本。人をその気にさせるデザインが気になる人も見るといいかも。

7. エイミー・E・ハーマン『観察力を磨く名画読解』岡本由香子訳、早川書房、2016年
テーブルにリンゴが一つ。その横に男の子が一人いて、リンゴに向けて手を伸ばしている。そんな絵があるとする。何が描かれているかと尋ねられたら、つい「お腹を空かせた男の子がリンゴを食べようとしているところ」と答えたくなるかもしれない。でも実際には、お腹が空いているかは不明だし、リンゴを置いた直後かもしれない。私たちは日頃、そんなふうに事実に解釈を加えて生きている。この本は、絵画を題材にして、人間のそうした認知の仕組みを実感させてくれる。名画に限らず、ものを見る目を養いたい人は一読の価値がある。
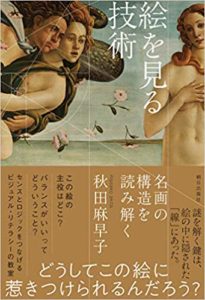
8. 秋田麻早子『絵を見る技術──名画の構造を読み解く』朝日出版社、2019年
一幅の絵を眺めながら、「うーん、なかなかいい配置だな」とか「ここに目が引き寄せられる」など、絵の上の視線の動きや絵の構成になにかを感じることがある。ただし、どうしてそうなのかとなると、これはなかなか分からない。著者は、絵のなかに走るさまざまな「線」や色の関係を浮かび上がらせて、なぜ絵からある感覚を受けるのかを見て取る方法を教えてくれる。名画の名画たる所以を、絵の構造から読み解くヴィジュアル・リテラシーを養える好著。
2:イメージ
お次はイメージの部です。ここでは形や色をめぐる探究を中心として、イメージのもつさまざまな性質を考察する本を選んでみました。込み入った情報をグラフィカルに整理するインフォグラフィクス、言語を超えて意思疎通をするためのアイソタイプの試み、素粒子から宇宙まで森羅万象を捉えんとする多様な表現の試み、あるいはイメージの達人たちによる貴重な講義など、いずれも必読必携の面白さです。

9. 永原康史『インフォグラフィックスの潮流──情報と図解の近代史』誠文堂新光社、2016年
図のすごいところは、たった一枚の紙に多種多様な要素をまとめられるところ。ただし、情報やデータをうまく整理しないと、見づらいものになってしまう。というのは、日頃目にするパワーポイントのごちゃごちゃしたスライドやウェブのあれもこれも並べたページなどで経験したことがあるかもしれない。では一体どうしたら、多様で複雑な情報を、見やすく魅力的に表現できるだろうか。情報を整理して表現するインフォグラフィクスの歴史をヴィジュアルで見せてくれる本書は、得がたいお手本集にもなる。
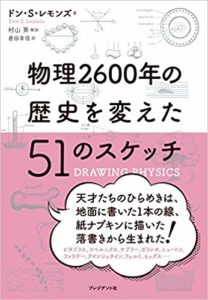
10. ドン・S・シモンズ『物理2600 年の歴史を変えた51 のスケッチ』倉田幸信訳、プレジデント社、2017年
古来、自然を研究してきた人びとは、観察したりものを考えたりする際に、言葉だけでなく図も活用してきた。例えば、テーブルに載っている物にどんな力が働いているかという状況を、言葉だけでも表現できるとはいえ、それだといささか分かりづらい。こんなとき、物体に働いている力を矢印で表せば、その向きと大きさを同時に示せるし、複数の力も一目で見てとれるようになる。しかもそうした図では、写真などと違って、説明に関係しない要素や細部をばっさり省略することもできる。先ほどの例なら、テーブルに載っている物が具体的になんであれ、○で表してしまえば用は足りるという具合。古代ギリシアから21 世紀の素粒子物理学まで、51 の例を集めて解説したこの本で、スケッチの威力を知るべし。そんな図の力を教えてくれる好著です。


11. ジョン・D・バロウ『美しい科学1 コズミック・イメージ』桃井緑美子訳、青土社、2010年
12. ジョン・D・バロウ『美しい科学2 サイエンス・イメージ』桃井緑美子訳、青土社、2010年
宇宙から地上の動植物や岩石や気象現象、あるいは細胞や素粒子まで、人類は自然の森羅万象をさまざまに捉えて表現してきた。例えば星空一つをとっても、あるときは絵画に写し、あるときは抽象化したモデル(模型)として図に表し、カメラが発明されれば写真に撮り、コンピュータが登場すればシミュレーションをCG で表したりする。科学の歴史上に現れた多様な自然のイメージを、数々の図版とともに解説したこの本は、驚きと楽しさに満ちている。
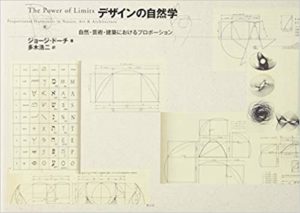
13. ジョージ・ドーチ『デザインの自然学──自然・芸術・建築におけるプロポーション』多木浩二訳、青土社、2014年
お手にとると直ちにお分かりのように、これは植物の形と幾何学図形、人体のプロポーション、魚や昆虫の形態、潮の満ち引きなど、自然と人工物に見られる形やパターンを、数理とデザインの目で見通そうという類を見ない本である。図版の美しさに加えて戸田ツトムさんと岡孝治さんによる日本語版のデザインも素晴らしい(新旧2種類ある)。いますぐ用はなくとも手元に置いてときどき開くだけで、たちまち形とパターンのワンダーランドで遊べる得がたい一冊。
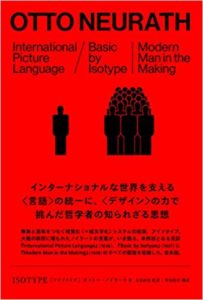
14. オットー・ノイラート『ISOTYPE』永原康史監訳、牧尾晴喜訳、BNN 新社、2017年
ご存じのように、世界の人びとが使う言葉は文化や人によって様々だ。日本語を使う人もあれば、英語、中国語、アラビア語、韓国語、ロシア語などなど、数え上げるのも大変なほど。使う言葉が違えば、お互いに意思疎通するのも一苦労。ではどうするかというので、これまでいろいろな試みがなされてきた。中でも秀逸なアイデアの一つは、哲学者のオットー・ノイラートが考えた、世界共通言語になるような図(絵文字)のシステムである。アイソタイプと呼ばれるこの試み、グラフィックやデザインをする人なら一度は見て検討しておきたい。
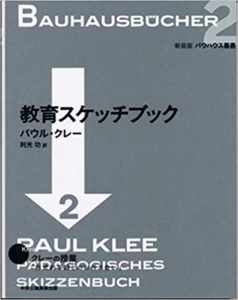
15. パウル・クレー『教育スケッチブック』利光功訳、新装版バウハウス叢書2、中央公論美術出版、2019年
これは、パウル・クレーがバウハウスで行った形と色にかんする講義のエッセンスに触れられる貴重な本だ。クレーは自分の講義を「形式的手段とのお付き合い」と呼んだのだとか。開くと分かるように、いろいろな線から始まって、各種の図形について、それらがどんな構造を持っているのか、どんな効果をもたらすかを考察したスケッチとメモが満載。ぜひとも『絵には何が描かれているのか』の隣に並べておきたい1冊。ついでに言えば、本書を含む「バウハウス叢書」(全14 巻)は、目下新装版として再刊中。見逃せない叢書である。
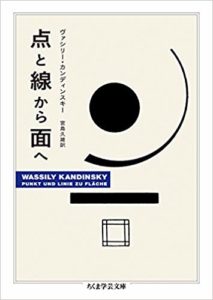
16. ヴァシリー・カンディンスキー『点と線から面へ』宮島久雄訳、筑摩書房、2017年
クレーの本が、もっぱら眺めて考えるための黒板に描かれた図形集のようなものだとすれば、同じバウハウス叢書の1冊として刊行されたカンディンスキーのこの本は、「抽象とは何か」という問題を、言葉でとことん追求してみせた思索の筋道を見せるもの。点から線へ、線から面へと進む道行きでは、図形そのものはもちろんのこと、それが私たちにどのような印象や連想をもたらすかといった心理の側面も疎かにされていない。
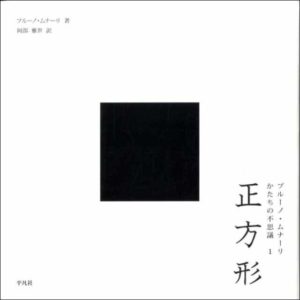


17. ブルーノ・ムナーリ『かたちの不思議1 正方形』阿部雅世訳、平凡社、2010年
18. ブルーノ・ムナーリ『かたちの不思議2 円形』 阿部雅世訳、平凡社、2010年
19. ブルーノ・ムナーリ『かたちの不思議3 三角形』阿部雅世訳、平凡社、2010年
ブルーノ・ムナーリの本は、丸ごと全部ここにリストアップしたいくらい。といっても、そういうわけにもいかないので、『かたちの不思議』で我慢しよう。これは、正方形や円や三角といった図形を、古今東西森羅万象の事例に探して集めて並べたもの。ムナーリの作品がいつでもそうであるように、遊び心とユーモアもまぶされている。なんだ、単純な図形じゃないかとゆめゆめ油断召されるなかれ。形というレンズから世界を見たら、思わぬところにつながりが見えてきて、アイデアの幅も広がること間違いなし。

20. ジョセフ・アルバース『配色の設計──色の知覚と相互作用』永原康史監訳、和田美樹訳、BNN 新社、2016年
色は、隣にどの色を並べるかで、がらりと印象が変わる。印象どころか、目に見える色まで変わって見えることがある。色と色、色と私たちの知覚はインタラクション(相互作用)を起こして、いろいろな(そう、色々な)現象が生じる。でも、どうして? どんなふうに? アルバースのこの名著で、色と私たちのあいだで何が起きているのかを体験してみよう。
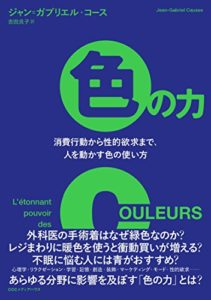
21. ジャン=ガブリエル・コース『色の力──消費行動から性的欲求まで、人を動かす色の使い方』吉田良子訳、CCC メディアハウス、2016年
色が人に影響を与えることは、さまざまな実験でも知られている。例えば、こんな実験がある。オレンジジュースに色をつけて、赤っぽくしたのとそのままのと緑っぽくしたのを被験者に飲んでもらう。色が違うだけで味は同じである。だがどうだろう、全員一致で一番おいしいと答えたのは赤っぽいので、酸味が強いと感じたのは緑っぽいのだった。同じジュースなのにそんなことってあるだろうか。つまりは色の違いが飲む人の感じ方に違いをもたらしたという次第。本書は、そんなふうに色が人間に与える影響を、たくさんの具体例で示している。もちろん同じ色でも文化によって人が受ける印象が違うという点も考慮されている。
3:人間
最後は人間の部です。絵やイメージについて考えるのに、どうして人間が出てくるのか。というのも、絵やイメージは、誰かが見てなにかを感じてこそであります。イメージと人のあいだで何が起きるのかを考える上では、どうしたって人間の仕組みを無視するわけにはゆかない道理です。というわけで、神経科学(脳科学)の観点から見た芸術の捉え方、そもそも人間の情動や感情とはなんなのか、あるいは神経美学のようなイメージ学の最前線など、比較的最近の本から何冊かを選んでみました。

22. 石津智大、渡辺茂『神経美学──美と芸術の脳科学』共立スマートセレクション、共立出版、2019年
人が絵を見たり音楽を聴いたりするとき、実際には何が起きているのか。この問いについてはいくつかの答え方がある。例えば、絵を見ている人に印象や感想を聞くのは主観的な調べ方。その人の目がカンヴァスの上をどのように動くかを追跡する認知科学の調べ方もある。さらには絵を見ているとき、脳がどんなふうに働いているかを(ある程度)調べることもできる。いま、最後に述べたのが「神経美学」という研究領域の仕事である。では、実際には何をどんなふうに研究しているのか。本書はまだ若いこの領域の概要を説いた入門書で、その可能性と限界を知ることができる。

23. エリック・R・カンデル『なぜ脳はアートがわかるのか──現代美術史から学ぶ脳科学入門』高橋洋訳、青土社、2019年
記憶の研究でノーベル医学生理学賞を受賞し、神経科学の教科書などでも知られるエリック・カンデルが、脳科学の観点から抽象芸術を見る人の経験に迫ろうとする本である。カンデルによれば、脳科学と抽象芸術は似ているところがある。どちらも、複雑な物事をシンプルな要素に切り縮めて、それを組み合わせて捉えようとする。そういう考え方を「要素還元主義」と呼んだりする。ちなみにこの本の原書のタイトルを直訳すると『芸術と科学の要素還元主義──二つの文化に橋を架ける』といって、ここにカンデルの意図が表明されている。さて、どんなふうに架橋するのかは読んでのお楽しみ。

24. 坂本泰宏+田中純+竹峰義和編『イメージ学の現在──ヴァール ブルクから神経系イメージ学へ』東京大学出版会、2019年
ドイツの美術史家アビ・ヴァールブルク(1866‒1929)は、多様なイメージを集めて 並べ、そこにさまざまな形の系譜を見てとった。「ムネモシュネ・アトラス」と名付け られた大きなパネル群を目にしたことがあるかもしれない(そのパネルに掲載された 図像を集めた書物もありな書房から刊行されている)。ヴァールブルクの試みを起点と する各種図像研究から現代の神経美学まで、主にドイツ語圏で切り拓かれてきたイメー ジ学の現在を全20 章で展開する論集。

25. 石田英敬+東浩紀『新記号論──脳とメディアが出会うとき』ゲンロン、2019年
「記号論」という言葉はピンと来づらいかもしれない。かつて言語学に端を発して、 20世紀後半の人文学方面で一世を風靡したものの見方である。言語はもちろんのこと、 社会や文化のさまざまな現象を、記号の観点から見てとろうという試みだった。21 世 紀の現在、実は世界は以前にも増して記号に満ちている。そう、あらゆるものを0と 1の二つの記号で処理するコンピュータという究極の記号マシンが文字通り世界を動 かしている。記号全盛時代なのだ。本書は、かねてからメディアと人間の関係を探究 してきた石田英敬さんが、東浩紀さんというまたとない聴き手を相手に、こうしたデ ジタル環境が人間になにをもたらすのかを語った刺激的なレクチャーである。

26. リサ・フェルドマン・バレット『情動はこうしてつくられる── 脳の隠れた動きと構成主義的情動理論』高橋洋訳、紀伊國屋書店、2019年
怒り、恐れ、嫌悪、驚き、悲しみ、幸福といった基本的な情動は、人が生まれつきもっ ているもので、古今東西を問わず人間に普遍的なものだ。また、人の表情や体の状態 を見れば、その人の情動を特定できる──というのは、長いあいだ心理学で常識のよ うに見られてきた情動の見方。この発想に基づいて、実際、空港で不審者を判別する システムなどもつくられてきたという。ところが著者は、これに真っ向から異を唱える。 情動は、言ってしまえば人が育った環境によって作られるというのだ。ここからも窺 えるように、実は人類はまだ情動とは何かということについて合意していなかったり する。そしてどうなるのかはまだ誰も知らないけれど、この本を読むと何が問題なの かがよく分かって面白い。
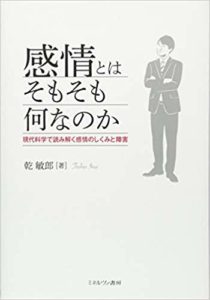
27. 乾敏郎『感情とはそもそも何なのか──現代科学で読み解く感情のしくみと障害』ミネルヴァ書房、2018年
「感情」と「情動」という言葉がある。同じ意味で使われる場合もあるけれど、本書では両者を区別する。情動は、体に生じる生理的な反応で外から観察できる。これに対して感情は、そうした情動を人が意識で感じる状態を指している。あとは書名が雄弁に語っている通りで、これまで捉えどころのないものだった感情を、科学の見方で取り押さえようという次第。人間の身体のしくみや脳科学の知見、あるいは感情障害などを手がかりに、感情が生じるメカニズムをモデル化する野心的な試みの是非を、その目でご覧あれ。
山本貴光さん関連図書

28. 山本貴光、吉川浩満『脳がわかれば心がわかるか』太田出版、2016年
「パラドックス」と「カテゴリー・ミステイク」をキーワードに、「脳情報のトリック」をみきわめよう! 脳科学と哲学にまたがる、見晴らしのよい・親切で本質的な心脳問題マップ。
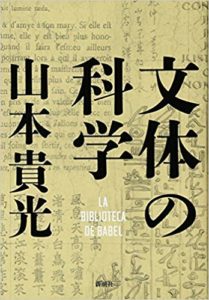
古代ギリシアの哲学対話から、聖書、法律、数式、広告、批評、小説、ツイッターまで。理と知と情が綾なす言葉と人との関係を徹底解読。
《絵画と表現を読みとく7 冊》
選者:松田正行

30. ジュリアン・ベル『絵とはなにか』長谷川宏訳、中央公論新社、2019年
絵画の歴史を、19 世紀以前の、神話や自然を模倣した「再現」の絵画と、それ以後の、自然を模倣していない、イメージを形にしたような絵画や抽象絵画を「表現」と定義し、絵画の意味を探ろうとしています。特に、暗箱(カメラ・オブスクラ)と写真術が絵画にもたらした影響について注目しています。
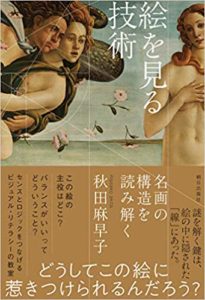
31. 秋田麻早子『絵を見る技術──名画の構造を読み解く』朝日出版社、2019年
絵画を造形、構図などから読み取ろうとしています。著者はそれを翻訳作業といい、絵画にとって重要なポイント(焦点)の見つけ方、表面的な特徴である、輪郭や配色、視線の流れ方、バランス、レイアウトなどから導きだされる絵の隠れた構造と、歴史的な背景などを踏まえて、「総合的に絵を解釈しよう」と説きます。

32. エリック・R・カンデル『なぜ脳はアートがわかるのか――現代美術史から学ぶ脳科学入門』高橋洋訳、青土社、2019年
ターナーを「模倣という退屈な雑用」から絵画を解放した最初の画家と語り、続いて、図と地の区別をあいまいにしはじめたモネ、そしてカンディンスキー、ポロック、デ・クーニングへといたる抽象表現の流れに、視覚の特性である「パターン認識」との相似性を重ねていて読み応えがあります。
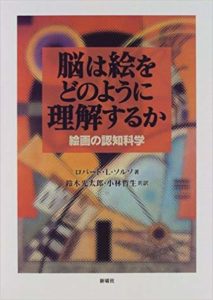
33. ロバート・L. ソルソ『脳は絵をどのように理解するか──絵画の認知科学』鈴木光太郎、小林哲生訳 、新曜社、1997年
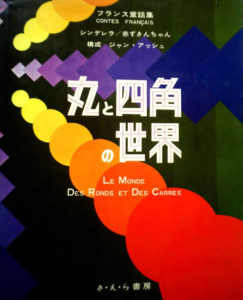
34. ジャン・アッシュ『丸と四角の世界──フランス童話集』さ・え・ら書房、1977年
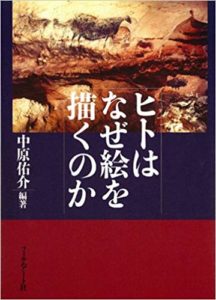
35. 中原佑介『ヒトはなぜ絵を描くのか』フィルムアート社、2001年
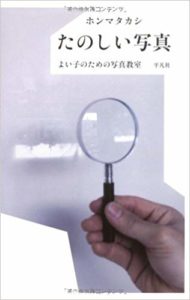
36. 深作秀春『眼脳芸術論──眼科学と脳科学から解き明かす絵画の世界』生活の友社、2015年
松田行正さん関連図書
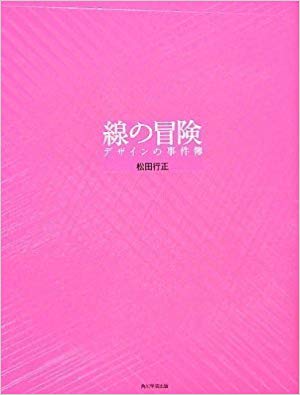
37. 松田行正『線の冒険──デザインの事件簿』角川学芸出版、2009年
規格化された線、ひび割れ線、魔方陣の線、旋回する線、恐怖の視線、ニ分割線、骨組み線など、日頃気にも留めない線たちが繰り広げる世界。気にも留めていなかったさまざまな線が、視覚世界を刺激する。
《絵本の可能性がひろがる5 冊》
選者:名久井直子
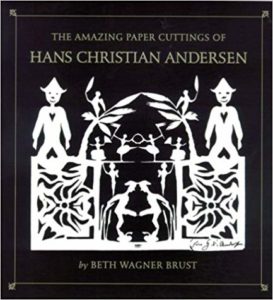
アンデルセンは切り絵を見せながら子どもたちに童話を聞かせたとのことですが、白と黒で描かれる世界は、まるで彼の童話そのもののようです。明るさの裏に、ひっそりと影があるような。
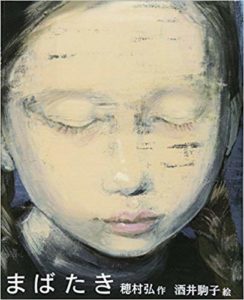
「しーん」「カチッ」「はっ」「ちゃぽん」「みつあみちゃん」これで本文が全部の絵本。短い言葉に合わせて、すすむ時間。最後は、絵の持つ魔法の力に驚かされました。
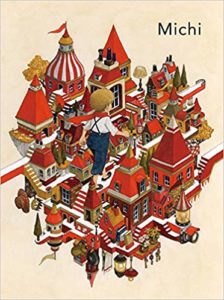
40. Junaida『 みち Michi』 福音館書店、2018年
本を左側から見たときと、右側から見たときと、両方楽しめます。ひろがる迷路のような絵は、ついつい指でなぞるアクションを誘います。
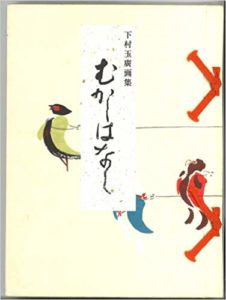
名久井直子さん関連図書

42. グラフィック社編集部『ブックデザイナー・名久井直子が訪ねる紙ものづくりの現場から』グラフィック社、2015年
普段は見ることができない、印刷や製紙、紙加工、製本の現場を、実際に読者が見ているかのように豊富な図版でレポート。日常、私たちが接している紙という物質が、また違った角度で見えてくる。
《「認識」と「関わり」を考える4 冊》
選者:大原大次郎
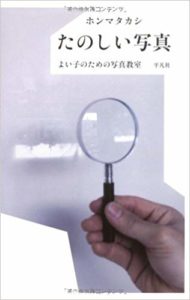
43. ホンマタカシ『たのしい写真――よい子のための写真教室』平凡社、2009年
歴史をたどる、対話をする、ワークショップに起こして試してみる……。絵や写真などを観る際に、その作者は「世界をどのように認識しているのか」、そして作品は「どのように描かれている(撮られている)」のか。本書はその視点・姿勢・方法などを柔らかく紐解いていく。写真に限らず、絵・デザイン・建築・音楽など、さまざまな領域について観察し、実践する際に最も影響を受けた本です。

頭で理解するというよりも、腑に落ちること。能楽を始めとした古典芸能、古来の言葉や文字、身のこなし、所作などを例に、私達が言語や芸術に触れる際に「からだ」と「こころ」を通してどのように感受し表現するのかということを、肚(はら)に落ちる言葉で紡ぐ「身にしみる」一冊です。

45. 荒井良二『ぼくの絵本じゃあにぃ』NHK 出版、2018年
〈山形ビエンナーレ〉にて、荒井良二さんのインスタレーションと、その人となりを間近で拝見する機会がありました。土地や風土への眼差し、子どもだけでなく、年齢や地域を問わない様々な人との関わり方、絵本の中の世界と実空間を結ぶ展覧会やワークショップへの開き方など、それはとても衝撃的な体験となり糧となっています。その荒井さんのルーツや考え方をさらに読み解きたいと願い手にしたのが本書です。
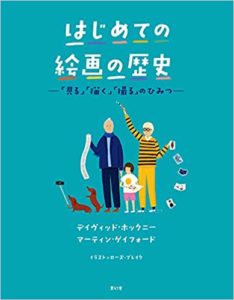
46. デイヴィッド・ホックニー『はじめての絵画の歴史 ──「見る」「描く」「撮る」のひみつ』青幻舎、2018年
大原大次郎さん関連図書
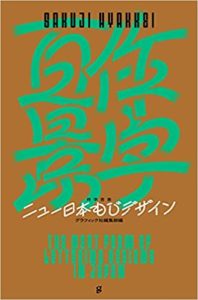
47. 大原大次郎他監修『作字百景 ──ニュー日本もじデザイン』グラフィック社、2019年
筆書、描き文字、レタリングなどさまざまな時代のスタイルを大胆に取り込み、アナログとデジタル、表現と技術の枠組を越えて生み出される、誰も見たことのない文字デザインの世界。
《『絵には何が描かれているのか』からつながる3 冊》
選者:細馬宏通
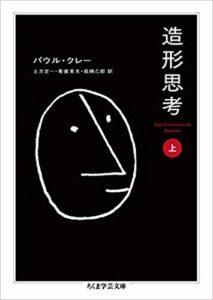
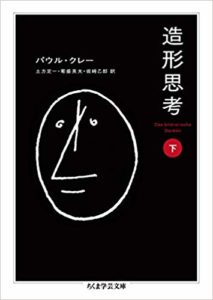
48. パウル・クレー『造形思考(上)』土方定一他訳、筑摩書房、2016年
49. パウル・クレー『造形思考(下)』土方定一他訳、筑摩書房、2016年
バングは色と形から始める。クレーは運動と線から始める。
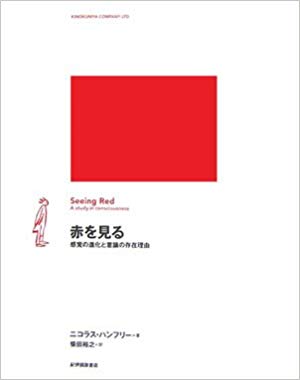
50. ニコラス・ハンフリー『赤を見る ──感覚の進化と意識の存在理由』柴田裕之訳、紀伊國屋書店、2006年
バングは赤い三角形から始める。ハンフリーは、あなたの見ている赤はわたしの見ている赤と同じかどうかを考え始める。
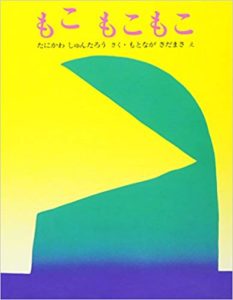
51. 谷川俊太郎 、元永定正『もこ もこもこ』文研出版、1977年
バングは、赤ずきんちゃんから始める。谷川俊太郎と元永定正は、生まることから始める。
細馬宏通さん関連図書

52. 細馬宏通『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか ── アニメーションの表現史』新潮社、2013年
ポパイの歩行、ベティ・ブープの大きな口、『トムとジェリー』の音楽の魅力とは? アメリカン・アニメーションの傑作を読み解き、ウィンザー・マッケイ、ウォルト・ディズニー、フライシャー兄弟など、巨匠たちの表現技法の謎に迫る。
《「世界に「何」が存在していると絵は考えているのか」が見えてくるような3 冊》
選者:平倉圭
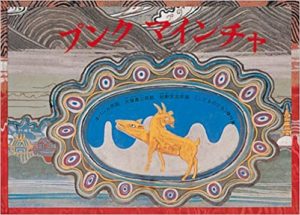
53. 大塚勇三再話、秋野亥左牟画『プンク マインチャ』福音館書店、1968年
「絵には何が描かれているのか」という問いの手前には、そもそも「世界に「何」が存在していると絵は考えているのか」という問いが隠れています。この本では、ウネウネとうねる線が、髪になり、山になり、大地の謎めいた襞になり、異なるものたちをつらぬいて存在する運命の母胎を作るようです。

54. かたやまけん『おなかのすく さんぽ』福音館書店、1981年
同種の線をとおして入り混じる人の子供と他の動物たちの間に、どこかで不穏な切断の気配があらわれます。混交はいつ終わったのか? 歯と舌はどこで現れたのか? そのとき言葉は何を? かたちと言葉が作り出すサスペンスです。畳まれることで絵に力と奥行きを与える、見開きの配置にも注目。
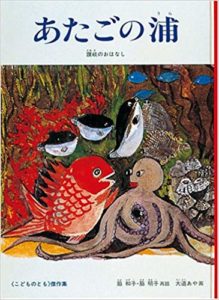
55. 脇和子・脇明子再話、大道あや画『あたごの浦』福音館書店、1984年
絵の原則は、一つではありません。一つ見つけたらその外に行くことも大切です。この本では「斜め」の形は、奇妙に揺らいだ世界に生えてくる奇跡的な「型」を作ります。その周囲で、キラキラした粒が、人の心理にはけっして還元できないような世界の感情を照らします。妙々々々々々……。
平倉圭さん関連図書
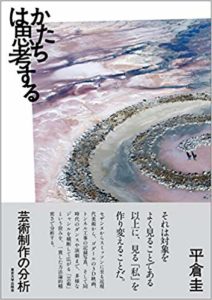
56. 平倉圭『かたちは思考する ──芸術制作の分析』東京大学出版会、2019年
セザンヌからスミッソンに至る近現代美術、ゴダールの3D 映画、トンネル工事の記録写真、そして同時代の演劇やダンスまで。芸術作品を見ることを通して、見る「私」を作り変える、驚異の芸術論。
《合わせて読むと思考が進みそうな2 冊》
選者:菅俊一

57. ドナルド・D・ホフマン『視覚の文法 ──脳が物を見る法則』原淳子、望月弘子訳、紀伊國屋書店、2003年
私たちは僅かな手がかりによって、様々な情報を頭の中で作り出している。この本の中には、見て理解するということの驚きや素晴らしさを知るためのヒントが溢れている。イメージを作り出すためには、イメージを産みだす仕組みについても深く知らなければならない。

58. マシュー・レイノルズ『翻訳 訳すことのストラテジー』秋草俊一郎訳、白水社、2019年
例えば頭の中のイメージを言語にするのも、何らかの図版によって表現するのも、一種の翻訳と言うことができる。情報を置き換える際の工夫や難しさ、漏れてしまうものがどこにあるのかを知ることは、イメージによる表現を考える上で重要なことだと思っている。
菅俊一さん関連図書

駅やオフィス、街や家の中で出くわす、小さな違和感。あるいは、市井の人々が生み出すささやかな工夫や発明のようなもの。数多の「観察」の事例を読み解く思考の追体験をしていくことで、読み手にもアイデアの種を与えてくれる。