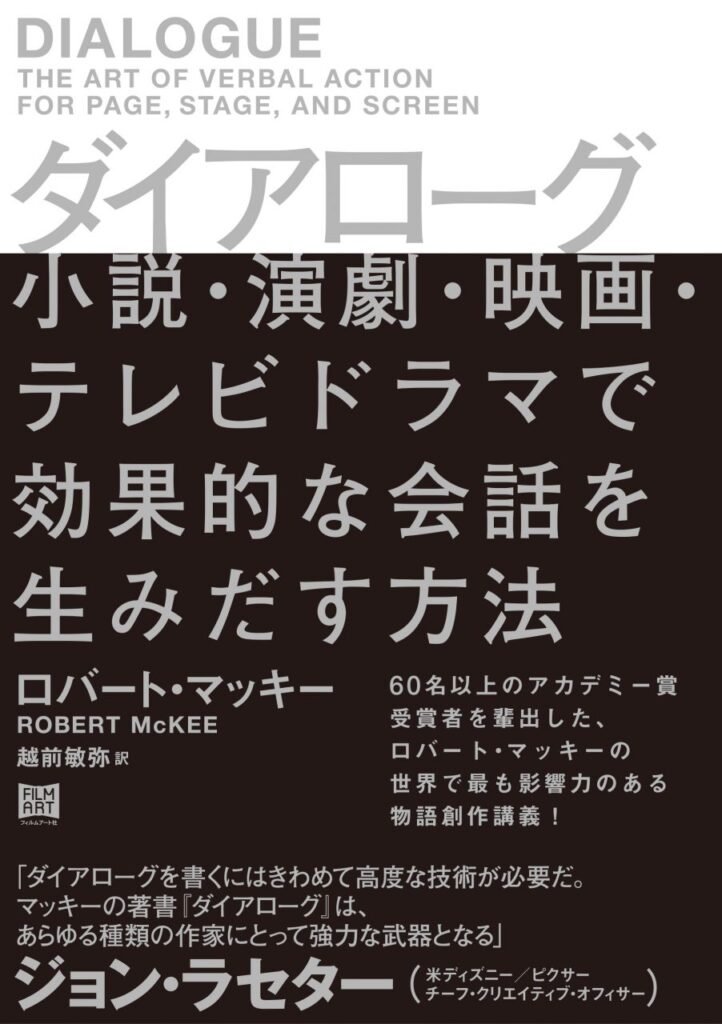まえがき ダイアローグをたたえて
人は語らう。
ほかの何にも劣らず、語りには人間らしさが表れる。恋人にささやく。敵を罵る。配管工と口論する。飼い犬を褒める。母親の墓に誓う。人間関係とは、つまるところ、日々の生活にストレスや喜びを与えるさまざまな要素にまつわる長い長い語らいである。家族や友人たちとの面と向かった語らいが何十年とつづく一方、自分自身との対話には終わりがない。良心の呵責が破廉恥な欲望を叱りつけ、無知が知をあなどり、希望が失望を慰め、衝動が慎重さをあざける。そして、それらすべてを才知が笑い飛ばし、内なる善と悪の声が最後の瞬間までせめぎ合う。
何十年にもわたって降り注ぐ語らいの雨は、ことばから意味を奪い去ることもある。意味がすり減れば、日常の深みが消える。だが、時間が薄めるものを、ストーリーは凝縮する。
作家はまず、日常生活の凡庸なものや些末なもの、騒々しい雑談などを切り捨てて、意味を凝縮する。そして、複雑で相反する欲望の渦巻く重大な局面を築きあげていく。緊張感のもとで、ことばには言外の意味や含みが満たされる。ある登場人物が葛藤に面して口にしたことばが、その奥底にひそむ真意を浮かびあがらせてしまう。表現豊かなダイアローグは半ば透明なものとなり、読者や観客はそれを通して、登場人物の目の奥に静かに影を投じた思考と感情を理解する。
すぐれた作品は、読者や観客をいわば超能力者に変身させる。劇的な会話は、語られないふたつの領域、すなわち、登場人物の内面と読者や観客の内面とを結びつける力を持つ。無線機さながらに、われわれの本能が登場人物の内面の揺らぎを感じとると、潜在意識が同調していく。文芸評論家のケネス・バークが言ったとおり、物語はわれわれに、この世界で生きるため、他者と親しむため、そして何より大事なことに、自分自身と親しむための知識を与えてくれる。
作家はわれわれにこの力を授けるために、つぎのような手順を踏む。まずは人間の性質の隠喩となるものとして、登場人物を作り出す。つぎに、その心理を探究し、意識と無意識の両方のレベルの欲求、自己の外側も内側も駆り立てるような願望を掘り起こす。この洞察をもとに、作家はその人物のやむにやまれぬ欲求を、対立や対立や葛藤葛藤の引火点へと送りこむ。そしてシーン(場面)を重ねながら、変化の節目のまわりにその人物の行動や反応を織り混ぜていく。最終段階で、ようやく本人に語らせるが、それは日常会話のように冗長で単調なものではなく、半ば詩的な〝ダイアローグ〞として知られるものだ。作家は錬金術師さながらに、特徴や葛藤や変化という調合物を掻き混ぜ、形作り、それをダイアローグに飾り立てて、ありふれた地金を輝く黄金の物語へと昇華させる。
ひとたび語られると、ダイアローグはわれわれを感情と本質の波へとまで押し進め、そこから〝言うこと〞、〝言わないこと〞、そして〝言えないこと〞へと波紋をひろげていく。言うこととは、ある登場人物が別の登場人物に対して口に出して述べる考えや感情を指し、言わないこととは、内なる声で自分に対してのみ告げる思考や心情を指し、言えないこととは、黙したままで意識が及ばないせいで自分に対してすら告げることができない、意識下の衝動や願望を指す。
どれほど演劇の制作費が高額だろうと、小説の描写が鮮明だろうと、映画の撮影技術が高度だろうと、ストーリーの奥底にある複雑さや皮肉や深みを形作るのは登場人物の語りにほかならない。表現豊かなダイアローグがなければ、出来事は奥行きを欠き、登場人物は立体感を失い、ストーリーは単調になる。登場人物の肉づけの技巧(性別、年齢、衣服、階級、配役)のどれにも増して、ダイアローグには人生の層を幾重も経たうえでストーリーを引きあげる力があるため、ただのこみ入った話を重層的な高みへ上昇させることができる。
わたしはよく、気に入った台詞を暗記するが、あなたはどうだろうか。ダイアローグを暗記するのは、それらが描く生き生きとしたことばの風景にあらためて息を吹きこみたいからだけではなく、登場人物の考えに共鳴した自分の声も聞きたくて繰り返し口にするからだ、とわたしは考えている。
あす、あす、そしてあす
一日一日と小刻みに忍びおり
時の記録の最後の一語にたどり着き
きのうという日はすべて、愚か者たちのために
塵と化す死への道を照らしてきた。
―――『マクベス』のマクベス
世界じゅうのあらゆる町に酒場は山ほどあるのに、おれの店に来るとはな。
―――『カサブランカ』のリック
わしはこの波に乗って、おまえと闘う。何もかも打ち壊す無敵の鯨よ。最後までおまえとつかみ合い、地獄のただなかからおまえを刺し、今際の息にも憎しみをこめて、おまえの面に吐きかけてやる。
―――『白鯨』のエイハブ
それが悪いってわけじゃないんだけど。〔ゲイと勘ちがいされたときの嘆き文〕)
―――『となりのサインフェルド』のジェリー
この4人のように、だれもが皮肉なめぐり合わせに苦悩したことがあるはずだ。世間の仕打ちに、さらにひどい場合は、自分に対する自分の仕打ちにふと気づくことや、冗談のような出来事に見舞われてどうとでも受け止めうる瞬間に出くわし、笑うべきか嘆くべきかと窮したこともあるだろう。だが、そうした皮肉を作家がことばのマリネに浸けて風味づけしてくれるので、われわれはその甘美な苦味を堪能することができる。ダイアローグの記憶があるからこそ、矛盾に満ちたものの数々を心にとどめておくことができるのだ。
わたしはありとあらゆるダイアローグの技巧を愛している。その親愛の情にほだされて本書を執筆し、ストーリー作りにおける至高の作業――登場人物に声を与えること――の解明に取り組むことにした。
本書の概要
第1部 ダイアローグの技巧では、ダイアローグの定義を大幅に拡張して、使い道を増やす。第2章から第5章では、登場人物の語りの機能、内容、形式、テクニックについて、4つの媒体にわたって考察する。
第2部 欠陥と対処法では、嘘っぽさ、月並みな決まり文句、正確すぎる記述、過剰な繰り返しなどの欠点を突き止めて、原因を探り、改善策を伝授する。技巧を凝らしたダイアローグを生み出すさまざまなテクニックを説明するために、小説、演劇、映画、テレビからいくつか例を示す。
第3部 ダイアローグを作るでは、最後の仕上げ、すなわち、テクストを形作ることばの見つけ方を考えていく。われわれがある作家を「すぐれたダイアローグの書き手」と評するのは、その作家が登場人物に適合したダイアローグを生み出しているときだ。それぞれの登場人物の語りに筋道とリズムと色調があり、何より大切なことに、その人物以外は使いそうもないことばが選ばれている。すべての登場人物が独自のことばに彩られた用語辞典になることが理想的だ。それゆえ、ダイアローグの独創性は語彙からはじまる。
登場人物に適合したダイアローグの力を説明するために、ここではシェイクスピアの戯曲『ジュリアス・シーザー』、エルモア・レナードの小説『アウト・オブ・サイト』、ティナ・フェイのテレビシリーズ「30ROCK/サーティー・ロック」、アレクサンダー・ペインとジム・テイラーの映画『サイドウェイ』のシーンを取りあげて説明する。
第4部 ダイアローグの設計は、ストーリーやシーンの構成要素を研究することからはじめる。第12章では、それぞれの表現形式が登場人物の語りをどのように形作るかを示す。ケーブルテレビのシリーズ「ザ・ソプラノズ」からは均衡のとれた対立のシーン、ネットワークテレビのシリーズ「そりゃないぜ!? フレイジャー」からは喜劇的な対立のシーン、戯曲『ア・レーズン・イン・ザ・サン』からは不均衡な対立のシーン、小説『グレート・ギャツビー』からは間接的な対立のシーン、中編小説『フロイライン・エルゼ』と長編小説『無垢の博物館』からは内省的な葛藤のシーン、映画『ロスト・イン・トランスレーション』(03)からは暗黙の葛藤のシーンを選び出し6件のケーススタディをおこなう。
こうした分析を通して、効果的なダイアローグにおいてふたつの主原則を考察していく。第一は、ダイアローグが交わされるたびに、シーンを進展させる行動(アクション)や反応(リアクション)が生まれることである。第二は、そうした行動は語りの表層で具現するが、登場人物の行動の水脈はサブテクスト(言外の意味)から目に見えぬ形で流れていることだ。
作家にとってのGPS機能のごとく、本書は創作志望者には道案内を提供し、道に迷った者には方向づけをする。この技巧を試そうとして、創造の袋小路にはまりこんだ者を、本書は卓越への道に押し進める。創作や著述を生業としながらも、考えるよりどころを失っている者を、本来の居場所へと導くだろう。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。