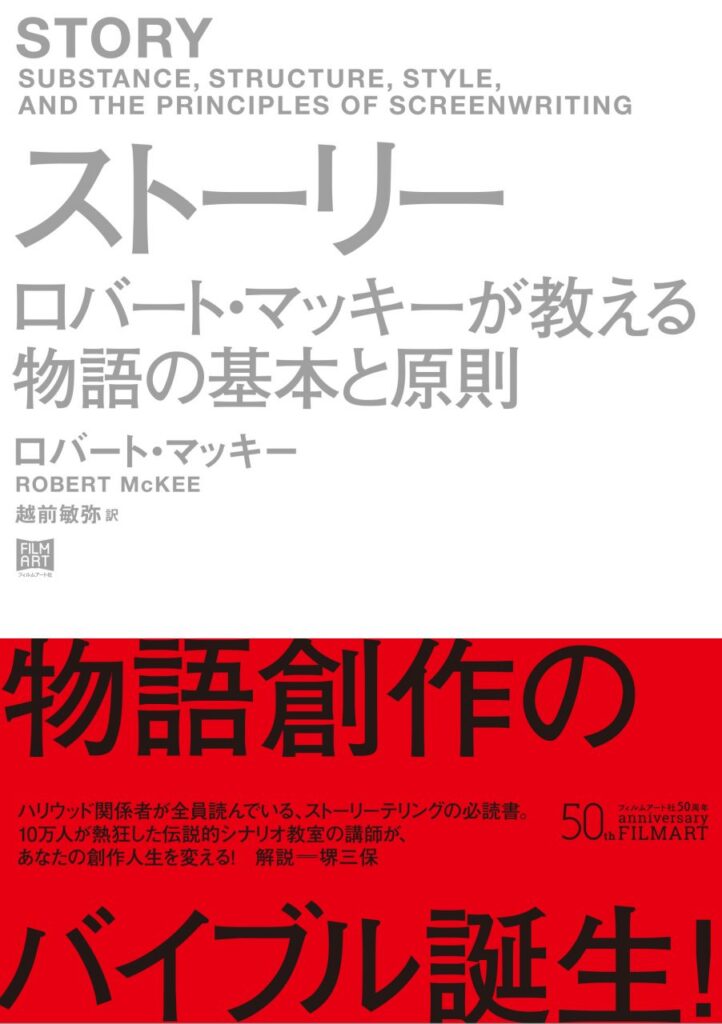イントロダクション
本書で論じるのは原則であって、ルールではない。
ルールは「このようにしなくてはならない」と命じるが、原則は「こうすればうまくいく……そして、記憶に残るかぎりずっとそうだった」と示唆する。このちがいは重要だ。「出来のよい」作品を真似て書く必要はない。それよりも、われわれの芸術を形作る原則のなかで、よい出来であることをめざすべきだ。経験が浅く自信のない作家はルールに黙従し、訓練不足で反抗的な作家はルールに従わない。真の芸術家はうまく型を使いこなす。
本書で論じるのは永遠に変わらない普遍的な型であって、公式ではない。
商業的成功をおさめるための定型や、たやすく書けるストーリーの手本などという考えは、すべてばかげている。流行やリメイクや続編はあっても、ハリウッド映画全体を概観すれば、ストーリー設計は驚くほど多様で、手本などない。『ダイ・ハード』(88)がハリウッド映画の典型でないのと同様に、『バックマン家の人々』(89)、『ハリウッドにくちづけ』(90)、『ライオン・キング』(94)、『スパイナル・タップ』(84)、『運命の逆転』(90)、『危険な関係』(88)、『恋はデジャ・ブ』(93)、『リービング・ラスベガス』(95)も、笑劇から悲劇まで何十ものジャンルやサブジャンルに及ぶ何万という名作も、ハリウッド映画の典型というわけではない。
本書は、6つの大陸の観客を沸かせ、繰り返し上映・上演されて何十年も生きつづける作品を生み出すことをめざしている。ハリウッドの残り物をあたためなおす方法を記したレシピ本など、もうだれも求めていない。必要なのは、われわれの芸術の根底にある理論、才能を解き放つ指針となる原則を再発見することだ。映画が――ハリウッドであれ、パリであれ、香港であれ――どこで制作されようと、元型(アーキタイプ)としての質の高さを具えていれば、映画館から映画館へ、世代から世代へと、楽しみの連鎖反応を世界じゅうに果てしなく引き起こす。
本書で論じるのは元型であって、紋切り型ではない。
元型的なストーリーとは、人間の普遍的な経験をあらわにして、ある文化特有の表現で包んだものだ。紋切り型のストーリーとは、これとは逆の特徴を持つもので、内容も形式も貧しい。それは特定の文化に依存したせまい経験に閉じこもり、平凡で陳腐な一般論をまとっている。
たとえば、かつてスペインには、娘を歳の順に嫁がせなくてはならないという風習があった。きびしい家父長、無力な母親、結婚できない長女、苦しみつづける末娘といった19世紀の家族を描いた映画は、スペインの文化圏でこの風習に親しんだ人たちの心を動かすかもしれないが、スペインの文化圏以外では観客の共感を得にくいだろう。かぎられた層にしか訴えないことを恐れる脚本家は、過去に観客が喜んだおなじみの設定、登場人物、出来事にばかり頼る。その結果、どうなるだろうか。そうした陳腐な展開では、なおさら共感を得られない。
一方、この抑圧的な風習は、芸術家が腕を振るって元型を追求すれば、この題材によって世界じゅうで成功をおさめうる。元型的なストーリーは、珍しい設定や登場人物を作りあげるので、われわれの目は細部までを味わいつくしたくなり、しだいに明らかにされる真に迫った人間の葛藤が、文化の壁を越えて心に訴える。
ラウラ・エスキヴェル原作の『赤い薔薇ソースの伝説』(92)では、束縛と独立、永続と変化、自己と他者をめぐって、母と娘が衝突する。これはどんな家族にも見られる確執だ。しかし、家庭と社会、人間関係と行動についてのエスキヴェルの観察がかつてないほどくわしく豊かなので、われわれはこれらの登場人物に無性に惹かれ、未知の世界、想像もつかない世界にすっかり魅せられる。
紋切り型のストーリーは停滞をともない、元型的なストーリーは旅をともなう。チャーリー・チャップリンからイングマール・ベルイマンまで、サタジット・レイからウディ・アレンまで、映画界の名匠たちは、われわれが求めるふたつの出会いを提供してくれる。第一は未知の世界の発見だ。身近な話であれ叙事詩的な壮大な話であれ、現代の出来事であれ歴史上の出来事であれ、現実であれファンタジーであれ、すぐれた芸術家の描く世界は、つねにどこか風変わりで新鮮なものだ。われわれは森のなかを進む探検家のように、目を瞠りつつ未踏の社会に足を踏み入れ、クリシェとは無縁な、日常が非日常と化した世界を進んでいく。
第二に、いったんこの新奇な世界にはいれば、われわれはそこに自分自身を発見する。登場人物やその心の葛藤の奥深くに、人間本来の姿が見つかるのだ。われわれが映画を観るのは、新しい魅力的な世界にはいりこみ、最初は自分とかけ離れて見えても根底では似かよった別の人間の生き方を重ね合わせるためであり、架空の世界の体験によって日常の現実を浮き彫りにするためだ。われわれは人生から逃避したいのではなく、人生を発見し、斬新で実験的な方法で頭を使い、感情をうまく解放し、楽しみ、学び、日々に深みを与えたいと願っている。わたしが本書『ストーリー』を書いたのは、元型的な力と美を具えた映画を数多く生み出して、ふたつの喜びでこの世界を満たすためである。
本書で論じるのは綿密さであって、近道ではない。
アイディアがひらめいた瞬間から最終稿に至るまで、脚本の執筆には、小説の執筆に劣らず長い時間がかかるものだ。脚本家も小説家も、密度の濃い世界、登場人物、ストーリーを作り出す点では同じだが、脚本の紙面には余白が多いので、脚本のほうが短時間で簡単に書けると誤解されやすい。ただの創作マニアはタイピングと同じ速さでページを埋めてしまうが、映画の脚本家は最小限のことばで最高の表現をつむぎ出したいという思いから、容赦なく無駄なものをそぎ落としていく。かのパスカルは、ある友人に長々と手紙を書いたあと、短い手紙を書く時間がなかったと追伸で詫びている。パスカルと同じく、簡潔さが肝要であること、それには時間がかかること、すぐれた作品を書くには粘り強さが必要であることを有能な脚本家は知っている。
本書で論じるのは現実であって、執筆にまつわる種明かしではない。
芸術の真理を隠しとおすための陰謀がめぐらされたことなど、かつて一度もない。アリストテレスが『詩学』を著してから23世紀ものあいだ、ストーリーを書く「秘訣」は町の図書館と同じくらい、あらゆる人々の手の届くところにあった。語りの技巧は難解でもなんでもない。それどころか、映画のストーリーの作り方は、一見簡単そうにも感じられる。だが、核心に迫るにつれて、シーンからシーンへとストーリーをうまく展開させるのはむずかしくなり、スクリーンにはまったく隠れ場所がないことに気づく。
小説家であれば語り手の声、劇作家であれば独白という手立てを使えるが、脚本家の場合、演じられる場面だけで観客の心を動かさなくてはならず、ことばの陰に隠れることができない。論理の穴や染みだらけの動機、色あせた感情を、説明や形容の表現で滑らかに覆って、どう考えるべきか、どう感じるべきかをただ「示す」わけにはいかないのである。
カメラはあらゆる見せかけを暴く恐ろしいレントゲン装置だ。人生を何倍にも拡大して、ストーリーの弱点や偽りをすべてさらけ出すので、書く側は混乱と落胆のあまり逃げ出したくなる。それでも、強い意志を持って研究をつづければ、やがて答えが見つかる。脚本の執筆は不思議なことだらけだが、解けない謎ではない。
本書で論じるのは技術の習得であって、市場の予測ではない。
何が売れて何が売れないのか、何が大あたりして何が大失敗になるのかは、だれも教えることができない。そんなことはだれにもわからないからだ。ヒット作と同じ興行予測に基づいて作ったハリウッド映画が大失敗することもあれば、金儲けの禁則リストに並んでいるかのような陰鬱な作品――『普通の人々』(80)、『偶然の旅行者』(88)、『トレインスポッティング』(96)――が国内外で静かなヒットを呼ぶこともある。この世界に成功が約束されたものはない。だからこそ、あまりに多くの人々が「参入すべきか」、「成功するかどうか」、「作品の内容に干渉を受けるか」をめぐって頭を悩ませる。
こうした懸念に対する率直で都会的な答えは、まずはエージェントを見つけて作品を売りこみ、それが忠実に映像化されるのを見届けることだが、それは良質の作品が書けたらの話であり、まずはそんな作品を書くことを考えよう。前年のヒット作のコピーを作っていては、毎年ハリウッドを月並みなストーリーで満たす凡庸な作家たちの仲間入りをするだけだ。売れるかどうかで頭を悩ますのではなく、そのエネルギーをすぐれた作品の創作につぎこむべきだ。才気あふれる独創的な脚本を見せることができれば、エージェントはこぞって契約しようとするだろう。その後、あなたが雇ったエージェントが、ストーリーに飢えた制作者たちのあいだで争奪戦を巻き起こし、勝者から信じられないほどの大金が転がりこむ。
さらに、いったん制作にはいれば、完成された脚本への干渉は驚くほど少なくなる。組む相手に恵まれず、良質な作品が台なしになる可能性はゼロではないが、ハリウッドで有数の演技力や演出力の持ち主なら、自分のキャリアがすぐれた脚本をうまく生かすことにかかっていると理解しているにちがいない。とはいえ、ストーリーを貪欲に求めるハリウッドが、熟する前に脚本を摘みとって、撮影現場で修正を強いることも少なくない。賢明な脚本家であれば、原案の段階で売ったりはしない。辛抱強くリライトを重ねて、監督や俳優がそのまま使えるレベルにまで質を高めていく。未完成の作品は改竄を招きうるが、磨きあげられた完成度の高い作品は手を入れる余地がない。
本書で論じるのは観客へのリスペクトであって、侮蔑ではない。
才能ある脚本家の作品が不出来であるとき、その原因はふたつのどちらかであることが多い。自分の力を証明しなければと思いつめているか、表現したい気持ちが強すぎるかだ。一方、才能ある脚本家の作品の出来がよいのは、観客の心を動かしたい思いが原動力となっている場合が多い。
長年にわたる演技や演出を通して、わたしは夜ごと、観客とその反応力に畏敬の念をいだいてきた。魔法にかけられたように仮面が剥がれ、傷つきやすく感受性豊かな顔を見せる。映画ファンは自分の感情を隠したりしない。それどころか、恋人にすら見せないような形で語り手に心を開き、笑い、涙、恐怖、怒り、同情、情熱、愛、憎しみを喜んで受け入れる――その儀式のせいで疲れ果ててしまうこともある。
観客は驚くほど感受性が豊かであるだけでなく、照明の落とされた映画館や劇場に腰を据えるや、IQが25も跳ねあがる。映画を観ていると、スクリーンに映っている物事をじれったく感じることはないだろうか。あるいは、登場人物が実際に動くよりも先に何をするか予想がついたり、かなり前に結末がわかったりしないだろうか。観客はただ頭がよいどころか、ほとんどの映画よりも賢明だが、スクリーンの向こうの作り手の側へ移動しても、その事実は変わらない。脚本家にできるのは、自分が習得した技巧を余すことなく使い、集中した観客の鋭い知覚の一歩先を行くことだけだ。
観客の反応や期待を理解していなければ、どんな映画も成功させることができない。ストーリーは書き手の思いを表現しつつ、観客の望みを満たすことも考えて書かなくてはならない。ストーリー設計において、観客はほかのどの要素にも劣らない重みを持つ。観客がいなければ、創作そのものが意味を持たない。
本書で論じるのは独創性であって、模倣ではない。
独創性とは内容と形式が融合したもの――独自に選んだ題材に、独自の語り口を加えたもの――である。内容(舞台設定、登場人物、アイディア)と形式(出来事の選び方と並べ方)は、互いを必要とし、互いに刺激し、影響し合う。書き手は一方の手に内容、もう一方の手に形式の技術を携えて、ストーリーを彫りあげる。ストーリーの内容に手を加えるにつれ、語りはみずから形を変える。ストーリーの形をいじるうちに、知的にも感情的にも進化していく。
何を語るかだけでなく、どのように語るかも大切だ。内容が陳腐なら、語りも陳腐になるが、深遠で独創的な考えがあれば、ストーリー設計も独特なものになる。逆に、語りが型どおりで意外性に欠ければ、ありふれた行動を演じる紋切り型の役柄が必要になるが、ストーリー設計が斬新であれば、それに応じて舞台設定、登場人物、アイディアも同じように斬新でなくてはならない。内容に合うように語りの形を決め、ストーリー設計を支えるために内容を練りなおすべきだ。
ただし、奇抜さと独創性を取りちがえてはいけない。商業的必要性に隷従するのに劣らず、差別化のための差別化はむなしいものだ。何カ月も、おそらくは何年もかけて事実や記憶や想像力を掻き集めて、ストーリーの題材の宝庫を築いてきた真摯な脚本家なら、自分の考えを無理やり公式に押しこめたり、前衛的な断片へと矮小化したりはしない。「よくできた」公式がストーリーの声を詰まらせることがある一方、「芸術映画」の奇矯さは声を完全に殺してしまう。子供がおもしろ半分に物を壊し、注意を引こうとして癇癪を起こすように、スクリーン上で幼稚な仕掛けを使って「見て、見て!」と叫ぶような映画の作り手があまりにも多すぎる。成熟した芸術家はけっして自分に注目を集めようとはしないし、賢明な芸術家は固定観念を破るためだけに何かをすることはない。
ホートン・フート、ロバート・アルトマン、ジョン・カサヴェテス、プレストン・スタージェス、フランソワ・トリュフォー、イングマール・ベルイマンといった巨匠たちの映画はきわめて独創性が高く、3ページのあらすじを読めばDNA鑑定並みの正確さで作り手を特定できる。すぐれた脚本家は、その人独特の語りのスタイルを持ち、それは本人の思考のあり方と切り離せないばかりか、深い意味において思考そのものとなっている。形式上の選択――主人公の数、展開のリズム、葛藤の程度、時間の配分など――は、内容上の大きな選択――舞台設定、人物造形、アイディアなど――と互いに作用したり衝突したりしながら、やがてすべての要素が溶け合って、唯一無二の脚本となる。
だが、映画の内容をひとまず脇へやり、出来事が起こるパターンだけを検討すれば、歌詞のないメロディー、実体のないシルエットのように、ストーリー設計そのものに大きな意味があることがわかるだろう。どんな出来事を選んでどう並べるかは、個人、政治、環境、心理など、あらゆるレベルにおいての現実の結びつき方を示す隠喩にほかならない。人物像や所在地といった表面の皮を取り除くと、ストーリーの構造は作り手の内的宇宙をあらわにし、この世で物事がなぜ、どのように起こるのか、その根底にある法則や誘因についての作り手の考え方、言い換えれば、人生の秩序についての脳内地図が見えてくる。
あなたのヒーローがだれであれ――ウディ・アレン、デヴィッド・マメット、クエンティン・タランティーノ、ルース・プラワー・ジャブヴァーラ、オリバー・ストーン、ウィリアム・ゴールドマン、チャン・イーモウ、ノーラ・エフロン、スパイク・リー、スタンリー・キューブリックのどれであれ――すばらしいと感じるのは、みな唯一無二の存在だからだ。彼らがおおぜいのなかから頭角を現したのは、ほかのだれも選ばない内容を選び、ほかのだれも考えつかない形式を考え出し、そのふたつを組み合わせて、まぎれもない独自のスタイルを作りあげたからだ。あなたにもぜひそうなってもらいたい。
ただし、能力や技術だけを求めているのではない。わたしはすばらしい映画に飢えている。この20年というもの、多くのすぐれた映画や、少数のきわめてすぐれた映画を観てきたが、圧倒されるほどの力と美を具えた映画に出会ったことはほとんどない。ひょっとすると、それはわたし自身の問題で、ただ飽きてきただけかもしれない。いや、やはりちがう。まだ飽きていない。いまでも芸術が人生を変えてくれると信じている。だが、想像の世界にどんな音楽があるにせよ、ストーリーというオーケストラのあらゆる楽器を鳴らすことができなければ、古い曲を口ずさむしかない。あなたが技巧をうまく使いこなし、人生についての独自の考えを思いのままに表現し、従来の常識にとらわれない斬新な内容、構成、スタイルを持った作品を生み出すことを願って、わたしは本書『ストーリー』を執筆した。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。