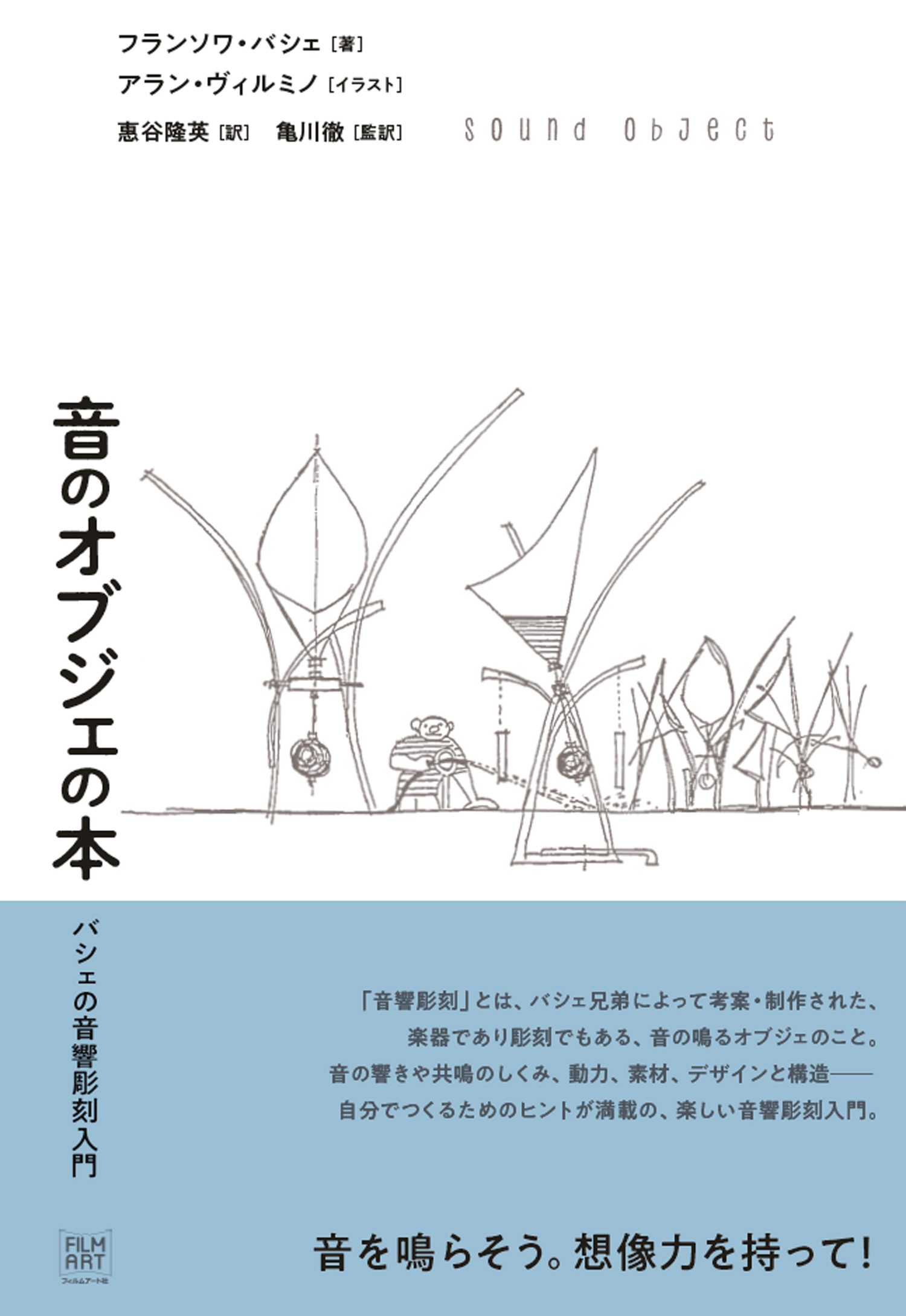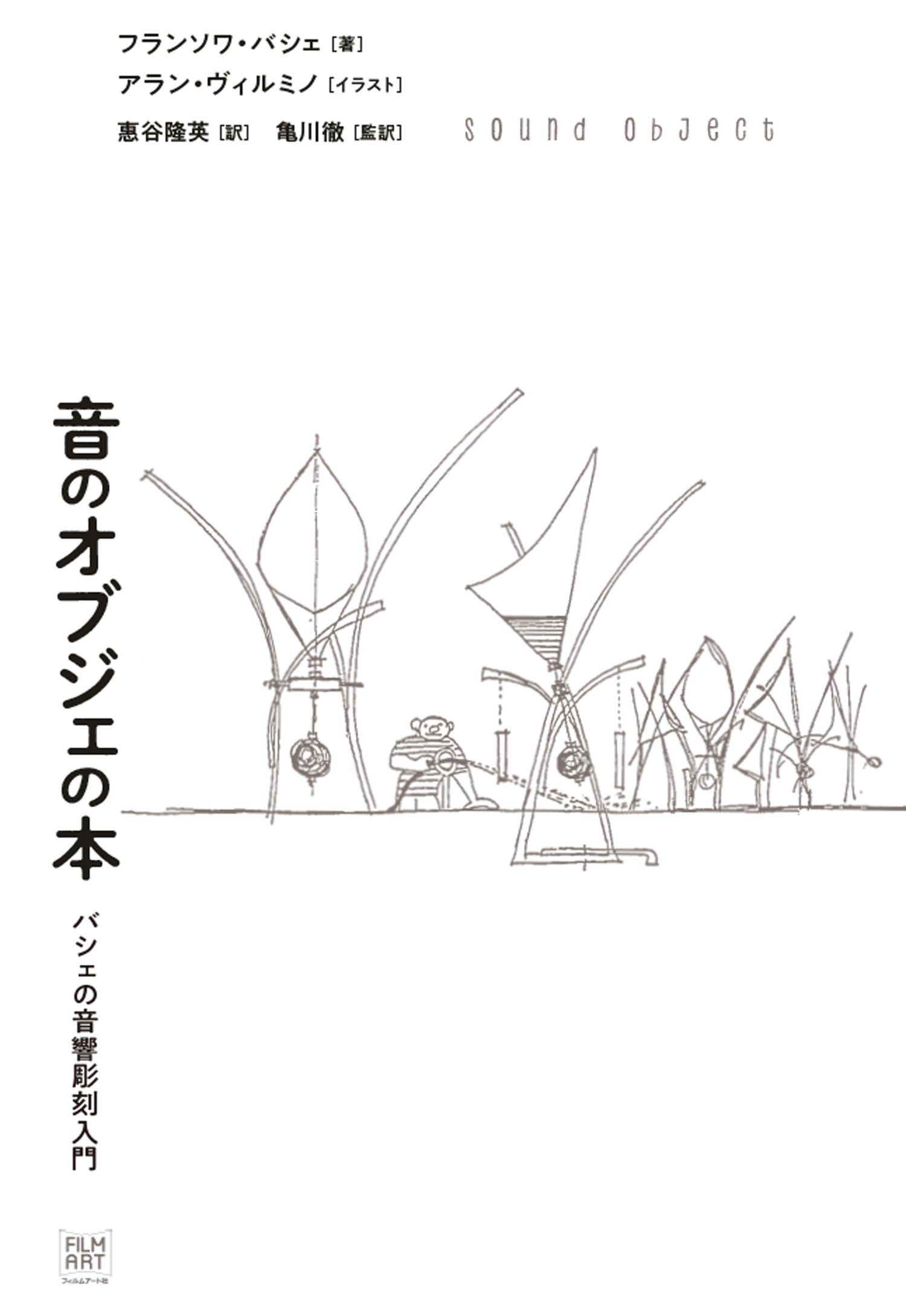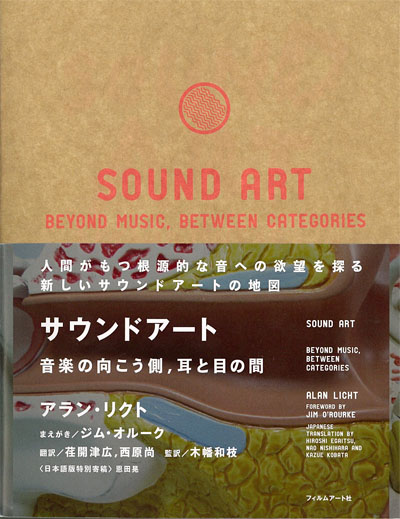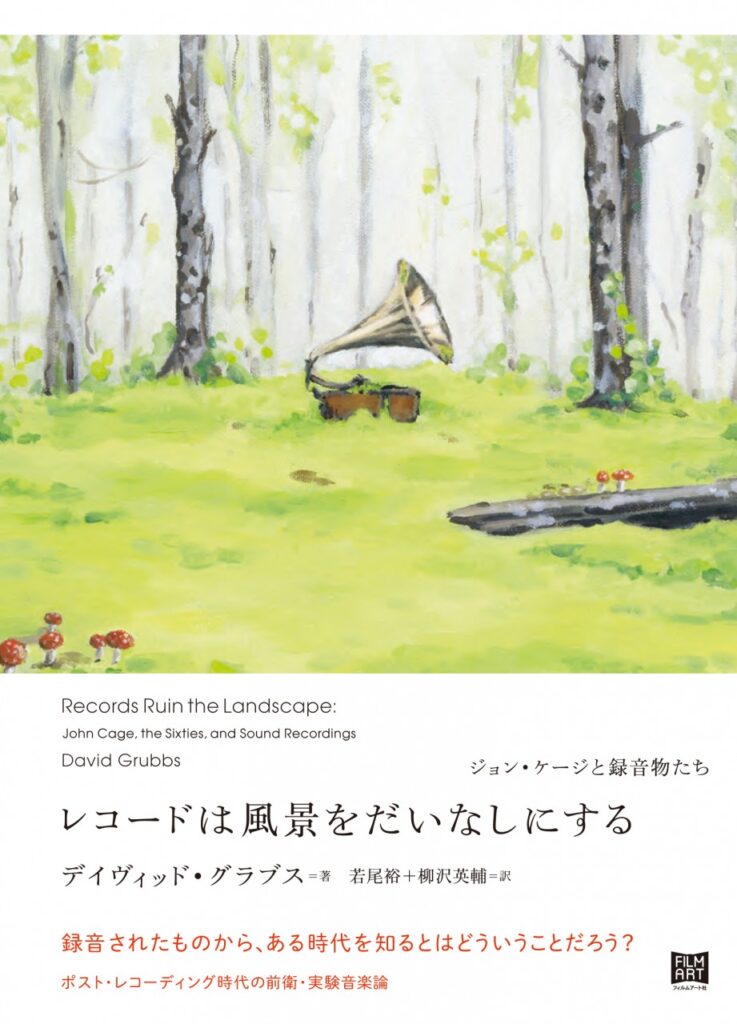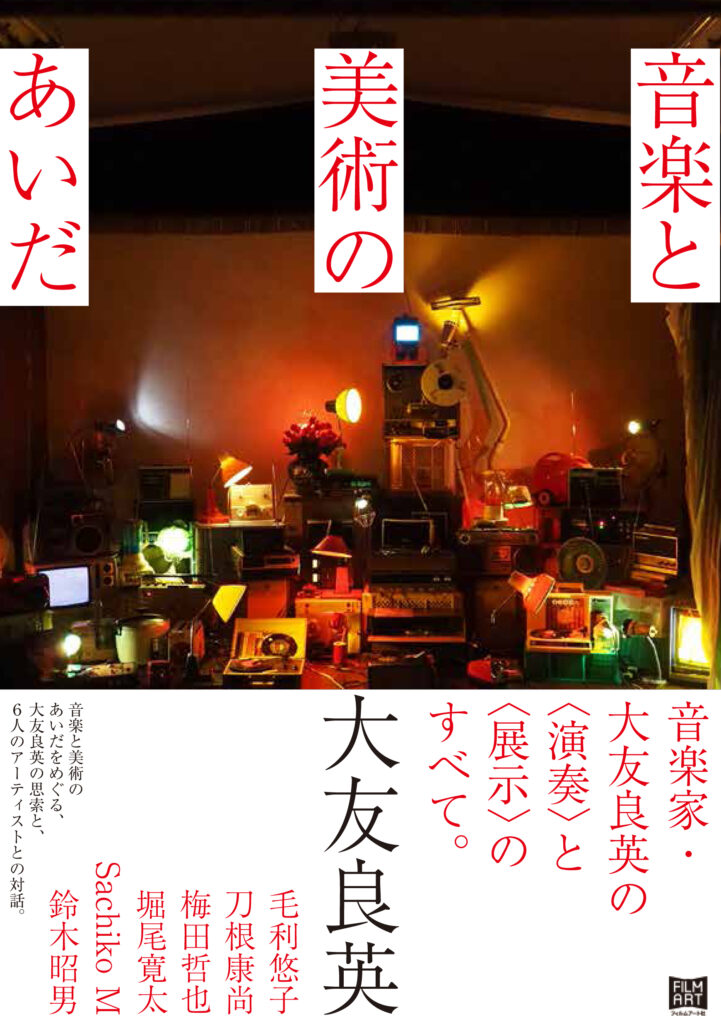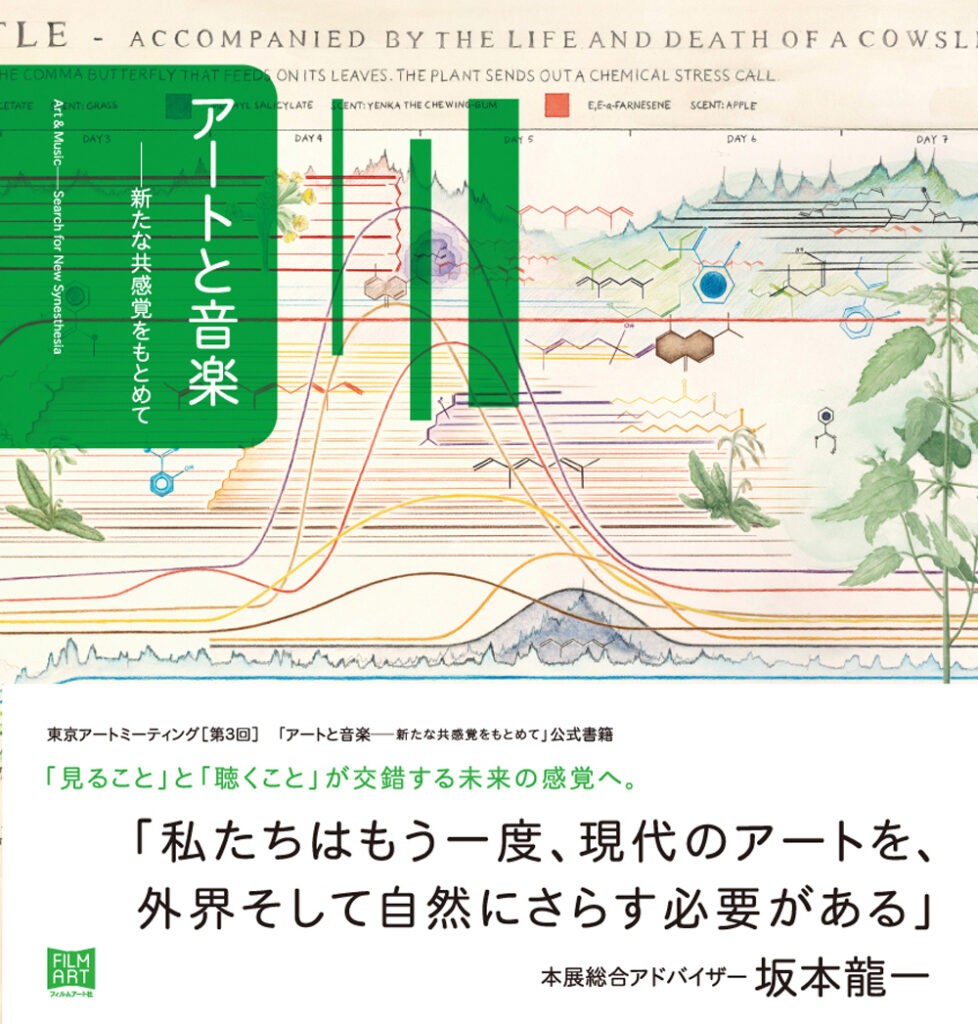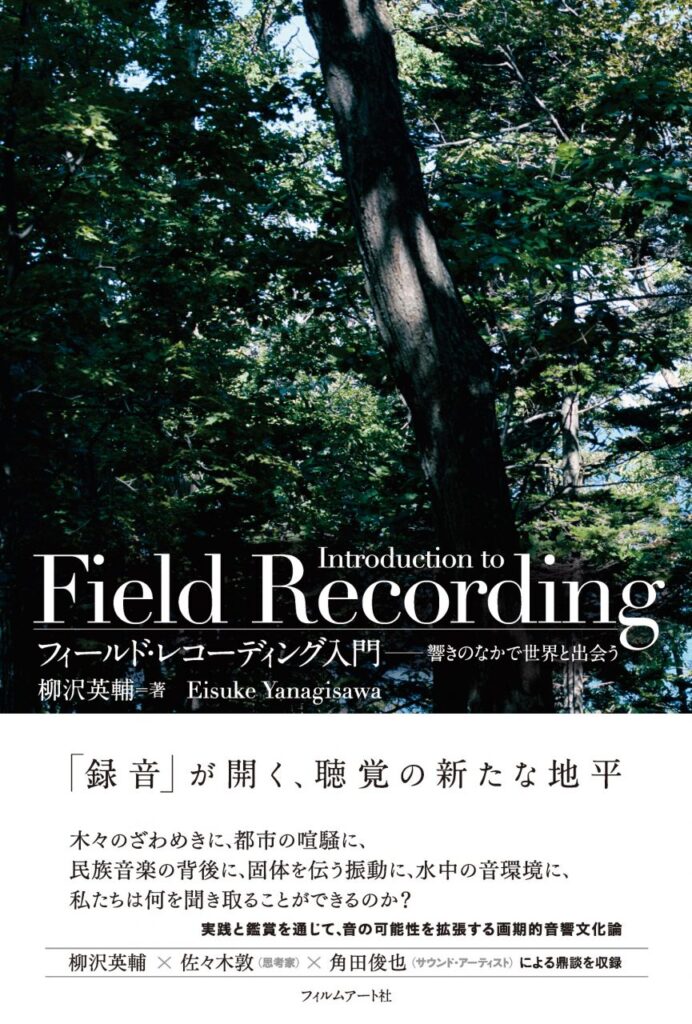フランスを拠点に世界で活躍したサウンド・アーティスト、バシェ兄弟が生み出した「音を奏でるオブジェ=音響彫刻」。
フランソワ・バシェ自身のテキストによる、楽しい音響彫刻入門。
「音響彫刻」とは、バシェ兄弟によって考案・制作された、楽器であり彫刻でもある、音の鳴るオブジェのこと。本書は1992年にフランソワ・バシェによって著された、音響彫刻の入門書です。
音の響きや共鳴、動力、素材、デザインと構造など、音と科学のしくみをさまざまな角度からやさしく解説。
身近なものを使って思うままに音を鳴らしてみたり、自分で作ってみたくなる、
あなたを自由な「音」の世界へといざなう、好奇心と想像力をかきたてる一冊です。
前半では、音や振動、素材ごとの音の特性など、音響学の基礎知識がユニークなエピソードともに解説され、後半では、音響彫刻を作るために大切な動力学の基礎と、実際の素材を例にした制作ノウハウが紹介されます。
音についての幅広い知識と、制作に役立つヒントが満載の、読んで楽しく見ても楽しい、音響彫刻の世界への招待。
(私は)「音楽の」創造は芸術以上のものであり、それは美しさ以上のものを含む哲学だと考えています。
それは、人々に自己実現の手段を与えることで、自分自身の人生を豊かにするだけでなく、それらの楽器を使う人々の存在、そしてさらにそれを聴く聴衆の人生までも豊かにする方法なのです。
(本書「フランソワ・バシェからの手紙」より)
再注目されるバシェの音響彫刻
バシェ兄弟は1952年から音響彫刻の開発に取り組み、その造形美と音響は瞬く間に世界から注目の的となった。ニューヨーク近代美術館(MoMA)やロンドンのバービカン・センターをはじめ、世界各地の美術館で展覧会が開催され、日本においては、1970年の大阪万博で鉄鋼館の芸術監督を務めた作曲家・武満徹がフランソワ・バシェを招聘し、鉄鋼館ホワイエに展示された音響彫刻は大きな注目を集めた。
そして、大阪万博から40年を経た2010年、鉄鋼館がEXPO’70パビリオンとしてリニューアルしたのをきっかけにバシェの音響彫刻が修復されることとなり、それを契機に、EXPO’70パビリオンのみならず、京都市立芸術大学、東京藝術大学でも修復プロジェクトが遂行された。また2015年には、東京国立近代美術館で「フランソワ・バシェ音響彫刻の響き」と京都芸術センターで「バシェ音響彫刻コンサート&映画上映会」が開催され、2020年には川崎市岡本太郎美術館「音と造形のレゾナンス-バシェ音響彫刻と岡本太郎の共振」、京都市立芸術大学ギャラリー@KCUAで「バシェ音響彫刻特別企画展」が開催された。
また、2017年には作曲家の坂本龍一がバシェの音響彫刻を用いて楽曲を制作し、アルバム『async』に収録していることも記憶に新しい。
その他、映画音楽にも影響を与えており、ジャン・コクトー監督『オルフェの遺言』(1960)、黒澤明監督『どですかでん』(1970)のほか、2024 年のエドワード・ベルガー監督『教皇選挙』では、音響彫刻《クリスタル・バシェ》が楽曲に使用され、2024年度のアカデミー作曲賞にもノミネートされている。
以上のように、現代においてもバシェの音響彫刻はその独創性やユニークさによって、美術家、演奏家、作曲家、音楽学者などをいまなお惹きつけている。
目次
まえがき
音と音響
楽器と音
音を聴く
音の伝達
共鳴(共振)
共鳴は人生を変える──実際にあった話
スプーンを使った実験
歯を使って音を聴く
糸電話
ピアノの幽霊
サウンドエレメント
平らな金属棒
鉄琴の調律
ケーニッヒの法則
金属板──ゴング、シンバル、ベル
クラドニ図形──1枚の金属板から出せるさまざまな音の模様
板の素材の強化
セラミック製のサウンドエレメント
パイプ
パイプの材料
ゴング
鐘
金属棒
音風車の構成要素
弦
圧縮空気を利用した音
空気の吸引によって発生する音
笛
笛の調律
さまざまな笛
メカニック
「音の噴水」のための水動力
水掻き車
歴史的な発明
回転式のスプレー
桶のチェーン
伝達
重要なディテールの構造
特別な装置
振り子装置と蹴り上げ装置
制作時の注意点
サイフォン
どのようにポンプで水を送るのでしょうか?
水槽
デザインと構造
木材を使ったデザイン
羽の取り付け
鳥を動かす
その他の例
金属を使ったデザイン
水車と回転するフィギュア
配管材を使ったデザイン
銅菅
ウォーターゲーム
風車
仕入れ先
著者について
フランソワ・バシェからの手紙
訳者あとがき
プロフィール
[著]
フランソワ・バシェ(François Baschet)
1920年生まれ。兄のベルナールとともに、音響彫刻の発明者である。60年代に、彼らは最初の音響彫刻を開発。フランソワ・バシェは、共同で前衛音楽団を立ち上げ、新たな楽器を開発。その後、世界ツアーをおこない、多くの注目を集める。70年代には、動力学的な効果を作品に取り入れ、音響彫刻をさらに発展させる。ベルリンのナショナル・ギャラリーなど、世界中から音響彫刻や「音の噴水」の製作依頼を受ける。彼の作品は、65年のニューヨーク近代美術館、70年の大阪万博、71年のバービカン・センター、83年のハンブルグ美術工芸博物館などにおける、数多くの国際的な個展で披露されている。彼は自身の芸術活動を、教育的な課題と捉えている。長年にわたり、主に若者と共同で創作するプロジェクトを率いてきた。2014年2月11日逝去。
[イラスト]
アラン・ヴィルミノ(Alain Villeminot)
1932年生まれ。バシェと同じ申年。パリで建築を学ぶ。10年間、フランス観光クラブでコンサルタントとして活動したあと、フリーランスとなり、世界中の建築プロジェクトを手がける。チュニジアで知り合った仕事仲間を通して、フランソワ・バシェと出会う。パリにある2人の自宅が、わずか50メートルしか離れていないことが判明し、66年から定期的にバシェと仕事をするようになる。70年の大阪万博における大規模な音響彫刻の展示や、ベルリンのナショナル・ギャラリーにおける「蓮の音噴水」の製作など、多くの企画を共同で実現。2017年5月29日逝去。
[訳]
惠谷隆英(えたに・たかひで)
医師。ドイツ・フランクフルト生まれ。博士(学術)。専門は音楽心理学、音楽神経科学、精神医学。2013年に慶應義塾大学法学部を卒業後、2015年に東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程を修了。2019年に東京大学大学院総合文化研究科博士課程を修了、2024年に金沢大学医薬保健学域医学類を卒業。これまでに、早稲田大学人間総合研究センター招聘研究員、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科研究員を務め、現在は慶應義塾大学病院に所属。2021年にスロイス賞(金沢大学)、2024年に日本音楽知覚認知学会研究選奨を受賞。
[監訳]
亀川徹(かめかわ・とおる)
九州芸術工科大学音響設計学科卒業後、NHKに入局し、N響コンサートなどの音楽番組の音声を担当。2002年に東京藝術大学音楽環境創造科に就任し、音響、録音技術について研究指導をおこなう。近年は22.2マルチチャンネル音響などの3Dオーディオに関する研究や、アーカイブ化、インターネットによる発信などにも取り組んでいる。主な著書に『音響学講座第9巻 音楽音響』(2023年、編集・共著/コロナ社)、『音を追求する』(2016年、共著/放送大学教育振興会)、『音響技術史』(2011年、共著/芸大出版)、『サラウンド入門』(2010年、共著/芸大出版)などがある。AES(Audio Engineering Society)フェロー。博士(芸術工学)。