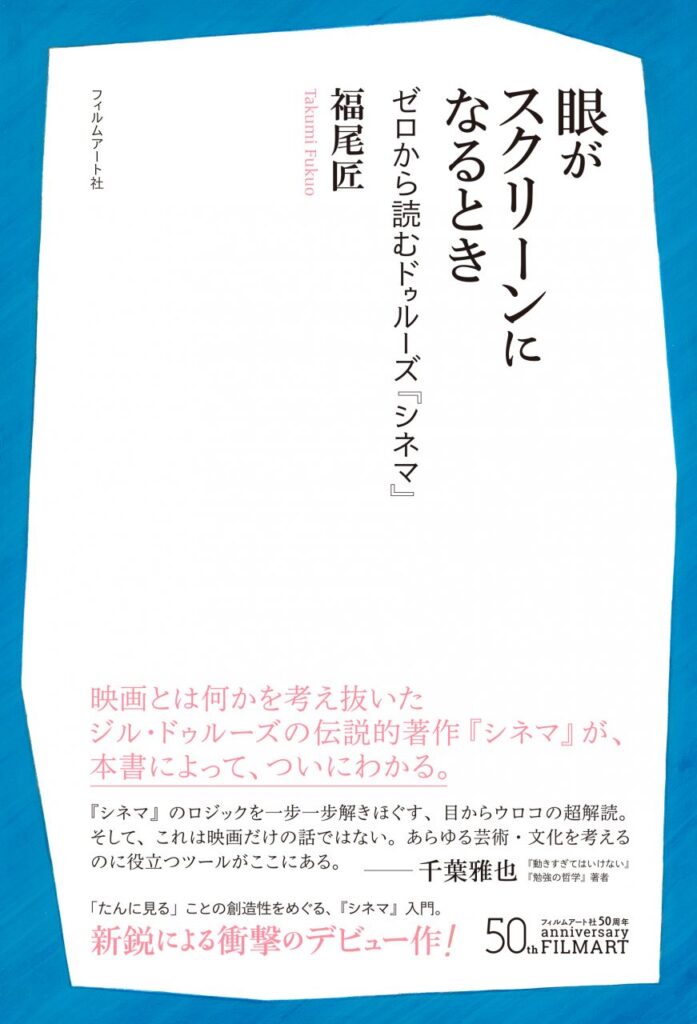はじめに
「ゼロから読む」という名前のとおり、この本はジル・ドゥルーズの『シネマ』という書物の入門的な解説書だ。したがって本書を読むにあたって、ドゥルーズについても、哲学についても、映画理論についても知っている必要はない。映画をどれだけ見たことがあるかということもまったく問題にならない。いずれにせよ本を読みながら映画を見ることはできないのだから。
ジル・ドゥルーズ(Gilles Deleuze)。1925年に生まれ、1995年に自殺したフランスの哲学者。兄を喪った第二次世界大戦は彼の人生を子供時代と大人時代に二分する。このふたつの時代のなかで、彼はそれぞれのやり方で映画を楽しんだと語っている(1)。どこへ行くのにも、行った先で閉じこもるためにしかどこへも行かなかったこの哲学者にとって、映画館もまたひとつの巣であった。彼が好んでいたたとえ話で言えば、彼は蜘蛛であり、光と音がその蜘蛛の糸を震わせていたのだ。この蜘蛛にとって光と音は糸の振動それ自体であり、糸の振動がその外にある光と音を知らせるのではない。「眼がスクリーンになるとき」というこの本の名前のもうひとつの片割れは、映画の観客が蜘蛛になり、映画がもはやイメージの向こうにある何かを知らせるものではなくなる状況を指し示している。眼がスクリーンになるとき、イメージがそれ以上でもそれ以下でもなく見たままで現れる(2)。これが『シネマ』のゼロ地点であり、ゼロから読むという試みには、この地点がどのようなものであるか見定めたうえで『シネマ』全体を見渡すという意味も込められている。この地点でドゥルーズは「映画からまっすぐに哲学へ」、そして「哲学からまっすぐに映画へ」と向かう仕事を開始するからだ(3)。
この出発点には、もうひとりの哲学者、アンリ・ベルクソン(Henri Bergson, 1859–1941)の名前が刻み込まれている。ドゥルーズは、リュミエール兄弟による映画の発明(1895年)と、ベルクソンの『物質と記憶』の刊行(1896年)がほぼ同時期であることに、イメージに運動が吹き込まれたのと思考に運動が吹き込まれたのは同時だったと驚く(4)。『シネマ』が映画をあつかうのとおなじくらい熱心にベルクソンのテクストに取り組むのは、彼が「真の運動」というものを哲学に導入したからだ。
『シネマ』は二巻に分かれている。1983年に刊行された『シネマ1――運動イメージ』、そして1985年に刊行された『シネマ2――時間イメージ』。大まかに言って前者は戦前の映画を、後者は戦後の映画を考察の対象としており、ここでも戦争という断絶が両者を隔てている(5)。有機的な全体を志向する戦前映画と、無機的な断片化に晒される戦後映画。運動と時間。そのあいだの戦争、死。
『シネマ』は不幸なすれ違いをこうむってきた。哲学研究者は「映画の本だから」と、映画研究者は「哲学の本だから」と、読まないでいる理由があらかじめそこに横たわっている書物だからだ。哲学研究においてはドゥルーズのほかの著作の図式を当てはめて読むもの、映画研究においては見栄えのする概念を本書から借りてきて映画作品に当てはめるものの多さが、なおさら本書を読まずに済ませる、あるいは読んだことにすることへの欲求の根強さを証し立てている(6)。
この二重の当てはめ、つまり「適用」こそが、ドゥルーズが『シネマ』で想定している敵であることは本論に入ってすぐ見ることになる。「いかなる仕事も引き継ぎのシステムのなかに組み込まれています」(7)と彼は語っているが、われわれは二重の適用に代えて二重の引き継ぎをおこなう書物として『シネマ』を読む。映画から、そしてベルクソンから、何がどのように引き継がれているのか。その「システム」を辿ることと『シネマ』を読むことはおなじことだ。
ドゥルーズの哲学の「創造性」については、たくさんのことが言われてきた。いわく、過去の哲学者の「怪物的」(8)な子を孕ませる「自由間接話法的なビジョン」(9)によって、もはや誰が語っているのかわからないところから新たな概念を創造した、あるいは「芸術の新たな用法」(10)を発明し、芸術ともっとも幸福な関係を結んだ哲学者である、と。しかしそうであるのなら、ベルクソン論であると同時に映画論である本書をドゥルーズの「主著」だとしない理由はどこにあるだろうか。哲学史をかえりみてなお、本書ほど芸術のひとつの表現形態を全面的に引き受けた哲学書がほかにあるだろうか。200人以上の映画作家を取り上げ、映画の誕生から刊行当時の80年代の作品までを視野に収める本書はまさしく全面的なものであるが、言及される作品の多さよりも本書が「イメージと記号の分類」(11)をこととする書物だという点にこそ『シネマ』の映画に対する全面性はある。
しかし本書では、映画作家についても、作品についても、可能な限り一切の言及をしないことにする。その理由は第一に、作品を適用することでドゥルーズの語っていることを説明することこそが重大なつまずきのもととなるからだ。フェデリコ・フェリーニの映画を持ち出して「結晶イメージ」を、アラン・レネの映画を取り上げて「時間イメージ」を説明するのはあまりにたやすいが、このとき参照される作品は理論のためのたんなる具体例になり下がってしまう。ドゥルーズが『シネマ』の分類は開かれたものであり変更されうるものであるとしているのは(12)、新しいイメージが、あるいは彼がすでに言及しているイメージさえもが、分類を内側から突き破るポテンシャルをもっていることを彼が信じていたからだ。
映画作品について具体的な言及をおこなわないのは、第二に、この本が試みるのは『シネマ』におけるイメージの分類を改変することではなく、あくまでその分類の原理を明らかにすることであるからだ。これは分類を担う諸々の概念の概要を『シネマ』の章立てに沿って順に説明するということを意味しない。というのも『シネマ』は書かれている順番で読むことが――ドゥルーズの著作のなかでおそらくもっとも容易であると同時に――根本的な誤解を招きかねない本だからだ。とりわけ運動イメージ(第一巻)と時間イメージ(第二巻)の関係を、そのあいだに第二次大戦が横たわっているという事実をもとに、論述の推移あるいは歴史的な前後関係だけで説明してしまうことは、『シネマ』の体系的な理解を妨げてしまう。
すでにできあがった分類の一覧表の上をぴょんぴょんと項目から項目へと飛び移りながら、各項目の内容に適ったイメージを召喚していけば、それだけで『シネマ』の入門的な解説書には十分かもしれない。しかしそのような態度こそが、「運動イメージから時間イメージへ」という単線的な推移を読解の軸に据えることを余儀なくさせるだろう。そしてそこには、すぐさま「ドゥルーズによるベルクソンの乗り越え」というもうひとつの単線的なストーリーが否応なくくっついてくる。
最終的に本書が疑うことになるのは、ドゥルーズという哲学者の能動性、主体性だ。たしかに『シネマ2』の後半ではベルクソンが言及される場面は極端に少なくなり、そこで語られることもおよそベルクソン的とは言いがたい内容になっている。しかしもし、そのような内容が、たんにドゥルーズがベルクソンをそのように読んでしまっていたことから帰結したものだとしたらどうだろうか。もはや私の言いたいことはベルクソンではカバーできないからと、そこから出ることを選択したのではなく。とうぜん、「本当は」どうだったのかなどということは誰にもわからない。しかし本書は、ベルクソンからの「逸脱」はドゥルーズのベルクソン読解の内部にはじめから亡霊のように取り憑いており、その帰結はほとんど自動的に導かれるものであることを両者のテクストに基づいて示すつもりだ。
このある種の受動性は、「素朴な観客」であることをみずから吐露するドゥルーズの映画に対する態度にも密接なつながりがあるものであり、われわれはここにこそドゥルーズの哲学の創造性、彼が哲学に求めた創造性、そして哲学が哲学でないものにふれることによる創造性の根源を見ることになるだろう。
最後に、今後本書にはそうした話題は出てこないのだが、現代におけるわれわれとイメージ=映像の関係についてひとことだけ述べておく。映画論、映像論、映像文化論、映像メディア論をあつかう書物は決まって、われわれがいかに無数のイメージに囲まれて生活しているか意識するよううながすことから始まる。しかし、現在われわれを取り巻くイメージは、われわれにおのれを見せようとしているのだろうか。むしろ現代のイメージは、それを見ずに済ませてもらうために躍起になっていないだろうか。われわれはイメージを見るかわりに、「消費」を、「コミュニケーション」を、「インタラクション」をひっきりなしに要求されている。本書は「たんに見る」ことの難しさと創造性をめぐって書かれる。
註
1.「ふたつの完全に分け隔てられた時代を経験した私はめぐまれています。戦前に、子供のころ、私はよく映画館に行きました。〔……〕それから、戦後になってまた映画館に戻りました。とはいえべつのしかたでです」(ドゥルーズ『狂人の二つの体制――1983–1995』、[263] 129-130頁)。
2.丹生谷貴志『ドゥルーズ・映画・フーコー』における「それ以上でもそれ以下でもなく」というイディオムの多用は、本書の中心的な主題である眼-スクリーン的な視覚性において現れる「見たままの」イメージという水準とその危うさを指し示していると思われる。
3.ドゥルーズ『狂人の二つの体制――1983–1995』、[263–264] 130頁。
4.ドゥルーズ『記号と事件』、[166] 254頁。
5.『シネマ1』と『シネマ2』のあいだの1984年には、ミシェル・フーコーの死が横たわっているが、『シネマ2』において「言葉と物」あるいは「外の思考」というフーコー的な主題が重要になるのもこのことと無関係ではないだろう。二年後の八六年にドゥルーズは『フーコー』を刊行する。
6.『シネマ』の安易な適用が映画研究に及ぼす弊害については、平倉圭『ゴダール的方法』(229頁)を参照。
7.ドゥルーズ『狂人の二つの体制――1983–1995』、[265] 132頁。
8.ドゥルーズ『記号と事件』、[15] 17頁。
9.國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』、第一章。Flaxman, Gilles Deleuze and the Fabulation of Philosophy, pp. 215–226.
10.Sauvagnargues, Deleuze et l’art, p. 10.
11.『シネマ1』、[7] 1頁。
12.ドゥルーズ『狂人の二つの体制――1983–1995』、[202] 31頁。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。