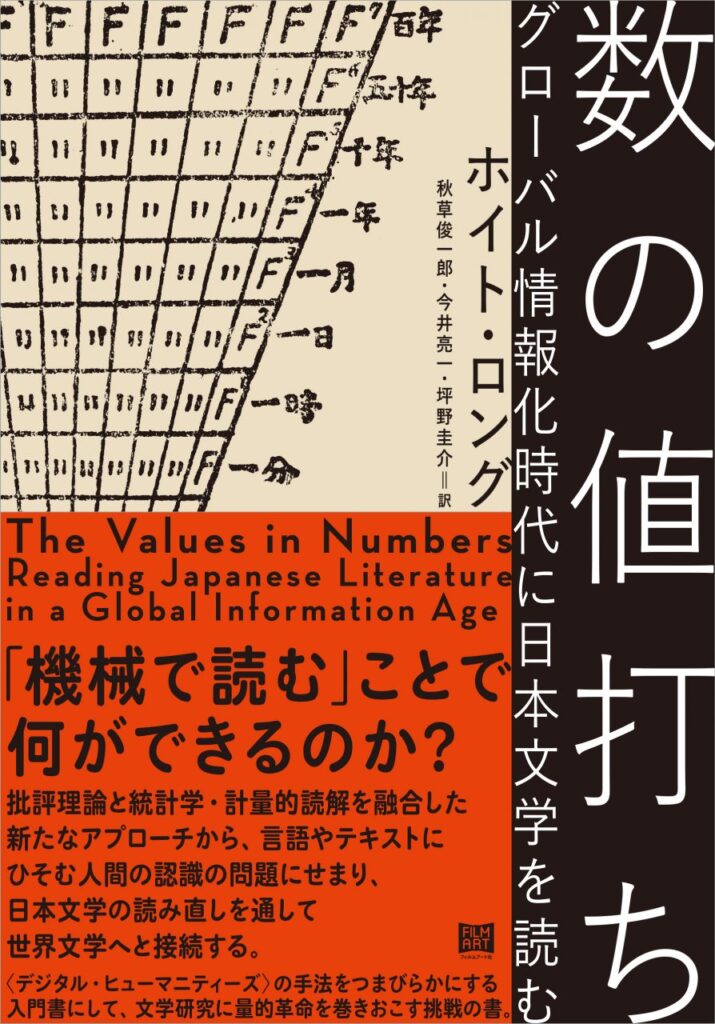序章 数の不確かさ【前編】
思考の歴史は思考モデルの歴史でもある。
──フレドリック・ジェイムソン(1972)[1]世界を知り尽くした者にとって、症例を数えあげ、平均を導きだす行為は、途方もない多様性をもった人間の行動の根底に潜む動機に迫る手法として得策ではない。
──B・J・I・リスエーニョ=ダマドール(1837)[2]
1837年4月25日、パリの医学アカデミーで開かれた会議の俎上に取りあげられたのは、医学における統計というテーマだった。さかのぼること2週間前、パリ大学医学部教授の座にあったジャン・クリュヴェイエが、本件についての議論を呼びかけたのだった。クリュヴェイエのような医学者は統計学的手法を医学に持ちこむことへの懸念があった。ここ数年間、シメオン・ドニ・ポアソンの「大数の法則」やアドルフ・ジャック・ケトレーの「平均」のような新たな統計の考え方が出現していた。前者は、ある事象が起こる確率のばらつきは、測定の数を増やせば増やすほど小さくなるというもので、後者は多くの人間を観察すればするほど、個々人の特徴は「捉えづらくなり、一般的な事実に道を譲る」という仮定に基づくものだ[3]。こうした考え方はまだ端緒についたばかりであって、統計学の分野ですらほとんど事実として認められてはいなかったが、物議をかもしながらも人口学、法律、そして医学と他分野の学問に広まりだしていた[4]。じっくりとした議論を呼びかけつつも、クリュヴェイエは自分をふくめ医者のほとんどは事実上議論などなにもする気はないと信じてもいた。医学とは「数字や計測器を相手にするような学問ではない。観察と経験(experience)の科学なのだから」。生命の学問に数字を押しつければ、「生体現象の千変万化、融通無碍の性質に反してしまう」。クリュヴェイエが「数字の硬直性」と呼んだものは、生命の移ろいやすさに対応することが求められる医学の手法──その知のかたちそのもの──と相いれないものだったのだ[5]。
いよいよ議論がはじまると、「反統計思考の王者」として人気をさらったのはスペイン人のB・J・I・リスエーニョ=ダマドールだった[6]。リスエーニョ=ダマドールが得意とした議論の運びは、討論相手は、医学上確かな知見(特定の患者を診察し、観察することで培われる)を、確かな数字という錯覚とすりかえているとして誤りを指摘するものだった。なぜ数字の錯覚なのかと言えば、リスエーニョの意見では、平均の集計や計算は「大多数の症例を事実上総計と等しいものと化す機械的な手法」であって、人間の行為(や病気)の「途方もない多様性」へのアプローチを否定するものだったからだ。言ってしまえば、数字なんてつかえば、多様性そのものに目を塞ぐのも同然なのだった。医学を「芸」と呼びならわし、医学の知見を裏づけるのは芸術家の感覚だとする伝統に立ち返り、リスエーニョは「生命の移ろいやすさを把握できる唯一の知のありようとは、「芸術家個人の才能」であり、だからこそそれぞれの患者を個別の症例において診断」するのだと主張した。医学が数字の道をいけば、この芸は「くじ」と化すだけではない。平均によって覆い隠された「マイノリティを看過する」リスクを冒し、医学固有の不確かさに誤った処方箋を出してしまうだろう。
反論する番になって、数字の擁護者たちは「普通の」(平均的な)人体や患者といった考え方への留保を即座に表明した。しかし問題は、この考え方が誹謗者によって誤解され、誤ったかたちで広められていることだった。それがある観察の範囲におけるばらつきの幅を特定するための尺度であり、ばらつきをなくした唯一の値ではないと理解されてやっと、有益な概念ツールになったのである。医者だって本当は、患者ひとりひとりをまったく別の人として診るのではなく、症状が一定の範囲に収まる場合には、患者への治療を一般化することだってできるはずだった。しかしそんな反論に説得される医者はごくわずかだった。議論の終わりに、リスエーニョの同僚のM・ダブルが「数字主義者」にとどめの一撃をくらわせた。平均などというものは理論の噓であって、臨床をすれば平均的な人体も病理も、平均的な患者もどこにも存在しないことがわかるのだ、と。「比較が許されるなら、私が思い浮かべるのは、千人だかの足を測って、平均なるものを考案して、その空想の型に合わせて靴をつくる靴職人みたいなもんですよ」。もちろん、そんな靴職人は靴職人なんかじゃないという冗談だ[7]。この時点では、数字はものの数ではなかったのだ。
こういった議論は今日の医療とはかけ離れているように思えるが(個人の才覚のみを権威の源にする医者を信用できるだろうか? )、北米の学術界で現在進行中の文学研究における数の値打ちをめぐる議論をフォローしている人間には、レトリック自体はまったく見慣れたものに映る。ときに文学が統計的思考への抵抗の最前線になったかのように思えるのは、リスエーニョとその仲間が依拠していた二分法と概念区分が持ちだされているからだ。つまりは凝り固まった解釈柔軟な解釈、職人芸機械的な処置、多様性への気づき画一化され、均一化されたものの算出。統計上の平均が生む錯覚のかわりに、コンピュータと人工知能のそれを手にした今日の数字主義者にむけられた辛辣なコメントに、リスエーニョとその仲間のこだまを聞かないようにするのは難しい。そのせいで、人間が積み重ねてきた読みの交響楽が、テキストの「野蛮な光学スキャン」にすりかえられてしまうのだ──せっかく「探求の方向をランダムにふりわけ」、「発想の飛躍を生む脳の自然な知性」によってテキストを味わえているのにもかかわらずだ[8]。奴らはじかにテキストを観察し、体験しようとしない。まるで「窓を開け、外は寒くて雨が降っていると気づくのではなく、インターネットで気温をチェックする人間」みたいなのだ[9]。奴らときたら「文学的、文学史的、言語的複雑さ」を「還元的還元主義についての」ディシプリンに徹底的に還元し、「機械的に起きることと洞察を混同する」のもしばしばなのだ[10]。数字をまったく相いれない分野に持ちこもうとする連中は、足がなんなのか忘れてしまった愚かな靴職人みたいなものだ。メルヴェ・エムレの言葉を借りれば、われらがデジタル・エイジの「悪い読者」なのだ[11]。
今日の「悪い読み」は昨日の「悪い医療」に似ているかもしれないが、後知恵で言えば時間が利したのは数量思考の側だったと結論せざるをえない。1830年代の議論は、今日の医療にいかに数字が絡んでいるかを知れば、古色蒼然としている。しかし「質的か、量的かをめぐる綱引き」は、「よい」医療とはなにかをめぐる道徳の議論でもあって、新しいテクノロジーが知の対象としての人間の身体に影響をあたえ、医者を悩ますさいには決まってむし返されている[12]。裏を返せば、文学研究における現行の議論で、こういったレトリックが申し立てられたのは今回がはじめてのように見えても、少なくとも19世紀後半に文学研究が学術分野として制度化されて以降、実際は何度も、言葉を変えて蒸しかえされてきた議論のつづきなのだ。こうした議論が表面化した例のごく一部をあげておこう。ヴィクトリア朝時代の読書の生理学理論。19世紀に興隆したドイツ文献学。I・A・リチャーズの語彙の統計分析。キャロライン・スパージョンやジョセフィン・マイルズの初期の計量的文体論。ロシア・フォルマリアズム。冷戦期の機械読解と機械翻訳の発展に対抗するニュークリティシズムの深化。ブック・ヒストリー。読書の社会学的研究[13]。こうした事例ではいずれも、数の値打ちをめぐる賛否両論が巻き起こったが、それも情報の新しい秩序や新しいテクノロジーの亡霊を前にしてのことだった。そしてそれこそが知的生産の制度やインフラを(よくも悪くも)変容させていくように見えた。数字的思考は装いを変えつつも、質的推論と量的推論の概念区分を崩壊させたり、固定したりするような引火点の役割を果たしてきた。議論のサイクルは、知の体系化と生産をめぐる大規模なインフラが入れ替わるたびに、情報へのアクセス方法を一変してしまうような技術革新がおきるたびにくりかえされるものだ。その都度その都度において、文学を読むとはかくあるべしという言説を支えるレトリックはアップデートされてきた。
『数の値打ち』は文学研究における現在進行形のその綱引きについての本であると同時に、その秘めたる未来への貢献をめざす本である。私の関心は、私たちがいかにして現在の膠着状態に至ったかということ、これまでとどこが同じでどこが違うのかということにある。そのため、2つの異なる理論的フレームワークを用いることにした。1つ目は、文学研究が数字をとりこむべきかどうかという道徳上の主張の背後にある科学史的な観点である。こうした主張は避けて通れないものであり、確立した知の実践の境界線を保持する(あるいは変えようとする)うえでも間違いなく必要なものである。さらに、テキストの実質は、患者にも似て、それをどうとらえるかというモデルによって異なるという事実を避けることはできない。しかし、こういった主張が方法論や学術分野の区分をいままで以上にかっちりさせてしまえば、そのあいだを行き来するどころかコンセプトの流れを渋滞させかねない。分野における学術的真理が、質的思考を量的思考からかけはなれたものにしてしまう役割を果たすのなら(あるいはその逆もしかり)、知の産出の2つのモードの絡み合いが見えづらくなるだけではなく、モードの社会的慣習や実践者同士もそうなり、両者のあいだに障壁を生み、存続させてしまう。歴史のふるいにかけられた、価値をめぐる制度内の妥協と交渉の産物こそが「事実」となり、それに基づいて──あるいはそれに反して、ディシプリンが奉じる真実が鍛えられるのだ。
この原理は、1830年代の医学界で議論の中心だった平均や普通といった概念から生まれたものだ。ピーター・クライルとエリザベス・スティーヴンスの指摘によれば、医学史の分野では、ポアソンやケトレーによる統計的思考によって支持された「普通」は、(あたかもそれがその唯一の文化的機能であり、現実に対する唯一の主張であるかのように)「抑圧し、標準化する機能」を批判されるのが常だったという。それは、平均の算出によってもたらされた世界に対する見方のひとつと受けとられたが、主張する事実がゆえに、イデオロギー的に疑わしいものとされた。しかし、より長いスパンで概念史を見てみれば、「普通」はそのはじまりから平均と理想、計算と価値の両方の意味で解されていたことがわかる。これはあらゆる人間(計算によって平均化された)が従わなくてはならない規範(「平均人」)を主張するために、つくられた事実だった。だが「普通」は、個人が規範からどれほど逸脱したのかという度合いを可視化したので、個別化や差異化のためにも用いられた。フーコーが書いているように、それは「逸脱を測定したり水準を規定したり特性を定めたり、差異を相互に調整しつつ有益にしたりを可能にする」のである[14]。ゆえに「普通」の解釈と文化的機能は、人間が思いつくありとあらゆる政治利用(および濫用)にさらされ、交渉次第のものだったのだ。
この交渉可能性は、フランス医学界で平均の意味が争点となったまさにそのときにはっきりしたものだ。計測を批判する人間は、平均なんて理論の噓なのに、擁護者はあたかも直接見聞きした現実かのようにあつかっていると批判した。しかし擁護者の側ではそれが噓だとよくわかっており、まったく同じあらわれをする病気はないと認めていた。若き医師P・F・O・レイヤーは、病気は一定のものではないが、「その変異はかなり狭い範囲にとどまることがある」として反論した。こうした変異の幅をひとまとまりと見なしてやれば、複数の患者を同時に診るうえで役に立つ。逆に、「平均から明らかに逸脱した症例」の患者なら処置を変えればいい。平均は、同じ症状の患者をグループ分けするだけでなく、症状がおさまる変異の幅が異なり、ゆえに対応を変えなくてはならない外れ値の患者を特定するうえでも、役立つ噓なのだ。計測するかどうかは別として──レイヤーは答弁した──医者が治療をおこなうさいに頭の中で組み立てる病気の「平均的なイメージ」と、このプロセスはなにか違うだろうか? 平均のような概念の利点を認めず、どの患者も唯一無二だという主張にしがみついてあらゆる統計的思考に反対すれば、「同じ事実はまたとなく、同じ治療行為はなく、理論になにかを一般化する資格などない」と言っているに等しいではないか[15]。変異を絶対的な差異として認識すれば、学術的な営為や理論は無意味なものと化し、医者はすべての靴を最初で最後のものであるかのようにつくりあげる靴職人になるのだ。
この事例からえられる教訓のひとつは、議論の道徳的側面の下には、ある種共通の知的土壌があったということだ。その中で個別性、差異、類似、パターンといった概念は、ある種別個の思考モデルのもと疑義が付され、論じられている最中だった。討論者同士話が嚙み合っていないわけではないとすれば、互換性のない推論方法を用いつつも同じ概念空間を航行し、自分のやり方で物事の差異を把握していたせいだ。その過程で──これが2つ目の教訓になるが──彼らは自分たちの思考モデルを、コミュニティや仕事上の約束事の積み重ねの結果として提示した。ゆえに、交渉と解釈の余地がのこったのだ。あるディシプリンの「事実」は、リアリティを構築する揺るぎえない基盤であると同時に、価値の淵源でもあるのだが、ほかのディシプリンの事実と交差する地点ではその確からしさは相対化されてしまう[16]。上記の教訓を胸に刻んで、私が模索する分析空間とは、私たちが今日生きるグローバル情報化時代においてテキストに適用可能な統計的事実およびモデルと、文学研究の慣例が再交渉しうるような空間である。私自身、10年間を費やして文学研究の慣例にしっかり根ざした本を1冊書きあげ、さらに10年間を費やして量的方法がこうした慣例をいかに補うのかを探求してきたので、断言できるのは、ドツボに嵌った靴職人や機械読者なんかじゃない、この空間を航行する人間にはもっとふさわしいメタファーがあるということだ。
『数の値打ち』の2つ目の理論的な枠組は、1つ目を補うものであって、数の値打ちとその使用を決めるポリティクスを考えるうえでは、学術的な、歴史的な、社会的な文脈が重要だということだ。このことは近頃の量的転換を証だてる専門書の山に目を通したものなら誰の目にも明らかである──こういった本が手を変え品を変えしめしているのは、量的手法を議論するうえでコンテキストが方向性を決めてしまうということだ(文学研究がそのような方法を使わないよりも使った方がましだというコンセンサスが前提になっているにしても)[17]。私がこの不協和音のコーラスに加えたい声は、地域研究の関心の枠組と、文学が地政学と文化的・言語的差異に絡めとられている時代にわきおこる疑問にしっかりと根を下ろしたものになる。こうした疑問は、文学をどうして/どうやって数字で読むのか、という疑問に比べて派生的なものに映るかもしれない。だとすれば、議論の出発点としていまや古典となった、フランコ・モレッティの「遠読」への呼びかけが、そうした疑問に端を発し、(めったに言及されなくても)日本近代文学史に触発されていたという事実を思い出さなくてはならない。モレッティによれば、自分のもともとの「世界文学への試論」(モレッティが試験し、遠読というコンセプトが発展するもとになったもの)は、柄谷行人の『日本近代文学の起源』へのフレドリック・ジェイムソンの序文での見解に触発されたものだと言う。つまり、「日本近代文学の出発点において、「日本人の経験をもとにした素材と、西洋小説の構成からパターンの形式を抜き出したものとのあいだは、いつもぴったり溶接できるとは限らない」」のである。同じ現地の素材と外国の形式の組み合わせがインドやブラジルのような場所でも起こっているのを発見したモレッティは、この潜在的な「文学進化の法則」がほかの地域にもあてはまるのではと思い、距離を置いて読むというプログラムを始動させた。ここで「距離(遠さ)」とは、「知識をえる条件」であって、テキスト以外の単位──「装置、テーマ、文彩──あるいはジャンルやシステム」──に焦点をあてるものだった[18]。
英文学者のアンドルー・ゴールドストーンの指摘によれば、このプログラムが進展し、方法が圧倒的に量的なものになるにつれ、遠読は当初の動機であった比較文学的な問題意識から切り離されてしまった──そしてその対象は典型的に、「ほとんどの文学研究者がそうであるような、国別の、言語別の専門」によって徐々に組織されるようになっていった。かつては文学の多様なシステムを横断していかに読むかが問題だったのが、いまや問題は一見まとまっている単一のシステム内部の、「まったく読み切れそうもない」読まれざる傑作に移ったのだ[19]。本書で、私が取りくんだのはこうした問題をいかに溶接するかということだ──つまり、量的なアプローチで比較とスケールを同時にあつかえないかという問題だ。私は英文学という主流のコンテキストを超えた各国文学のコンテキストで数を使って読むという可能性を──さらにはコンテキストとそれぞれの文化的・言語的歴史のあいだで読むという可能性を探求した。そうすることで、私は入れ子状になったコンセプト上の区分を行き来した。ひとつは数字と文学。もうひとつは(大文字の)文学と複数形の文学である。こうしたムーヴメントは、それ自体ユニークな問題群(量的手法とモデル)を生みだしたが、それらは英文学研究のためにデザインされたものであって、ほかの文学・言語コンテキストに輸出・適用されるプロセスで、特定の解釈実践とアーカイヴのインフラに依拠していることを露呈した。たとえば、単語と単語のあいだにスペースがあることや、何世紀分もの文献を読めるのも、どこでも技術的に可能な前提条件などではなく、英語の言語的・帝国的な歴史の産物だと露呈してしまったわけだが、だとすれば数字とその文学(たち)との関係をめぐる現行の議論はいかに変わるだろうか? [20]
関連して──モレッティの遠読プログラムのたどった運命がしめすように──量的なアプローチとは、国別の文学というカテゴリーを生来強化してしまうものなのかという疑問がある。数字による抽象化が、類似した単位とカテゴリーの構築──つまりは言語的・美的・文化的な差異を比較可能な単位へと還元してしまうこと──を前提にしていると解するのなら、量的方法が国家を手ごろな比較単位として優遇するのは直観のうえではぴんときそうだ。しかし、厳格な質的アプローチと比べて量的アプローチがそれを重視したり、軽視したりすることに根拠はあるのだろうか? 国別の文学が優遇される傾向がありそうだとして、それは(量的アプローチそのものよりも)どれぐらいディシプリンに染みついた仕組みによるものなのだろう? 私は、数と国が自然と結びつくという考え方に反対だ。比較可能な単位にこだわれば、国民文学同士いかにちがうのかという定説をうまく波立たせることができるし、(凝り固まった価値システムではヒエラルキーしか見えないようなところで)対象同士の等価もしめすこともできる。数字によって差異をフラットにすることが、複数の文学間の関係を再考する上で役に立つこともあるのだ。この主張は、『数の値打ち』が文学と数字の異なるシステムのあいだを──世界と国別の文学のイマジナリーのあいだを──常に漂い、行き来しているという事実から生まれた。柄谷は『日本近代文学の起源』のあとがきで、デカルトのコギトとは「多様なシステム間の「差異」が不可避的に生みだす疑念のプロセス」だと述べている。もしそうなら、本書は二重の意味で疑念に包まれていることになる。柄谷は疑念を「歴史的に生みだされてきたものを自然なものとして、偶発的なものを必然的なものとして受け止める方法を明らかにする」うえで認識論上有意義な立ち位置だと主張した[21]。ならば私は疑念と、異なる知の体系の衝突から生まれる不確かさに則ろうではないか。そうすることで、数字をまじえて/まじえずに語られる文学についての偶発的なお話を脱自然化してみよう。
このような多様なシステムのあいだを行き来するために、私は本書をいくつかのテーマ(事実、アーカイヴ、ジャンル、影響、言説)とサブテーマ(差異、サンプル、反復、判断、キャラクター)で構成した。これらのテーマはシステム同士のあいだをつなぐコンセプトの架け橋となってくれるだけでなく、複雑化・差異化のポイントになる。それぞれのテーマとサブテーマはこの二重の役割を果たす。数字と文学という概念の分断を超えて思考する道をひらく一方で、日本文学とほかの文学との関係についての専門的議論(とりわけ国民文学の正典形成をめぐる議論、小説という形態の進化と国際的な流通、コロニアルな文学の関係)において、この思考をローカライズするのだ。また本書をデジタル・メソッドの入門書とする狙いで、テーマごとの枠組に、量的手法を徐々に導入していく構成をとった。思考モデルも随時紹介するが、こうした手法や、それぞれの経験知の歴史に織りこんだかたちで提示する。章が進むにつれて手法は手のこんだものになり、用いるデータ量もまた増加するので、さまざまなスケールで「事実」を生成する新たな道具だてを組みあげるための理論的前提や解釈判断をあつかうこともできた。本書で明らかにするように、こうした道具だては、フランスの医学アカデミーの医師たちにとっての平均と同じように不安定かつ交渉の余地があるものだ。そして19世紀当時、未来の医療インフラにおける平均の立ち位置が不確かだったように、こうした新しい道具だてのなかには、そもそもの借用先のディシプリンの内部ですらその未来が不鮮明なものもある。それらが文学研究でどれほど確立されるかはおおよそのところ、ユーザーのコミュニティのあいだでどれだけ広まるか、コミュニティにどれだけ活用されるかによって決まるだろう。そのため、本書を執筆するうえで使用したコードとデータは公開しておいた。これは、未来の文学研究のインフラへの貢献を道を探す第三者が、本書の結果をチェックし、再現し、再解釈できるようにでもある[22]。
註
[1]〔フレドリック・ジェイムソン『言語の牢獄──構造主義とロシア・フォルマリズム』川口喬一訳、法政大学出版局、2013年、ⅶ頁。〕
[2]Peter Cryle and Elizabeth Stephens, Normality: A Critical Genealogy(University of Chicago Press, 2017),84.
[3]以下の文献に引用されている。Peter Cryle and Elizabeth Stephens, Normality: A Critical Genealogy(Chicago: University of Chicago Press, 2017),80. この議論とその直接的な歴史的文脈の詳細については、二章を参照のこと。
[4]19世紀、ポワソンやケトレーの学説が医学やほかの分野でいかに受容されていたのかについての歴史的概観は、イアン・ハッキングの以下の文献を参照のこと。Ian Hacking, The Taming of Chance(Cambridge: Cambridge University Press, 1990),95–114.〔イアン・ハッキング『偶然を飼いならす──統計学と第二次科学革命』石原英樹・重田園江訳、木鐸社、1999年、138-168頁。〕こうした学説は、古典的・主観的な確率の概念から、社会現象の規則性を観測し、客観的・経験的事実としてあつかう統計データの頻度主義的解釈へと、より広い意味で認識を転換させた。
[5]Cryle and Stephens, Normality, 82. 数字が専門家の主観的な洞察や判断の地位を脅かすものだという抵抗は、19・20世紀において科学の各分野においても同様に展開された。生物学、物理学、心理学において、いかにこの力学が働いたかについての簡明な歴史は、以下の文献を参照のこと。Gerd Gigerenzer et al., The Empire of Chance: How Probability Changed Science and Everyday Life(Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
[6]Cryle and Stephens, Normality, 83.
[7]Cryle and Stephens, Normality, 81–87.
[8]Timothy Brennan, “The Digital-Humanities Bust,” Chronicle Review, October 15, 2017, https://www.chronicle.com/article/the-digital-humanities-bust/.
[9]John Whittier Treat, “Japan Is Interesting: Modern Japanese Literary Studies Today,” Japan Forum 30, no.3(2018), https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09555803.2018.1441171.
[10]Nan Z. Da, “The Computational Case Against Computational Literary Studies, ”CriticalInquiry 45, no.3(Spring 2019):638–39. 強調は原文。
[11]メルヴェ・エムレは、20世紀中盤の米国の読書実践をめぐる卓越した研究で、「悪い読者」を「読書において、自己投影や、社会化された感情や行動、相互作用のような行為にはまりこんでしまう」人々として書いている。エムレはある種特有の「悪い」読書について論じているわけだが、それが幾分は、エリート学術機関や純文学と結びついた読書実践を擁護する意図をもった人々によって構築された社会的なカテゴリーであることも認めている。私がここでこのフレーズをもちいるのは、数への批判が、ある種の制度化された読書実践の擁護にもなっているからである。以下の文献を参照のこと。Merve Emre, Paraliterary: The Making of Bad Readers in Postwar America (Chicago: University of Chicago Press, 2017), 3.
[12]Cryle and Stephens, Normality, 62. より近年の例については以下の文献を参照のこと。Richard Harris, “As Artificial Intelligence Moves Into Medicine, the Human Touch Could Be a Casualty,” All Tech Considered, April 30, 2019, https://www.npr.org/sections/health-shots/2019/04/30/718413798/as-artificial-intelligence-moves-into-medicine-the-human-touch-could-be-a-casual.
[13]以下の文献を参照のこと。Nicholas Dames, The Physiology of the Novel: Reading, Neural Science, and the Form of Victorian Fiction(Oxford: Oxford University Press, 2007); Chad Wellmon, Organizing Enlightenment: Information Overload and the Invention of the Modern Research University (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2015); Yohei Igarashi, “Statistical Analysisat the Birth of Close Reading, ”New Literary History 46, no.3 (Summer 2015):485–504; Rachel Sagner Buurma and Laura Heffernan, The Teaching Archive: A New History of Literary Study(Chicago: University of Chicago Press, 2020); Sean Michael DiLeonardi, “Cryptographic Reading: Machine Translation, the New Criticism, and Nabokov’s Pnin, ”Post 45, January 17, 2019, http://post45.research.yale.edu/2019/01/cryptographic-reading-machinetranslation-the-new-criticism-and-nabokovs-pnin/; Janice Radway, Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1991).
[14]以下の文献に引用されている。Cryle and Stephens, Normality, 8–9.〔ミシェル・フーコー『監獄の誕生──監視と処罰』田村俶訳、新潮社、2020年、213頁。〕クライルとスティーヴンスはフーコーの『性の歴史』や『監獄の誕生』における規格化の説明を引用し、いかに後続の研究が、フーコーが特筆した規格化の生産的・個別化機能を無視してきたかを述べている。
[15]Cryle and Stephens, Normality, 93–94.
[16]私の「事実」に関する議論は、アラン・デロジエールの統計史の議論によるところが大きい(本件については第一章でよりくわしく触れることになる)。とりわけ以下の文献を参照のこと。Alain Desrosieres, The Politics of Large Numbers: A History of Statistical Reasoning, trans. Camille Naish(Cambridge, MA:Harvard University Press, 1998), 335–37.
[17]私自身の研究に影響と霊感をあたえたモノグラフを列挙するなら、以下のようになるだろう。Sarah Allison, Reductive Reading: A Syntax of Victorian Moralizing(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2018); Katherine Bode, A World of Fiction: Digital Collections and the Future of Literary History(Ann Arbor: University of Michigan Press, 2018); Andrew Piper, Enumerations: Dataand Literary Study (Chicago: University of Chicago Press, 2018); Daniel Shore, Cyber for malism: Histories of Linguistic Formsin the Digital Archive (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2018); Ted Underwood, Distant Horizons: Digital Evidence and Literary Change(Chicago: University of Chicago Press, 2019).
[18]Franco Moretti, “Conjectures on World Literature,” New Left Review 121, no. 1 (January–February 2000): 58–60.〔フランコ・モレッティ「世界文学への試論」秋草俊一郎訳『遠読』秋草俊一郎・今井亮一・落合一樹・高橋知之訳、みすず書房、2016年、73-74頁。〕強調は原文。モレッティが述べるように、外国の形式と地域の素材というアイデアはもともと、ジェイムソンが柄谷と引き比べたマサオ・ミヨシから得ている。
[19]Andrew Goldstone, “The Doxa of Reading,” PMLA 132, no. 3 (May 2017): 639. 強調は原文。
[20]英語以外のテキストに対してコンピュータ解析をおこなううえで生じる問題についてのすぐれた概観は、以下の文献に記述されている。Quinn Dombrowski, “Preparing Non-English Texts for Computational Analysis,” Modern Languages Open 1, no. 45 (2020), https://doi.org/10.3828/mlo.v0i0.294.
[21]Karatani Kōjin, Origins of Modern Japanese Literature (Durham, NC: Duke University Press, 1993), 186.〔本引用は英語版では「文庫版あとがき」からされているが、日本語版の「文庫版あとがき」には該当する箇所はない。英訳にさいして、かなり書きえられたものと思われる。〕
[22]本書のコードおよびデータリポジトリへのリンクについては、本セクション冒頭の但し書きを参照のこと。あらゆるテキストデータは現行の著作権法が認める範囲で利用可能である。
(後編へ続く)
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。