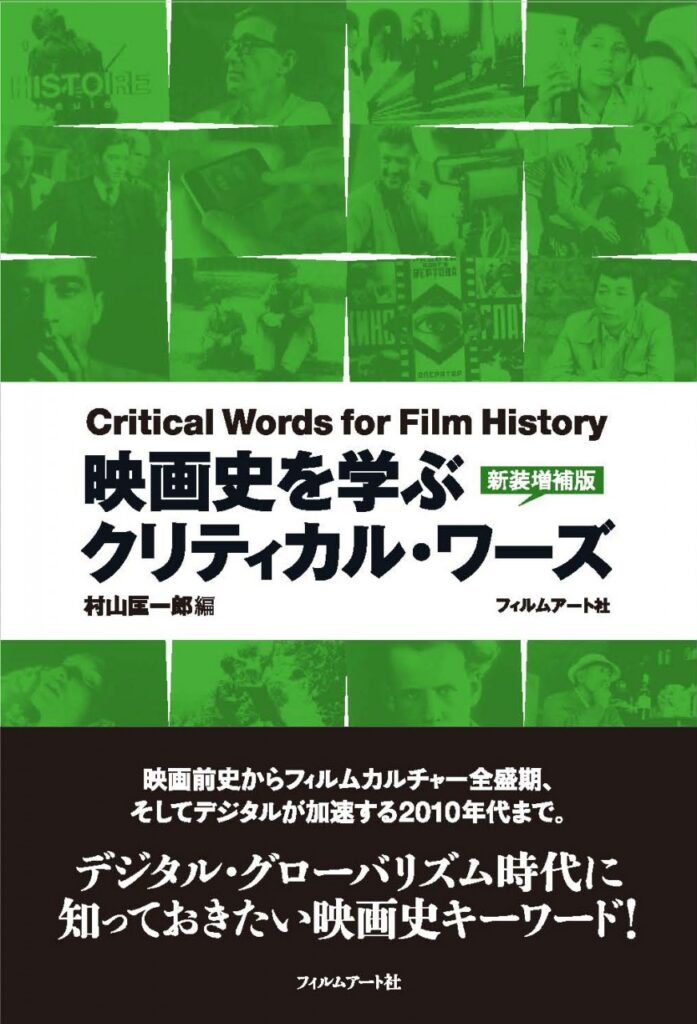映画史を学ぶクリティカル・ワーズとは?
「映像の時代」という言葉が巷に流通するようになってからすでに久しい。それにもかかわらず、映画教育ないし映像教育は、ほとんどなおざりにされてきたといってもいい。今日では、大学などで映画の講座が目立つようになり、またソフトパワーやコンテンツ産業などの流行を背景に、大学や大学院、あるいは専門学校で映画人育成がある程度行われるようになったとはいえ、それでもほとんどの学生にとって大学で初めて映画を学ぶというのが実態である。絵画や音楽などに比べても、映画やテレビ映像は幼年期から子供たちの生活に広く浸透しているにもかかわらず、中学や高校の授業といった公教育に恒常的に取り入れられているとはいいがたい。こうした状況は映像リテラシーという点からももっと考えるべきであるが、映画とその歴史に関する最小限の知識は、少なくとも公教育に取り入れられてもおかしくないほど、現代社会に有益なものといえないだろうか。
その一方、たとえば歴史や社会、あるいは文化や芸術などを学んだり、考えたりする人々にとっても、映画は恰好の参考資料や素材になっている。19世紀末に誕生した映画は、その歴史が20世紀の流れとほぼ重なっており、20世紀を通して唯一かつ最大の表象メディアとして時代のさまざまな様相を記録し提示してきた。そのため、20世紀における人間の営為に関して、映画とその歴史を無視することはできなくなっている。こうした映画のもつ資料的価値は今後も強くなっていくように思われ、映画がほかの分野で果たす役割と機会はますます大きくなるにちがいない。もちろん映画は学ぶためだけにあるものではない。楽しんだり、考えたり、作ったりと、映画との出会いはさまざまである。そして、どのような接し方をするにしても、映画史の知識をもつことによって、映画との接触がより深まることは間違いない。
映画が誕生してすでに100年以上、21世紀になった今日、映画は大きな変化を迎えている。フィルムからデジタルへの転換である。映画は誕生以来、フィルムをベースに成り立ってきたが、今、そのフィルムの消滅が問題となっている。映画=フィルムを大前提にしてきた映画にとって、このデジタル化の問題は、映画≠フィルムを映画と呼んでいいのかどうか、つまるところ、映画とは何か、を改めて問いかけているようにも思われる。映画がテクノロジーに依拠したメディアだとすれば、その歴史はいつも技術刷新によって変化してきた。情報のデータ化というデジタル・グローバリズムもその延長に位置するといえる。その一方、メディアが表象する視覚的イメージを映画と呼ぶなら、デジタル化の波も映画という観念を排斥することはないにちがいない。その場合、映画=フィルムとその歴史の知識は相変わらず必要不可欠なものとしてあるだろう。
フィルムにせよデジタルにせよ、また作る側にせよ見る側にせよ、映画とその歴史の知識に触れることによって、映画に対する姿勢が少しでも広く深くなるのはたしかだろう。そう願って企画されたのが本書である。
本書は映画史に関する最小限の知識を辞典的に取り上げている。映画の歴史は短いとはいえ、エンターテインメントから記録資料まで、また技術や産業から作品や表現まで、その領域はかなり幅広い。そのため、本書は映画史に関わる基礎的だが重要な出来事や人物、あるいは理論的かつ批評的な言説などを網羅的に取り上げている。そして、なるべく平易でわかりやすい記述を心がけるため、歴史を10年ごとに区切って線状的にまとめてある。そこに収められた事項や人物は当然ながら時代を跨っているものが多いが、その時代を象徴していたり際立っていたりする形で配置している。また、たとえば「初期映画の表象モード」の事項のように、後年に考察された理論的言説を対象となる当該の時代に組み込むことで過去と現在を同時に見せるようにしてある。さらに、その時代の必見映画(すでに現存しない作品もある)のささやかなリストを加えることで、それぞれの時代の映画を参照できるようにした。
本書はあくまで映画史への入門案内である。わが国では、翻訳本を除くと、世界の映画を通史的に概観した類書はそう多くない。各国の映画史や区切られた時代の映画史などに関しては一部に優れた本はあるが、映画の全体と各国の歴史との相関関係はなかなか見えにくい。本書では網羅的な記述の弱点を逆に長所にして、映画史に目を向けようとする人々に歴史の相関性を少しでも伝えられれば良しとしたい。いずれにしても、本書をどう読むかは自由である。読者が今後、関心ある事項やその組み合わせから、さらに一歩進んで映画史に分け入ることがあれば、本書の意味は十分にあったといえる。そうでなくても、本書を通して映画史の面白さを実感してもらうだけでも幸いである。実際、映画とは映画史そのものであり、映画史を知ることによって映画をもっと楽しめるようになるにちがいない。