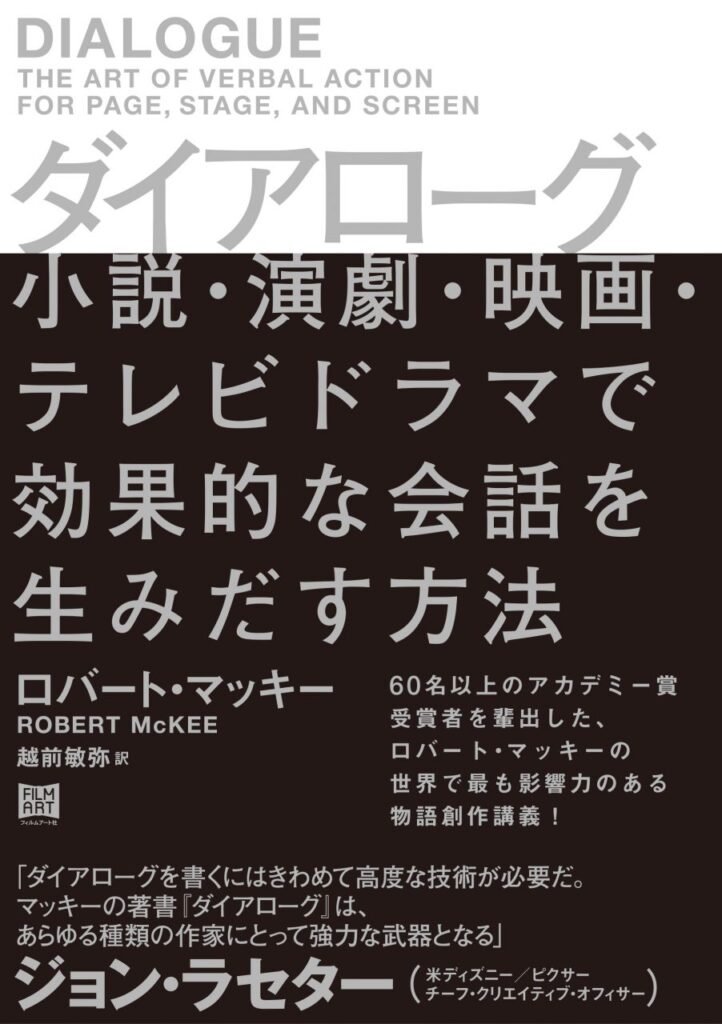1 ダイアローグの完全な定義
ダイアローグ:あらゆる登場人物が、あらゆる人物に対して発する、あらゆることば。
通常、ダイアローグは登場人物同士が交わす会話と定義されている。だが、ダイアローグを包括的かつ綿密に研究するために、そこから一歩もどって、できるかぎり広い視野でストーリーテリングを考察することからはじめよう。その見地に立ってまず気づくのは、登場人物の語りは、他者に話す、自身に話す、読者や観客に話すという、明確に異なる三つの流れに分かれることだ。
この三つの語りの形式を「ダイアローグ」という用語でまとめて呼ぶのには、ふたつの理由がある。第一に、ある登場人物が、いつ、どこで、だれに対して語るにせよ、作家はその役柄に個性を与えるために、その人物ならではの声を言語化して示さなくてはいけないからだ。第二に、心中のつぶやきであれ音をともなう声であれ、脳裏の思考であれ世間に向けた発言であれ、語るという行為はすべて、内なる活力が外へ発せられたものだからだ。語りはどれも、必要を満たし、目的を持ち、行動を引き起こす。どんなに曖昧で空疎に見えても、他者に対して、いや、自身に対してさえ、目的も理由もなく語りかける登場人物はいない。だから作家は、登場人物の発言ひとつひとつの裏に、欲望と意図と活力を組みこまなくてはならない。そしてその活力が、ことばの駆け引き、すなわちダイアローグになる。
では、ダイアローグの三つの流れをくわしく見てみよう。
一、他者に話す。二方向間の会話は対話劇デュアローグと呼ばれる。三人が会話をすると、三人劇トライアローグが生まれる。感謝祭の食事に大家族が集えば、多数劇マルチローグとなるのかもしれない。
二、自身に話す。シナリオライターは登場人物にひとり語りをあまりさせないが、劇作家はよくそうする。小説家にとっては、心のなかでの語りは散文技巧の大切な要素である。散文には、登場人物の心にはいりこんで、内面の葛藤を思考の風景へ投影する力がある。小説家が一人称か二人称で物語を書くとき、その語り手はかならず登場人物のひとりだ。したがって小説には、あたかも読者に立ち聞きさせるかのような、内省的で自分に語りかける形のダイアローグが満ちていることが多い。
三、読者や観客に話す。劇場では、独白や傍白という手法によって、登場人物が観客の目の前でひそかにひとり語りをすることができる。テレビや映画では、画面外で登場人物に語らせるのがふつうだが、カメラに向かって直接語らせる場合もある。小説では、これこそがまさしく一人称形式で、登場人物が自分の話を読者へ語り聞かせる。
「ダイアローグ(dialogue)」ということばの語源は、「〜を通して(through)」という意味のdia-と、「発話(speech)」という意味のlegein、ふたつのギリシア語である。この二語が直接英語に移されて、「発話による(through-speech)」という複合名詞ができ、「行為」と対比される語となった。他者へ向けて口に出したものでも、心のなかのつぶやきでも、登場人物が口にするすべての台詞は、ジョン・L・オースティンのことばを借りると、「遂行的」である。
何かを言うことも一種の行動であるから、わたしはダイアローグの定義をさらにひろげて、「ある登場人物が自分自身、他者、読者や観客に対し、なんらかの必要や欲求を満たすために発するあらゆることば」と再定義してきた。三つの場合のすべてにおいて、登場人物が話すときは、肉体ではなくことばで行動するのであり、「発話による」アクションのひとつひとつがその場面を少しずつ動かすとともに、登場人物は願望の実現へ近づいたり(肯定)、そこから遠ざかったり(否定)する。アクションとしてのダイアローグは本書の基礎を成す原則である。
ダイアローグはふたつの形式のどちらかでアクションを引き起こす。ドラマ型か、ナレーション型だ。
ドラマ型のダイアローグ
ドラマ型とは、場面内・で演じるという意味だ。喜劇調であれ悲劇調であれ、ドラマ型のダイアローグは相対する登場人物のあいだで台詞のやりとりをおこなう。それぞれの台詞には具体的な意図を持ったアクションが含まれ、場面内のある時点で反応を引き起こす。
これは人物がひとりしか登場しない場面でもあてはまる。人が「自分に腹が立つ」と言うとき、だれがだれに腹を立てているのか。鏡のなかに自分の姿が見えるように、想像のなかに自分自身が見えているのだ。自分自身と論じ合うために、心は第二の自己を生み出して、別の人物に対するかのように語りかける。内面のダイアローグは、同一人物中のふたつの自己が対立し合う、きわめて劇的場面になる。自己のどちらが口論に勝つかはわからない。したがって、厳密に定義すれば、すべてのモノローグは、実のところダイアローグだ。登場人物が話すときは、つねにだれかに向かって話す。相手がもうひとりの自分の場合もある。
ナレーション型のダイアローグ
ナレーション型とは、場面外・で語るという意味だ。この場合、現実と虚構を隔てるいわゆる第四の壁が消え去り、登場人物がドラマの枠から外へ踏み出す。ここでもまた、厳密に言えば、ナレーション型の語りはモノローグではなくダイアローグであり、登場人物は読者や観客や自分自身に対し、声を出して直接語りかける。
作り手の願望という観点から言うと、小説における一人称形式の語りや、演劇や映画における登場人物によるナレーションは、読者や観客に過去の出来事を知らせて、これから起こる出来事への好奇心を呼び起こしたいだけなのかもしれない。ナレーション型のダイアローグを用いて、そのような単純な野心を実現させたいだけで、それ以上の意味はないのかもしれない。
だが、もっとこみ入った状況では、たとえば語りによって読者や観客を誘導し、登場人物のかつての過ちを許させたり、敵に対する一方的な見方に共感させたりという効果を狙う場合もありうる。登場人物がアクションを起こす引き金となる欲望も、読者や観客に語りかける技巧も、ストーリーによってさまざまで、際限がないように思える。
それと同じことが、内面と向き合って自分自身に語りかける登場人物についても言える。目的はどんなものでもおかしくない。記憶をよみがえらせて楽しんだり、恋人の誠意を信じるべきか否かで頭を悩ませたり、先々の人生を夢想して希望を募らせたりしながら、その思考は過去を、現在を、そして起こりうる未来をさまよっていく。現実も空想も含めてだ。
三種類のダイアローグの形式で同じ内容が表現できることを示すために、スウェーデンの作家のヤルマール・セーデルベリが1905年に発表した小説『グラース博士』の一節を使って試してみよう。
この作品は、タイトルと同名の主人公による日記の形式で書かれている。日記というものは、自分自身に語りかける秘密の会話を記録するものだから、虚構の日記は、秘められた内面のダイアローグを盗み聞きしている気分に読者をさせなくてはならない。
セーデルベリの小説のなかで、グラース博士は(ひそかに恋心を寄せる)ある患者を、性的暴行を加える夫から救いたいと思っている。博士の心は日々、彼女の夫を殺すべきか否かと道義上の争論を繰りひろげていて、夜ごと見る悪夢のなかでは、決まって殺人を犯す(その後、実際に夫を毒殺する)。八月七日と記された日記には、悪夢で冷たい汗をかいて目が覚めたと書いてある。この忌まわしい夢は予知夢ではないと自分に言い聞かせようとするグラースの、とりとめのないナレーション型のダイアローグに耳を傾けてみよう。
「夢は小川のごとく流れゆく」。古き格言よ、おまえのことはよく知っている。そして現実には、人が見る夢のほとんどが思い返すに値しないことも。それらはまとまりのない経験の断片であり、しばしば意識が蓄えるまでもないと判断したこの上なくばかげて無意味な断片であるが、そんなものでも頭のなかの屋根裏部屋や納戸でひそやかに息づいている。だが夢の種類はそれだけではない。若いころ、午後をまるまる費やして幾何学の問題に挑み、結局解けないまま寝てしまったことがある。睡眠中でも脳は勝手に働きつづけ、夢のなかで解答を導き出した。正しい答だった。また、心の奥底から湧きあがる泡のような夢もある。このごろは夢についてもっとはっきりした考えを持つようになった――自分自身について夢が教えてくれたことが幾度もあり、いだきたくなかった願望や、白日のもとにさらしたくなかった願望をしばしば暴き出す。そうした夢や願望を、のちにわたしは明るい日差しのもとで秤にかけて見定めた。けれども日の光に耐えうるようなものはめったになく、たいがいはそれらが属すべき深い淀みへ追い返した。それらは夜になるとあらためて襲いかかるが、わたしはその正体を知っているから、夢のなかであっても笑い飛ばす。それらが現実に日の目を見たいという欲求をことごとく捨てさせてやる。
グラースは一行目で、まるで観念に心があるかのように、心に浮かんだ成句に対して語りかける。それから、寡黙で不道徳な自分の暗黒面、殺人願望で乱れる自己との論戦をはじめる。最後の文によって、善良な自己が議論に勝利したとグラースは考える……少なくともいったんは。冗長で反芻が積み重なった文で語られるさまに注目するといい。
つぎにこの一節を、グラース博士が直接読者へ向けて語るナレーション型のダイアローグとしてセーデルベリが書いたと仮定しよう。グラースが他者へ語りかけるときの声として、医師が患者を治療するときによく使う威厳ある声を想定してもいいだろう。一文の長さは短く、命令調になるかもしれない。発想に鋭いひねりをもたらすために、「〜べきだ」「〜してはいけない」「しかし〜」などが用いられることもある。
「夢は小川のごとく流れゆく」。聞き覚えがある成句だろう。これを信じてはいけない。たいがいの夢は思い返すに値しない。それらのまとまりない断片はばかげて無意味で、意識が蓄えるまでもないと判断したものだ。それでも頭のなかの屋根裏部屋でひそやかに息づいている。健全とは言えない。だが便利な夢もある。若いころ、午後をまるまる費やして幾何学の問題に挑んだことがある。結局、解けないまま寝てしまった。しかし、脳は睡眠中でも働きつづけ、夢のなかで答を導き出した。また、心の奥底から湧きあがる泡のような危険な夢もある。あえて考えてみると、そうした夢は自分自身について教えてくれる気がする│いだきたくなかった願望や、口にしたくなかった願望をだ。それらを信じてはいけない。よく考えてみたが、それらは明るい日の光に耐えられるものではない。だから健全な人間がすることをなすべきだ。それらが属すべき深い淀みへ追い返すべきだ。夜にあらためて襲いかかったら、それらを笑い飛ばし、現実に日の目を見たいという欲求をことごとく捨てさせてやるべきだ。
第三の選択として、戯曲も手がけていたセーデルベルグが、この話を舞台劇に仕立てた可能性もある。博士の役柄をふたつに分けたかもしれない――グラースとマーケルだ。小説では、ジャーナリストのマーケルはグラースの親友である。舞台劇では、マーケルにグラースの道義的な一面を体現させ、グラースには殺人の誘惑に苦しむ一面を演じさせることもできる。
つぎの場面には、グラースが厄介な夢から解き放たれたくてマーケルに助けを求めるという含みがある。それを感じとったマーケルは、グラースの質問への答として、前向きで道義的な意見を述べる。テクストには小説の比喩表現がそのまま残されている(実のところ、戯曲では象徴的な言いまわしが求められる)が、line design台詞の構成をcumulative累積型からperiodic周期型にして、俳優が話しはじめるきっかけを作ってある(台詞の構成の研究については第五章参照)。
グラースとマーケルはカフェにいる。夕暮れから夜になる時分で、ふたりは食後のブランデーを飲んでいる。
グラース 〝夢は小川のごとく流れゆく〞ということわざを知っているか?
マーケル ああ。ばあさんがしじゅう口にしてたけど、実のところ、ほとんどの夢は一日の断片にすぎない。覚えておく価値はないさ。
グラース 役立たずだとしても、頭のなかの屋根裏部屋でひそやかに息づいているんだぞ。
マーケル あんたの頭のなかではね、博士。おれのじゃない。
グラース しかし、夢が見識を与えてくれるとは思わないか?
マーケル ときにはね。若いころ、午後をまるまる費やして幾何学の問題に取り組んだことがあるんだが、結局解けないまま寝てしまった。でも、脳は働きつづけて、答が夢に出てきたんだ。翌朝たしかめたら、なんと正解だったよ。
グラース いや、わたしが言っているのはもっと秘められたもので、おのれを見透かす洞察とか、心の奥底から湧きあがる真実の泡とか、朝食を食べながらとても認める気にはなれないような邪悪な願望のことだ。
マーケル もしそんな願望があるなら、おれのなかにあるかどうかはともかく、それらがいるべき深い淀みへ追い返すよ。
グラース だが、願望が夜ごともどってきたら?
マーケル だったらそれをあざけるような夢を見てやり、笑い飛ばして頭から追い払うまでさ。
この三つでは内容の本質が同じだが、語りかける対象が自分自身から読者へ、さらに別の登場人物へと変わると、輪郭、ことばづかい、調子、構成が大きく変化する。この三つの基本的なダイアローグの形式には、くっきりと差がある三種の文体が求められる。
ダイアローグと主要媒体
すべてのダイアローグは、ドラマ型であれナレーション型であれ、ストーリーという大交響曲のなかで奏でられるものだが、舞台とスクリーンと書籍では、その楽器や編曲が著しく異なる。そのため作者がどの媒体を選ぶかは、ダイアローグの構成、その量と質に大きな影響を及ぼす。
たとえば、演劇はおもに聴覚の媒体であり、観客を観るより聴くほうに集中させる。その結果、舞台では外見より声が優先される。
映画はその逆で、おもに視覚の媒体であり、観客を聴くより観るほうに集中させる。そのため、映画では声より外見が優先される。
テレビの場合は、演劇と映画のあいだを浮遊している。テレビドラマは声と外見の調和をめざする傾向にあり、だいたいのところ、観ることと聴くことを等分に求める。
小説は心の媒体である。舞台やスクリーンで演じられる物語は観客の耳と目に直接訴えるが、文学は迂回路を通って読者の心へ訴える。読者はまず言語を解釈しなければならず、それから描かれている光景と音を想像し(どの読者の想像も人それぞれだ)、そこでようやく、描かれたものに身をまかせる。そのうえ、文芸作品の登場人物に演じ手は不在であるから、著者が適切と判断すれば、ドラマ型でもナレーション型でも、量に関係なく、ダイアローグを自由に用いることができる。
では、ストーリーの各媒体がダイアローグをどのように形作るかを見てみよう。[……]
小説のダイアローグ
舞台やスクリーンで表現されるストーリーは、大気や光という物理的な媒体を通り抜け、聴覚や視覚を介して頭にはいってくる。文章の形で語られるストーリーは、言語という知の媒体を介して、読み手の想像力のなかで息づく。想像力は感覚よりはるかに複雑であり、多面的で多層的でもあるため、文学作品は演劇やテレビや映画より多くの種類と柔軟性を持つダイアローグを提供できる。
小説のストーリーは、作品世界のなかの登場人物か、外の世界の語り手のどちらかによって語られる。しかし、この単純な区分は、小説に三つの視点が存在するせいで、はるかに複雑なものとなる。三つの視点とはすなわち、一人称、二人称、三人称だ。
一人称。一人称形式の語りでは、登場人物が自身を「わたし」や「おれ」などと称し、読者に対して、思いつくままに出来事を語っていく。出来事の説明をすることもあれば、自分とほかの人物が直接対話している場面で劇的に語りをはさむこともある。また、胸のなかで自分自身に語りかけることもできる。その場合、読者は語り手に寄り添って、内なる会話を盗み聞くかのように感じる。
一人称の語り手はストーリーに深くかかわる登場人物だから、周囲の日常を観察する者としては不十分であり、出来事の全体像もしばしば理解できずにいる。自分が何を追い求めているかを口にしなかったり、意識していなかったりするので、往々にして客観的とは言いがたい。そのため、一人称の語り手には、信用するに値する者からまったくあてにならない者まで、さまざまなタイプがある。
また、一人称の語り手は他人より自分自身に関心を寄せることが多いため、心の動きや内省や反芻でページが埋まる傾向がある。したがって、読者がほかの登場人物の内面を知るには、語り手の推測や暗示をもとにして、行間から読みとるしかない。
ほかの登場人物の思考や感情を知る超人的な洞察力を持った、全知の一人称の語り手というのは、めったに見られない仕掛けだ。そのような奇抜な着想には、特別の説明が必要になる。たとえば、アリス・シーボルドの『ラブリー・ボーン』では、一人称で語るのは殺害された少女の霊であり、天から下界をながめつつ、自分を失って苦悩する家族の心をのぞきこむ。
一人称の語り手には、物語の主人公(ウンベルト・エーコ『薔薇の名前』の修道士、バスカヴィルのウィリアム)、主人公の親友(シャーロック・ホームズにとってのワトスン医師)、一人称で語るグループ(ジェフリー・ユージェニデス『ヘビトンボの季節に自殺した五人姉妹』)、物語から距離を置いた観察者(ジョゼフ・コンラッド『闇の奥』の無名の語り手)などがある。
三人称。三人称形式の語りでは、語り手をつとめる知的存在が読者を導いて、ストーリーを案内していく。この語り手は全登場人物の思考や感情を知りつくしていることが多く、作中に顔を出さないにもかかわらず、物語世界と社会に関する強い倫理観やその他の意見を持っていることもある。登場人物を「彼」「彼女」「彼ら」という代名詞で呼んで、一定の距離を保つのがふつうだ。
三人称の語り手は登場人物ではないので、その語りはダイアローグではない。また、作家の声を書き表したものでもない。三人称で語りながら生きていく人間はいない。ナショナル・パブリック・ラジオのトーク番組に出演する、きわめて多弁なゲストですら、そんなことはできない。
この登場しない語り手は、著者よりいくらか情け深かったり、政治的だったり、客観的だったり、道徳的だったり、あるいはその逆かもしれない。いずれにせよ、それぞれの登場人物に声を与えるのと同じ要領で、作家はこの語り手の話し方を考え出す。観客が舞台上や画面外のナレーターにみずからを委ねるのと同じように、読者が話の進行の約束事として、非登場人物によるダイアローグなしの語りを受け入れることを作家は知っている。
このような知的存在が用いる文体は、きわめて表現豊かな場合もあるため、読者は自身の想像のなかで、何者かの声として聞くかもしれないが、それはだれの声でもない。真の声を持つのは登場人物だけだ。三人称の語り手の「声」と称されるものは、作家の生み出した文体にすぎない。だから、読者はその声に共感もしなければ、陰にいる語り手の運命に好奇心を持つこともない。
ホメロスより古い時代からつづく慣例により、作家が非登場人物の語り手を生み出した目的は、理解しやすいことばで話を進めることだけだと読者は知っている。一方、もしこの知的存在が突然みずからを「わたし」と呼びはじめたら、非登場人物は登場人物となり、語りは一人称へと変わる。
三人称の語り手の知識の幅は全知からほぼ無知まであり、物の見方の幅は中立的から批判的まであり、読者にとっての存在感は強烈から希薄まであり、語りの信頼性は誠実から(非常にまれだが)いいかげんまであり、実にさまざまだ。作家はこれらの特質をあれこれ考え、辛辣で突き放した立場からストーリーに深くかかわる立場まで、三人称の語り手を客観寄りにするか主観寄りにするか、濃淡をつけることができる。
客観的な三人称(潜在型や演劇型の三人称とも言う)は、見せることより語ることのほうがはるかに少ない。観察をするが、解釈をすることはない。この語り手は、人生劇場の後見人のごとく椅子に深々と腰かけ、内なる領域にはけっしてはいりこまず、どの登場人物の思考も感情も説明しない。有名な例としては、アーネスト・ヘミングウェイの「白い象のような山並み」「キリマンジャロの雪」などの短編がある。二十世紀半ばにフランスのヌーヴォー・ロマンがこの手法を採り入れて徹底させ、アラン・ロブ=グリエの『嫉妬』などの作品を生み出した。
主観的な三人称は、複数の登場人物の内面を見透かして、思考や感情を切り替えて描いていく。もっとも、主人公の内面だけに制限する作家も珍しくない。この形式は一人称の一種にも思えるが、「わたし」ではなく、主観を交えない代名詞「彼」「彼女」を用いて、距離をとる。
たとえば、ジョージ・R・R・マーティンの『氷と炎の歌』シリーズでは、各編において独立した話が展開し、視点はそれぞれの主人公のものにかぎられている。
主観的な探究の技法は、語り手が全知であれ、一部しか知らないのであれ、二十世紀の小説で最も用いられた語りとなった。主観的な語り手は、若干の個性と明確な意見を持っている場合もある(このあとの『コレクションズ』からの引用を参照)。だが、三人称の語り手がどんなに陽気だろうと辛辣だろうと、またどんなに通俗的だろうと個人的だろうと、その声は作家の創造物であり、外側からストーリーを進めるために生み出された作家自身の特殊な一面である。
作家はその気になれば、詩や散文が何千年もかけて築いてきた読者との信頼の絆を、語り手に壊させることもできる。まれにではあるが、作家が語り手の声に、混乱や不誠実といったキャラクターめいた特質を加える例もある。しかし、繰り返すが、三人称の語り手がいかにごまかしがうまく、信頼できず、気まぐれであったとしても、そのことばはダイアローグではない。語っているのは仮面を被った作者である。三人称の語りには独特の戦略と技法が求められるが、本書の目的からはずれるので、ここではふれない。
二人称。二人称形式は、一人称か三人称が形を変えたものだ。この形式では、ストーリーを語る声が「わたし/おれ/ぼく」などの一人称代名詞や、「彼女/彼/彼ら」の三人称代名詞を排除して「あなた/きみ/おまえ」などと呼びかける。この「あなた」は、主人公自身であることもありうる。たとえば、ある人が自分自身を「この愚か者」と叱咤するときは、自分の一面が別の一面を批判していると言えるだろう。だから、二人称の声が自身を分析したり、励ましたり、回顧したりできる(ミシェル・ビュトールの『心変わり』)。あるいは、「あなた」は声も名前もないほかの登場人物ということもあり、その場合、語りは一方通行のドラマ型ダイアローグとなる(イアン・バンクスの『ア・ソング・オブ・ストーン』)。また第三の可能性として、「あなた」が読者ということもありうる。ジェイ・マキナニーの小説『ブライト・ライツ、ビッグ・シティ』では、だれとも言えない意識が現在形で読者を物語へ引きこみ、読者は数々の場面をみずから演じているかのような気分になる。
どこへ行こうとしているのか、きみにもはっきりとはわからない。もう家へたどり着く元気など残ってはいまい。きみは足を速める。陽の光が路上を歩くきみを捕まえたら、きみの身体には取り返しのつかない化学変化が起こるだろう。少したってから、きみは指についた血に気がつく。手を顔にあてる。シャツにも血が滲んでいる。きみはジャケットのポケットからティッシュをとりだして鼻に詰める。頭を後ろに倒すようにしてきみは進む。(高橋源一郎訳、新潮社)
この一節を過去形で書きなおして「きみ」を「わたし」に変えれば、通常の一人称小説になるし、「きみ」を「彼」にすれば、通常の三人称小説になるだろう。二人称現在形は語りをどっちつかずのあいまいなものとし、主観カメラを思わせる映画的な空気のなかで流れを進めていく。
その複雑さをわかりやすく示すために、小説の慣例を舞台や映画と比べてみよう。
ドラマ型のダイアローグ
小説において、ドラマ型の場面は、一人称、二人称、三人称のいずれの視点でも書くことができる。どの形でも、それぞれの時空の設定で場面が作られ、登場人物とその行動が描かれ、語ることばがそのまま引用される。そういった場面がページを離れて舞台やスタジオへ移り、ほとんど手を加えずに俳優が演じることもありうる。
ナレーション型のダイアローグ
ドラマ型の場面以外で、一人称または二人称によって語られることばを、わたしはすべてナレーション型のダイアローグと見なしている。そういう個所は、物語を進める目的で語られていて、独白劇や、カメラを見据えた語りのような効果を読者に与える。ナレーション型のダイアローグが意識の流れ(後述)へ転調すると、演劇のひとり語りや、映画『メメント』『π』に見られる画面外の主人公の語りのように読むことができる。どの場合でも、著者は登場人物の役柄に合わせて書き進めていく。
間接的なダイアローグ
主要な四つの媒体のどれでも、作家は過去の出来事の説明をするか、読者や観客の前にそのまま提示して動かすか、どちらかを選ぶことができる。説明を選ぶ場合、ドラマ型のダイアローグの場面になりえたものは間接的なダイアローグに変わる。
登場人物を使って過去の出来事を説明させる場合、その人物は別の登場人物がかつて語ったことばを言い換えて口にする。例として、ブルース・ノリスの戯曲『クライボーン・パーク』から、ベヴが夫への不満を漏らすくだりを見てみよう。
ベヴ ――ひと晩じゅうそんなふうに起きててね。きのうは夜中の三時にぼんやりすわってたから、言ってやったの。〝ねえ、眠たくないの? 睡眠薬を呑むとか、トランプ遊びでもしたらどう?〞ってね。そしたらあの人、〝それになんの意味があるんだ〞ですって。まるで、人間がやることなすこと全部に立派な理由がなきゃいけないみたいに。
ベヴの言い換えが正確かどうかについては、観る者は推測するしかないが、この場面では厳密な発言内容は重要ではない。間接的なダイアローグによって、作者は観客に重要なことを伝えている。すなわち、ベヴ自身のことばで語る、夫のふるまいについての解釈だ。
三人称の語りで会話を言い換える場合も、それが口にされたときにどう聞こえたのか、読者は判断しなくてはならない。ジョナサン・フランゼンの小説『コレクションズ』にある夫婦の場面を見てみよう。
妊娠で幸福になった彼女は気がゆるみ、アルフレッドにまずいことを言ってしまった。セックスや生活の充足感やよその夫婦との比較を話題にしたわけではもちろんないが、それらとほとんど同じ程度に禁じられた話題がいくつかあり、ある朝上機嫌のうちにうっかり踏みこんでしまったのだ。彼女は夫にある銘柄の株を買ったらどうかと提案した。アルフレッドは、株式投資は非常に危険なもので、金持ちかやくざな投機屋がやるものだと答えた。イーニッドはそれでもこれは買ってみたらと提案した。アルフレッドは、おれは暗黒の火曜日を昨日のことのように覚えていると言った。イーニッドはそれでもそれでもやはり買ったらどうかと提案した。アルフレッドはその銘柄の株を買うのはきわめて不適切だと言った。イーニッドはなおも提案した。アルフレッドは金がないし、もうすぐ三人めの子供も生まれると言った。イーニッドはお金なら借りられるからと提案した。アルフレッドはノーと言った。大声でそう言って朝食の席を立った。そのノーの返事はあまりにも声高で、キッチンの棚の装飾を施された銅製のボウルが短く共鳴音を響かせたほどだった。アルフレッドは彼女にキスもせず、十一日と十晩、家にもどらなかった。(黒原敏行訳、新潮社、一部改変)
「提案した」を五度繰り返すことにより、イーニッドのしつこさとアルフレッドの怒りが、滑稽すれすれまで達している。「十一日と十晩」というのは、休暇のクルーズ旅行の日数を予示したものであり、壁にかかった皿が低く鳴るイメージは、この場面を、滑稽を通り越して不条理の域にまで突き進めている。
間接的なダイアローグは読者に情景を想像させるので、白熱してメロドラマ風になりかねない直接的なダイアローグを親しみやすくして、説得力のある形で読者に訴えかけることができる