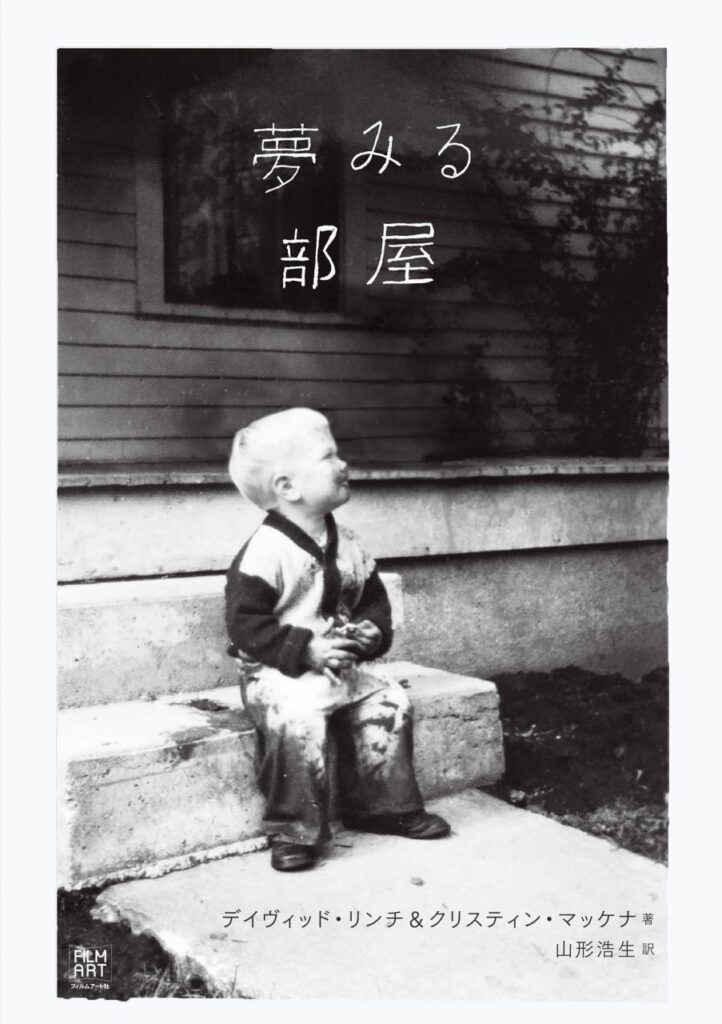『ツイン・ピークス』がどうやって実現したかというトニー版の説明は、トニーの頭の中ではそういうことになっているんだろうが、私の記憶とはちがう。それでも、トニーはいろいろ気に掛けてくれたと言わざるを得ないな。というのも『ツイン・ピークス』をやれるようにしてくれたし、『ツイン・ピークス』は大好きだったからだ。登場人物も世界も、ユーモアと謎の組み合わせも大好きなんだ。
パイロットは独自の映画と同じものだと見ているし、私に関する限り、最初の2シーズンすべてで本当に『ツイン・ピークス』と言えるのはパイロットだけなんだ。残りは上演用でテレビっぽくやったけれど、パイロットは本当に雰囲気をつかんでいた。それはみんなロケ撮影していたという事実と関係しているな。場所自体が実に重要。ロケはいつも面倒くさいけれど、でもあそこは本当に美しかったし、ABCがまったく口をはさまないから、自由の感覚があった。何度か表現についてメモがきて、台詞を少し変えさせられたけれど、でも代わりに思いついた台詞は、結局ABCが嫌ったオリジナルの台詞よりずっとよくなった。
そしてキャストが最高だったよ。シェリリン・フェンに会ったら、この娘ならオードリー・ホーンみたいな子を演じられるのがわかったし、パイパー・ローリーは有名だったけれど、この人ならキャサリン・マーテルに入り込めるのがわかったんだ。パイパーとリチャード・ベイマーとペギー・リプトンとラス・タンブリンがみんな同じ世代で似たようなキャリアを経てきたのは、ただの偶然だ。ラスはデニス・ホッパーのおかげだな。デニスは私の40歳の誕生パーティーをしてくれて、ラスがそこにきたんだ。ジャコービー医師の配役となると、頭の中で何かがカーン!と鳴った。そして彼がジャコービー医師になったんだ。
パイロットの脚本で、クーパーとトルーマン保安官がエレベーターに乗っていて、ドアが開いたときにクーパーが立ち去ろうとする片腕の男に気がつく場面がある。そしてアル・ストローベルはその役で雇われたんだ。『ツイン・ピークス』での出番はそれだけで、そのまま家に帰るはずだった。でもアル・ストローベルの声を聞いたら、すばらしい声だったから、その声のために何か書くしかなかった。確かディーパクが車を運転していて、ずばりどこにいたかも覚えている。高速を下りてきたところで、出口を下るとき、書いていたものの発端が「未来の過去の闇を通じて、魔術師は見ようと待望する」というものだった。だからアルがクーパーと部屋で会って、彼がこいつを暗唱する新しい場面を書いて、それを編集中のドュウェイン・ダンハムに送った。夜遅くてドュウェインは帰ろうとしていたのにこの映像が届いたから、彼は「冗談じゃないぜ」と言った。でもそのアルの場面はいろいろなつながりを生み出して、それが彼を物語に組み込んだんだ。
リチャード・ベイマーは私より前から瞑想していたし、長いことマハリシの下についていたんだが、ベン・ホーン役に起用したときにはそんなことは知らなかった。会ったときも瞑想の話なんかしなかった――とにかくリチャードが気に入ったんだ。イザベラも『ツイン・ピークス』に出る予定だったのにやりたがらなかったので、そのキャラクターはジョシー・パッカードとなり、ジョーン・チェンがそれを演じた。ジョーンは美しいし、イザベラのように異邦人だから、ジョシー・パッカード役にはぴったりに思えた。ペギー・リプトンが60年代には『モッズ特捜隊』で一大テレビスターだったのは知っていたけれど、その番組は観たことがなかった。放映されていた頃はテレビなんか観なかったからだ。ペギーを配役したのは、彼女がまさにノーマ・ジェニングスだったからだ。『ツイン・ピークス』の役者はみんなそんな感じだ。それぞれの演じるキャラクターを演じられた人は他にだれもいない。考えてみれば、クーパー捜査官を演じられるのはカイルだけだ。私はずっとカイルにやらせたいと思っていたけれど、最初マークは「ちょっと若すぎない?」と言った。でもマークも折れて、あとはご存じの通り。
クーパー捜査官の役柄はいろんなところからきている。たとえば、ウマ・サーマンの父親はダライ・ラマと関係が深く、私が訪問した彼女の家でもダライ・ラマ好きがうかがえたし、私もダライ・ラマには会ったから、それでクーパー捜査官はチベット人民支持となり、石を投げる場面もできた。ダライ・ラマと会えたのは光栄だった。ダライ・ラマは瞑想技法は教えないけれど、平和を支持してる。
丸太おばさんは、1973年以来私がキャサリン・コウルソン向けに考えていたキャラクターなんだ。丸太おばさんは当初、ジャックとキャサリンが暮らしている家に住んでいた。これはロサンゼルスのビーチウッド・ドライブから外れた、スペイン様式のアパートの2階だった。丸太おばさんの話はその部屋で始まるんだと考えていた。そして旦那が山火事で死んだから、暖炉は板でふさいである。その遺灰は、暖炉の上に彼の吸っていたパイプと並んで、骨壺に入っている。いつも丸太を抱え、そして五歳かそこらの小さな息子もいて、一種の学習番組『自分の丸太をあらゆる知識の枝で試そう』に出演していた。車は運転しないから、いつもタクシーだ。歯医者にいくときには丸太を抱えていき、歯医者はその丸太を椅子にすわらせて、小さなよだれかけを丸太にかけると虫歯を探す。時間をかけて、子供が歯医者の診察について何か学べるようにするんだ。歯の腐食の話とか、どうやって詰め物をするかとか、詰め物に何を使うかとかを説明して、歯を磨いて口の中をきれいにしておくのが大事なんだよと教える。
一部のエピソードでは、みんなでどこかのダイナーに出かけていっしょにすわり、彼女は丸太を抱え、少年はその隣にすわり、何かを注文してそこにすわっているんだ。心の中で、そのダイナーはおもしろそうな脇道話の可能性を持っている。だからキャサリンと私はときどきそのアイデアについて話し合った。 何年もたって『ツイン・ピークス』のパイロットを撮影しているとき、クーパー捜査官とトルーマン保安官が町の人々に殺人事件について話す市役所での場面を撮ることになった。私はよし、これはチャンスだと思って、キャサリンに電話して「あなたは丸太を抱えて、仕事は灯りをつけたり消したりして、この話が始まる時間だとみんなに報せることだよ」と言ったらキャサリンは「最高」と言って、飛行機でやってきたから、丸太を渡して、その場面を演じてもらい、それからあれやこれや。丸太には何か意味深いところがあり、みんな彼女はどんな身の上話を持っているのかと不思議がるようになった。まったく話はわけがわからないのに、なんだか筋は通っていて、そういう人がどんな町にもいて、そのまま受け入れられているもんだ。彼女は特別なツイン・ピークス人なんだ。
私が演じるゴードン・コールは、クーパー捜査官が、フィラデルフィアにいる名無しの上司を呼ぶ必要があったときに登場した。リアルさを高めようとして声だけやることにしたんだが、実際に自分が登場するとは思っていなかったよ。カイルに聞こえるようにかなり大声でしゃべっていて、それであのキャラが誕生した。ゴードン・コールという名前は、『サンセット大通り』からきている―― あの映画でコールはパラマウントスタジオからの人物で、ノーマ・デズモンドに電話して車を借りようとするんだ。人々が名前を思いつくやり方は様々で、ゴードン・コールのことを考えているときに、私はちょっと待ったと思ったんだ。パラマウントスタジオに車を走らせると、ビリー・ワイルダーはゴードン街を通り、それからコール街を通ることになる。ワイルダーがそこから名前を思いついたのはまちがいないと思うんだ。だから私が『ツイン・ピークス』で演じるキャラクターはハリウッドとビリー・ワイルダーを讃えて名付けられているんだ。
ボブというキャラクターは、もともとパイロットの脚本には登場しなかった。登場したのは、ワシントン州エヴェレットのパーマー家で撮影していたときだった。私は二階でなぜか四つん這いになり、ファンの下にいると、背後から女性の声で「フランク、その部屋に自分で自分を閉じ込めないようにしてね」という声が聞こえた。フランク・シルヴァは現場衣装担当で、部屋の中であれこれ動かしている間に、タンスを戸口の前に出してしまったのだった。女性はそれを一種の冗談で言っていたのだけれど、頭の中でフランクがローラ・パーマーの部屋に閉じ込められている様子が思い浮かび、なんかひらめいた。「フランク、君は役者なの?」と尋ねたら「ええデイヴィッド。役者です」というので「オッケー、この場面に出てくれ」と言った。
ローラ・パーマーの部屋でゆっくりしたパン撮影をしていて、フランクなしで三つテイクを行った。それから「フランク、ベッドの足下にいって、隠れてるみたいにしゃがんで、ベッドの枠をつかんでカメラをまっすぐ見て」と指示した。そこでフランクはそこに出かけて、フランクの入ったパンをやったんだが、自分でもなぜそんなことをしたか皆目見当がつかない。その晩遅く、パーマー家の居間の場面を撮影していて、そこに絶望しきったサラ・パーマーがいる。娘が殺されていたんだから。苦悶のなかでソファに横たわっていると、いきなり心の目で何かを見て怯え、突然跳ね起きて叫ぶ。それがあのショットだ。カメラのオペレーターは、ショーン・ドイルというイギリス人で、そのショットをやって「カット!」と私が言った。グレース・ザブリスキーは史上最高の女優の一人で、私は「完璧!」と言ったんだけれど、ショーンが「いやデイヴィッド、完璧じゃないよ――だれかが鏡に映ってた」と言う。「だれ?」と尋ねたら「フランクが鏡に映ってた」と言って、それで第二のボブが生まれた。そしてアイデアはそんなふうにやってくる。どこからくるのか? すべては贈り物だ。フランクはいいやつだし、知り合いたちはボブとは全然ちがうと言うんだけれど、でもボブがわかってる。顔も髪も――その存在すべてがボブに完璧だし、ボブを理解していたんだ。
当初『ツイン・ピークス』は大ヒットしたのに、ABCは本気でこの番組を愛してくれたことはなくて、視聴者たちが「ローラ・パーマーを殺したのはだれか、いつになったらわかるんですか?」と投書しはじめると、局の連中はそれを明かすよう無理強いさせて、そしたらみんな観るのをやめた。殺し屋を明らかにしたらおしまいだよと言ってあったし、その通りおしまいになった。そして別のことも起きていたんだ。続き物のストーリーが受け入れられている時期があって、視聴者もそれについてきていたのに、広告主たちが「視聴者が何度か見損ねると、話についていけなくなって視聴をやめちゃうから、一話完結にしてくれ」と言い出した。それも番組の雰囲気を変えたな。もうすべてお金次第だよ。ボブ・アイガーがやってきて「そろそろ謎を明かさないと」と言った頃には、どのみちうんざりしてたんだ。
『ワイルド・アット・ハート』から戻ってきたときには、番組がどうなってるのかわからなかった。なんか暴走列車みたいで、それを線路に戻すには一日二十四時間週に七日、つきっきりで面倒をみなきゃいけないと思ったっけ。マークと私がすべてのエピソードの脚本をいっしょに書いていたら、問題はなかったんだろうな。でもそうはならず、他の人たちが入ってきた。別にその人たちを悪く言うつもりはないんだけど、でもみんな私の『ツイン・ピークス』を理解してなくて、だから全然似ても似つかないものになっちゃってたんだ。戻ってきて一話監督するときには、いろいろ変えてこっちの思い通りにするんだけど、また別のくだらないことで全然別の方向にいっちゃうんだ。もう全然おもしろくなかった。そして番組が木曜日から土曜夜に移されて、それもよくなかった。なんで移ったのか見当もつかないよ。
『ツイン・ピークス』で私の知名度は上がったんだろうね。でもすべては相対的だ。有名って何? エルビスは有名だった。そしてまったく、このすべてがとにかくバカげてる。今日メル・ブルックスが街を歩いてても、二十五歳以下の人はだれもそれがだれかもわからないだろう。もうたまらないよ。彼のやったことやその偉大さを本当に知ってる人は、もうみんな死んじゃってる。わかってもらえるかなあ。歳を取ると、自分のやったことを記憶している人がいなくなっちゃうんだ。
※掲載しているすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。